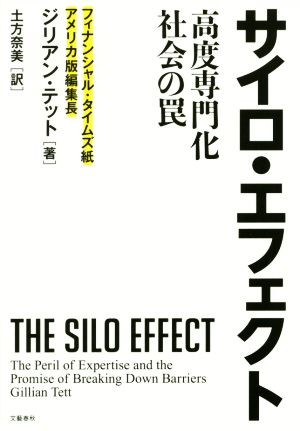サイロ・エフェクト 高度専門化社会の罠 の商品レビュー
アウトサイダーの持ち込む「異なる世界の切り分け方」がフロダクティビティを高めるという、胸のすくような事例が満載の本書。個人的には合成の誤謬に着目して利益を上げたブルーマウンテン・キャピタルのエピソードが面白く読め、「自明を疑う」ことの重要性を再認識できた。ただし本書のフェイスブッ...
アウトサイダーの持ち込む「異なる世界の切り分け方」がフロダクティビティを高めるという、胸のすくような事例が満載の本書。個人的には合成の誤謬に着目して利益を上げたブルーマウンテン・キャピタルのエピソードが面白く読め、「自明を疑う」ことの重要性を再認識できた。ただし本書のフェイスブック礼賛はやや過剰かと。彼らは確かにイノベーティブだが、たかだか単一のビジネスモデルを10年強持続しているだけに過ぎない。セクショナリズムの遠因となる「事業多角化」を未だ必要としていないだけとも言える。彼らが最初の行き詰まりを経験した時、初めて真に彼らが「ソニーでないか」が見えてくることだろう。逆に言えば、多角化を「余儀なくされている」ような大規模な組織に属する人こそ本書を読むべき人達なのだと思う。
Posted by
人類学という視点で組織内の部署間や集団間の壁を意味するサイロの意味と弊害や壁を超えた具体例などが非常に興味深く書かれている。大学組織内の職員研修などのテキストなどで用いたいと感じた。
Posted by
2016年29冊目。 グローバル化によってあらゆるものが「統合」に向かっていると思われがちだが、ある面では実は「細分化」に向かっている。 特に規模が大きくなった組織では、役割分担の中で高度に専門化した小集団が生まれ、集団間の情報の流れは乏しくなる。 そんな細分化した小集団・部門...
2016年29冊目。 グローバル化によってあらゆるものが「統合」に向かっていると思われがちだが、ある面では実は「細分化」に向かっている。 特に規模が大きくなった組織では、役割分担の中で高度に専門化した小集団が生まれ、集団間の情報の流れは乏しくなる。 そんな細分化した小集団・部門を著者は「サイロ(農産物や飼料の格納庫)」と呼び、サイロ化した組織が経営困難に陥る状況を「サイロ・エフェクト」と呼ぶ。 例えばソニーが1999年に発表した三つの製品には、同じ会社から出したものであるにも関わらず互換性がなかった。 これは、それぞれの製品を開発した集団がサイロ化し、横の情報共有ができていなかったことが原因だったそう。 この問題を憂慮してCEOになったストリンガー氏の「うちには三五のソニー製品があるが、充電器も三五個ある」と語っているのが全てを表している。 本書では、前半でこのようなサイロ・エフェクトによって困難に陥った事例が紹介され、後半では逆にサイロを打ち破ることで状況を好転させた事例が続く。 著者はフィナンシャル・タイムズ紙アメリカ版の編集長でありながら、元々はタジキスタンの小さな村に張り付く文化人類学者だった。 単にジャーナリストとしての視点からだけではなく、この文化人類学の視点からも問題を見ている点が面白い。 サイロは必ずしも悪いわけではなく、部門の専門化はある程度必要である。 しかし、そのサイロ間をつなぐ施策がなければ、高度専門化の罠に陥って凋落が待っているという警鐘を与えてくれる本だった。
Posted by
文化人類学者から転じたフィナンシャルタイムズアメリカ版編集長が、「インサイダー兼アウトサイダー」の視点で、鮮やかに描き出す、現代社会を捉えるもっとも重要なコンセプト。高度に複雑化した社会に対応するため組織が専門家たちの縦割りの「サイロ」になり、その結果変化に対応できない。その逆説...
文化人類学者から転じたフィナンシャルタイムズアメリカ版編集長が、「インサイダー兼アウトサイダー」の視点で、鮮やかに描き出す、現代社会を捉えるもっとも重要なコンセプト。高度に複雑化した社会に対応するため組織が専門家たちの縦割りの「サイロ」になり、その結果変化に対応できない。その逆説を「サイロ・エフェクト」という。
Posted by
未来を見ながら点と点を結びつけることはできない。つながりは過去を振り返ったとき初めてわかるものだ。だから点と点がいつかどこかで結びつくと、信じるしかない スティーブ・ジョブズ ダンパー数 進化生物学者、人類学者 ロビン・ダンバー 機能的な社会集団の規模は、人間、サルあるいは霊長...
未来を見ながら点と点を結びつけることはできない。つながりは過去を振り返ったとき初めてわかるものだ。だから点と点がいつかどこかで結びつくと、信じるしかない スティーブ・ジョブズ ダンパー数 進化生物学者、人類学者 ロビン・ダンバー 機能的な社会集団の規模は、人間、サルあるいは霊長類の脳の大きさと密接な関わりがあることをつきとめた サル、類人猿 脳が小さいと20-30 人間にとって最適な社会集団の規模は150人 真の発見の旅とは、新しい景色を探すことではない。新しい目でみることなのだ マルセル・プルースト サイロシンドロームに陥らないために 部門の境界を柔軟で流動的に 報酬制度やインセンティブについて熟慮 グループ同士が敵対しないように 全員がより多くのデータを共有できるようにする 分類法を定期的に見直す ハイテクを活用 PCは消去できない心理的バイアスをもたない
Posted by
サイロ・エフェクト ジリアン・テット著 断絶する組織のリスク検証 2016/3/13付日本経済新聞 朝刊 「サイロ」とは穀物や飼料を保管する貯蔵庫、ミサイルなどを格納する地下保管庫。もしくは他から隔絶して活動するシステムや組織、ときに心理状態を指すこともある。 ...
サイロ・エフェクト ジリアン・テット著 断絶する組織のリスク検証 2016/3/13付日本経済新聞 朝刊 「サイロ」とは穀物や飼料を保管する貯蔵庫、ミサイルなどを格納する地下保管庫。もしくは他から隔絶して活動するシステムや組織、ときに心理状態を指すこともある。 高度な専門分野を扱うには細分化された組織や仕組みが要る。世の中が複雑になればなるほど「体系化」は避けて通れない。現代社会は多数のサイロが縦横に重なり合った複雑構造でできている。 そうしたサイロ社会に負の側面があることはだれにでも想像がつく。その闇の奥深くにジャーナリストの問題意識と行動力で踏み入り、課題の本質に人類学者の経験と手法で挑んだのが本書である。ファクトと検証で事実を語り、既知の事実に新たな発見を加える。ちなみに著者はかつてフィナンシャル・タイムズの東京支局長も務めていた。 最先端にいたはずのソニーがなぜ時代遅れの会社になったのか。保守的な銀行だったUBSはなぜサブプライム危機で破綻寸前まで追い込まれたのか。経済学者はなぜ金融危機を察知できないのか。 サイロ化された組織で人々の視野は狭まる。それぞれが断絶し、意思疎通を欠き、ビジネスのチャンスもリスクも見逃す。なるほど、とうなずくポイントがあるだろう。日本にはとりわけたくさんのサイロがあることに気づく。土方奈美訳。(文芸春秋・1660円)
Posted by