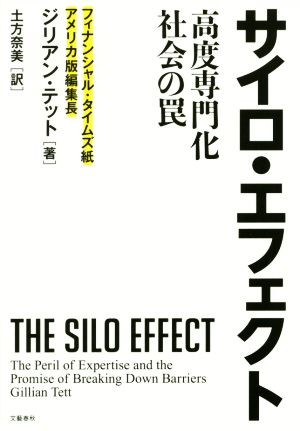サイロ・エフェクト 高度専門化社会の罠 の商品レビュー
組織が効率的に動くには体系だった部局化が必要だけど、それが行き過ぎると部局間協力が行われなかったり、部局(分類)漏れした仕事が回らなくなって組織にとっての損失になるよ!って話。 解決策としては1.個々人が他部門の人と積極的に交流すること2.給料体系を部局ごとの報酬体系にしないって...
組織が効率的に動くには体系だった部局化が必要だけど、それが行き過ぎると部局間協力が行われなかったり、部局(分類)漏れした仕事が回らなくなって組織にとっての損失になるよ!って話。 解決策としては1.個々人が他部門の人と積極的に交流すること2.給料体系を部局ごとの報酬体系にしないって感じ。
Posted by
微妙、結局、どこかで単位を区切る必要はあると思うし、文化や意識からアプローチしないと、仕組み押し当てても本質がかわるのか疑問。結局、非公式組織単位でまとまる気がする。
Posted by
ソニーの凋落の過程が書かれていて興味深い。アップルがまったく逆の組織体制をとっていたことも皮肉な話だ。 以下、本文より。 専門性の高いサイロを作ることで少なくとも短期的に会社の効率化は進んだように思われたものの、デメリットもあった。新たなサイロの経営陣は、カンパニーの財務に責任...
ソニーの凋落の過程が書かれていて興味深い。アップルがまったく逆の組織体制をとっていたことも皮肉な話だ。 以下、本文より。 専門性の高いサイロを作ることで少なくとも短期的に会社の効率化は進んだように思われたものの、デメリットもあった。新たなサイロの経営陣は、カンパニーの財務に責任負っていることを自覚すると、ライバル企業だけでなく社内のほかの部門からも「身を守ろうと」した。他の部門と斬新なアイデアを共有しなくなり、優秀な社員の他部門への異動も避けるようになった。部門同士が協力しなくなり、実験的なプレーンストーミングや、すぐに利益を生まない長期投資も手控えるようになった。誰もがリスクをとることに後ろ向きになった。 ジョブズの経営スタイルはワンマンで、社内にサイロをつくろうとはしなかった。そんなことをすれば管理職に未来に飛び込むより既存の製品アイデアや過去の成功にしがみつこうとするインセンティブを与えることになると恐れたからだ。 また、アップルの製品群は少数にとどめるべきだと考えていた。それは、新たなアイデアが生まれたら、代わりに時代遅れになった製品は廃止することを意味した。。。。。すべてのチームを厳格に管理し、全体として一体感と柔軟性のある会社として機能するよう促し、損益も一元管理した。
Posted by
総じて面白く読めた。 自分自身や自分が所属している組織のみの利益を考えると、他者が必要な情報を共有しなかったり、他のセクションと協力しなかったりというのはよくある話。制度設計やインセンティブの構造の問題で、小規模で和気あいあいとした、利益を平等に分配するような組織が上手くいく(...
総じて面白く読めた。 自分自身や自分が所属している組織のみの利益を考えると、他者が必要な情報を共有しなかったり、他のセクションと協力しなかったりというのはよくある話。制度設計やインセンティブの構造の問題で、小規模で和気あいあいとした、利益を平等に分配するような組織が上手くいく(ケースもある)というのはそういった要因を排除できるためであろう。 シカゴ警察の事例はサイロ化というよりデータを適切に使いこなせていないのが問題である気もした。
Posted by
具体例が多く、サイロとは何か、どういったリスクがあるかわかりやすい。 サイロの影響が大きくなったのはテクノロジーの進歩もあって企業のあり方や仕事の進め方、スピード間など変わってきたのも大きいのかなと思いました。 大企業でなくても、ある程度人数が集まれば起こりうる問題としてもとらえ...
具体例が多く、サイロとは何か、どういったリスクがあるかわかりやすい。 サイロの影響が大きくなったのはテクノロジーの進歩もあって企業のあり方や仕事の進め方、スピード間など変わってきたのも大きいのかなと思いました。 大企業でなくても、ある程度人数が集まれば起こりうる問題としてもとらえられ興味深い。
Posted by
基本的なアイデアは間違っていないし、文章力があって読んでて面白いのだが、社長以下はすべて平社員という超零細企業でもない限りサイロは必ずあるのだから、どんな企業の問題だってサイロで説明できる。なんでもかんでもサイロのせいにするのは少々こじつけっぽい。 以下コジツケの例。 第2章...
基本的なアイデアは間違っていないし、文章力があって読んでて面白いのだが、社長以下はすべて平社員という超零細企業でもない限りサイロは必ずあるのだから、どんな企業の問題だってサイロで説明できる。なんでもかんでもサイロのせいにするのは少々こじつけっぽい。 以下コジツケの例。 第2章 ソニー もう40年近いソニー信者だからわかるのだが、ソニーの不振はベータの敗戦に端を発していると思う。技術や品質では勝っていたのに規格戦争とコンテンツ競争で負けたとのトラウマから、やたら顧客を独自フォーマットで囲い込もうとして逆に嫌われたのと、コンテンツを自社で持っていたから著作権処理の融通が利かなかったためだ。あとハードの技術に偏りすぎてソフトがダメダメなことも大きい。ただソフトの点に関してはSCEのトップが(久夛良木ではなく)普通の経営者だったらこうはなっていなかったかもしれない。Sony製のMedia Goは酷い出来だけど、SCE製のトルネは素晴らしいもんね。 第3章 UBS UBSだけでなく世界中の金融機関が例外なくサブプライムのリスクを把握できなかった。仮にサイロがなかったとしてもリスクを正確に把握できていたかどうか。 第4章 BOE これも例えとしては適切でない。シャドウバンクは古くからあったものが組織の縦割りのせいで認識されなかったのではなく、全く新たに出現したものだ。新しく出現した概念がどこにも分類されないことはよく起こるが、それはサイロとは関係ない。 第5章 シカゴ市警 これもデータサイエンスの勝利であって、サイロに結びつけるのは無理がある。仮にサイロのない風通しの良い組織であったとしても、データベースとその分析がなければ同じ結果は得られなかっただろう。 第6章 Facebook Boot-campと呼ばれないだけで、合宿形式の新入社員研修は新卒一斉採用の日本では当たり前だ。定期的な人事ローテーションも珍しい事ではない。恐らくソニーでもそうだろう。それでもサイロ化は起こったのだ。Facebookも利益率が下がって効率化を志向しだしたら、間もなく大企業病の症状が現れてくると思う。 第7章 クリーブランド病院 これはサイロの破壊というよりも、別のサイロに入れ直したに過ぎない。組織の組み替えはどこの企業でもよくあることだ。 第8章 ブルーマウンテン これって組織の話じゃないよね。サイロを拡大解釈しすぎ。ビジネスチャンスは既存のカテゴリーの境界にある、と言うのは昔から言われていることで、大して目新しい内容ではない。 結局サイロの弊害を最小化するには、組織の構成員を意識的に混ぜ合わせることにあるという結論だが、それは短期的にはコストがかかってマイナスの効果を生む。著者が終章で言うように、効率化を追及しすぎると却って組織は機能しなくなるが、これを長期ビジョンの下に実行するかどうかはトップの考え方次第であり、詰まる所サイロが問題になるかどうかは経営者の器の大きさで決まる。多くの伝統的大企業のように、サラリーマン社長では自分の任期中の株価が上がれば十分なのであって、長期的に会社がどうなろうが知ったこっちゃない。創業社長が減って、器の小さい経営者が増えたことがサイロを問題化させているのだと思う。 残念ながら我が社のトップも器が小さいと言わざるを得ない。それと何のexpertiseも感じさせない人事部の連中にもぜひ読んでもらいたいものだ。
Posted by
組織の専門チーム間の交流が疎かになり、全体像の把握ができずに機能不全に陥る「サイロ・シンドローム」を扱った書。文化人類学を切り口に、第1部ではサイロの弊害事例を、第2部ではサイロの破壊事例と利用事例を扱っている。 第1部にはソニーが登場し、デジタルオーディオ市場でAppleに敗...
組織の専門チーム間の交流が疎かになり、全体像の把握ができずに機能不全に陥る「サイロ・シンドローム」を扱った書。文化人類学を切り口に、第1部ではサイロの弊害事例を、第2部ではサイロの破壊事例と利用事例を扱っている。 第1部にはソニーが登場し、デジタルオーディオ市場でAppleに敗北した原因の一端がサイロであると解説する。一方、facebookはサイロ化を防ぐために様々な施策を導入しているようで、興味を引く内容が記載されている。 サイロ・シンドロームの抑制方法としては、部門境を流動的にする、協調重視の報酬導入、データ共有強化し各自解釈、組織が多様な解釈に耳を傾ける、整理分類の定期的な見直し、ハイテク活用、などがあるという。何れにしても危機意識のあるトップと足回りの良い組織が揃わないとサイロ化の打破は難しそうだ。 他の事例としてはUBS、シカゴ警察、病院、英中央銀行、投資会社を取り上げている。
Posted by
大企業でよくあるセクショナリズムや蛸壺現象を、サイロを打ち破った事例を交えて完全否定せずに解説しているところがすごくいい。解説も専門的になりすぎず読みやすかった。
Posted by
組織のありかた。を考えさせられる内容でした。特に、規模が大きくなるとどうしても縦割りになってしまう。 いかに、互いの事を知り、組織として強くなれるか。非常に興味深かった本です。
Posted by
ソニーの凋落、というのはいろんな本で語られているけど、 こんな風に一般的な形に抽出できるんだ、と目から鱗。 他の例も面白い。とくにフェイスブックの成功。これからどうなるのかさらに見ていきたい。 なんどか本の中でも語られているが、この本はサイロ批判の本ではない。 サイロができると...
ソニーの凋落、というのはいろんな本で語られているけど、 こんな風に一般的な形に抽出できるんだ、と目から鱗。 他の例も面白い。とくにフェイスブックの成功。これからどうなるのかさらに見ていきたい。 なんどか本の中でも語られているが、この本はサイロ批判の本ではない。 サイロができると認めた上で、どうするか、の考えを与えてくれる。
Posted by