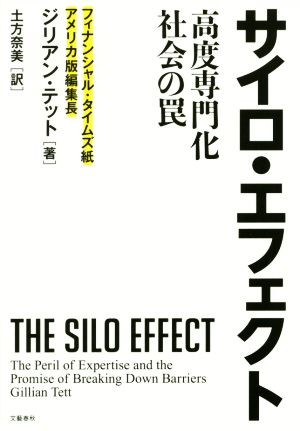サイロ・エフェクト 高度専門化社会の罠 の商品レビュー
効率化を狙って部署/事業を明確に線引きするとサイロとなる。調整が必要となり非効率ではあるが"重複"が必要。組織では重複よりも隙間ができることの方がずっと事態は深刻化する。 イノベーションはいつもサイロの境界線で起こる。 人類学と結びつけた組織論に初めて触れて...
効率化を狙って部署/事業を明確に線引きするとサイロとなる。調整が必要となり非効率ではあるが"重複"が必要。組織では重複よりも隙間ができることの方がずっと事態は深刻化する。 イノベーションはいつもサイロの境界線で起こる。 人類学と結びつけた組織論に初めて触れて面白かった。人類学勉強したい。
Posted by
私が所属する会社にもサイロがある。 規格の異なる同質のプロダクトがいくつもあり、それらの間には関連性はない。新たに作られるシステムには毎度同じ機能が異なる形で作られており、連携することはない。 私が取り組んでいるテーマはサイロを壊すプロダクトであり、壊すための取り組みだと思ってい...
私が所属する会社にもサイロがある。 規格の異なる同質のプロダクトがいくつもあり、それらの間には関連性はない。新たに作られるシステムには毎度同じ機能が異なる形で作られており、連携することはない。 私が取り組んでいるテーマはサイロを壊すプロダクトであり、壊すための取り組みだと思っている。 本書は会社が抱える難題「サイロ化」のネガティブな効果とそれに対応する術を紹介している。 ■ソニーの散々な実情 1999年にソニーは2つの全く異なるデジタルウォークマンを発表した。社内が完全に分裂していたからだ。互換性のない独自技術をつかって全く異なる音楽プレイヤーを開発した。異なる部門はどちらか一方の製品で合意することはおろか、アイデアを交換することも、共通の戦略を見出すことすらできない状態だった。当時のソニーにはこうした分裂状態を正そうとするどころか、状況が手に負えないものになっていることに気付いていた人すらいなかった。 ■アップルの戦い方 ジョブズはアップルを部門に分けなかった。管理職に未来に飛び込むより既存のアイデアや過去の成功にしがみつこうとするインセンティブを与えることになるからだ。 アップルの製品群は少数にとどめるべきと考えていた。それは新たなアイデアが生まれたら、代わりに時代遅れになった製品を廃止することを意味した。 ■フェイスブックが導き出した答え ・新入社員向けの研修プログラム「ブートキャンプ」を活用して、所属チームと研修メンバーという2つのネットワークを作ってサイロ化を回避した。 研修の参加者はさまざまな部署に散らばることになるが、共通の経験によって持続的な絆とお互いをニックネームで呼び合うような緊密さが生まれる。新入社員には職位に関わらず6週間の研修を受けさせた。 ■ ブートキャンプ2つの目的 1.社内を担当作業に応じた専門グループに分ける 2.個別のチームを超える非公式な社会的絆を取り結ぶ。社員が自らの所属するチームではなく、会社全体に帰属意識を持つようにする ■組織の外にあるリスク 会社そのものが大きな社会的サイロになるというリスクは常にある。行き遅れた会社がまさにそれ。日本そのものが社会的サイロ化しており、政府もまさにそれ。
Posted by
インサイダー兼アウトサイダーの議論は興味深かった。ビジネス書だと思って読み始めたら、ピエール・ブルデューについての言及があって驚いたが、著者が文化人類学で博士号を取得していたことを読んで納得した。
Posted by
『サイロ化しないように云々』と私の会社の経営陣は言っているが、現場ではサイロ化万歳状態。トップ・ミドルマネジメントが意識的にサイロを突破する意識と仕組みを構築する必要があると痛感。 テクノロジーの活用には触れられていたが、人類学的視点及び教養(リベラルアーツ)を一人ひとりが高めら...
『サイロ化しないように云々』と私の会社の経営陣は言っているが、現場ではサイロ化万歳状態。トップ・ミドルマネジメントが意識的にサイロを突破する意識と仕組みを構築する必要があると痛感。 テクノロジーの活用には触れられていたが、人類学的視点及び教養(リベラルアーツ)を一人ひとりが高められるか、というのもカギだろう。
Posted by
"この本に、日本語で題名をつけるとすれば、「タコツボ症候群」としたい。 企業や自治体の内部構造、部門を組織化するときに、各部門が高度に専門性を高める傾向がある。この場合隣の部門がどんなことをしているのか意識されず、同じ組織にいながら似たようなことをしていたり、同じ失敗を...
"この本に、日本語で題名をつけるとすれば、「タコツボ症候群」としたい。 企業や自治体の内部構造、部門を組織化するときに、各部門が高度に専門性を高める傾向がある。この場合隣の部門がどんなことをしているのか意識されず、同じ組織にいながら似たようなことをしていたり、同じ失敗をしていたりする現象を紐解いているのが本書。 タコツボのように部門内はよく見えており、その中での効率化、最適化は図られるが、企業あるいは自治体全体の最適化が図られない現実を見つめている。 その現象に気が付くには、内部にいながら外から眺めることができないといけない。 本書ではインサイダー兼アウトサイダーの視点と言っている。 見事な対比をしていて、残念な事例でソニー、一方サイロ化(タコツボ化)せずにうまくいった事例でアップルをあげ、デジタル音楽配信サービスの攻防で説明をしている。"
Posted by
・クリーブランド・クリニックの脳神経センター長のモディック「自分たちの事業モデルを広めるためのコンサルティング事業を手がけたらどうかという話が出たが、すぐにばかげたアイデアだと一蹴されてしまった。われわれのシステムをカネで買ったところでサイロを破壊することはできない。システムは自...
・クリーブランド・クリニックの脳神経センター長のモディック「自分たちの事業モデルを広めるためのコンサルティング事業を手がけたらどうかという話が出たが、すぐにばかげたアイデアだと一蹴されてしまった。われわれのシステムをカネで買ったところでサイロを破壊することはできない。システムは自ら作らなければ意味がない。新しいシステムを構築するプロセスやそれについての議論することを通じて、組織は変わっていくのだ」 ・組織はほとんどの人が得意分野の異なるスペシャリストであっていい。しかし、大規模な組織には、10%ぐらいは複数の専門領域に通じた翻訳家が必要だ
Posted by
組織が肥大化してくると、縦割りになり壁ができる。横の組織とは協力しなくなる。失敗例と結論付けられないが、ソニーが取り上げられている。
Posted by
高度に複雑化した社会に対応するため組織が専門家たちの縦割りの「サイロ」になり、その結果変化に対応できない。その逆説を「サイロ・エフェクト」という。 文化人類学者から転じたフィナンシャルタイムズアメリカ版編集長が「インサイダー兼アウトサイダー」の視点で、「サイロ・エフェクト」を描き...
高度に複雑化した社会に対応するため組織が専門家たちの縦割りの「サイロ」になり、その結果変化に対応できない。その逆説を「サイロ・エフェクト」という。 文化人類学者から転じたフィナンシャルタイムズアメリカ版編集長が「インサイダー兼アウトサイダー」の視点で、「サイロ・エフェクト」を描き出す。 ソニー、UBS銀行、シカゴ警察、フェイスブックなど、事例も面白かった。 「『構造主義』と呼ばれるその理論は、人間の脳は二項対立を特徴とするパターンにもとづいて情報を整理しようとする傾向があり、そうしたパターンは神話や宗教儀式といった文化的慣習によって表現され、強化されるという考えを示している。」 ブルデュー五つの理論 「第一にブルデューは、人間社会はある種の思考パターンや分類システムを生み出す、と考えた。… 第二に、こうしたパターンはエリート層の地位の再生産を助長すると考えた。… 第三に、こうした文化的およびメンタルマップはエリート層を含めて誰かが意図的につくりだすもの、あるいは意識的な企ての産物ではない、とブルデューは考えた。… 第四に、社会のメンタルマップで本当に重要なのは、公にかつ明白に語られていることだけでなく、語られていないことである。… ブルデューの著作が暗示している重要な五つ目の点は、人は必ずしも自らが受け継いだメンタルマップにとらわれる必要はないということだ。」 「『ジョブズはアップルを半独立的な部門に分けようとはしなかった。すべてのチームを厳格に管理し、全体として一体感と柔軟性のある会社として機能するよう促し、損益も一元管理した。』と、ジョブズの伝記作家であるウォルター・アイザックソンは書いている。ジョブズの後継者となったティム・クックも書いている。『アップルには独自の損益責任を持つ『事業部』は存在しない。会社全体で一つの損益があるだけだ』」 「リスクを嫌う、分別ある金融機関であることを自任していたUBSの人々は、こうした状況にかなり神経質になっていた。1998年にスイス・ユニオン銀行はヘッジファンド、LTCMへの投資の失敗で手痛い損失を被っていた。UBSの経営陣は、同じような過ちは犯すまいと心に誓っていた。」 「建前上UBSでは、3000人ものリスク担当者が銀行の活動を全体的な視点から監視していることになっていた。しかしリスク担当者は三つのグループに分かれて働いており、それぞれ異なるタイプのリスクを追いかけていた。グループ間の交流はあまりなく、情報交換もしなかった。」 「人間にとって最適な社会集団の規模は150人前後である、というのがダンバーの結論だった。150人までなら人間の脳は社会的グルーミングを通じて緊密な絆を維持できるが、それ以上は無理だから、と。集団がそれ以上の規模になると、直接的交流や社会的グルーミングを通じてつながりを維持することができなくなり、強制あるいは官僚機構に頼るしかなくなる。」 「要するにフェイスブックの経営陣は、ブートキャンプを通じて二つの目的を両立させようとしていたのだ。一つ目は社内を担当作業に応じた個別のプロジェクトチームや専門グループに分けることだ。… 一方ブートキャンプの二つ目の目的は、こうした個別のプロジェクトチームの公式な境界を越える、非公式な二つ目の社会的絆を取り結ぶことだ。それによってプロジェクトチームが内向きの硬直的な集団になるのを防ぎ、社員が自らの所属する小さなグループではなく会社全体に帰属意識を持つようにするのが狙いだ。」 「一つ目の教訓は、フェイスブックがしたように、大規模な組織においては部門の境界を柔軟で流動的にしておくのが好ましいということだ。… 二つ目の教訓は、組織は報酬制度やインセンティブについて熟慮すべきだということだ。… 三つ目の教訓は、情報の流れも重要であるということだ。UBSやソニーの例からは、各部門が情報を抱え込むととてつもないリスクが蓄積される可能性があるのがわかる。これに対する一つの解は、全員がより多くのデータを共有するようにすることであり、現代のコンピューティング技術をもってすればそれは容易に実現できる。… 四つ目の教訓は、組織が世界を整理するのに使っている分類法を定期的に見直すことができれば、願わくは代替的な分類システムを試すことができれば、大きな見返りがあるということだ。… 五つ目の教訓は、サイロを打破するにはハイテクを活用するのも、有効である、ということだ。」
Posted by
以前、会社の幹部が紹介していたため読んでみました。 サイロ(縦割り)化してしまった企業の様々な実例、逆にサイロ化しないように取り組んできたスタートアップ企業などを紹介しており、大変分かりやすく、興味深く読むことができました。 警察、役所、ソニー、フェイスブックの話、サブプライ...
以前、会社の幹部が紹介していたため読んでみました。 サイロ(縦割り)化してしまった企業の様々な実例、逆にサイロ化しないように取り組んできたスタートアップ企業などを紹介しており、大変分かりやすく、興味深く読むことができました。 警察、役所、ソニー、フェイスブックの話、サブプライムローン問題の顛末、などなど。 問題はどうやってサイロ化しないような視点に立つかですが、分かっていてもこれが難しいのです・・・
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
人類学の観点からみると、人間は自ら特定の環境(サイロ)に属そうとし、それ以外の環境に違和感を感じるようにすらなる。企業においてサイロが発生するのは、その意味で当然の傾向である。 本書では、ソニー、政府機関、金融業界などサイロが発生し事業に悪影響を与えた事例や、サイロを壊すための取組も紹介されている。主張されている内容には納得できる。
Posted by