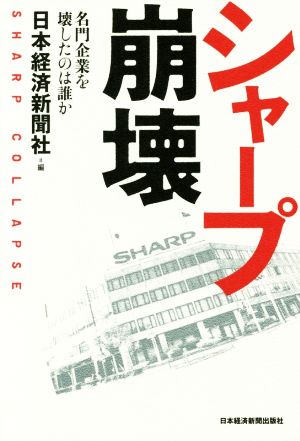シャープ崩壊 の商品レビュー
内部の派閥争いや意思決定のミスによってシャープがどう崩壊していったのか。について時系列で記述している。 特に片山社長から高橋社長について、社長を軸に語られている。 意思決定バイアスが会社に悪影響を及ぼした事例
Posted by
会社は誰のものかということを、考えさせられる本。 少なくとも、権力争いは良くないですね。 われのこととし、日々改めよう。
Posted by
シャープが液晶への大型投資を始めるのは2000年代前半である。2004年1月に亀山第一工場が稼働する。続けて2006年8月には亀山第二工場を稼働させる。大型投資は、これで終わらず、2009年10月には堺工場を稼働させる。 この投資は、はじめはうまくいった。亀山第一工場稼働前の20...
シャープが液晶への大型投資を始めるのは2000年代前半である。2004年1月に亀山第一工場が稼働する。続けて2006年8月には亀山第二工場を稼働させる。大型投資は、これで終わらず、2009年10月には堺工場を稼働させる。 この投資は、はじめはうまくいった。亀山第一工場稼働前の2003年度のシャープの連結営業利益は、1,217億円。それが、以降、1,510億円、1,637億円、1,865億円、1,837億円と成長していく。ところが、液晶の需要が落ち込んでいった、2011年度の営業利益はマイナス376億円、12年度はマイナス1,463億円。2013年度は一息つくが、14年度はマイナス481億円、15年度はマイナス1,620億円と落ち込んでいく。その後、シャープは台湾資本の鴻海に買収されてしまう。 「亀山ブランド」として、日本国内に製造拠点をつくり、液晶技術を囲い込み、台湾・韓国勢に打ち勝っていくという、シャープの液晶事業の戦略はうまくいかなかった、ということである。 ただ、本書は、この戦略がうまくいかなかった原因は突き詰めて分析していない。むしろ、経営陣の内紛を描き、シャープがこのように凋落したのは、液晶に関する戦略的判断の間違いと同時に、経営陣が一枚岩になれなかったためである、としている。それはそれで正しい分析であろうが、もう少し戦略分析の部分を詳しく読みたかった。
Posted by
保身、メンツ、自己正当化などドロドロに渦巻く大企業の凋落ぶりが見てとれる。 何を大切にどこを向いて仕事をするかを見誤ると、シャープのような豪華客船でも沈みゆくことがよく判った。 結果として鴻海に買ってもらって良かったのだと思う。
Posted by
ブックオフで買って積んでた本。読み始めたら一気に読めました。ちょうどシャープが液晶で席巻していた時代も、その後の凋落も見ていたため、裏側でこんなことがあったのか…と思いながら読みました。一時期はマンUのユニフォームのメインスポンサーはってたはずなのに…結局は、読み間違いということ...
ブックオフで買って積んでた本。読み始めたら一気に読めました。ちょうどシャープが液晶で席巻していた時代も、その後の凋落も見ていたため、裏側でこんなことがあったのか…と思いながら読みました。一時期はマンUのユニフォームのメインスポンサーはってたはずなのに…結局は、読み間違いということなんだと思いますが、そこには、人事抗争、保身、メンツなどからくる焦りがあったのかと。しかし、日本企業はなかなか世界レベルに到達するのは難しいと感じた本ですね
Posted by
経済誌かなんかの書評で読んで知ってから積読。 2016年にシャープが鴻海に買収された直前まで、シャープの転落の様子を日経の番記者が描く。 大叔父がシャープの電器屋だったし、仕事でも多少絡んだこともあるので、比較的好きな家電メーカーではあったシャープ。でも、書かれている内容はまるで...
経済誌かなんかの書評で読んで知ってから積読。 2016年にシャープが鴻海に買収された直前まで、シャープの転落の様子を日経の番記者が描く。 大叔父がシャープの電器屋だったし、仕事でも多少絡んだこともあるので、比較的好きな家電メーカーではあったシャープ。でも、書かれている内容はまるで日曜劇場のドラマに出てくるようなドロドロ話。こりゃダメだな。 途中出てくるJDIや東芝が今でも迷走しているのを見ると、鴻海に買われてよかったんだろうなと思う。確かに日本人としては微妙な気もするけど、海外で仕事をしている身からすると、資本の国籍で今更選り好みしてもって気もするし。
Posted by
創業者が去り、創業期を知るメンバーが去り、生え抜きのサラリーマン経営者達がトップに着き、自らの虚栄心を目的とした近視眼的な施策を続けた結果、崩壊した。ありふれた事柄だが、これが大きな規模で起こったというのが本書を読んだ印象だ。 持論だが、世間で最盛期と思われる施策は衰退を招くも...
創業者が去り、創業期を知るメンバーが去り、生え抜きのサラリーマン経営者達がトップに着き、自らの虚栄心を目的とした近視眼的な施策を続けた結果、崩壊した。ありふれた事柄だが、これが大きな規模で起こったというのが本書を読んだ印象だ。 持論だが、世間で最盛期と思われる施策は衰退を招くものが多いと思う。 「液晶のシャープ」しか知らない世代であるし、それ故に「強いシャープ」のイメージが強く、当時の凋落に際しては「まさか…」としか思えなかったが、少しだけ謎が解けたように思う(本書の内容が正しいかは分からないが)。 積読本だったが一気に読んでしまった。
Posted by
人事抗争をメインに書かれていますが、やはり巨額の投資が本質と思います。一度狂った歯車を修正することの難しさを、ひしひしと感じました。
Posted by
今更ながら読了。 権力争いというところを基盤に敷いているが、 むしろ途中で自浄作用が働かなかった点に問題がある気もする。 まぁ投資の失敗は命取りだよなぁと、しみじみ。
Posted by
「東芝の悲劇」と同様、会社にとって経営トップの誤りがいかに酷い影響を与えるかがよくわかる。 自身が育てた液晶事業が生んだ「AQUOS」のヒットで、念願の企業ブランドを手に入れた片山社長が、その液晶事業への過剰投資で会社を傾ける原因を作ったのは皮肉である。 創業者と二代目社長の...
「東芝の悲劇」と同様、会社にとって経営トップの誤りがいかに酷い影響を与えるかがよくわかる。 自身が育てた液晶事業が生んだ「AQUOS」のヒットで、念願の企業ブランドを手に入れた片山社長が、その液晶事業への過剰投資で会社を傾ける原因を作ったのは皮肉である。 創業者と二代目社長の「社員を大切にし」「身の丈に合った」経営が続いていたら、ここまでの失敗はなかったのかもしれないが、かといって大規模な投資と迅速な判断が要求されるバクチのような家電・半導体業界の経営環境でそれが許されたかどうかはわからない(少なくともマスゴミの受けは悪そうだ)。 凋落の原因には、南鮮の技術窃盗、鳩山の円高放置といった環境もあるが、少し業績が良くなると調子に乗って、取引先や下請けに尊大な態度を取ったという社風も無視できないだろう。 経営理念の「言葉」は伝えることができても、理念そのものは伝えられないという指摘が面白かった。 他山の石として慢心の怖さを肝に銘じておきたい。
Posted by