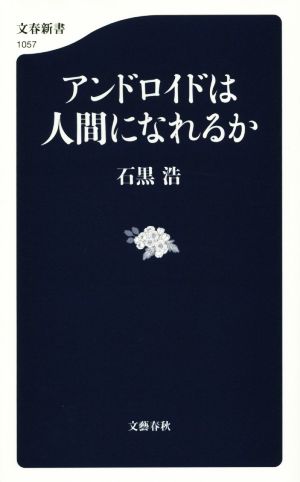アンドロイドは人間になれるか の商品レビュー
特に亡くなった人を墓ではなくアンドロイドにして遺すと言う話が面白かった。 確かに形式化した墓参りよりも亡くなった両親に自分の近況を報告しに行くような状況、そしてそれに生きていた時のように応えてくれる両親のアンドロイドという構図はとてもいいなと思ってしまった。 考えること、をやめな...
特に亡くなった人を墓ではなくアンドロイドにして遺すと言う話が面白かった。 確かに形式化した墓参りよりも亡くなった両親に自分の近況を報告しに行くような状況、そしてそれに生きていた時のように応えてくれる両親のアンドロイドという構図はとてもいいなと思ってしまった。 考えること、をやめない限り人間としての価値を残せるのは、間違いないと感じるし、今後も考えることのできる人間になりない。
Posted by
著者がいう「ロボット作製とは人間とは何か、心とは何かを探求すること」という意味が良く分かりました。人は自分の外に「心、気持ち」を感じるんですね。二つの知覚の組み合わせで「わかった」という気分になるとのこと。ロボットに対する方が人間は素直になれる、という事実。人間が生み出した技術を...
著者がいう「ロボット作製とは人間とは何か、心とは何かを探求すること」という意味が良く分かりました。人は自分の外に「心、気持ち」を感じるんですね。二つの知覚の組み合わせで「わかった」という気分になるとのこと。ロボットに対する方が人間は素直になれる、という事実。人間が生み出した技術を外部化して突き詰めていったのがロボット。であれば人間とロボットとの境目はない。何故石黒さんが話題の人になっているか、理解できました。更に先を知りたくなりました。
Posted by
著者は阪大の先生らしい。僕もオーケストラの方で阪大とは縁があるので勝手に親近感笑。たまたま友達に貸してもらった本だったのだけどめっちゃ面白かった。ロボット、アンドロイドをどのように作っていくかの紹介と同時に、アンドロイドがこれから果たすであろう社会的な役割、人間の心とは何か?とい...
著者は阪大の先生らしい。僕もオーケストラの方で阪大とは縁があるので勝手に親近感笑。たまたま友達に貸してもらった本だったのだけどめっちゃ面白かった。ロボット、アンドロイドをどのように作っていくかの紹介と同時に、アンドロイドがこれから果たすであろう社会的な役割、人間の心とは何か?という所まで話を広げていて刺激になった。シンギュラリティが来てアンドロイドが人間の能力を凌駕すると嫌悪感を感じるみたいだけど、「何となく嫌」ではなくて何故そう感じるのか、本当に嫌なことなのか?と理詰めでどんどん切り込んでいくスタイルはさすが研究者だと思った。タブーとされていてみんなの中で暗黙のうちに、曖昧に把握している世界にズバっと踏み込んでいける姿勢は真似したいなぁ。僕も肉体がもう一つあって、頭脳もついていけるならこんな研究してみたいなぁ...。
Posted by
読み始めるまであの、イシグロイドやマツコロイドを作った石黒さんによる本だということに気付いていなかった。 さすが石黒さん、こんなこと考えながらロボットやアンドロイドを作っているんだなあ。少し前に読んだAIは心を持てるか、という本よりだいぶ分かりやすい。言ってることはわりとラディカ...
読み始めるまであの、イシグロイドやマツコロイドを作った石黒さんによる本だということに気付いていなかった。 さすが石黒さん、こんなこと考えながらロボットやアンドロイドを作っているんだなあ。少し前に読んだAIは心を持てるか、という本よりだいぶ分かりやすい。言ってることはわりとラディカルだけど。 石黒さんの思い描く社会が早く実現するといいな。楽しそうだ。
Posted by
図書館でふと気になっで読んでみた。脳科学的なアンドロイドの有用性が述べられていて面白い。石黒先生的な人生や科学に対する哲学も興味深い。
Posted by
アンドロイドロボット研究の第1人者である石黒先生がご自身のロボット研究について語っている。 石黒先生のことは知っていたが、本を読んだのは初めて。 一言一言がかなり強烈だが、うなづける。 先生の考えが、途中でカギかっこでくくられてバーンと訴えかけてくる。 「人の気持ちを考える」とい...
アンドロイドロボット研究の第1人者である石黒先生がご自身のロボット研究について語っている。 石黒先生のことは知っていたが、本を読んだのは初めて。 一言一言がかなり強烈だが、うなづける。 先生の考えが、途中でカギかっこでくくられてバーンと訴えかけてくる。 「人の気持ちを考える」という言葉を理解するためにロボット研究をしている、という。ロボット研究にのめりこめばのめりこむほど、ロボットではなく「人間」とはどのような存在なのかを考えずにはいられない、という。 ロボットの研究は哲学なのだ、という言葉にとても納得がいった。
Posted by
ペッパーくんが20万ほど(月額使用料を入れると約120万)で手に入る現在。 ロボットが身近にいる時代がもう来てます。 個人的には近い将来ロペットが「コンバインOKコンバインOK」って言うてる時代が来るように思います(笑) 「技術への偏見は時間と共に解消する」 これは至言やと思い...
ペッパーくんが20万ほど(月額使用料を入れると約120万)で手に入る現在。 ロボットが身近にいる時代がもう来てます。 個人的には近い将来ロペットが「コンバインOKコンバインOK」って言うてる時代が来るように思います(笑) 「技術への偏見は時間と共に解消する」 これは至言やと思います。 いかにテクノフォビア(科学技術恐怖症)の人であっても便利さには勝てないんやと思います。 おそらくマイナンバーも過渡期でこれからの少子高齢化で労働力不足問題に直面する中において手作業で名寄せしたり突合させたりするのが正義という人は減ってくるんやと思います。 AI時代になったらますますブラックボックス化が進んで誰もその結果に説明をつけることが出来ない時代が来るんですから。 そういった意味でも今こそ正しい科学技術に対する理解を深めて隣にいるテクノフォビアな人たちに説明することが必要なんやろなあと思います。
Posted by
「人の気持ちを考える」ことへの著者の幼い頃からの疑問から始まる。アンドロイド、ロボットの技術的な話ではなく、哲学的な話であったり、相手が人間であるよりもロボットのほうが心を許して接しやすくなることが中心。
Posted by
以前、NHKのSWITCHインタビューや「最後の授業」という番組で とても面白く興味深かった石黒さん。 「最後の授業」に内容が通じていて、語りを文章にまとめた形で読みやすい。 本人の持つ雰囲気、ユーモアのセンスが、この本の中からもうかがえる。 人の気持ち、感情という曖昧なものを突...
以前、NHKのSWITCHインタビューや「最後の授業」という番組で とても面白く興味深かった石黒さん。 「最後の授業」に内容が通じていて、語りを文章にまとめた形で読みやすい。 本人の持つ雰囲気、ユーモアのセンスが、この本の中からもうかがえる。 人の気持ち、感情という曖昧なものを突き詰めていくと、 プログラミング可能な範囲がどんどん広がっていく。 結局「自分」は「他人の目」によってしか規定されない。 「自分」だと思っているものも、 もともとは他者をまねて覚えたものなのだ。 仕草や間(ま)などを覚えさせることで、 見る側もロボットであることを越えて、親しみを感じることができる。 対人の生々しさの無さが、より気持ちを近くし、引き出しやすくなる。 何度でも同じ動きを、倦まず繰り返すロボットだからこそできる 丁寧で継続的な教育や指導や仕事の可能性。 逆に人間のピークのときのパフォーマンス(芸術や技能など)を残し、 その人が亡くなってからも後世に伝えていくことの可能性。 また、ロボットだからと、信頼しているからこそ起こってくるであろう弊害に どう対応していくべきかを、早くから準備しておく必要があること。 ロボットを作る人、仕組みに立ち入って使える人と、 ただ使う人の間での格差は、より一層大きくなっていく。 それは今の、PCからスマホに移り、 誰にでも簡単に使えるようになった情報端末における格差よりも なお大きくなるだろう。 番組「最後の授業」では、 人間がいなくなった後の、 ロボット(アンドロイド)だけになった世界についても触れていたが それこそが、いずれ来るかもしれない外部の生命体に対し、 当時の世界の姿を残し、伝える手段になるというくだりにはゾクゾクした。 人間を考えアンドロイドを考えまた人間を考える。 石黒さんの仕事の可能性と挑戦の今後が気になる。
Posted by
【由来】 ・図書館の新書アラート 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・「マツコとマツコ」で全国的にブレイクした感のある石黒...
【由来】 ・図書館の新書アラート 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・「マツコとマツコ」で全国的にブレイクした感のある石黒ハカセ。ロボットを作っていく過程でのブレイク・スルーが「心は捉える側の問題」。そこから、モダリティを抽出してから具体に還元していく。それも二つで十分。例えば触覚と匂いだとか。 【目次】
Posted by