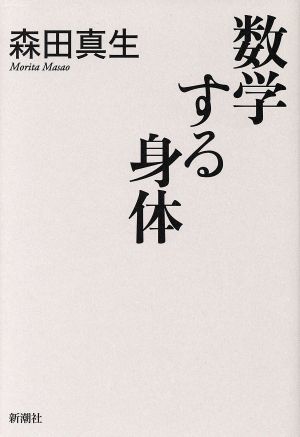数学する身体 の商品レビュー
岡潔や芭蕉、禅の本を読みたくなった。 何かを突き詰めて行くと、同じようなところにたどり着くのだろうか。 俳句であっても、数学であっても、料理であっても、重ね煮クラッカーであっても。 ・学びとは、はじめから自分の手許にあるものを掴み取ることである、とハイデッガーは言う。同様に、...
岡潔や芭蕉、禅の本を読みたくなった。 何かを突き詰めて行くと、同じようなところにたどり着くのだろうか。 俳句であっても、数学であっても、料理であっても、重ね煮クラッカーであっても。 ・学びとは、はじめから自分の手許にあるものを掴み取ることである、とハイデッガーは言う。同様に、教えることもまた、単に何かを与えることではない。教えることは、相手がはじめから持っているものを、自分自身で掴み取るように導くことだ。 ・動くことは考えることに似ている。 ・その人とはその人の過去のことである。 ・「わかる」という経験は、脳の中、あるいは肉体の内よりもはるかに広い場所で生起する。 ・「自分の」という限定を消すことこそが、本当に何かを「わかる」ための条件ですらある。 ・「無心」から「有心」に還る。その刹那に「わかる」。 ・自我を薄め、情緒を清め、深めなさい。
Posted by
485 森田真生(モリタ・マサオ) 1985年、東京都生まれ。独立研究者。東京大学理学部数学科を卒業後、独立。 現在は京都に拠点を構え、在野で研究活動を続ける傍ら、全国各地で「数学の演奏会」や「大人のための数学講座」など、ライブ活動を行っている。 たとえば、「虚数」と呼ばれる...
485 森田真生(モリタ・マサオ) 1985年、東京都生まれ。独立研究者。東京大学理学部数学科を卒業後、独立。 現在は京都に拠点を構え、在野で研究活動を続ける傍ら、全国各地で「数学の演奏会」や「大人のための数学講座」など、ライブ活動を行っている。 たとえば、「虚数」と呼ばれる数がある。虚数とは、2乗すると1になる数のことだ が、普通に考えると「意味」がよくわからない。どんな数も2乗すると0以上になるの ではないか。2乗したらマイナスになる数など、いったいどこに存在するというのだろうか。わかる、わからないにかかわらず、数式を変形していると、虚数が出てきてしまうことがある。「わからない」のはあくまでこちらの話で、数式の方は平気でそ の存在を主張してくる。 記号を使うとしばしばこういうことが起こる。計算をしているうちに意味の分からないものが出てきてしまうのだ。作図を使った推論の過程では、思考と意味が並走しているが、数式を計算していると、意味が置いてけぼりを食うことがある。それでも意味が あとから追いつくならば、問題ないのである。 実際、いまでは√-1の「存在」を疑う数学者はいないだろう。「虚数」という不名誉な呼ばれ方をしているが、その存在を抜きにしては現代数学は成り立たない。はじめは 直観を裏切る対象でも、使っているうちに次第に存在感を帯び、意味とその有用性がわかるようになってくる。そうして少しずつ、数学世界が広がっていく。 私はその日手にした『日本のこころ』を、夢中になって読んだ。そこには今まで知ら なかった広大な世界が開けているように思われた。それでいて、どこか懐かしく知っている世界のような、不思議な感覚に包まれた。そこには狭い数学を超えて、生きること、あるいは「わかる」ことについて、全身の実感のこもった言葉が並んでいたのだ。 岡潔の言葉を読んでいると、なぜか不思議と、バスケに捧げた日々を思い出した。こ の人にとって数学は、全心身を挙げた行為なのだと思った。頭で理屈を捏ねることでも、 小手先の計算を振り回すことでもなく、生命を集注して数学的思考の「流れ」になりきることに、この人は無上の喜びを感じていることが伝わってきた。 私は、岡潔のことをもっと知りたいと思った。彼が見つめる先に、自分が本当に知りたい何かがあるのではないかとも思った。簡単に言えば、「この人の言葉は信用できる」 と直観したのだ。 数学と身体を巡る私の旅も、ここから始まったのである。岡潔の語る数学は、それまで私が知っていたものとはまったく違った。そこには、生きた身体の響きがあった。 「数学」と「身体」――とてつもなくかけ離れて見えるこの二つの世界が、実はどこか深くで交わっているのではないか。その交わる場所を、この目で確かめたいと思った。 ならば、数学の道へ分け入るしかない。私は、数学を学ぶ決心をした。 およそ十年前に岡潔の『日本のこころ』に出会って以来、私は何度も何度も、頁が擦 り切れるくらい、この本を読み返してきた。不思議なことに、その度に新しい発見があり、毎回違った箇所に線を引いている。文章の方は動いていないはずだから、変わってるのはこちらの方なのだろうが、まるで生き物のように、同じ言葉が何度し味を帯びて蘇ってくるのだ。実感に裏打ちされた言葉の底力である。
Posted by
「数学する身体」森田真生著、新潮社、2015.10.15 206p ¥1,728 C0095 (2023.03.19読了)(2023.03.17借入)(2016.12.25/10刷) 新聞のコラムで紹介されていたので、読んでみることにしました。 ちょっと変わった数学史の本というと...
「数学する身体」森田真生著、新潮社、2015.10.15 206p ¥1,728 C0095 (2023.03.19読了)(2023.03.17借入)(2016.12.25/10刷) 新聞のコラムで紹介されていたので、読んでみることにしました。 ちょっと変わった数学史の本というところでしょうか。 数学は、人間の心と体に制限されて作られている、ということのようです。 たとえば、漢数字の一、二、三やローマ数字のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、等は、三個までは、ひと目で認識できるので数をあらわすのにもそのまま使われている、ということです。 後半の方では、アラン・チューリングや岡潔が取り上げられています。 著者は、大学では文系に属していたけれど、岡潔の『日本のこころ』という文庫本に出合って、理系に鞍替えし、数学の勉強を始めたのだそうです。 ●学校で教わる数学(49頁) 私たちが学校で教わる数学の大部分は、古代の数学でもなければ現代の数学でもなく近代の西欧数学なのである。 【目次】 はじめに 第一章 数学する身体 人工物としての〝数〟 道具の生態系 形や大きさ よく見る 手許にあるものを掴みとる 脳から漏れ出す 行為としての数学 数学の中に住まう 天命を反転する 第二章 計算する機械 I 証明の原風景 証明を支える「認識の道具」 対話としての証明 II 記号の発見 アルジャブル 記号化する代数 普遍性の希求 「無限」の世界へ 「意味」を超える 「基礎」の不安 「数学」を数学する III 計算する機械 心と機械 計算する数 暗号解読 計算する機械の誕生 「人工知能」へ イミテーション・ゲーム 解ける問題と解けない問題 第三章 風景の始原 紀見峠へ 数学者、岡潔 少年と蝶 風景の始原 魔術化された世界 不都合な脳 脳の外へ 「わかる」ということ 第四章 零の場所 パリでの日々 精神の系図 峻険なる山岳地帯 出離の道 零の場所 「情」と「情緒」 晩年の夢 情緒の彩り 終章 生成する風景 あとがき 註と参考文献 ☆関連図書(既読) 「春宵十話」岡潔著、毎日新聞社、1963.02.01 「岡潔 数学の詩人」高瀬正仁著、岩波新書、2008.10.21 「精神指導の規則」デカルト著・野田又夫訳、岩波文庫、1950.08.10 「方法序説」デカルト著・小場瀬卓三訳、角川文庫、1963.11.10 「近世数学史談 3版」高木貞治著、共立全書、1970.10.20 (アマゾンより) 思考の道具として身体から生まれた数学。 ものを数える手足の指、記号や計算…… 道具の変遷は数学者の行為を変え、記号化の徹底は抽象化を究めていく。 コンピュータや人工知能の誕生で、人間の思考は変貌を遂げるのか? 論考はチューリング、岡潔を経て生成していく。 身体を離れ、高度な抽象化の果てにある、新たな可能性を探る。
Posted by
岡潔、アランチューリングなどが数学とどのように向き合っていたのか、数学において、どのような心のあり方、働き方がなされるのか、といった数学の根本と哲学の関係性について語っている。 岡潔が百姓をしながら数学を研究していたこと、宗教を信ずるようになり、念仏を唱えるようになった後に、人生...
岡潔、アランチューリングなどが数学とどのように向き合っていたのか、数学において、どのような心のあり方、働き方がなされるのか、といった数学の根本と哲学の関係性について語っている。 岡潔が百姓をしながら数学を研究していたこと、宗教を信ずるようになり、念仏を唱えるようになった後に、人生第三、かつ最大の発見をしたことが印象に残る。不定域イデアルを発見したのが岡で、後に層という概念となる。 チューリングについても、数理論理学から人工知能に興味を持ち、ひとの心を解き明かそうとしたことは興味深い。 筆者の文才によって、簡潔かつ情感豊かに数学や哲学の深層を垣間見ることが出来た。筆者開催のセミナーなどにも興味がある。 もう一度数学をしてみたいと思わせる。
Posted by
面白かった。 人間が「数学」という道具を原始の時代から現代まで如何にして進化させてきたかを解説しながら、それは「数学」を使用する人間の知性・心の歴史でもあるという。 私では分からない所も沢山あったけど、面白さはちっとも減じていない。 研究者さんというのは、ずーっと、既知ではなく...
面白かった。 人間が「数学」という道具を原始の時代から現代まで如何にして進化させてきたかを解説しながら、それは「数学」を使用する人間の知性・心の歴史でもあるという。 私では分からない所も沢山あったけど、面白さはちっとも減じていない。 研究者さんというのは、ずーっと、既知ではなく未知に向き合うので、なんだか非常に自分より大きなものの存在を信じていて敬虔な感じがする。
Posted by
「身体が数学をする」。 これは、哲学の本ですね、「わかる」ということ、数学的思考は、非記号的な身体レベルで行われているなどなど、瞠目する言葉に溢れた本でした。 何度も読み直していきたい。
Posted by
数学を身体との関連から捉えざっくり数学の流れを紹介し,チューリングと岡潔について語る.どちらも数学と「心」のあり方に注目しその解明に向かったことやアプローチの仕方が違ったことなど,それぞれ興味深かった.岡潔さんの数学理論は難しいでしょうが,エッセーなど読みたいです.
Posted by
☆肩書がいい。「独立研究者」。どうも、岡潔を見習っているようだ。 ☆この本を読むと、大学生の頃を思い出す。足し算の意味が急にわからなくなったり、無限を実在のものと扱うために、東洋の数学をつくるべきだと思ったり。 (参考) アンディ・クラーク 『現れる存在』 県立、エニグマ アラン...
☆肩書がいい。「独立研究者」。どうも、岡潔を見習っているようだ。 ☆この本を読むと、大学生の頃を思い出す。足し算の意味が急にわからなくなったり、無限を実在のものと扱うために、東洋の数学をつくるべきだと思ったり。 (参考) アンディ・クラーク 『現れる存在』 県立、エニグマ アラン・チューリング伝 県立 市立、岡潔集、評伝岡潔 県立 大学、岡潔数学の詩人 県立 青森 市立 大学、『荒川修作の軌跡と奇跡』 県立、数覚とは何か? 県立 青森 市立、『ライプニッツ普遍数学の夢』、チューリングを読む 市立、吉田ほか 数学序説 青森 大学
Posted by
うまく言えないけど、脳だけじゃなく、身体、取り巻く環境ひっくるめて、思考という行為が成り立つ、という冒頭は興味を惹かれた。チューリングの人工知能の話と、岡潔の話を対比すると、こないだ読んだ「ホモデウス」の人工知能への見解へのカウンターパンチとなる気がして、希望が持てたのも得した気...
うまく言えないけど、脳だけじゃなく、身体、取り巻く環境ひっくるめて、思考という行為が成り立つ、という冒頭は興味を惹かれた。チューリングの人工知能の話と、岡潔の話を対比すると、こないだ読んだ「ホモデウス」の人工知能への見解へのカウンターパンチとなる気がして、希望が持てたのも得した気分。しかし、数学でもなんでも、突き詰めると哲学的というから、人間って、って考えにいきつくのは、おもしろいなとあらためて思う。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
普通、船や潜水艦にとって海水はあくまで克服すべき障害物である。ところが、マグロは周囲の水を、泳ぐという行為を実現するためのリソースとして積極的に生かしている、というわけだ。 示唆に富む話である。周囲の環境と対立し、それを克服すべきものと捉えるのではなく、むしろ環境を問題解決のためのリソースとして積極的に行為の中に組み込んでいく。マグロにとっての周囲の水の流れは、運動のためのリソースであって、障害ではない。(p.38) 数学が人の心を惹きつけてやまないのも、それが、解けるか解けないか、あらかじめ判定できないような「パズル」に満ちているからである。(中略)チューリングあ、いかなる難問を前にしても、常に「解ける」方に賭けて挑み続けたことだけは確かだ。不安の中に、すなわち間違う可能性の中にこそ「心」があると、彼は誰よりも深く知り抜いていたからである。(p.110) 岡潔によれば、数学の中心にあるのは「情緒」だという。計算や論理は数学の本体ではなくて、肝心なことは、五感で触れることのできない数学的対象に、関心を集め続けてやめないことだという。自他の別も、時空の枠すらをも超えて、大きな心で数学に没頭しているうちに、「内外二重の窓がともに開け放たれることになって、『清冷の外気』が室内にはいる」のだと、彼は独特の表現で、数学の喜びを描写する。(p.116) たとえば「2」という数字を思い浮かべてみる。それは個々人の前に広がる「風景」の中で、何かしらの実感を帯びた対象として現れるだろう。私たちは、純粋に主観の排除された「2」そのものを経験することなどできない。あらゆる数学的対象は、「風景」の中に立ち現れるのだ。(p.127) 生きた自然の一片をとらえてそれをそのまま五七五の句形に結晶させるということに関して、芭蕉の存在そのもの以上に優れた「計算手続き」はない。水滴の正確な運動が、水を実際に流してみることによってしかわからないのと同じように、芭蕉の句は、芭蕉の境地において、芭蕉の生涯が生きられることによってのみ導出可能な何かである。 数学もまた、同じように進むことはできないだろうか。数学的自然の一片をとらえて、その「光いまだ消えざるうちにいいとむ」には、数学者もまた、それ相応の境地にいる必要がある。境地が進まなければ読めない句があるのと同じように、境地が進まなければできない数学があるだろう。「第三の発見」において、岡はそれを身をもって経験したのだ。(p.160) 西欧世界で生まれた近代数学は、記号と計算の力を借りて、かってない高見にまで登り詰めた。記号の徹底は、数学の抽象化を進めるとともに、素朴な幾何的・物理的直観に依存しない、機械的な計算や論証を可能にした。 それまで数学を支えていた人間の直感は、曖昧で間違えやすいものとして不安視されて、数学から身体をそぎ落としていくかのように、数学の形式化が進んだ。数学を、機械でも実行できるような記号操作の体系に還元することが、数学という営みを救う唯一の道だと考える人たちまで出てきた。(pp.186-187)
Posted by