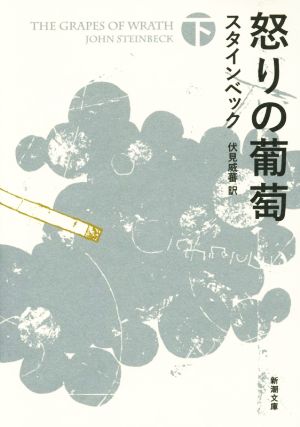怒りの葡萄(下) の商品レビュー
最後まで救いはなく、それでも営みを続けるしかなく、そこで巡る生命の循環。 女性の強さ、生きるために働くこと、団結することの強さと難しさ
Posted by
星2つか5つか迷って、星3つ。正直なところ、少しも面白くなかったが、これに感動できる人になりたい気持ちが捨てきれない。 プロレタリア文学ということで、勝手に労働争議の話だと思い込んでいたため、「いったいいつトムは労組を作るのか」いぶかりながら上巻を読み終わり、どうもそういう話...
星2つか5つか迷って、星3つ。正直なところ、少しも面白くなかったが、これに感動できる人になりたい気持ちが捨てきれない。 プロレタリア文学ということで、勝手に労働争議の話だと思い込んでいたため、「いったいいつトムは労組を作るのか」いぶかりながら上巻を読み終わり、どうもそういう話ではないらしいと思った頃には物語も終盤だった。 出エジプトを下敷きにしているというし、元伝道師が人を救っているし、キリスト教の何かしらが主題なのだろうが、キリスト教に疎いのでさっぱり分からなかった。解説書を読んでから再挑戦したい。 作中のベーコンがおいしそうで、カリカリベーコンにはまってしまった。
Posted by
世界恐慌真っ定中のアメリカをジョード一家と言う人家族に焦点を当てた、苦境を切り抜けようとする情愛深い家族の物語だった。苦境を切り抜けるのに愛と知恵と勇気が大切であるのは、太古からの物語の主題として変わらない。また彼らは常に、家、土地、仕事というアメリカンドリームを追い求め続けた。...
世界恐慌真っ定中のアメリカをジョード一家と言う人家族に焦点を当てた、苦境を切り抜けようとする情愛深い家族の物語だった。苦境を切り抜けるのに愛と知恵と勇気が大切であるのは、太古からの物語の主題として変わらない。また彼らは常に、家、土地、仕事というアメリカンドリームを追い求め続けた。 また働くことの尊さも教えてくれた。 人間に最後に残された確かな機能-働くことを渇望する肉体と、一人の人間の入用を超えて作ることを渇望する頭脳こそが人間である所以なのだと。 とりあえずお母さんと、伝道師ケイシーの紡言葉一つ一つが好きでたまらん!!
Posted by
なんという結末だ! この結末を創造できることがスタインベックという作家であることならば、やはり時代を超えた名作を生み出す力は生半可なことではないと、改めて衝撃を受けた。 上下巻合わせて1000ページ近いこの物語は、20世紀初頭の世界恐慌を背景として、英雄や悪人を描くのではなく...
なんという結末だ! この結末を創造できることがスタインベックという作家であることならば、やはり時代を超えた名作を生み出す力は生半可なことではないと、改めて衝撃を受けた。 上下巻合わせて1000ページ近いこの物語は、20世紀初頭の世界恐慌を背景として、英雄や悪人を描くのではなく「当時の大多数の人々」を題材にした、読みやすい、しかし壮大なドラマ。 ここで登場するいくつもの事柄は、いくつもの連想を呼び起こす。 まずキリスト教的な宗教観、そして当時の政治経済と社会的構造の矛盾、社会主義思想、アメリカという国の成り立ちに係る歴史的因果などなど……。 さらに、 これらが、一国の事情や特別な宗教観とどまらず、世界のどの国や地域にもあてはまり、かつ、過去のことではなく現在そして近い将来に起こりうるとして、恐ろしさすら感じてしまう。 そう……誰でもが「お父」であり「お母」であり「トム」「アル」がいて、その逆も、また敵対する立場にもなりうる。 「シャロンの薔薇」は、希望、不安、後悔、絶望、救済が、常にすぐそばにいることを表す。「ケイシー」は迷い、ボヤキ、沈黙し、叫ぶ……。 そしてこのエンディング! 実に心に余韻を残し、噛みしめることのできる終わり方だ。
Posted by
カリフォルニアの綺麗な白い家で家族で暮らそうと夢見たお母。カリフォルニアに着いてからの日々はそれとはかけ離れていた。フルーツピッキングや綿摘みも季節労働だから仕事が無い時は本当に何もない。それでも食べていかなくてはいけない。妊娠中の家族もいる。そのうち離れてゆく家族もいる。いつだ...
カリフォルニアの綺麗な白い家で家族で暮らそうと夢見たお母。カリフォルニアに着いてからの日々はそれとはかけ離れていた。フルーツピッキングや綿摘みも季節労働だから仕事が無い時は本当に何もない。それでも食べていかなくてはいけない。妊娠中の家族もいる。そのうち離れてゆく家族もいる。いつだって一家の中心で踏ん張るお母が大好きになる。 オクラホマからカリフォルニアまでの自然の描写や家族の結びつきの描写、どれもが目のまえに浮かんで「踏ん張れ!頑張れ!」と思いながら読んだ。
Posted by
この直前にオーウェル「一九八四」、アトウッド「侍女の物語」を読了した所だったので、今回はやっとディストピア路線から逃れられると読み始めたのだが、スタートからのヤバイ予感は的中してしまった。 「一九八四」「侍女の物語」が"社会主義的ディストピア"とすれば、当作品...
この直前にオーウェル「一九八四」、アトウッド「侍女の物語」を読了した所だったので、今回はやっとディストピア路線から逃れられると読み始めたのだが、スタートからのヤバイ予感は的中してしまった。 「一九八四」「侍女の物語」が"社会主義的ディストピア"とすれば、当作品は"資本主義的ディストピア"といえるのかもしれない。 現代的便利さや合理性が、人の気持ちや温もりを踏みにじる装置になりうることも示唆されている。 世界恐慌という時代に否が応でも経済は困窮し、家族は離散し、人としての尊厳すら奪われていく。この困難に敢然と立ち向かう「お母」の姿、心意気が極めて男前で頼もしい。 抜け道のない閉塞感の中、最後は命を慈しむ気持ちでいっぱいになった。
Posted by
昔の文学は婉曲的な表現が多く、時折関係のない話も挟んでくるからどうも苦手だった。 しかし、現時点で制覇したスタインベック作品は信じられないくらいに書き方がストレート。おかげで今回も、難なくストーリーを追うことができた。 世界恐慌の煽りを受けオクラホマの農地を追われたジョード一家...
昔の文学は婉曲的な表現が多く、時折関係のない話も挟んでくるからどうも苦手だった。 しかし、現時点で制覇したスタインベック作品は信じられないくらいに書き方がストレート。おかげで今回も、難なくストーリーを追うことができた。 世界恐慌の煽りを受けオクラホマの農地を追われたジョード一家は、仕事を求めカリフォルニアを目指す。マイル表記ではピンと来なかったので距離を調べたら、何と5州をまたぐ2,800㌔…!(ルート66が完成していたから何とか行けたものの、辛い長旅には変わりなかった…) 物語はジョード一家と、彼らと同じ境遇にいた人々の足取りを交互に追う形式。 果樹園の求人ビラを手に現地へ向かえば、募集人数の倍の人間が同じ職を求めて来ている。自ずと路頭に迷う者が出てくるが、秩序を乱す者たちとして現地住民からは「オーキー」(オクラホマ人のことだが軽蔑的な意味合いが込められている)と蔑まれる。 ジョード一家の涙ぐましい流転生活も辛かったが、一番こたえたのは差別する側の人間(現地住民)の実態だった。 労働者達が州に入るまで、現地住民は何不自由ない生活を送っていたという。しかし労働者達の貧困や怒りを初めて目の当たりにし危機感を覚え、やがて"自衛"へと走る。元々地主でもないのに自分達の土地だと主張し、生活を守るためならと武器まで手にする始末。 先住民を追放した開拓時代とやっていることがさほど変わらない。何なら今なお銃社会であるのも、その頃の排他主義が未だにアメリカ人の潜在意識に根付いているからなのかなって。 「ほんとうに生きている民は、あたしたちなんだ。あいつらが、あたしたちを根絶やしにすることなんかできない」 「旧約聖書の出エジプト記を思わせる一大叙事詩」とあらすじに書いてあった。安住の地を目指す点では確かに共通している。 少し残念なのは出エジプト記のように希望が見えなかったこと。開拓時代色の強い、プロレタリア文学にしか捉えられなかったことだ。 怒りに囚われても働く(=生きる)ことさえ諦めなければ、人としての幸せを手にすることができる。 …と、本書の主題である「働くことの尊さ」を考えてみたが、これじゃない感が強い。これは再考の余地ありだな(-_-;) 高校時代、同じ著者の『ハツカネズミと人間』を読んで見事打ちのめされた記憶がある。 ハッピーエンドやサクセスストーリーから程遠く、幸福や成功を希求するほど遠ざかってしまう。今回の展開や結末にもそれに通じるものがあった。 ただ前回と違う点は、そこまで打ちのめされることなく、一家同様最後まで心に根を張り続けられたところ。本当に、こればかりは誰も根絶やしにできない。
Posted by
20世紀初頭の資本主義の矛盾、世界恐慌「前夜」のアメリカにおける下層階級の悲惨な状況がありありと描かれている。 経済の矛盾、不景気の予兆は下から現れるものなのでしょうか。 ところで、ストーリーから外れるが厚切りのベーコンを焼いてその脂をパンにつけるところが、とても美味しそうで、読...
20世紀初頭の資本主義の矛盾、世界恐慌「前夜」のアメリカにおける下層階級の悲惨な状況がありありと描かれている。 経済の矛盾、不景気の予兆は下から現れるものなのでしょうか。 ところで、ストーリーから外れるが厚切りのベーコンを焼いてその脂をパンにつけるところが、とても美味しそうで、読後厚切りベーコンにハマってしまいました(笑)
Posted by
労働条件や食糧不足に悩まされながらもジョード家が行き延びるために戦う物語。トムが主人公的な立ち位置ではあるが、彼だけでなく、父母、ジョンおじさん、シャロンの薔薇、アルといった複数のキャラクターが均等にフォーカスされ、成長していく。 オクラホマからカリフォルニアまで移動する様は、...
労働条件や食糧不足に悩まされながらもジョード家が行き延びるために戦う物語。トムが主人公的な立ち位置ではあるが、彼だけでなく、父母、ジョンおじさん、シャロンの薔薇、アルといった複数のキャラクターが均等にフォーカスされ、成長していく。 オクラホマからカリフォルニアまで移動する様は、「荒れ野」と言う聖書を連想させるようなワードや、聖書をときどき引用することから、「出エジプト記」に重ねることができる。 もっとカジュアルに例えるならば映画「スタンド・バイ・ミー」にて、子供たちが長い道のりを歩いていく大冒険に似ているとも言えなくない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ノーベル文学賞作家ジョン・スタインベックの名作。土地を追われたジョード一族が、安住の地を求めて移動する物語であるが、行く先先で災難に襲われてしまい、どこまで行っても救いがない。最後には、まさかロザシャーンが死産となってしまうとは。個個の登場人物の心までは荒んでいないことが唯一の明るい要素で、ラスト・シーンもそれを反映したものとなっているし、またまさに「肝っ玉母さん」と呼ぶにふさわしい、「お母」の一本筋が通った堂堂とした生きかたには感動すら覚える。しかしその前向きさが救いようのなさを余計に際立たせており、読者をよりやるせない気持にさせる。さらに絶望的なのは、この物語が決して単なるフィクションでも、この時代に限った話でもないということである。「下層」の人人が大資本に土地を追われ、あるいはいいように扱われるというのは、現在でも世界中で普遍的に見られる現象である。日本においても例外ではなく、たとえば跋扈するブラック企業のことを考えればよくわかるだろう。このような世界を見事に描いているため、現在まで読み継がれていることにも納得である。一方で、このような読み方もできる。主人公たちは「絆」を重んじるなど懸命に生きているが、みんなどこか自己中心的な部分も持ち合わせている。そもそもトムはカリフォルニア州から出ては行けないのに、無視して勝手に移動してしまっている。あれだけ「強い」お母も、このことでは謗りを免れないだろう。このような人物「だからこそ」、こういう目に遭っているという見方もできないか。そして、このような見方こそがまさに、現代社会で「上層」に立つ人間が「下層」にいる人間に向けている視線と同じだろう。これら二つの読み方いずれを取っても今日でも通用するといえ、やはり名作であると強く実感させられる。
Posted by