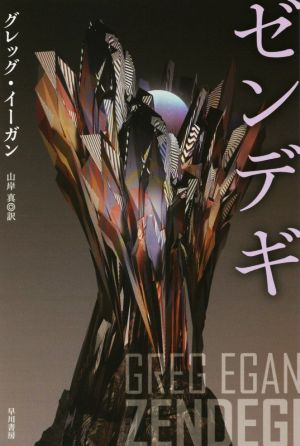ゼンデギ の商品レビュー
これまで自分が読んできたイーガン作品と一味違う感じ。イランといいAIといい、ネタの鮮度は落ちていない
Posted by
みんなが思ってそうなんだけど、私がイーガンに求めているのは、ディアスポラとかのガチガチのハードSFなのだ… 流しながしで読んでいたので、イランの政治の話とかマーティン親子以外の登場人物とゼンデギの仮想空間がどう関連してくるのかいまいち掴めなかった。
Posted by
はじめて読むイーガン長篇。 これまで読んだ作品はすべて短篇。その短篇ですら文系の私にはついていけない作品があって、長篇だったらなおさら大変だろう、読了できないのではないか、という不安から長らく手に取れていませんでした。ところが、本書「ゼンデギ」は長篇ながら”比較的”読みやすい、と...
はじめて読むイーガン長篇。 これまで読んだ作品はすべて短篇。その短篇ですら文系の私にはついていけない作品があって、長篇だったらなおさら大変だろう、読了できないのではないか、という不安から長らく手に取れていませんでした。ところが、本書「ゼンデギ」は長篇ながら”比較的”読みやすい、というウワサ。それでは挑戦してみよう、といざ購入。たしかに読みやすい。けれども、ちょっと物足りなさも感じました。 記者のマーティンは妻を不慮の事故で亡くし、自身の癌も発覚。余命いくばくもない彼は、まだまだ幼い息子の将来を案じ、自身の分身をVRシステム上に構築し、死後も息子を導こうと試みる。VRシステムの開発者ナシムは、マーティンの依頼を受け、技術の更なる発展に資すると見込んで開発に着手。果たしてマーティンは、ナシムは、幼い息子を指導するに足る分身をVR上に構築できるのか… VR上に創造する分身は意識ある生命なのか。いわゆるクローン人間に対する倫理的問題の提起は本書でも言及されます。マーティン側から見る、技術の可能性と、倫理的な側面から見る、技術の危うさは相容れないものですが、本書はそこに決着をつけているわけではありません。 しかし、この結論。要はこの試みは失敗するのですが、なんだか肩透かし感があります。これは技術が大いに発展する前夜の話なのか。 一方で、マーティンがそもそも懸念していた息子の将来を案ずる、という点には、一定の結論がもたらされます。テクノロジーに頼らず、ひとを信頼する。もしかしたら、いや、たぶんありきたりでよくある物語のオチなのでしょう。ただ、イーガンの作品でこのオチは何か意味がある気がします。なんとなく。 遠い未来の話ではなくて、近い未来の話。もしかしたらすぐそこまで手が届いている技術の話。もちろんそんな過渡期では技術も未熟で、望ましい答えが返ってくるとは限らない。それでもテクノロジーにすがる人はでてくるし、それに反発する人も、裏切られる人も出てくる。その根底にはそれぞれ特有のドラマがある。なんというか、そんな現実を切り抜いたような作品だったように思えました。
Posted by
近未来のVR技術と、コンピュータへの人格転移がテーマ。 グレッグ・イーガンの中では読みやすくわかりやすい。 模造人格だとしても息子のために存在を残したいという父。 父と息子のヒューマンドラマとしても秀逸。 SF養分は少なめ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
はるか彼方の未来の壮大な話ではない。近未来の、仮想現実の技術をめぐる、骨格だけを言ったら他のだれかでも書いていそうなワンアイディアストーリーのよう。でも、かの国を舞台にしてのディテールの書込みの説得力はこの著者ならではのものか(その妥当性の判断はわたしにはできないのだけれど)。そして、「情」の部分で、わたしはこの話が大好きになった。主人公が聴いてきた音楽の趣味のあれこれにも、ちょっと共感♪
Posted by
ちょっと苦手なイーガン。比較的読みやすいということで懲りずに挑戦。 舞台はイラン。2012年の政権交代と第一部とし2027年以降の近未来を第2部とする構成。相変わらず、イーガンの言い回しとか表現とか理解しにくい感じがつきまとう。よっぽど僕には合わない作家なんだな。でも、テーマは...
ちょっと苦手なイーガン。比較的読みやすいということで懲りずに挑戦。 舞台はイラン。2012年の政権交代と第一部とし2027年以降の近未来を第2部とする構成。相変わらず、イーガンの言い回しとか表現とか理解しにくい感じがつきまとう。よっぽど僕には合わない作家なんだな。でも、テーマはまさにタイムリーなAIのななめ上を行っている。人格そのものもを仮装空間にアップロード(本文中ではサイドロードという表現)できるか、できたとしたらどんな問題が引きおこされるのか? 自分という人間の「プロキシ」と表現されているのが上手いなぁと思う。脳スキャンによって不完全なマッピングを前提にした部分的人格(?)は人間なのか?不死の存在となるのか?意識と呼べるのか?興味は尽きません。 読んでいる最中に母が入院という、状況的にも心に刻まれる一冊となりました。
Posted by
脳を非侵襲的スキャンして仮想環境に仮想人格を構築する話。前半は中東の政治的な革命の話だが、そもそも、部隊が中東である必要はあったのかよくわからん。
Posted by
3D感覚で実際に自分がその場にいるかのようにゲームをプレイできる、オンラインゲームの高度進化版(ハンターハンターのGIを思い浮かべるとイメージしやすい)を軸にしたSFものだが、親子の絆などの要素も込められた物語。 グレッグ・イーガンというと、現在SF作家の最高峰だったり、ハードS...
3D感覚で実際に自分がその場にいるかのようにゲームをプレイできる、オンラインゲームの高度進化版(ハンターハンターのGIを思い浮かべるとイメージしやすい)を軸にしたSFものだが、親子の絆などの要素も込められた物語。 グレッグ・イーガンというと、現在SF作家の最高峰だったり、ハードSFの旗手と呼ばれたりで、とっつき難い印象があった。 いずれ読まねばと思うが、これより前の「ディアスポラ」などは非常に理解が難しく、「白熱光」に至っては筆者のウェブサイトにて図付きの解説が載っているという事実が二の足を踏ませる。 それらよりは遥かに読みやすい(理解力に乏しい我々にイーガンが歩み寄った)作品ではあるようだが、いかんせん長すぎるのではないかという印象は拭えない。全部で500ページ近くあるが、200ページほどの第1部はイランの政治情勢とデモについて長々と書かれており、SF要素はほぼ皆無である。ここで投げ出してしまった読者も多いのではないだろうか。 第2部は1部から10数年後の未来で、2020年代が舞台である。同書が執筆されたのが2010年であり、科学技術などはかなり想像がしやすく、実際に起こり得りそうな出来事を目にすることになる。 と言うより、SF黎明期の名作の発表時期に比べると、現在の科学技術が如何に発達したかと思わせられる。 おれ達、未来に生きてんな。 イスラム教徒が多く住む地域で、発達し過ぎた科学はどのような受け取られ方をするのか?というのも見所の一つ。 自分が心に描き、理想としている自分自身の像と、自分自身の知識と人格を投影して作成した像の乖離を目の当たりにするシーンはなかなかに壮絶だった。 冒頭で、海外へ引っ越しする準備中の主人公が、これまでの自分史を象るレコード群達を手放して、後からお気に入りだけダウンロード購入するべきか否か葛藤するシーンがとても好きだ。音楽好きなら分かるはず。 「自分が二度とディーヴォとかレジデンツとかヴァージン・プルーンズに金を出す気にならないのは分かっているが、そのページを日記から破りとって、エルヴィス・コステロやザ・スミスといった高尚な一団に青春の全てを捧げていたふりをするのも嫌だった。世に知られていなく、いかがわしいアルバムほど、それを自分の過去から削除することで失ってしまうものが大きかった」
Posted by
小説をどうはじめるかというのは重要なテクニックだろうが、「ア・ロング・ロング・タイム・アゴー、イン・ア・ギャラクシー……」などと説明的には始めたくないものである。さりげない場面をおいて、しかも主要テーマをそこに反映させる。 ジャーナリストのマーティンはシドニーからテヘランに赴...
小説をどうはじめるかというのは重要なテクニックだろうが、「ア・ロング・ロング・タイム・アゴー、イン・ア・ギャラクシー……」などと説明的には始めたくないものである。さりげない場面をおいて、しかも主要テーマをそこに反映させる。 ジャーナリストのマーティンはシドニーからテヘランに赴任するにあたり、荷物を整理しているが、二百枚を超えるLPをどうしようか悩んでいる。CDはもうHDにはいっているのだが、LPを捨てるには忍びないし、すべてダウンロード音源で買い直すほどのものでもない。彼は離婚したばかりだが、LPは結婚前に買ったもので、彼の青春と結びついているのだ。そこでマーティンはLPの音源をコンピューターに取り込むことにする。最初の数枚は慎重に音量を調整して読み込んだが、あとは大丈夫とみて機械的に読み込みを行った。ところがiTunesで取り込んだLPの音源を機上で聞いてみると多くのトラックが音量オーバーでダメになっていたのに気づく。隣に乗っていたアラブ人の技師が、いまわれわれはすばらしい新しい世界の入口にいるが、足許を見失うと何度もつまずくことになるだろうなどと述べる。 テーマは人格のアップロード。音源のアップロードにつまずくエピソードをまず配しているわけである。 第1部の時代は2012年(本書原書の出版は2010年)。マーティンはイランで強権的な政権に対する民主化運動のうねりに揉まれながら取材をする。そしてもうひとりの主人公ナシムはイラン人コンピュータ科学者。政治的弾圧で父を殺されて母とともにアメリカに亡命し、そこで彼女は鳥の神経系のシミュレーションの研究をしている。 マーティンとナシムのエピソードが交互に描かれる。イランの民主化運動は遂に成功する。ありえたかもしれないが実際はなかった2012年の歴史である。ナシムはイランへ戻る決心をする。 そして第2部はその15年後。マーティンはイラン人女性マフヌーシュと結婚して書店を営み、6歳の息子がいる。マフヌーシュは民主化運動のデモの中にいた印象的な女性。最初からデモの中のスナップ写真のように描写され、15年後も描写が希薄だと思ったら、すぐに事故死してしまう。最初から得られなかったものが失われるとでもいうような寂寞感を醸す、何たる見事な技法。 その時代すでにヴァーチャル・リアリティのゲームマシン「ゼンデギ」(ペルシャ語でライフの意味)が実用化されている。マーティンは息子にせがまれてゼンデギで一緒にゲームをするようになる。その開発者はナシム。そしてナシムはマフヌーシュのまたいとこだった。 妻と一緒に事故に遭い一命を取り留めたマーティンだが、その際に進行癌を発見される。彼は息子のために彼の精神をソフトウェア化して残そうと考える。ナシムの力を借りて。 いつもそのアイディアのぶっ飛び具合でわれわれをびっくりさせるイーガンがここではじっくりと人物を描いている。息子ひとりを残して死なねばならないマーティンと、父に先立たれたナシムがひとつの目的に手を携えるようになっていく。SF的アイディアの連射を期待していると、物語の進行は若干だれて感じられる。 左様、イーガンの他の作品のようにヒトの神経系に直接電極をつないでダウンロードするような先進技術はまだない。コンピュータの中に構築した鋳型のようなソフトをもとに、MRIなどの画像技術による神経系の模写とゼンデギの中でのマーティンの反応をフィードバックし続けていくという、原始的な方法だ。 ソフトウェア知性構築の倫理的問題や、世間の反発やテロ組織など様々なテーマを巻き込みつつ進む物語は、マーティンとナシムの取り組みのつまずきがどういう方に行くのか評者にはなかなか予測できなかった。ソフトウェア知性が暴走する映画『サマーウォーズ』や『トランセンデンス』のような話ではないのである。イーガンは新しい世界とそこに入っていこうとする人間に対して変わらず肯定的なのであった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「脳スキャン技術により開発されたVRシステム〈ゼンデギ〉――マーティンは幼い息子のため、そこに〈ヴァーチャル・マーティン〉を作るが……」 というのが帯文。読み始める前は、ヴァーチャル人間が当たり前のように存在する世界で人間の存在を脅かすような大事件がおきるのかと期待したが、実際はヴァーチャル人間が作れるようになるまでの技術的な苦労話と、息子のために自分のヴァーチャル分身を作ろうとして、それはイカンと死の直前に気づいた父親の、哀愁漂う物語だった。
Posted by
- 1
- 2