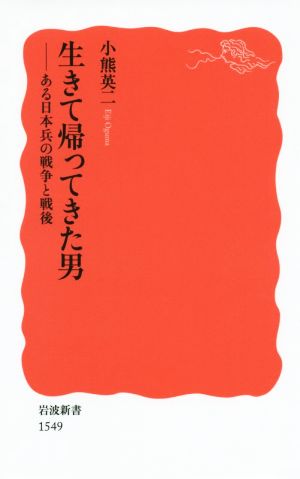生きて帰ってきた男 の商品レビュー
著者の父親を題材として、オーラルヒストリーの手法をとって戦前、戦後の日本の歴史を知識層ではない層から見たものとして記述。 中国派兵、シベリヤ抑留の後に日本に帰国して結核で片肺を失いながらも運と時勢をつかんでき、戦争時の体験をベースに元日本植民地の徴兵後の保証に関する社会運動に晩年...
著者の父親を題材として、オーラルヒストリーの手法をとって戦前、戦後の日本の歴史を知識層ではない層から見たものとして記述。 中国派兵、シベリヤ抑留の後に日本に帰国して結核で片肺を失いながらも運と時勢をつかんでき、戦争時の体験をベースに元日本植民地の徴兵後の保証に関する社会運動に晩年は携わる。時代にほんろうされつつも生きる逞しさおよび世の中の流れを社会学者としてわかりやすく背景描写を重ねている一級の資料。
Posted by
古本屋で何気なく手にして読み始めた。 小熊英二が社会学の英知を傾けて描いた父親の『自分史』である。社会状況や経験した事実を丹念に聴き取り丁寧に書いている、視点や文調が独特で新鮮だ。 戦争に明け暮れた昭和の混乱期、逆境を這いながら地道に生きた父親の人生を口承で辿った一人息子の計らい...
古本屋で何気なく手にして読み始めた。 小熊英二が社会学の英知を傾けて描いた父親の『自分史』である。社会状況や経験した事実を丹念に聴き取り丁寧に書いている、視点や文調が独特で新鮮だ。 戦争に明け暮れた昭和の混乱期、逆境を這いながら地道に生きた父親の人生を口承で辿った一人息子の計らいに共感を持って読むことができた。 小熊謙二の自分史であると同時に、日本が太平洋戦争に向かう時期から、敗戦、戦後の高度成長へ、そして現在までの推移を、一国民の目を通して語り表現した『社会史』でもある。 彼は敗色濃い満州に徴兵され、敗戦になり捕虜でシベリアに抑留され、帰国して結核で隔離病棟生活を経てスポーツ用品店の経営者となり、結婚し四人家族の長男に死なれ、残った一人息子の英二を育てる。 貧困と不運が重なり、人に迷惑をかけず補償など国には頼らず、波乱のなかを実直に生きた父の生涯を感情を抑えて冷静に描写している。 あの時代を生きた生活者への讃歌である。 小林秀雄賞の受賞は宜なるかなであり、自分も星五つの評価をした。 読みながら、地方の没落家系に育ち大企業の技術者から出征後零細事業者になり、妻や祖母と貧困に苦労し一人の娘を失い、事業税を払い続け軍人恩給の受給を拒み、子供たちを大学まで出した自分の父の切実な人生を思い胸を締め付けられた。
Posted by
戦前・戦中・戦後を生きた一人の国民の人生を、それぞれの時代の社会背景を交えながら綴った歴史書であると言える。 記述の対象は、小熊英二先生の父親である小熊謙二氏。 先の戦争に学徒兵として徴兵され、満州にて終戦を迎える。その後、ソ連軍の捕虜となってシベリアに3年間抑留された。 帰国...
戦前・戦中・戦後を生きた一人の国民の人生を、それぞれの時代の社会背景を交えながら綴った歴史書であると言える。 記述の対象は、小熊英二先生の父親である小熊謙二氏。 先の戦争に学徒兵として徴兵され、満州にて終戦を迎える。その後、ソ連軍の捕虜となってシベリアに3年間抑留された。 帰国後もなかなか安定した生活基盤を築くことができず、「死の病」と言われた結核にかかるなど、不運は続く。 サナトリウムからの退所後、職を転々とする中でスポーツ用品の販売会社に就職し、サラリーマン生活を送る。 結婚し子をもうけ、「一億総中流」の日本社会の一員として戦後日本を生きることになる。 こう要約してみるとなかなか分かりにくいが、興味深く戦後史を学ぶことができる良書だと思います。 分量が多く、読み応えあり。
Posted by
とある一人のシベリア抑留者がたどった人生の軌跡から、著者の父(小熊謙二)へのインタビュ-を通して、戦前から戦後の生活模様や世相を浮き彫りにしたドキュメンタリ-。▷サイパン陥落後、東条内閣が倒れたが「背景の情報はないし、何も分からなかった」▷最初の冬は飢えと寒さの闘いだった...
とある一人のシベリア抑留者がたどった人生の軌跡から、著者の父(小熊謙二)へのインタビュ-を通して、戦前から戦後の生活模様や世相を浮き彫りにしたドキュメンタリ-。▷サイパン陥落後、東条内閣が倒れたが「背景の情報はないし、何も分からなかった」▷最初の冬は飢えと寒さの闘いだったが、二年目からは少しずつ別の苦痛、捕虜たちの間で、共産主義思想に基づいてお互いを糾弾する民主運動が始まった。「母上様お元気ですか。私もしごく元気で、スタ-リン大元帥の温かいご配慮のもと、何不自由ない毎日を過ごしています...」
Posted by
・いわゆる学徒兵や将校など、中産層ではなく、都市下層の商業者という「庶民」の視点から、淡々と当時のシベリア抑留を起点とした戦争体験が描かれている。 過剰かつ感傷的な表現が少なく、全体がとても読みやすい文章で描かれており、当時の日本軍や戦争に対するある意味「冷めた」感情もまた、当時...
・いわゆる学徒兵や将校など、中産層ではなく、都市下層の商業者という「庶民」の視点から、淡々と当時のシベリア抑留を起点とした戦争体験が描かれている。 過剰かつ感傷的な表現が少なく、全体がとても読みやすい文章で描かれており、当時の日本軍や戦争に対するある意味「冷めた」感情もまた、当時のリアルの一側面なのだろうと感じた。 ・時代を経ていくごとにいわゆる高度経済成長の波に乗り変化する筆者の生活に、 当時の社会全体の「希望」を感じた。 ・・その延長線上にある現代日本は若者が「希望」を持てる国になっているか?果たして信義をもって人権を尊重する国になっているだろうか。 そんな疑問を持ちつつ、読み終えた。
Posted by
ある一般市民がどのように戦争に巻き込まれ、戦後を生きたか記録されている。 戦時に始まり、シベリア抑留から帰国するところで終わる本だと思っていたが、彼の両親・祖父母がどのように暮らしていたかから丁寧に紐解かれ、彼がどのようにして徴兵されたか、戦後どのように生計を立て、引退後の生活...
ある一般市民がどのように戦争に巻き込まれ、戦後を生きたか記録されている。 戦時に始まり、シベリア抑留から帰国するところで終わる本だと思っていたが、彼の両親・祖父母がどのように暮らしていたかから丁寧に紐解かれ、彼がどのようにして徴兵されたか、戦後どのように生計を立て、引退後の生活をどのように過ごしたかが克明に記録される。 いままでわたしが触れてきた戦争について描かれている媒体では、戦争中の悲惨なエピソード、玉音放送を聴いて打ちひしがれる国民、という描写に留まるものが多かった。本書を読んで、一般的な市民にとっては、戦争が終わっても、無事生き残っても、必死の思いで生還しても、特に金銭的・物理的な救いがあったわけでもなく、ただ単に戦後の貧しい暮らしが続くだけだったということがわかった。 あとがきにもあるように、個人の体験を残すのはその体験を文章に残すことができる高学歴の者によることが多いから、こんなに素朴というか、「下の下」の人の戦争体験は初めてだった。 あの戦争で国民の日々の暮らしは否応なく変わり、命を失った人までいたにも関わらず、力のある者が声を上げ続けない限り国が補償を行わなかったというのはショックだった。 そしてまた、謙二による裁判での陳述は胸に迫るものがあった。何も間違ったことは言っていないのに、それにもかかわらず請求棄却されたということが、日本人として本当に残念だと感じた。 わたしの祖父母は戦争について語りたがらなかった。わたしの祖父母にも、本書で記録されているような、祖父母たち固有の歴史があると思う。聞くことができなかったのが惜しい。 「昔は水族館だったというアパート」という描写が気になった。
Posted by
時系列が行ったり来たりするので第一章で挫けましたが、少し時間が経ってから何も考えずに開くと読めました。この一冊を参考に他の昭和を題材にした本を読むと面白いと思います。
Posted by
著者の父である小熊謙二に対し、2013年5月から12月に行われた聞き取りからなる民衆史・生活史であり、出版時点で89歳の謙二氏の来歴を辿るものである。タイトルからすれば戦争体験に焦点を当てた内容を予想させられるだろう。戦争・捕虜体験も本書の重要な要素ではあるのだが、約380ページ...
著者の父である小熊謙二に対し、2013年5月から12月に行われた聞き取りからなる民衆史・生活史であり、出版時点で89歳の謙二氏の来歴を辿るものである。タイトルからすれば戦争体験に焦点を当てた内容を予想させられるだろう。戦争・捕虜体験も本書の重要な要素ではあるのだが、約380ページのうちその時期に該当するのは第2章から4章の全体の三割弱であり、けっして戦争体験だけを切り取る意図で綴られたものではない。戦前と戦後から高度経済成長にいたるまでの日本の社会や風俗を、自らを「下の下」と称する謙二氏の記憶を通して鮮やかに映し出す。 戦争に関する一人の兵士の記録を期待していたが、早い段階でそのような著書ではないことに気付いた。だからといって当てが外れて裏切られたかといえば全くそんなことはなく、謙二氏が入営するまでの家族の来歴や庶民生活を読んだ時点でも期待以上で、戦争にまつわる情報だけを得たいという意識は早々に薄れた。とくに戦記ということに関しては、戦争末期の1944年11月に召集された謙二氏には実戦の機会は一度もなく、当人が言うようにシベリアに抑留されるためだけに満州に送りこまれたような結果となっており、明らかに戦記を期待するような読者に向けられた内容ではないため、その点は改めて注意したい。 あとがきにあるように、高学歴中産層による各種の記録は多く残されていても、著者の父のように貧しく学歴もコネもない民衆による記録を読む機会は限られており、あったとしても短い証言を集成したアンソロジーのようなもので、一生涯を貫くまとまった形の生活史は貴重ではないだろうか。本書は一人の名もない平凡な民衆が見た、昭和元年から戦争を経て豊かな時代に至る日本社会を知る格好の内容である。謙二氏の記憶と比較すれば、一般に知られている個々の時代の日本社会の様子は、やはり高学歴であったり公的組織や大企業に属する人々の「高い」視点からもたらされた偏ったものだと改めて思わずにいられない。 著者自身が指摘しているとおり、何といっても謙二氏が終始淡々としており、思い入れによってフェアな視点を崩されることがないうえに、優れた洞察力と記憶力を兼ね備えた人物であることが本書に資するところが非常に大きい。そのような人物は先述の通り、往々にして高い立場にあったり学歴を備えているケースが多く、結果的に地に足のついた民衆の視点から社会を見渡したような記録は残りにくいはずだが、謙二氏の人間性によって本書ではそのことが可能となっている。そんな謙二氏の視点で語られる80年ほどの日本社会を身近に感じ、抑留と結核療養でフイにした20代の十年間も、その後の高度成長期を背景にした仕事や家庭生活の様子にも強く引きつけられた。 生涯を語るということでは多くの伝記作品などが残されているが、功績が偉大すぎたり、環境の隔たりの大きさによって、結局は別世界の人間のお話だと鼻白むことが少なくなかった。その意味で本書は伝記作品の対極に位置する。語り手はあくまで一人の民衆であり、違う時代にありえた等身大の自分としてまさに身近に感じることができた。偶然から、私が求めていた生活史に出会えたという思いである。
Posted by
著者の父で、「立川スポーツ」創業者・経営者でもあった小熊謙二の戦争体験・戦後の生活史体験の聞き取りの記録。1925年生まれの小熊謙二は、北海道・佐呂間に生まれ、北海道に残った父と離れて東京の祖父母のもとで育ち、早稲田実業学校卒業後に富士通信機に勤めるが、1944年に徴兵のため召...
著者の父で、「立川スポーツ」創業者・経営者でもあった小熊謙二の戦争体験・戦後の生活史体験の聞き取りの記録。1925年生まれの小熊謙二は、北海道・佐呂間に生まれ、北海道に残った父と離れて東京の祖父母のもとで育ち、早稲田実業学校卒業後に富士通信機に勤めるが、1944年に徴兵のため召集。電信第17連隊の二等兵として満洲に送られる。敗戦後は牡丹江でソ連軍に投降、シベリア送りとなり、1948年3月に帰国するまでチタの収容所で強制労働を強いられた。 日本敗戦後は貧困にあえぎ、職を転々とする中で結核に罹患。1956年に退所後は東京学芸大で職員として勤務していた妹・秀子を頼り、多摩に向かう。その後、つてをたどって立川ストアに就職、高度成長期にスプロール状に拡大していった住宅地に出来ていく中学校・高等学校にスポーツ用品を売り込むセールスマンとしてようやく生活の安定を得ていった。退職後は地域の住民運動を手伝う傍ら、シベリア抑留のわずかな縁から再会した朝鮮人元日本軍兵士の国賠訴訟を支援、自らも共同原告として裁判に参加した。 「立川スポーツ」という社名には記憶がある。高校教員時代、クラブ活動の関係でお世話になったことがあったかもしれない。小熊は父親の生活史をある種の典型性というレベルで捉えているが、父親のコメントの周囲に当時の文脈や資料を紹介していくというスタイルは、確かに政治史や社会史の記述ではすくい取れない生の実感というか、生きた人間がそこにいる、という感覚を与えてくれる。 しかし、「あまりにもよくできている聞き取りの記録」という気がしないでもない。いかにも典型的な日本敗戦後の社会党支持者という父親のイメージだが、聞く側の姿勢というか、聞く側の質問やコメント(どんな質問をしたかは記録されていない)が引き出される記憶に無視できない作用を及ぼしているとは思う。
Posted by
仕事のスタイルは 時代が求めるものによって変化する。 当たり前のことだけれど 社会はどんどん変化していく。 戦中、戦後 激動の時代に求められた「生きる力」は? 全体を俯瞰的に見ること。 ニーズを把握すること。 ニッチな分野に目を向けること。 人と繋がり合うこと。 ご縁を大切にす...
仕事のスタイルは 時代が求めるものによって変化する。 当たり前のことだけれど 社会はどんどん変化していく。 戦中、戦後 激動の時代に求められた「生きる力」は? 全体を俯瞰的に見ること。 ニーズを把握すること。 ニッチな分野に目を向けること。 人と繋がり合うこと。 ご縁を大切にすること。 今求められる力と、同じ。
Posted by