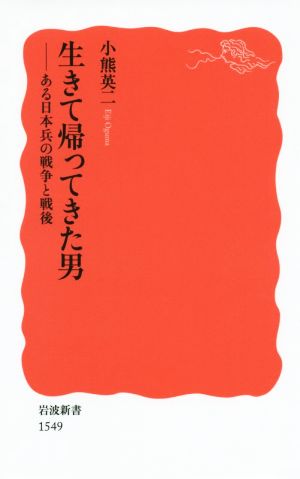生きて帰ってきた男 の商品レビュー
昭和を生きた一人の男の生涯の記録。時代背景と庶民の暮らしがバランスよく記述され、大変読みやすい。書いたのがご子息だとは読み終わるまで気がつかず。
Posted by
淡々と書かれているが、内容は壮絶。 シベリア抑留、結核療養所など、身体的にも過酷で精神的にも厳しい状況でただただ日々を精一杯生きて、今日まで命をつないできた人生に、心から敬服する。 当時の日本を生きてきた人は、多くがそういう思いを経験を乗り越えてきたのだと思うと、なんとも言えない...
淡々と書かれているが、内容は壮絶。 シベリア抑留、結核療養所など、身体的にも過酷で精神的にも厳しい状況でただただ日々を精一杯生きて、今日まで命をつないできた人生に、心から敬服する。 当時の日本を生きてきた人は、多くがそういう思いを経験を乗り越えてきたのだと思うと、なんとも言えない気持ちになる。 あのような戦中、戦後を生き残った人々が、必死で今日を作り上げてきてくれたのに、今の世代がこれでいいのだろうかと申し訳ないような気がする。 後半、現代に近い部分は少し駆け足で語られたような気がするが、社会的な動きは自分でもある程度記憶があるので、それほど物足りない気はしなかった。 戦後補償の問題など、きっと当事者の方たちには語り切れない思いがあるのだろうということが察せられる。 しかし、何よりもやはりシベリア抑留時代から引き揚げのあたりの想像を絶する体験談が圧巻だった。
Posted by
個人史は、ある事柄をそれがどのような政治・経済・社会状況の中にあったのか、総体的に見せてくれる。自分の中でよくわからなかった、位置づけできなかったことが収まっていく楽しさも与えてくれる。
Posted by
慶応義塾大学教授の小熊英二氏が、自らの父親である小熊謙二氏から聞き取った戦前・戦中・戦後の体験を記録した本です。当時の人々の暮らしや考え方などが誇張されることなく淡々と描かれています。「現実は映画や小説と違う」(p172)という謙二氏の言葉どおり、それらはあまり劇的ではないけれ...
慶応義塾大学教授の小熊英二氏が、自らの父親である小熊謙二氏から聞き取った戦前・戦中・戦後の体験を記録した本です。当時の人々の暮らしや考え方などが誇張されることなく淡々と描かれています。「現実は映画や小説と違う」(p172)という謙二氏の言葉どおり、それらはあまり劇的ではないけれど、事実ということの重みを感じさせます。 謙二氏が六〇歳を過ぎてから社会運動といえるものに関わり始めたことには、さすがに「社会を変えるには」の著者である英二氏の父親だと思いました。 社会問題に対する謙二氏の言葉には、どきりとさせられるものがありました。 「現実の世の中の問題は、二者択一ではない。そんな考え方は、現実の社会から遠い人間の発想だ」(p211) 「自分が二〇歳のころは、世の中の仕組みや、本当のことを知らないで育った。情報も与えられなかったし、政権を選ぶこともできなかった。批判する自由もなかった。いまは本当のことを知ろうと思ったら、知ることができる。それなのに、自分の見たくないものは見たがらない人、学ぼうともしない人が多すぎる」(p377) それにしてもすごい記憶力ですね。いつか失われていく貴重な記憶を本にしてしっかり残すことは大切だと思いました。
Posted by
小熊謙二の生涯の軌跡をたどっていくことで戦前から戦中、そして戦後の日本の姿を描いている。著者の小熊英二(謙二の息子)があとがきで書いているように、本書が他の戦争体験記と異なるのは次の二点。 ・戦時のみならず戦前と戦後の生活史がカバーされている点 ・個人的な体験記に社会科学的な視点...
小熊謙二の生涯の軌跡をたどっていくことで戦前から戦中、そして戦後の日本の姿を描いている。著者の小熊英二(謙二の息子)があとがきで書いているように、本書が他の戦争体験記と異なるのは次の二点。 ・戦時のみならず戦前と戦後の生活史がカバーされている点 ・個人的な体験記に社会科学的な視点がつけ加えられている点 本書は戦争というものが国だけではなく個人の人生をいかに破壊するかを物語っている。たとえば、謙二が戦前のように水道とガスのある生活に手に入れたのは1959年のことである。終戦から考えても15年近くの歳月を要しているのである。戦争とはかくも悲惨なものであるということは肝に銘じておく必要があるだろう。また、本書の主人公、小熊謙二の「ものを見る目」の鋭さにも注目して読むと面白い。
Posted by
読む前は一時期話題となったフィリピンの密林から帰ってきた日本兵の話と思っていたが、本書はシベリア抑留から帰還した方の話だった。 私の母方の祖父もシベリア抑留からの生還者であったが、今まで全く知らずに生きてきた。本書を通じてその経験者の生の体験を知ることができ、その過酷さや当時の...
読む前は一時期話題となったフィリピンの密林から帰ってきた日本兵の話と思っていたが、本書はシベリア抑留から帰還した方の話だった。 私の母方の祖父もシベリア抑留からの生還者であったが、今まで全く知らずに生きてきた。本書を通じてその経験者の生の体験を知ることができ、その過酷さや当時の背景を知ることができた。特に終戦時に関東軍が労務の提供を申し出ていたというのは驚愕したし、憤りを感じた。 また、帰還後の生活にも多くの紙数を割いており、あまり知ることの無い庶民の戦後の生活を知ることができる。韓国人や台湾人なども強制的に日本兵として動員していたという事実も重い。昨今の軽々と在日排斥を叫ぶ人達はどのくらいこの事実を知っているのだろう。
Posted by
どんなに平凡に見える人にもそれぞれの人生があり、社会や時代といった背景を舞台にして語られる時、それは個人を超えた同時代のドラマにもなる。NHKにファミリーヒストリーという出演者の知られざるルーツをたどる番組があるが、これは父兼二の人生を中心に語られた社会学者小熊英二自身のファミリ...
どんなに平凡に見える人にもそれぞれの人生があり、社会や時代といった背景を舞台にして語られる時、それは個人を超えた同時代のドラマにもなる。NHKにファミリーヒストリーという出演者の知られざるルーツをたどる番組があるが、これは父兼二の人生を中心に語られた社会学者小熊英二自身のファミリーヒストリーでもある。 以前、辺見じゅん著「収容所(ラーゲリ)から来た遺書」を読みシベリア抑留の一端に触れ、過酷な環境を生き抜いた日本人捕虜の姿に感銘を受けた記憶があるが、今回この著書を通じてソ連全土に散らばった収容所ごとに環境は異なり、そこでの処遇も過酷さの中にも程度の差がかなりあったことを知った。歴史の多様性と複雑さに思いを致し、複眼的にそして謙虚に歴史に向き合うことの大切さを改めて感じた。
Posted by
社会学者の小熊英二氏が、父親、小熊謙二氏から聞き取りを行いまとめた1925年(大正14年)から今日の記憶。戦争、シベリア抑留、結核療養所、高度経済成長、未精算の植民地支配。ひとりの、平均的ではないにせよ平凡な男の個人史を大きな文脈に結び付ける作業を通して、東アジアと日本の大きな変...
社会学者の小熊英二氏が、父親、小熊謙二氏から聞き取りを行いまとめた1925年(大正14年)から今日の記憶。戦争、シベリア抑留、結核療養所、高度経済成長、未精算の植民地支配。ひとりの、平均的ではないにせよ平凡な男の個人史を大きな文脈に結び付ける作業を通して、東アジアと日本の大きな変動、その中における都市下層商人の生活や意識、移動が浮かび上がる。 晩年には朝鮮系中国人とともに戦後補償裁判の原告にもなり、今も人権団体の活動を支援しているという謙二氏も興味深い人物だが、その人生と絡めて語られる社会事情の細かい話が知らないことが多くてとても面白い。たとえばホワイトカラーとブルーカラーの間には城詰めの侍と農民の間のような身分差別があったとか、結婚式が宗教化したのはつい最近のことであるとか。 本書のもつ大きな意味は、このように一人ひとりの人生がいかに異なる形で大きな文脈と結びついているのかを明らかにすることによって歴史を多様な視点から立体化することが可能であること、そして私たち一人ひとりが身近な人々を通して歴史と接近することが可能であることを示したことにあるといえるだろう。とはいえ身近な人が必ずしも謙二氏のように細部を鮮明に記憶しているとは限らないのだが…
Posted by
ソ連の捕虜になって「生きて帰ってきた男」の体験記なんだけど、その戦前と戦後の生活をその社会情勢とを交えてよくわかる。 あまりにも淡々としていて、これがリアルなのか… 抑留と結核療養の思うままにならない期間を経て、食べていくためにさまざまな仕事をし、裁判や運動に係わっていく。 謙二...
ソ連の捕虜になって「生きて帰ってきた男」の体験記なんだけど、その戦前と戦後の生活をその社会情勢とを交えてよくわかる。 あまりにも淡々としていて、これがリアルなのか… 抑留と結核療養の思うままにならない期間を経て、食べていくためにさまざまな仕事をし、裁判や運動に係わっていく。 謙二にとっては下の下で生きてきたという一貫した姿勢。特別才能と幸運に恵まれていると思うが。 多摩に住む私には身近に感じる部分も多くあり、自分の記憶する事柄なども微かに思い出され、戦後は終わっていないという人も未だにいるのが腑におちた。
Posted by
戦争から「生きて帰ってきた男」の話だと思って読んだのだけれど、そうではなかった。 「男」は社会学者である著者の父親。大戦末期に招集され、満州に送られるが戦闘はせずに終戦を迎え、そのままソ連軍の捕虜になって、収容所に送られた。戦争から「生きて帰ってきた」というよりはソ連の収容所から...
戦争から「生きて帰ってきた男」の話だと思って読んだのだけれど、そうではなかった。 「男」は社会学者である著者の父親。大戦末期に招集され、満州に送られるが戦闘はせずに終戦を迎え、そのままソ連軍の捕虜になって、収容所に送られた。戦争から「生きて帰ってきた」というよりはソ連の収容所から「生きて帰ってきた」というべきだし、あるいは帰国してから結核になって収容された療養所や、退所してからの職を転々とする食うや食わずの生活から、「生きて帰ってきた」というべきだろう。戦後の話のほうがずっと長いし。 戦争を知ろうと思って読むと目論見が外れる。そういう経験をした一人の男の人生をたどる旅。 人は歴史の断面を経験するに過ぎない。それは歴史というより個人的な経験に過ぎないし、ひとそれぞれ、千差万別なのは当たり前だ。 だが、逆を言えばある時代を生きた人の千差万別の経験は、いずれもその時代の流れに無関係ではありえない。 わずかな期間ながら日本兵であり、ソ連の収容所に収容された経験のあるただの「男」が、戦後を通して政治に冷ややかな視線を送り、無駄と知りつつ元日本兵だった朝鮮人の訴訟に協力する、ぼくはそちらの心情に興味がある。本題ではないらしく、あまり書いてなかったけれど。
Posted by