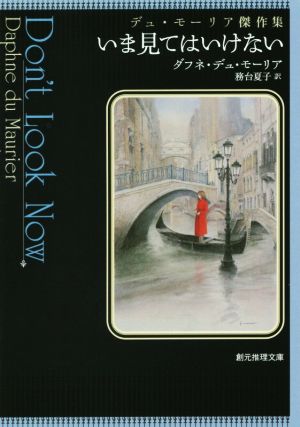いま見てはいけない の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ずっと読みたかった「いま見てはいけない」。唯一無二の存在感のある作品だった。水面下で不吉なことが起こりつつある不安感。唐突の幕切れは鉛のような後味の悪さを残す。 ホラーかと思っていたので、想像していたストーリーとは違ったが、ある意味これもスピリチュアルホラーか。 そのほかの収録作品は、暗示的な内容が多くて少し難しかった。【鳥】のほうが娯楽小説として楽しめたが、「いま見てはいけない」ではモーリアの底知れぬ筆力を再確認できたので、読んでよかったと思う。
Posted by
先が読めないハラハラ加減に、早く読み進めたくなるところを、ぐっと堪えて堪能。とてもおもしろかった。 一番好きなのは十字架の道。
Posted by
不条理、ホラーチックなものなど、様々なジャンルの短編集。 表題作は、子供を失くした傷心の夫婦の旅行中に起こる不可思議な体験談。妻の方が行方不明になったかと思いきや…不思議な結末。
Posted by
1966年、1970年、1971年に出版された原著からセレクトして訳出されたデュ・モーリアの短編集。 やはりこの作者の文体は濃く、なかなか巧みに書かれており、それを辿ってゆく読書体験は一種の「充足」である。このような「充足」を感じさせる文章といえば、久生十蘭を思い出す。それは...
1966年、1970年、1971年に出版された原著からセレクトして訳出されたデュ・モーリアの短編集。 やはりこの作者の文体は濃く、なかなか巧みに書かれており、それを辿ってゆく読書体験は一種の「充足」である。このような「充足」を感じさせる文章といえば、久生十蘭を思い出す。それは単純なパロールの流れというよりも、よく寝られたコンポジションだ。 そんな完成度の高いデュ・モーリア文学だが、本書のうち、巻頭の「いま見てはいけない」はオチが弱くて、そこに至るまでは秀逸なだけに惜しいような作品だった。 最後の「第六の力」はSF小説。こんなものも書いたのかと驚いた。1編のSF短編として、ちゃんと水準に達していると思う。
Posted by
5つの短編集。いずれも見えないはずのものが見えたり、霊感とか、そういう感覚が書き込まれている。「いま見てはいけない」「真夜中になる前に」あたりがよかった。 「いま見てはいけない Don't look now」1970 ベネチアに旅行に来た夫婦。そこで双子の老夫婦に出...
5つの短編集。いずれも見えないはずのものが見えたり、霊感とか、そういう感覚が書き込まれている。「いま見てはいけない」「真夜中になる前に」あたりがよかった。 「いま見てはいけない Don't look now」1970 ベネチアに旅行に来た夫婦。そこで双子の老夫婦に出会う。夫妻には男と女と子供がいたが、幼いうちに女の子を失っており妻はいまだ喪失の絶望から立ち直っていない。寄宿舎にいる男児が盲腸だとの連絡を受け、妻はイギリスに戻るが、夫は戻ったはずの妻の姿を水路に見るが・・ 表紙の絵はこの情景を描いたものだろう。「赤い影」として1973年に映画化。 「真夜中になる前に Not after midnight」1971 寄宿学校で古典を教えていた私。教師をやめ趣味の油絵を描くためにクレタ島にやってきた。バンガロー形式の宿ですぐ隣の小屋は日に焼けた男と耳のきこえないという妻。毎朝海に釣りにでかける。岬で二人を見つけた私は二人がやっていたのは釣りではなかったのが分かるが・・ 「ボーダーライン A border-line case」1971 突然亡くなった父の死の謎を解くために、ダブリンから百キロ、湖の点在するバリーフェインにに住む父の旧友をたずねたシーラ。荒涼とした風景を想像しながら読む。着いてみると、さらにトラー湖のなかの小島に住んでいるという。 「十字架の道 The way of the cross」1971 急病に倒れた牧師のかわりにエルサレムへの24時間ツアーの引率者に次々と降りかかる災難。多様な参加メンバー。 「第六の力 The break through」1966 ロンドンから遠く離れた研究所で行われていた研究とは? 原題:DON'T LOOK NOW AND OTHER STORIES 2014.11.21初版 図書館 「真夜中すぎでなく」三笠書房1972刊と収録作は同じ。今見てはだめ、真夜中すぎでなく、シュラの場合、十字架の道、第六の力
Posted by
中学生の時に河出の世界文学全集でレベッカを読んだ。とりこになった。10代の間に何度読み返しただろう。あの頃の気持ちを思い出した。忘れていたぞくぞくするような感覚がよみがえってきた。レベッカしか知らなかったがこれ!!!な作品だ。すごいなデュ・モーリア!まさに物語世界に心がもっていか...
中学生の時に河出の世界文学全集でレベッカを読んだ。とりこになった。10代の間に何度読み返しただろう。あの頃の気持ちを思い出した。忘れていたぞくぞくするような感覚がよみがえってきた。レベッカしか知らなかったがこれ!!!な作品だ。すごいなデュ・モーリア!まさに物語世界に心がもっていかれる感じ。他の傑作集2冊も読まねばなるまい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
全5編あるなか、まず、先陣を切っている表題作の『いま見てはいけない』から。ヴェネツィアに観光旅行に来ている、水難事故で幼い娘を無くしたばかりの夫婦の夫が主人公です。旅先で出会った、霊感を持つらしい老姉妹に、夫は不信感を持つのですが……。エンタメの神髄的な、語りのうまさ、構造や設定の巧みさ、そして、終わり方の見事さに、もう舌を巻きました。読了した瞬間、あっ、と思ったら頭が真っ白になり、しばらく放心したため、その次の作品を読むのをあきらめて寝たくらいです(まあ、すでに夜中でしたが)。続いて、『真夜中になる前に』。ギリシャのクレタ島へ休暇にやってきた美術教師の男性が主人公。なにげないところで生じる奇妙さの連続が、それを気にすることでどんどん日常を歪めていくような話。人間心理の怖さとしても読めるし、神話を織り交ぜているので、祟りだとかそういうオカルト的にも読めます。次に、『ボーダーライン』。父の死の瞬間にひとり立ちあう事になったまだ20歳の役者志望の娘が主人公。父の旧友に会いにいくことからドラマが始まっていきます。世界の表裏をつうじて、進行するラブストーリー的なところがありますが、主人公の女性の冒険というか、彼女が個人的に探偵ごとをするので、サスペンス形式みたいになっています。ちょっとしたハードボイルドとも言えるんじゃないだろうか、女性が主人公でも。敵対しながらも惹かれあう、っていうところがよかったです。そして、『十字架の道』。急きょエルサレムのガイドの代役をまかされることになった若き牧師を中心とした群像劇です。群像劇ものってたぶん読んだことがなかったですから、新鮮でした。こんなに複雑になるものなんだ、と。登場人物がみんな独自の世界観のなかで生きていて、違う方向を向いて生きています。それをちまちま克明に書いていったら、たぶん読み手は面倒くささを感じると思うのですが、作者はちゃんと踏みとどまって、物語的な佳境にもっていく。ちゃんとエンタメにしています。最後に、『第六の力』。これはSFです。主人公が出向を命ぜられた先が、政府筋の、あやしい研究をしているらしい研究所なのです。まず、そこまでたどり着くまでの描写で何度も笑えます。作者の力量ですね。デュ・モーリアという人は、こういう技術もあるんだなあ、と。物語の終わりにむけて、だんだんシリアスにもなっていきますが、その高低差は計算されているんでしょうね。科学面での細かいところの設定では、とりあえずの説得力をもっています。作者がいろいろな知識をそれなりの深さで取り入れる力量があるからですね。さすがの知的体力。そして、その裏付けとなるような設定を読者の腑に落ちる段階に作り上げたならば、そこから壮大な幻想の影を持った現実的物語はすすんでいきます。そういう構造を見つめてみると、やっぱり序盤にいくつかの笑い、滑稽さを持ちこんだのは、全体のバランスのとり方として上手だなあと思えます。というような、5編です。いろんなことをやっています。そりゃあ、5編だけを集めているわけですから、その他の作品を読んでみない分には断定できませんが、焼き直し的なものは一切ない。すべてまっさらなところから作り上げた、オリジナリティー十分の、独立した5編でした。肝が座っているというか、体力があるというか、姿勢が違うというかで、すばらしいです。
Posted by
いま見てはいけない、というタイトルに惹かれて手に取りました。 全体的に不穏な雰囲気の漂う短編集でした。旅先で出会う奇妙な人物、奇妙な出来事…ホラー?ミステリー?分類が難しいので奇妙な味のカテゴリに入れておこう。 「いま見てはいけない」「真夜中になる前に」「ボーダーライン」の3編は...
いま見てはいけない、というタイトルに惹かれて手に取りました。 全体的に不穏な雰囲気の漂う短編集でした。旅先で出会う奇妙な人物、奇妙な出来事…ホラー?ミステリー?分類が難しいので奇妙な味のカテゴリに入れておこう。 「いま見てはいけない」「真夜中になる前に」「ボーダーライン」の3編は、ラストにズドンと落とされる感じが良い。 エルサレムを旅するご一行の群像劇「十字架の道」は表面上はうまくやっている面々が、水面下ではお互いを軽蔑しあっているというところがリアルで、イヤミス的な面白さもあった。 ラストの「第六の力」はSFチックで他作品とはちょっと毛色が違う感じ。 「いま見てはいけない」は「赤い影」というタイトルで映画化されているらしい。他にも映画化されている作品がいくつかあるようです。次は「鳥」を読んでみようかな。
Posted by
日常とは異なる感覚を生む、旅先を舞台にした短編集。オカルトあり、メロドラマあり、コメディありと、それぞれ違った味わいです。短い話の中でも人物像が浮かび上がってくるような心理描写、得体の知れない不安感の煽りはさすがサスペンスの名手。どう落とし込むのだろうと期待が高まるのですが…。読...
日常とは異なる感覚を生む、旅先を舞台にした短編集。オカルトあり、メロドラマあり、コメディありと、それぞれ違った味わいです。短い話の中でも人物像が浮かび上がってくるような心理描写、得体の知れない不安感の煽りはさすがサスペンスの名手。どう落とし込むのだろうと期待が高まるのですが…。読み込み不足かもしれませんが、謎が謎のまま終わってしまったり、余韻が残らなかったり、物足りなさを感じました。原著で読める英語力と、文化的背景への知識があれば、もっと楽しめるのかもしれません。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
目次より ・いま見てはいけない ・真夜中になる前に ・ボーダーライン ・十字架の道 ・第六の力 ゴシックサスペンスの小説『レベッカ』で有名な、ダフネ・デュ・モーリアの短編集。 全体像が見えないことによるドキドキ感は健在で、「どういうこと?どういうこと?」と手さぐりで読み進めていくことの快感。 特に表題作の「いま見てはいけない」は、なんとなく結末が想像できるのではある。 けれど、押し寄せる不安で、結末を確認しないではいられない。 ただ、カタルシスを得られるかと言えば、それはない。 この短編集全体がもやもやを抱えたまま沈んでいくような読後感。 「ボーダーライン」はアイルランド問題、「十字架の道」はキリスト教をもっと知っていれば理解が深まったのだろうか。 私の中で消化不良のまま残されている。 「第六の力」 映画化作品が多いデュ・モーリアだけど、これについては清水玲子で漫画化を希望。 絶対合うと思うんだ、彼女の作風と。 オカルトと科学の融合?混濁? 濃密なイギリス臭漂う作品集。 全部違う作風なのに、全部イギリスだったわ。
Posted by