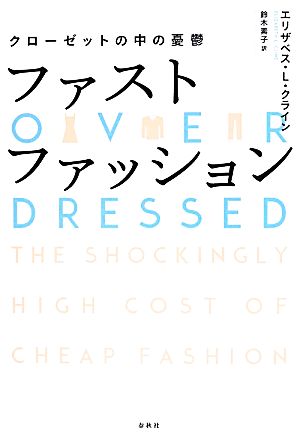ファストファッション の商品レビュー
相変わらず同じような本。私、なんだかんだ服に興味があるみたい。なんといっても、生まれてからずっと身につけるものだもんね。 裸で生まれてくるのに、その直後からほとんど裸になることはないって、考えてみると、とても不思議。 本の中で著者は2001年くらいの中国に乗り込んで、縫製工場を...
相変わらず同じような本。私、なんだかんだ服に興味があるみたい。なんといっても、生まれてからずっと身につけるものだもんね。 裸で生まれてくるのに、その直後からほとんど裸になることはないって、考えてみると、とても不思議。 本の中で著者は2001年くらいの中国に乗り込んで、縫製工場を見て回ってますが、当時、すでに中国の方もどんどんおしゃれになっていて、服をどんどん買うようになっていること、中国で作るコストも上がっていることなどが書かれています。 今はもう、だいぶ中国離れが進んできているようなことがあとがきに書いてありました。 かなり長い本で、でも、アパレル業界の問題点が網羅されているような感じのよい本だと思いました。 著者の熱意を感じます。 高い服はどんどん高く、逆に安い服はとことん安くなっていて、二極化が進んでいること。 薄利多売方式の維持のため、安い服をたくさん買ってもらえるよう、どんどんたくさんの服を作るようになってること。 昔、服は自分で作るものだったし、既製服が普及してからも買うほうは服についてそれなりの知識を持っていたけれど、今は誰もがデザインと値段でしか服を選ばなくなっていること。 安いからとりあえず買っておいて、気に入らなければ捨てたり寄付したりすればいいや、と思っている人が多いけれど、すでに服はリユース不可能な量が生み出され続けていて、ほとんどがゴミになるしかないこと。 そして、大量の服が生み出される過程で、自然も資源も人も損なわれていること。 最後は、自分で服を作ったり、繕ったりしている人を取材していて、やっぱり行き着くところはそこなんだ!と嬉しくなりました。 一年間一枚の服で暮らす「ユニフォーム・プロジェクト」、着る服のアイテムを6点以下に絞り一ヶ月それだけを着て過ごす「シックス・アイテムズ・オア・レス」などのプロジェクトを知れたことも面白かった。 最近、3ヶ月33アイテムで暮らすという「プロジェクト333」というのを知ったのだけど、そういう試みをしている人がいると知ると励みになるよね。 なんといっても、少ない服で暮らすことの最大のネックは、人の目だと私は思っているので。 「あの人、いつも同じ服着てる」って思われてるんじゃないかという、勝手にそんなことで自分を責めて、いろんな格好しなくちゃって思ってるところがあるから、こういうプロジェクトに取り組んでるんですよ、って言えるのはいいなって思います。 私もスローファッションで。 慎重に選んで買う量を減らし、繕ったりしながら長く着る、を実践したいと思います。
Posted by
アメリカではアパレル業界が30年ほどで大きく様変わりした。国産の衣料品が姿を消し、超高額な品と格安品の二極化が進んだ。値段の高いブランド品でも品質が高いとは限らず、市場は大量の粗悪品であふれて人々は服を使い捨てるようになった。アメリカの服飾産業でなにが起きたのか?本書はこの疑問に...
アメリカではアパレル業界が30年ほどで大きく様変わりした。国産の衣料品が姿を消し、超高額な品と格安品の二極化が進んだ。値段の高いブランド品でも品質が高いとは限らず、市場は大量の粗悪品であふれて人々は服を使い捨てるようになった。アメリカの服飾産業でなにが起きたのか?本書はこの疑問に答えてくれる。 本書によれば、アメリカ人はいまだかつてないほど多くの服を持っている。とは言えアメリカ人が昔と比べて衣料品にお金をかけるようになったわけではない。格安ファッションが出回り、衣服の価格が下がったのが理由だ。アパレル企業は服を「格安」で提供するために縫製工場をアメリカ国内ではなく人件費の安い中国やバングラデシュに置く。しかし消費者が求める低価格に応えるためには工場をアジアに移すだけでは不十分だ。最低賃金(を下回る賃金)を従業員に強い、劣悪な労働環境を放置し、生地の質を可能な限り下げる。それでも低価格に慣れた消費者は「高い価格を不当と見なす」ため、企業はさらに価格を下げざるを得なくなる。「いまだかつてない大量販売」(128ページ)を展開するファストファッションがこの悪循環を助長している。 こうした状況は多方面に多くの損害をもたらしている。著者の主張は3つにまとめられるだろう。①ファッション関連企業が海外へ進出した結果、産業が衰退し多くの人が失業した。また、賃金も下がった(2章)。②市場に出回る服が粗悪になり、生地の品質や仕立ての良い服を見つけるのが難しくなった。本当に質の良い服があっても、それらの価格は手が届かないくらい高い(3章)。③資源を枯渇させるほど大量に服を製造することで環境に過大な負荷がかかっている。それらの大量生産された服は大半がリサイクルされず大量のゴミを生んでいる(5章)。 この状況を改善するための方策として著者が本書で提案するのが裁縫(8章)とスローファッション(9章)だ。どちらにも共通するのは一人ひとりが購入数を減らし、それぞれによりお金をかけるということ。つまり良い物を少なく持って長く使おうというのである。著者自身は裁縫を覚えて格安ファッションと距離をおくようになった。服を自分に合うように作り直すことを知って、服との接し方が変わったようだ。スローファッションにはファッション性という強みがあり、地域で作られた「自己表現のための服」にお金をかければ社会全体を元気にすることができるとも著者は言う。 「最新のものを最安値で手に入れる」を信条として格安ファッションを買いあさっていた著者は、本書の書き終えるころにはすっかり宗旨変えしてしまった。「格安ファッションにお金をかけるのがどんなに無駄か、今は身にしみて感じている。何しろ生地も仕立ても、持つ価値のないものがほとんどなのだから」(252ページ)という著者の言葉は印象的だ。
Posted by
「GUだけでこんなにおしゃれ!」とか、もう時代に合ってないと再認識。犠牲者が多すぎるよな…。おじいちゃんのお下がりがいまだに着れるのに、先月買ったザラのシャツは毛玉だらけ、とか、よくある。裁縫はできないので、さっそくお直しの店に行った。行動を変えてくれた一冊。
Posted by
ツテなしの状況から調べ得る限りの連絡先にメールをして中国やバングラデシュの工場に業社のふりして話を聞きに行ってたのがすごい。 ブルックリンにある仕立て屋や古着屋など、独自のセンスと運で取材に行っているのも面白かった。 Forever21ももちろん、高級ブランドをそのままコピーし...
ツテなしの状況から調べ得る限りの連絡先にメールをして中国やバングラデシュの工場に業社のふりして話を聞きに行ってたのがすごい。 ブルックリンにある仕立て屋や古着屋など、独自のセンスと運で取材に行っているのも面白かった。 Forever21ももちろん、高級ブランドをそのままコピーして売っているだけではない。ファッションショーのデザイナーたちがシーズンごとに発表するデザインは、せいぜい30から40点だ。年に365日休み無く走り続けるファッションの世界で新しいスタイルを求めるという、底なしの欲望を満たすためには、それでは足りない。ファストファッション店が流行を先取りしているように見えるのは、必ずしもコピーのせいばかりではないのだ。ショーデザイナー達も、どういうわけか突然いっせいに、大きな幾何学模様やレザー素材を使うことがある。不思議な事だが、次に述べるような流行を見通す力も関係しているようだ。 (略)「来年度どんなものが流行るかについてのヒントは、今このときにあります。そして花の聞く人や直感力のある人たちは、同じ予想に行き着くことが多いのです。デザインが当たるためには大勢に受けなくてはなりません。それをヒントにすれば、次の流行を嗅ぎつけることは可能です」。 デザイナーたちはお互いのスケッチブックを除き会うだけでは足りなくなっている。そこで昔の流行を繰り返したり、過去のデザインを盗んだりするケースも増えてきた。それがはっきりしたのは、2010年だった。スタイルが1990年代に回帰したのだ。小花柄のプリントやルーズなタンクトップ、ハイウエストのショートパンツ、コンバットブーツといったアイテムを、」昔の流行だとは知るよしもない女の子たちが買いあさっていた。 コピー商品の一番の犠牲者は比較的手の届きやすい価格の商品を扱っているブランドや中級クラスの店だという見方に、スカフィディも賛成する。「誰でもお金を取っておいて、もっと素敵なもののために使いたいと思うでしょう?消費者が「なんでわざわざ?」と考えるのはわかります」と彼女は言う。「ほとんど同じように見えるものがいつでもはるかに安く手に入るのに、なんでわざわざ本物を買う必要があるのでしょう?」 急激な変革は、テクノロジーの世界では技術の向上を生む。だがファッションの世界では、スタイルをむやみに変化させるだけだ。ファッションには向上はなく、変化しないからだ。最先端を追い求める少数の人々にとってもデザイナーにとっても、今の変化のスピードは喜ばしいものではない。その速さは常軌を逸し始めている。 ヴィンテージものの魅力は懐古趣味と高級感だが、それだけではない。アメリカの服飾業が全盛だった時代の今は失われた仕立てを身につけられる魅力もある。大衆向けチェーン店が出現する以前に作られた服はデザインがユニークで、仕立ても良さそうに見える。そして多くの場合、実際にそうなのだ。ベレケットは「今の服にはディテールというものがないわ」と切なそうに言いながら、改造作品を収めたウォークイン・クローゼットの中を歩き回った。(略)「昔はプリーツやサイドジッパー、おもしろい形の留め金やボタンなんかが見つかったものよ」と彼女は言う。 中国の工場にて リリーが私の手に押し付けたドレスは、胸の真ん中に大きな花の飾りがついた、体にぴったりフィットするミニドレスだった。香港から北に車で数時間の子の工場では、こういった流行のドレスが月に二万二千種類も生産されている。「これ、とても人気があるんですよ」とリリー入った。「お好きな色でおつくりできます」。安価な流行の服を瞬時に大量生産する大工場を自分の目で見るために、わたしは中国にやってきた。そうした工場は最先端の技術を持ち、海外からの注文を手ぐすね引いて待っている。ここも、そんな工場のひとつだった。 それでも西ヨーロッパとアメリカを除くと、中国は服の品質では世界一だ。中国には技術も熟練労働者も揃っている。人件費の安い国の中で、複雑な縫製が可能なのは中国だけだ。「他の国だと品質管理はもっと難しい」。(略)「他の国も試してみたが、」品質と値段を考えると中国以外の選択肢はないね」。 大げさ過ぎると思われるのを承知で言いたい。わたしたちは誰もが、自分の服に仕える執事であり、服が年を取っていき、やがて一生を終えるまで見届ける義務がある。不要になった服があったとしても、それを直ちに埋め立てゴミにしないで済むかどうかは、わたしたち次第なのである。次の人にも着てもらえるよう、いい状態に保っておくべきだ。つまり、持っている間は手入れと管理を怠らず、寄付したり売ったりする前には選択肢、修理するのだ。
Posted by
なんとも罪悪感でいっぱいになる。大量に服を買い、飽きたら捨てるを繰り返してきた身としては、実感を伴う。安くて流行の服はいい。買うことに対する躊躇もないし、捨てることに対する罪悪感もない。しかし、その考えに警鐘を鳴らす著者。ファッションという身近なことから、今の暮らし、幸せのあり方...
なんとも罪悪感でいっぱいになる。大量に服を買い、飽きたら捨てるを繰り返してきた身としては、実感を伴う。安くて流行の服はいい。買うことに対する躊躇もないし、捨てることに対する罪悪感もない。しかし、その考えに警鐘を鳴らす著者。ファッションという身近なことから、今の暮らし、幸せのあり方など深く考えさせられる。
Posted by
なぜ最近は服も安くてあんなに便利なんだろう、と思っていたけど、裏側ってこんなのだったのか。知った上で選択することが、消費者としては必要だと思う。
Posted by
これまでファストファッション(というか繊維業そのもの)の構造をほぼ知らなかった自分にとっては衝撃的な一冊だった。衣類も食べ物と同じで、どこでどんな風に作られたものなのかを私たち消費者がきちんと理解していないと、そのツケはいずれまた消費者に回ってくる。
Posted by
アメリカにおけるファッションの現状。流行がめまぐるしく変わるので、格安ブランドのコピーデザイン服を、多量に使い捨てる。低質のため古着にもならない。途上国の安い労働力を搾取。高品質で仕立ての良い、持続可能で地域密着型のスローファッションに目覚める。 最後はスローファッションに行き...
アメリカにおけるファッションの現状。流行がめまぐるしく変わるので、格安ブランドのコピーデザイン服を、多量に使い捨てる。低質のため古着にもならない。途上国の安い労働力を搾取。高品質で仕立ての良い、持続可能で地域密着型のスローファッションに目覚める。 最後はスローファッションに行き着いていますが、いまの時代、なかなか難しそうです。
Posted by
著者は自らもH&Mなどのファストファッションが大好きで、「お店が開けるぐらい」にたくさんのワードローブを持っている女性ライター。 翻訳物でアメリカのアパレル業界のことを書いた本なのに、他国のこととまったく思えないところに(悪い意味での)グローバル化を感じます。 ファスト...
著者は自らもH&Mなどのファストファッションが大好きで、「お店が開けるぐらい」にたくさんのワードローブを持っている女性ライター。 翻訳物でアメリカのアパレル業界のことを書いた本なのに、他国のこととまったく思えないところに(悪い意味での)グローバル化を感じます。 ファストファッション(H&M、ZARA、Forever21など)の歴史から業界の儲けの仕組み、業界の今(中国の縫製工場は人件費が高騰していて、次の一手を悩み中なことや劣悪な労働環境、安さと引き換えに品質がどんどん落とされていること等々)まで。ものすごく色んなことを考えさせられます。 印象に残ったのはアメリカのアパレル業界でも、ファストファッションの勢力拡大と合わせて、デパートが無くなり、アウトレットが流行るという現象が起きていること(デジャブ?日本も同じような気が)、ファストファッションは環境問題にも結びついていること(言われてみれば大量生産、大量廃棄な商品ですものね)。 「わたしたちは企業を非難するけど、結局、行動に責任を持つべきは消費者自身」(p258)という言葉が心にしみます。 あと権利に厳しいアメリカでもファッションのデザインには著作権が無いということを初めて知りました。だからファストファッションブランドは出たばかりの他のブランドの真似とか、過去のファッションの真似を堂々とできるそうな。(ただしこれは悪い面ばかりではなく、そうやってデザインが真似されることを歓迎しているデザイナーや企業もいる) ファストファッション中毒とも言える状況だった著者がこの取材を通じて、一つの服をリフォームで大事に着たり、服を自分で作ることに興味を持つ方向へ変わってファストファッションと手を切ったことは象徴的。読み応えのある1冊でした。
Posted by
2/3あたりまでは面白く読んだ.残り1/3は内容に新鮮味がなくなり,読み飛ばしてしまった.商品の品質は問われなくなっているというあたりが一番ビックリしたことである.
Posted by
- 1
- 2