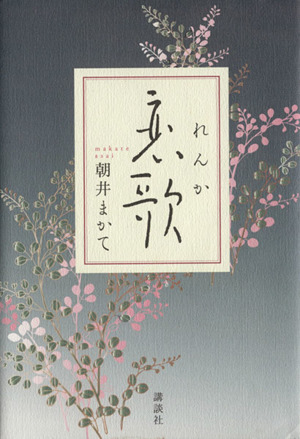恋歌 の商品レビュー
まかてさん2冊目 とても読みやすい! 歴史にもしもは無いけれど もし幕末のリードが薩長でなく 最後まで水戸だったら? 水戸藩がもっと豊かな藩だったら? 小説の内容とは離れているけど そんなことを思ってしまった これまた脱線だけど 天狗納豆が天狗党からきてることは 知らなかった...
まかてさん2冊目 とても読みやすい! 歴史にもしもは無いけれど もし幕末のリードが薩長でなく 最後まで水戸だったら? 水戸藩がもっと豊かな藩だったら? 小説の内容とは離れているけど そんなことを思ってしまった これまた脱線だけど 天狗納豆が天狗党からきてることは 知らなかった... ブックオフにて購入
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
いや〜まさかこれまで一気に読んでしまうとは思わなかった。これも直木賞受賞作だから、面白いのは間違いないはず…とはいえ、正直、この本は知らなかった。直感で手に取ったものの、まあまあの厚さだから、読めないかな〜とも思ってたんだけど。 朝井まかてさんは単行本で読むのは初めてかな? 樋口一葉が萩の舎という和歌の会の門下生であることは知ってた。なんという名前の会だったかというのは、この本読むまで覚えてなかったんだけどね。 同じ門下に三宅花圃という女性がいて、一葉より先輩で、小説も先に発表していたのは知らなかった。(思わず青空文庫で探してしまった) その女性が、病床の萩の舎の主宰だった「師の君」を訪ねるあたりから始まる。予備知識がないもんだから、そのあたりをウロウロしてたら、本編はその後のこと。そこからは一気に。 「師の君」こと中島歌子、元の名の中島登世は縁あって、幕末の水戸藩士のもとに嫁ぐ。その顛末を書いた手記が、歌子の留守宅で見つかり、花圃と師匠の秘書澄がそれを読んでいくという筋立て。 水戸藩といえば、桜田門外の変に関わりがあったり、最後の将軍慶喜公を輩出したところ。歴史音痴の私でも、昨今の大河ドラマで、多少の知識はあるつもりだったが、こんな凄まじいジェノサイドとも言えるような内乱が起こっていたとは⁈たまたま、Eテレの100分de名著でルワンダの話を聞いたばかりだったので、なんだか重なるものも感じた。同じ藩でありながら二派に分かれ、逆賊と見做すと、その家族まで根絶やしにしようとする。登世(歌子)とその義妹が投獄されたところは、ホロコーストやシベリアの収容所の話をも思い出させるような悲惨なものだった。 もちろんそんな手記が実在したわけではなく、ここが作者の腕の見せ所。 言ってみればこれも時代小説なわけで、読み慣れない言葉は何度か辞書を引いた。たまに独特の言い回しをされてるみたいな言葉もあって、老婆心ながら、朗読する時はどう読むのかな…と思ったところもあったけど。結局、読み方のわからない人物名とかあったし(音読みしたけど、それで良かったか) 最初の方でうっかり読み飛ばしてた人物が実は深い関わりがあることがわかる。慌てて前の方を探した。なるほどね。この辺りの人物はもちろん創作なんだろうな。 とりあえずこれで萩の舎と中島歌子の名は忘れないでおこうと思う。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ただひたすらにあなたを思って生きたわたし。 身ひとつで歌人として大成した師の中島歌子は、水戸藩士の妻であった。師の残した手記を読んでいくのは樋口一葉の姉弟子である花圃と、中島歌子のかつての女中である澄。師の手記は誰に何を告げるものだったのか——。 手記に引き込まれて一気に読んだ。水戸藩の天狗党の乱は、幕末の作品に割と出てくるけど、大抵の場合、時勢の読めない愚かな者として描かれる。その渦中にあった者に寄せた立場の作品を読めてよかった。だからこそ、一層あの時代に藩の中で争い、貴重な人材を枯らした水戸藩の無念をも悲しく思う。 今風の心をさらけ出すような歌をよしとしなかった師が残していた手記にあふれていた、夫への想い。そして敵への強い恨みと拭えない寂しさ。中島歌子がとてもチャーミングな人であることが、花圃の語りを通じて伝わってきた。それは復讐のために近づいた澄に、復讐を思いとどまらせるほどに。願掛けの短冊に書いた歌、牢の中の百人一首、処刑された人たちの辞世の句、思いをつないでいく歌が、さまざまなシーンで活かされているのが印象的だった。
Posted by
君にこそ恋しきふしは習ひつれ さらば忘るることもをしへよ というわけで地元びいきの★5でございますよ! ていうかなんでもっと早く天狗党の話だって教えてくれなかったのさ!もう! 茨城県人10人のうち18人は天狗党好きやっちゅうねん! 天狗納豆好きやっちゅうねん! 注...
君にこそ恋しきふしは習ひつれ さらば忘るることもをしへよ というわけで地元びいきの★5でございますよ! ていうかなんでもっと早く天狗党の話だって教えてくれなかったのさ!もう! 茨城県人10人のうち18人は天狗党好きやっちゅうねん! 天狗納豆好きやっちゅうねん! 注1)「天狗納豆」ってほんとにあります。もちろん水戸天狗党から名付けられました いやぁそれにしてもさ、小説の舞台が自分の見知ったところだとなんかこうちょっと嬉しいよね なんかソワソワしちゃうよね もちろん本作は幕末の頃の話なんで、今とはだいぶ見える景色も違っただろうけどさ もっちゃんさー、五軒町から偕楽園なんて目と鼻の先なんだからさっさと連れてったれや!なんなら水戸城より近いやろが!とか 注2)もっちゃんとは林忠左衛門以徳の愛称、勝手に付けました 注3)五軒町はもっちゃん家があったところ 注4)偕楽園は日本三大なんちゃらのひとつ 笠間街道の峠越えてそんな言うほど大変じゃなかったと思うけど、とか 注5)猪はたぶん出る 那珂川のあの辺て鯉なんか釣れたっけ?そもそも今、老女が釣り糸を垂れるよな場所じゃねーな、とかね 注6)那珂川のあの辺はけっこう深い いろいろ本筋とは違うところでにんまりしちゃうよね それも本を読む楽しみのひとつだよね 本筋には一切触れずに終わるのもレビューの書き方のひとつだよね 《私信》まかてさん次は何がオススメなのさ
Posted by
翻弄。 翻弄以外の何物でもない。 でも、翻弄されているってわかったからってそれが何かになるわけでなく、自分で生きていかねばならない。 自分の生を生き抜かねばならない。 そして誰かの生を見つめていかねばならない。 良く生きましたね。
Posted by
読み応えあり。最後の「女性が内線を終わらせた」という感じも良かった。ただ史実に基づくフィクションの場合、私のように歴史に疎い者は、『どこまでが事実???』となります。勉強しないと、、、
Posted by
幕末の江戸~水戸に生きた女性歌人の話。壮絶な時代背景、武士とは、尊皇攘夷とは何だったのだろうか。和歌の味わいをかみしめました。久しぶりに恋愛描写にきゅんとしました。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
初 朝井まかて作品。 中島歌子の歌人になるまでの、幕末激動の前半生記。 「あまりの貧しさと抑圧が怖いのは人の気ぃを狭うすることやな」貧しさゆえに制限と抑圧をお互いに強要しあう(復讐を恐れて手加減できない)。現在の私たちにも考えさせられます。 私たちは今、政治に社会情勢に無関心でいられるほど、平和で倖せに暮らしてきたと言える。こんな究極の選択に迫られる時代が、百五十年ほど前にあったとは、しかも水戸で。そして負けた方が一家で投獄・処刑させられるとは。 更に、政治は、藩内の闘争に留まらず、日本全体の幕末の激流に巻き込まれてゆく。それが”運命”というものでしょうか、あるいは、”定め”と呼ぶものでしょうか。”どうしてこうなったの?”、誰も答えられない。 尊王攘夷は、何だったのでしょうか。天狗党の乱は、何だったのか。ただ、歴史に弄ばれただけだったのでしょうか。薩長が、明治政府が天下を取っただけなのでしょうか。幕末の悲しさが浮き彫りになるようです。 牢から出た登勢とてつが、水戸からの逃避行に心が奪われる。川越から小石川そして、「萩の舎」。地獄を見た二人の生き様が恐ろしく怖い。その圧倒的なパワーはどこからって。 「明治生まれのひよっこに、いったい何がわかる」そうです。昭和、平成生まれには、もっと、深い溝を感じる。命を越えた何かを。だから、命懸けだったんですね。そして、『恋歌』。 歌人としての生き方(後半生)も気になります。関連本を探してみなきゃ!
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
幕末に、江戸で水戸藩の御定宿「池田屋」の一人娘として大事に育てられていた登世が、水戸天狗党の志士、林以徳と恋におち、激動の人生をおくった話。 当時にしては珍しいと思われる相思相愛の二人だったけど、時代が二人を引き離す。 親の反対を押し切りようやく結婚しても、肝心の夫は藩の仕事でほぼ不在。 義妹のてつは、箱入り娘(しかも町民)の登世を役立たずとしてなにもさせず、華やかな江戸から来た登世には水戸は余りにも陰気に静まり返り、実家から同行した爺やと話すことだけが日々の楽しみだった。 しかしそれすらも許されなくなる。 苛烈に尊王攘夷を主張する天狗党と、御三家として佐幕を主張する諸生党にわかれた水戸藩は、藩内での主権争いをとうとう公のものとし、幕府を味方につけた諸生党は天狗党を反逆者として討ち、天狗党志士の妻女を牢に押し込め、斬首するのだった。 登世もてつも囚われの身になり、地獄のような日をおくるが、大切な人がいつか迎えに来てくれる、それを支えに生き延びたのだ。 で、解放された二人は、江戸を目指すことにするのだが…。 の、その後の話が駆け足だったのが、残念。 いかにして登世が歌人中島歌子として世に出ることになったのかが、ほぼ書かれてなくて。 幕末の水戸が、あれだけ尊王攘夷を主張していた藩が、激動の時代にほとんど名前が出てこなくなる理由が今回わかってよかった。 しかし、水戸藩というのは、家康の思惑として勤皇を義務付けられた藩だったのではないの? 世の中が変わって幕府がなくなった時も、勤皇の藩として徳川家を残す手段として。 だとしたら御三家として佐幕を、という諸生党の主張は、時代を読んでもいないし歴史を勉強もしていないことになるね。 肝心の恋の方は、以徳も登世も純粋で誠実でとてもいい人なのだけれど(しかも美男美女?)、数々の困難を乗り越えて互いを思い合っていたのはわかるんだけど、ひとめぼれ以外の何にそんなに惹かれたのかがあまり伝わってこなかったな。 水戸藩の行方の方が気になる私が悪いのですが。
Posted by
水戸藩主・徳川斉昭(烈公)亡き後の尊王攘夷派「天狗党」と佐幕派「諸生党」との派閥争いを背景に、過酷な運命に翻弄されながら幕末から明治を生きた実在の女性を描いた感涙の歴史小説です。江戸小石川の宿屋「池田屋」の娘(中島登世)が、美男の水戸藩士(林忠左衛門似徳)に恋い焦がれ、政争に明け...
水戸藩主・徳川斉昭(烈公)亡き後の尊王攘夷派「天狗党」と佐幕派「諸生党」との派閥争いを背景に、過酷な運命に翻弄されながら幕末から明治を生きた実在の女性を描いた感涙の歴史小説です。江戸小石川の宿屋「池田屋」の娘(中島登世)が、美男の水戸藩士(林忠左衛門似徳)に恋い焦がれ、政争に明け暮れる水戸藩へ嫁いだことが、登世(後の歌子)の稀代の人生を決定づけることに。〝君にこそ 恋しきふしは 習ひつれ さらば忘るる こともをしへよ〟の31文字の恋歌に秘められた壮絶優美な結末に、感極まりました。
Posted by