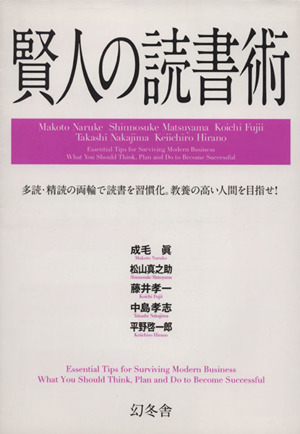賢人の読書術 の商品レビュー
賢人シリーズの一冊 5人の著名人の読書術 成毛眞氏や芥川賞の平野啓一郎氏が披露しています。 多読、選書術、インプット・アウトプット術、読書週間術、スローリーディングと多種多様です。 あなたに合った読書術が学べるでしょう。
Posted by
各人で言ってることが反発しあってたりする が、絶対的に正しい読書法がない以上、誰か一人の読書術を読むよりも複数人の読み方を知った方がいいと思う
Posted by
速読を勧める人もいますが、ぼくはスローリーディングがしっくりきます。また同時並読していますので、平野啓一郎氏の項が参考になりました。 しかし時間的制約を考えると、ハズレ本をスローリーディングすることはできないので、やはり本を選ぶ時点で慎重になる必要があるようです。 そう考える...
速読を勧める人もいますが、ぼくはスローリーディングがしっくりきます。また同時並読していますので、平野啓一郎氏の項が参考になりました。 しかし時間的制約を考えると、ハズレ本をスローリーディングすることはできないので、やはり本を選ぶ時点で慎重になる必要があるようです。 そう考えると、ジャンルを超越し読む本に合わせて、読むスピードや同時併読の量を調整していけるのが理想だと思いました。
Posted by
読書において重要なのは、本を全部読んで内容を頭に詰め込むことではなく、読むことで衝撃を受け、自分の内部に精神的な組み替えを発生させることである。 これだね!
Posted by
・良書は口コミで伝わることも多い。本の愛好家からの口コミ情報を大切にする。 ・信用できるのは現場の声。社長が書いた本ではなく、社員が書いた本を読む。 ・脳はキリの悪いのが好き?あえて途中で中断したほうがよい読書ができる。
Posted by
成毛眞さん,松山真之助さん,藤井孝一さん,中島孝志さん,平野啓一郎さんの読書術が書かれています。 が...どうなんでしょうね。 速読・多読を勧めている人がいる中で、ゆっくりじっくり読むことを勧めている人もいる。 この本の趣旨・意図がよくわかりません。 こういう所にネガティブなコ...
成毛眞さん,松山真之助さん,藤井孝一さん,中島孝志さん,平野啓一郎さんの読書術が書かれています。 が...どうなんでしょうね。 速読・多読を勧めている人がいる中で、ゆっくりじっくり読むことを勧めている人もいる。 この本の趣旨・意図がよくわかりません。 こういう所にネガティブなコメントは書きたくないのですが、自分の記録でもあるので書きました。
Posted by
成毛真氏の勧める多ジャンル多読、平野啓一郎氏の勧めるスローリーディング、それぞれの根拠などが、自分にとっては納得が入った。図解有り、大きな文字で忙しい人にもわかりやすい構成。
Posted by
読書術、ここ1、2年でほんとに少数の本を読むようになった私にはまだ早かったかな。 でも、一度に何種類もの本を読む速読やじっくりゆっくり読む読書の仕方、いろんな読み方があって面白いなと思った。 自分にあった読書術を探したい。 あと、少し読み終わらなかった。 また借りるぞ。
Posted by
どんなことが書かれているのかと図書館で借りてみたのだが???何のことはないただの、単純なハウツー本でした。 しかし、こんなこと書く必要あるのかしら? 読書好きならば、皆さん行っている事のような気がします。 勿論私も・・・・多読超並列読書型です。 「読書術」なんて大げさなタイトル...
どんなことが書かれているのかと図書館で借りてみたのだが???何のことはないただの、単純なハウツー本でした。 しかし、こんなこと書く必要あるのかしら? 読書好きならば、皆さん行っている事のような気がします。 勿論私も・・・・多読超並列読書型です。 「読書術」なんて大げさなタイトルだよ・・・まったく。
Posted by
参考になる部分もあれば、参考にならない部分もあって、結局読書なんていうものは、自分で自分のスタイルを確立していくのが一番なのかもしれないという結論にいたった私は、この本が参考になっというべきか、はたまたならなかったというべきなのか。むむむ。 ちなみに一番参考になったのは、松山真...
参考になる部分もあれば、参考にならない部分もあって、結局読書なんていうものは、自分で自分のスタイルを確立していくのが一番なのかもしれないという結論にいたった私は、この本が参考になっというべきか、はたまたならなかったというべきなのか。むむむ。 ちなみに一番参考になったのは、松山真之介さんの『価値ある良書を手にするための「選書術」』の章。
Posted by