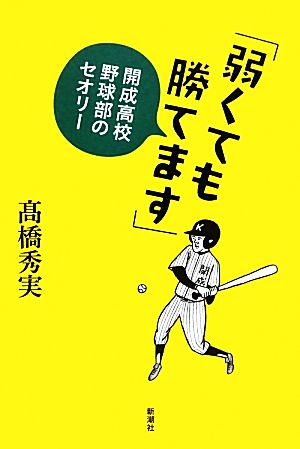「弱くても勝てます」 の商品レビュー
何度も笑ってしまい、妹にうるさいなと怒られた。野球で勝つために必死なんだけれど、必死のポイントが他の強豪校とは違っていておもしろい。守備は、大きく崩れない限りエラーをしてもオッケイ。それより、どさくさに紛れて得点するという野球。思いっきり振る。ボールに当てるのでなく物体に当てる...
何度も笑ってしまい、妹にうるさいなと怒られた。野球で勝つために必死なんだけれど、必死のポイントが他の強豪校とは違っていておもしろい。守備は、大きく崩れない限りエラーをしてもオッケイ。それより、どさくさに紛れて得点するという野球。思いっきり振る。ボールに当てるのでなく物体に当てる。賢い子たちなので何事も論理的に説明し、練習は、仮説と実験の場。発想が面白い。週に一度の練習でいかに勝つかいろいろ考えて試しているところがおもしろい。根性論でないところもいい。
Posted by
進学校がスポーツ弱いってのがそもそも偏見だし、特に野球は番狂わせも多いので、ベスト16ぐらいならどんな学校でも狙えるだろうと思う。 山際淳司的なものを期待したのだが、所詮レベルが違うということか。本書に描かれているのは普通の高校生の部活動の話であり、どこにでも転がっている単なる青...
進学校がスポーツ弱いってのがそもそも偏見だし、特に野球は番狂わせも多いので、ベスト16ぐらいならどんな学校でも狙えるだろうと思う。 山際淳司的なものを期待したのだが、所詮レベルが違うということか。本書に描かれているのは普通の高校生の部活動の話であり、どこにでも転がっている単なる青春モノでしかなく内容もお粗末。この程度の理論はどんな学校でも考えてるし、そもそも複数の学校を取材し比較したのか?表面的な理屈を取り上げているだけで、本音も引き出せないし、内面にも迫ってない。著者は全国大会に出る見込みが殆どないチームで部活動をする事とは何か?という基本的な事がわかってない。「開成」というブランドで書籍化すればいいってもんじゃないだろう。しかも活動中に実名で連載したとの事。これはいろんな意味で生徒に影響を与えたのではないか?著者のモラルに非常に疑問を感じる。
Posted by
この本はものすごく面白い。 毎年毎年、日本で一番東大へ数多くの合格者を送り出している私学の名門開成高校。 その野球部に関する話なのだが、部に所属する生徒たちにインタビューをすると、ほとんどの生徒が何でもかんでも論理的に説明しようとする。 その論理的思考によって捉えられる野球論は...
この本はものすごく面白い。 毎年毎年、日本で一番東大へ数多くの合格者を送り出している私学の名門開成高校。 その野球部に関する話なのだが、部に所属する生徒たちにインタビューをすると、ほとんどの生徒が何でもかんでも論理的に説明しようとする。 その論理的思考によって捉えられる野球論は、時としておかしな方向に進んでいく。 超論理的で、逆に素直すぎて融通が利かない頭の良い子供たち。 はたしてこんな子たちが東大へ行き社会に出て形成される将来の日本は大丈夫だろうか? と不安にもなる。 医者、弁護士、あるいは役人などには向いているだろうが、政治家や企業のトップには不向きだ。 彼らも自覚しているらしく、将来の希望を尋ねると医者や研究者などという答えが返ってくる。 おそらく開成出身で国家を動かしている人間は数少ないのではないだろうか。 そういう思いを抱く書でもある。 筆者の高橋秀実氏は、開成高校の生徒たちの裸の姿を見事に描き出している。 彼らと筆者との言葉のやり取りは、まるで異次元の会話のようで、時として笑いを誘う。 でも、彼らはふざけているわけではない。純粋に対峙しているのだ。 その方向性が常人と少し変わったアプローチの仕方だとしても。 今どきの頭の良い、日本最高峰の偏差値を持った高校生がどんな考えをしているのかを紐解くのにも最適の書でもある。 なかなか鋭い抉り方をしているので、興味のある方は是非。 おすすめです。 最後に:この中に登場する長江豊君が、東大に合格し、野球部で活躍してくれることを切に願うばかりである。
Posted by
野球というものに興味がないせいか、なるほどそういえばそうかな、というくらいの感想しか持てなかった。 打率というものは高々3割程度。 守備は、各ポジションごとでは滅多にボールは飛んでこない。 力のないチームでも、そういう野球の特性にフィットした対策を施せば「勝てる」可能性が高い...
野球というものに興味がないせいか、なるほどそういえばそうかな、というくらいの感想しか持てなかった。 打率というものは高々3割程度。 守備は、各ポジションごとでは滅多にボールは飛んでこない。 力のないチームでも、そういう野球の特性にフィットした対策を施せば「勝てる」可能性が高いし、そこそこの成果が出ている。 ということか。 でもだとすると、それは開成でなくても、指導者にその采配の能力があればいいことな気がするし、出てくる開成の生徒たちが賢げなのは、結果とリニアにリンクしない気がする。 「マネーボール」の世界が、「弱くても勝てます」なんだろうし、マネーボールの世界は、割安な戦力の組み立てで勝つことにより、その情報がいきわたれば、次の勝負では強者がその戦略を取り入れることで、崩れ去るものでしかない。 「勝てます」の程度がよくわからないが、期待したほどには面白くなかった。
Posted by
いや〜単純に野球一筋一生懸命やってる高校生に対して失礼でしょ。 「弱くても勝てます」って、勝ててないやん! 確かに普通の高校生が、普通の部活で野球やってるってことはわかるけど、本気で「甲子園」を目指して野球やってる高校生には「何甘いこと」ってなるだけだよ。
Posted by
為にはならないけど、元気がでる本。 野球が頭脳ゲームだと改めて思う。頭のいい彼らが真摯に取り組んでいるのは、野球というより命題。ともかく可笑しけくって、誰かに話したくなる。
Posted by
某元プロ野球監督なら「弱者の戦い方」とか言い出しそうだが、所詮高校野球。単純にゲームに没頭すれば良いってことです。 高校生の思考回路への途惑いを著者共々感じつつ、結局のところ、監督の青木さんの「大きさ」が端々に行き渡り、共振していく様子が下手な小説を読むより楽しめる。 それにして...
某元プロ野球監督なら「弱者の戦い方」とか言い出しそうだが、所詮高校野球。単純にゲームに没頭すれば良いってことです。 高校生の思考回路への途惑いを著者共々感じつつ、結局のところ、監督の青木さんの「大きさ」が端々に行き渡り、共振していく様子が下手な小説を読むより楽しめる。 それにしてもいつか甲子園に行けるんだろうか?読者に究極の想像の余地を与えてくれるなぁ。
Posted by
【概要と感想】 野球は単なるゲームで無駄なもの。青春とか、教育的意義とかよくわからない。 説教的なものを乗せるからつまらなくなる。本来の野球はタダのゲームの一つで、 ゲームだからこそ、勝ち負けに拘ると言ってしまったほうが良い。 日本で一番頭のいい高校の野球部に関するノンフィク...
【概要と感想】 野球は単なるゲームで無駄なもの。青春とか、教育的意義とかよくわからない。 説教的なものを乗せるからつまらなくなる。本来の野球はタダのゲームの一つで、 ゲームだからこそ、勝ち負けに拘ると言ってしまったほうが良い。 日本で一番頭のいい高校の野球部に関するノンフィクション。 半年か1年ほど前に話題になっていた1冊。 筆者の言葉を借りるなら東京大学への合格者が毎年200人近く出る 「開成高校が甲子園に出場するまでの道のりを記録”しようと”した」一冊。 記録しようとしたけど、”まだ”出場できていない。あくまでも”まだ”なのだ。 トンネルをするわ、かろうじてストライクが入るようなピッチャーが投げていようが、 筆者が描いている通り、もしかしたら甲子園に行けるかもしれないと読みながら感じてしまう。 それは他の学校と違うことをやっているから。 厳しい練習をしておらず、練習量は極端に少ない。 攻め方も”清々しい”高校野球のようなバントや盗塁などを交えた細かい野球ではなく、 打って打って、どさくさ紛れで勝つ野球。 このやり方がハマればもしかしたら、強豪校の野球エリートたちを驚かせて、トントン拍子で勝っていくかもしれない。 そんな開成高校の快進撃を見てみたい。 とてつもなく力のある相手に対して同じやり方で戦いを挑んでも負けることが目に見えている。 そんな時はやり方をダイナミックに変えてみよう。0%だった勝率が10%にまで上がるかもしれない。 【引用】 「野球には教育的意義はない、と僕は思っているんです」。 青木監督はきっぱりと言った。野球はゲームにすぎないと。(86) 【入手きっかけ】 話題になっていて、オススメもされたので購入!
Posted by
★2013SIST読書マラソン推薦図書★ 本を読んで読書マラソンに参加しよう! 開催期間10/27~12/7 (記録カードの提出締切12/13)
Posted by
開成高校野球部が甲子園予選でベスト16まで勝ち進むまでの話。 野球の楽しさと、勝つためのハイリターン、ハイリスク野球がおもしろい。少年野球チームにも取り入れたらすごくおもしろいチームができそう。頭脳派の開成のメンバーの考え方もおもしろい。野球チームの指導者にも読んでもらって感想を...
開成高校野球部が甲子園予選でベスト16まで勝ち進むまでの話。 野球の楽しさと、勝つためのハイリターン、ハイリスク野球がおもしろい。少年野球チームにも取り入れたらすごくおもしろいチームができそう。頭脳派の開成のメンバーの考え方もおもしろい。野球チームの指導者にも読んでもらって感想をきいてみたい。
Posted by