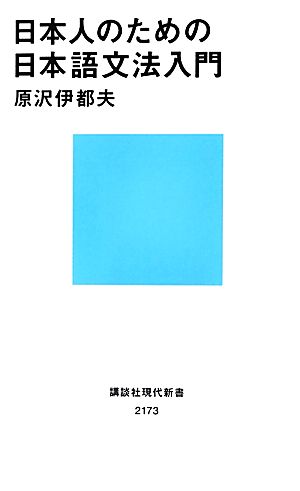日本人のための日本語文法入門 の商品レビュー
日本語の文法についての説明。学校で習った文法とは少し異なる視点で日本語文法についての見方がかわる。 主語と述語、の捉え方が違って見えるようになった。相手がわかるだろう言葉は省略されるとか。 堅苦しくなく、さらっと読めるのがよい。 また言語学者では有名な「象は鼻が長い」が引用...
日本語の文法についての説明。学校で習った文法とは少し異なる視点で日本語文法についての見方がかわる。 主語と述語、の捉え方が違って見えるようになった。相手がわかるだろう言葉は省略されるとか。 堅苦しくなく、さらっと読めるのがよい。 また言語学者では有名な「象は鼻が長い」が引用されていた。
Posted by
なんとなくもやっとしか捉えられていなかった日本語の諸現象を解釈する枠組みが得られた感覚がある。 諸所に若干の疑問を抱く部分もあったが、改めて日本語について、その背景にある思想を含め考えるとても良いきっかけをもらえた。 今後日本語学習者に質問をされた際には、再度読み返したいなと...
なんとなくもやっとしか捉えられていなかった日本語の諸現象を解釈する枠組みが得られた感覚がある。 諸所に若干の疑問を抱く部分もあったが、改めて日本語について、その背景にある思想を含め考えるとても良いきっかけをもらえた。 今後日本語学習者に質問をされた際には、再度読み返したいなと思えた。
Posted by
学校の国語で習う文法が大得意だった私。どこかで「『は』は主語に付ける助詞だから、『カレーは昨日食べました』のような文は誤りで、『カレーを昨日食べました』が正しい」と学び、今までそれを守ってました。でも、世間では主語以外にも「は」を付けて話すし、ずっとモヤモヤしていました。そんなと...
学校の国語で習う文法が大得意だった私。どこかで「『は』は主語に付ける助詞だから、『カレーは昨日食べました』のような文は誤りで、『カレーを昨日食べました』が正しい」と学び、今までそれを守ってました。でも、世間では主語以外にも「は」を付けて話すし、ずっとモヤモヤしていました。そんなとき出会ったのがこの本。学校の文法とは違った切り口から日本語が解説されていて、「は」の使い方を始めとした、学校文法では納得いかなかったところも理解することができました。
Posted by
言語は使用している国や地域の文化を表している。 日本の自然と調和・共存するような言い回しが、他言語と比較するとはっきりと浮き上がってくるのはとても興味深かった。 2章(だったかな)の「日本語文法はコト+ムード(本書参照)で完成する」と言うのは初めのうちは何を言っているんだ、コトだ...
言語は使用している国や地域の文化を表している。 日本の自然と調和・共存するような言い回しが、他言語と比較するとはっきりと浮き上がってくるのはとても興味深かった。 2章(だったかな)の「日本語文法はコト+ムード(本書参照)で完成する」と言うのは初めのうちは何を言っているんだ、コトだけで文法上は成立するだろう、と思っていたが、7章で著者がその言わんとしていることを理解できた。 「〜は」=主題、「〜が」=主格という、三上章氏の主語廃止論も納得のいく理論だった。格という成分(主格・所格・共格・対格など)は全て主題となり得、その主題をどの格にしようが文章は変化しない。 【太郎がカフェで次郎とケーキを食べる。】 ①主格が主題 太郎はカフェで次郎とケーキを食べる。 ②所格が主題 カフェでは太郎が次郎とケーキを食べる。 ③共格が主題 次郎とは太郎がカフェでケーキを食べる。 ④対格が主題 ケーキは太郎が次郎とカフェで食べる。 主格と述語の関係性はいずれの格が主題となろうとも変わらないため、述語が「食べられる」というような受身の文とならないのだ。 またこの他にも「〜は」と「〜が」の違いを説明する情報の新・旧という問題があり、これは英語の冠詞に類似するという。さらに一般論を説明する場合と中立描写文を説明する場合に分けられるという違いがある。 今までは無意識のうちに発していた日本語が、このように理論的に分かるとなんだか楽しい。他にも多くの理論を学べた。日本語って面白い。
Posted by
日本人でも(日本人だからなのか)細かい部分まで理解しようとすると、説明が難しい問題に直面する。仮に外国語として習得するとなったら、結構大変そう。特に語尾とか格助詞のニュアンスや語法は理論的に説明するのは難しい。(今ここでサマリー書くのも難しい、、) 結構印象的だったのが、言語体...
日本人でも(日本人だからなのか)細かい部分まで理解しようとすると、説明が難しい問題に直面する。仮に外国語として習得するとなったら、結構大変そう。特に語尾とか格助詞のニュアンスや語法は理論的に説明するのは難しい。(今ここでサマリー書くのも難しい、、) 結構印象的だったのが、言語体系は思っていた以上にその国の文化の影響を受けていたこと。「思いやり」の表現、「ウチ」と「ソト」の発想は確かに日本語独特。
Posted by
日本語は難しい。 日本語が難しい。 どちらも文法的には正しいけれど、与える印象が違う。 その「なぜ」を紐解く一冊でした。 普段何気なく選んでいる言葉の繋ぎには 理由と意味があったんだなあと改めて感じます。
Posted by
学校で習った国文法ではなく、論理的に日本語を説明することができる文法理論、それが日本語文法である。眼からうろこである。面白かった。ボイス(態)、アスペクト(相)、テンス(時制)、ムード(法?)。表題と解説。コトと話者の気持ち。
Posted by
読んだきっかけは文章が下手くそであるから上手く書けるようになりたいのと、国語辞典に載っている言葉の説明で物足りない時も、外国人向けの日本語教員をしている人のサイトでは納得のいく詳しい解説があったりするので、その解説の元になっている日本語文法の入門書だからである。 日本語は「必須...
読んだきっかけは文章が下手くそであるから上手く書けるようになりたいのと、国語辞典に載っている言葉の説明で物足りない時も、外国人向けの日本語教員をしている人のサイトでは納得のいく詳しい解説があったりするので、その解説の元になっている日本語文法の入門書だからである。 日本語は「必須成分+述語+ムード」で出来ている。とくにムードがなければ日本語として成立しないというのが驚きであった。自分が文末に「~と思う」を付けるのは非断定のムードをつけたくなるからだろう。 専門的には「~と」は複文の引用節というらしい。使い勝手がよいため「~と思う・~という」を頻繁に用いる傾向にある。 とてもためになる本だった。新書版のページ数の限界もあるので、もっと日本語文法について詳しい本が欲しくなった。ひとまず先に注文した国文法の参考書を読むつもりである。
Posted by
国文法(日本語)をさらっとやり直せないかと思って買った本だった。 がしかし、読んでみるといわゆる国語ではなく外国人向け(?)の日本語文法の本だった。 内容的には、膠着語の特徴をわかりやすく砕いた感じ、広く浅い。新しい発見はなく、物足りない感じ。
Posted by
外国人の学ぶ、日本語を運用するための”日本語文法”を0から教えてくれる入門書。言葉も平易でとっつきやすく、初学者には最適。
Posted by