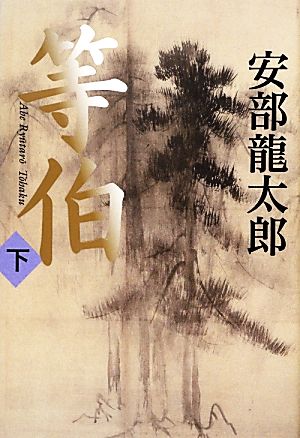等伯(下) の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
安土桃山時代、能登七尾の出身で国宝の松林図屏風を残した画家、長谷川信春(等伯)の波乱万丈な人生が描かれていた。 生家の奥村から長谷川家に養子として入り日蓮宗の絵仏師で有名なるも絵師をめざす者なら知らぬ者はいないという、大徳寺が秘蔵する牧谿筆の観音猿鶴図に魅せられ33歳で一流の絵師をめざし狩野派、狩野永徳に魅せられながらも挑戦して、頂点にたつのだが、辛く悔しい想いをしながらも認められる存在になられる姿に感動。 そこには陰日向となり支えられる2人の内助の功があってこそと感じた。 絵心の分からない自分でも松林図屏風初めとする色んな作品を鑑賞したくなった。 本当に素敵な本で沢山の片に是非、読んで欲しいなと思った。
Posted by
「残された者は死んで行った者を背負って生きて行くしかない」が印象に残りました。そして、その上で書かれた松林図を本当に観たくなりました。
Posted by
学校の授業ではさらりと終わってしまうので、狩野派のことも全然知らないことが多く、長谷川等伯の絵も見たくなりました。
Posted by
面白くはあったのだけど、等伯の人間像にもう少し深みと凄みがあっても良かったのでは?時々急に愚かになるのが、どうも納得ゆかないというか、「そういった懲りない愚かさが人間らしい」とかいうのかもしれないけど、急に他力本願か流れのままにな愚かさ発揮なだけに、その移ろい様についてけないフシ...
面白くはあったのだけど、等伯の人間像にもう少し深みと凄みがあっても良かったのでは?時々急に愚かになるのが、どうも納得ゆかないというか、「そういった懲りない愚かさが人間らしい」とかいうのかもしれないけど、急に他力本願か流れのままにな愚かさ発揮なだけに、その移ろい様についてけないフシあり。
Posted by
-2012/07/01 狩野家の総帥として才能の有無と関わりなく振舞わなければならなかった画家と溢れんばかりの才能を備えた画家の生き様の終の姿が興味深い。
Posted by
良かった。 京に出て、久蔵も絡んで本格的に狩野派と対決。 ついにここまで来たとわくわくして読み進めた。 永徳像は意外だった。 こんな風に考えたことはなかった。 でも、人物像を思い描いたことすらなかったことに気づいた。 等伯から見ることで気づかされる、 狩野派の姿というものが、興...
良かった。 京に出て、久蔵も絡んで本格的に狩野派と対決。 ついにここまで来たとわくわくして読み進めた。 永徳像は意外だった。 こんな風に考えたことはなかった。 でも、人物像を思い描いたことすらなかったことに気づいた。 等伯から見ることで気づかされる、 狩野派の姿というものが、興味深かった。 しかし、ここに来てまでも切れない畠山家と兄との繋がりが、 この時代を生きた人間の悲しさと難しさを突きつける。 そして、等伯の絵に、他の絵師とは何かが違うと感じていたことが、 彼が武家出身で、法華宗徒であることが、 深く関係しているのだということを納得した。 例えこれが、真実ではなく作られた話だと分かっていても、 こういうことを身にしみて感じられるのが、 小説の強みだと思う。 そこを描ききったという点で、この物語は成功している。 それでも、この作家を好きかというと、やはり普通。 5つに届かないのは、そこ。
Posted by
只今、石川県に長期出張中なので、七尾の人と言えば...と思い読んでみました。 活動のほとんどは京・大坂なのね♪
Posted by
恥ずかしながら、本書を読むまで長谷川等伯という人物の生涯や作品をぼくはなに一つ知りませんでした。 本書は、33歳で絵師として都へ出て、信長や秀吉の時代に翻弄されながらも現代に残る国宝松林図を描いた等伯の生涯を追うもので、親近感をもって読み進めることができました。 狩野永徳にし...
恥ずかしながら、本書を読むまで長谷川等伯という人物の生涯や作品をぼくはなに一つ知りませんでした。 本書は、33歳で絵師として都へ出て、信長や秀吉の時代に翻弄されながらも現代に残る国宝松林図を描いた等伯の生涯を追うもので、親近感をもって読み進めることができました。 狩野永徳にしてもそうですが、国宝級の絵を生み出す絵師という既成イメージを覆すような人間性豊かな人物に引き込まれました。 そしてやはり人の一生は全て繋がり、過去があって現在を生きる、今があるから未来があるという感覚を再認識しました。 直木賞受賞作品ということでまずは上巻だけのつもりでしたが、一気に下巻まで読了してしまうほど、等伯に没頭できました。
Posted by
画家の生涯を描いた歴史小説。 戦国時代と聞くと狩野永徳に意識が向きやすいが、等伯もまた素晴らしい画家であったと、この本を読めばわかるだろう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ようやく安部龍太郎『等伯(下)』日本経済新聞出版、を読了。(「上」はこちら→ http://booklog.jp/users/ujikenorio/archives/1/4121022068)。同じく、雑感を書き殴っておきます。 安部龍太郎『等伯』(上)。本書は、英雄豪傑・剣客でもなく、かといって市井への惑溺でもない「絵描き」が主人公に驚くが、まったく「時代小説」なので二度驚く。阿倍さんの「読ませる」力に戦慄した。(上)ははおおむね共感を持って読んだが、(下)は結論から言えば、自分自身との「対話」になったように思う。 安倍『等伯』。個人的趣味かもしれないが、人知を超えた英雄にも「シカタガナイ」と嘆く民衆にも興味はない。その両端には“生きた”人間は存在しないからだ。想像力を張り巡らせるなかで、等身大の人間を描き出す思考実験の一つが時代小説であるとすれば、本書は、時代を画する一書になるであろう。 安倍『等伯』。さて戻るが、(上)は共感しつつ読んだが、(下)は、「等伯」のどうしようもなさに、本を投げ出したくなるほど気分が上下した。しかし、ここが味噌なのだろう。先に自分自身と「対話」と表現したが、等伯の軌跡とは、作業仮設としての両端を排した人間としての「私」自身の歩みであるからだ。 安倍『等伯』。だから、等伯の「どうしようもなさ」にうんざりし、成功のうぬぼれに喜び警戒する。そこには、歴史教科書記載の先人がいるのではなく、読みながら自分自身の姿をみているように感じた。だから、本書を読むことは、自分の姿を等伯を通してまざまざと見せつけられることになったと思う。 安倍『等伯』。通俗的教養小説の説教も無用だが、諦めた人々の後ろ姿を匿名的に活写するのもうんざり。だから、本書は時代を画する一冊だ。英雄色を好むのでもなく、諦めの惑溺のなかに、私たちは存在するわけではない。その意味では本書は日本発のアルゲマイネ・ビルドゥングといってよいだろう。 安倍『等伯』。これは僕の読後観だけど、千差万別の誰が手にとっても違う景色でありながら同じよな軌跡を見て取るのではないだろうか。超越と内在が交差するその瞬間に、松林図を前にした近衛公のぼやき「等覚一転名字妙覚やな」が浮上する。これは日蓮の法華経講義の一節だ。 安倍『等伯』。人間が一番直視したくないものは、私自身だ。だから奇を衒う英雄に憧憬し、蓋を閉じて嘯くことで安心する。そこに七転八倒しながら……だから、どうしようもない人間なんだ、等伯は!……「生き抜いていく」。とすれば、私自身も「生き抜いていく」ことができるはずだだろう。 安倍『等伯』。松林図は、ひとつの曼荼羅である。それは仏教に由来し、きわめて「特殊」な形態をとる。文化と言葉の制限があるから「特殊」とならざるを得ない。しかし、そうでありながら「超越」していく普遍性が同時に内在する。人間も同じなのであろう。日蓮観を新たにすると同時に人間観が一新された。 直木賞受賞の安部龍太郎『等伯』日本経済新聞出版は、勿論、読んで「面白い」。しかし、ほんとうに恐ろしい小説だ。本書を手に取ることで、自分自身と対峙し、自己認識を一新していく手掛かりにして欲しいと思う。「等伯」とは、極めて私自身の事柄でありながら普遍的なのである。
Posted by