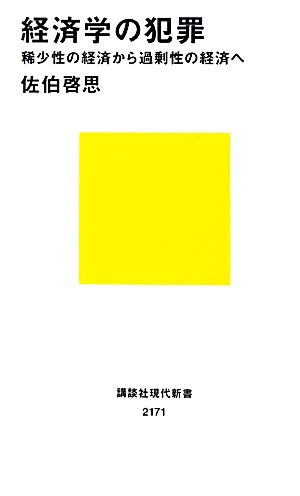経済学の犯罪 の商品レビュー
大学生のときに経済学の講義を取らなかった(今でも後悔している)が、学生の時に本書を読んでいれば経済学の講義を受講していたと思う。 受講していないので大学の経済学で何を学ぶかわからないが、おそらくStiglitzの経済学の教科書を片手に数学的な手法によって経済を分析する手法を学ぶ...
大学生のときに経済学の講義を取らなかった(今でも後悔している)が、学生の時に本書を読んでいれば経済学の講義を受講していたと思う。 受講していないので大学の経済学で何を学ぶかわからないが、おそらくStiglitzの経済学の教科書を片手に数学的な手法によって経済を分析する手法を学ぶのではないだろうか。 もっと進んで、市場を詳しく分析するために確率微分方程式を学び(伊藤のレンマ!)、市場をモデル化するのだろうか。 翻って、このような経済学は、希少性のある財をいかに効率よく分配するか、という基礎をおいている。 即ち、人は効率良くかつ合理的に動くことを仮定しているし、公開されている情報はすべての人に対して対象であるし、企業は最適な戦略をとることを仮定している。 そもそもこんな人間がいるのかという疑問はさておき、そもそも価値基準はすべての人にとって同じであろうか? お金儲けを第一と考える人もいるだろう。いやいや、働かず気ままな生活を望む人もいるだろう。環境を第一に考える人もいるだろう。 これらの考えを、無味乾燥な数式に置き換えることは可能であろうか。 経済学を勉強するのはもちろん良いのであるが、そもそも経済学の基礎をなす仮定をおろそかにしてはいけない。 本書は経済学にかかわるいろいろな論点が議論されている。 このような論点があるのか、ということを知るためにも良いと思う。
Posted by
いろいろと考え、感じていたことが、昔から経済学でちゃんと扱われてきたことが分かった。そして、私は左派なのだと理解した。 二重の経済という考えがとてもしっくりきた。
Posted by
グローバリゼーションが進むと国家の垣根が小さくなって…なんてのは戯言で、資本は激しく動くけど労働はそうでもなくて、そういう下、不安定な雇用などを安定させることこそ国家の役目。グローバリゼーションで勝っている国というのは、皆国家が強い。 そうかあ。 僕は経済学には理解も興味がな...
グローバリゼーションが進むと国家の垣根が小さくなって…なんてのは戯言で、資本は激しく動くけど労働はそうでもなくて、そういう下、不安定な雇用などを安定させることこそ国家の役目。グローバリゼーションで勝っている国というのは、皆国家が強い。 そうかあ。 僕は経済学には理解も興味がないが、脱成長というキーワードから読んでみた。今日は、とある仕事で「夢のマイホーム」という名の死屍累々な場所に行ってきた。需要もあって供給もされて、誰も損をしていないように見える事業、だけれどそこにあるのは風景も歴史も隣近所にも全く無理解、無関心、無責任な家々。こういうものを連発してきて、これからも作り続けることで景気浮揚を、なんてことの片棒はもう担ぎたくないなあ、と強く思った。 今日ご一緒した人たちは、市場の中で価値を認められないであろう。けれど豊かな場をつくることが出来る。豊かというのはもちろん過剰供給される市場流通品ではない。市場では社会的な価値は選べない、と本書も伝える。そして「善い社会」についてのいかなる「ナショナル・イメージ」も生み出せないなら、その国は文明の闇に沈んでも仕方ないのだ、とも。善い社会のパーソナルイメージは出来ている。どうナショナルにすればいいのか。こればっかりは、言葉ではなく、やってみせて、広げていくしかない。がんばろ。
Posted by
リーマンショックからのEU危機の年代に書かれた本。 主にアダム・スミスとケインズを中心にして、グローバル経済や金融問題について書かれている。
Posted by
いまお金と時間が十分にあったら何に使うだろう。やはり本を思い存分買うかな。レコードプレーヤーを買って、むかし買いためたレコードも聴きたい。旅行にも行きたい。パリには早く行っておきたいけれど(2001年9月18日出発予定が、すべてキャンセルになった)、近場の温泉にもつかりたい。エコ...
いまお金と時間が十分にあったら何に使うだろう。やはり本を思い存分買うかな。レコードプレーヤーを買って、むかし買いためたレコードも聴きたい。旅行にも行きたい。パリには早く行っておきたいけれど(2001年9月18日出発予定が、すべてキャンセルになった)、近場の温泉にもつかりたい。エコカーを買おうか、ソーラーパネルをつけようか、もっと動きのいいパソコンを買おうか。やっぱりお金が十分にあれば、買いたいものはあるよな。けれど、全体としては車がどんどん売れるわけではないし、家がどんどん立ち並ぶわけでもない。収入は減るし、安いものばっかりが売れる。というか、何でもかんでもびっくりするほど安くなった。選挙があれば、景気の回復とか、経済の成長をうたう政治家たちがいるけれど、もう成長はいいよな。人口も減り始めているわけだし、あくせく働かずに、もう少しおおらかな気持ちで過ごしてもいいよな。十分に満足しているわけではないけれど、お金の呪縛からは逃れて、太陽の恵みを受けて、幸せを感じながら暮らしていければいいかなあ。本書を読んで、私のそんな気分が、理論的にもそれほどまちがっているわけではない、ということがわかった。
Posted by
現代経済に対する批判本が数多く出版されているのは、それが簡単に書けるからではないだろうか。あたりまえのように享受されているメリットについては黙して語らず、リーマンショックやギリシャ経済破綻のようなショッキングな出来事に対してその原因をもっともらしく語り、恐怖心を煽ってこのままじゃ...
現代経済に対する批判本が数多く出版されているのは、それが簡単に書けるからではないだろうか。あたりまえのように享受されているメリットについては黙して語らず、リーマンショックやギリシャ経済破綻のようなショッキングな出来事に対してその原因をもっともらしく語り、恐怖心を煽ってこのままじゃダメだと世の中を喝破する。本書も御多分にもれずそのようなうちの一つ。しかも、証券化の際に行われるリスク分散とリーマンショックの関係など、かつてのリスク管理やグローバリゼーションのデメリットの解説としては納得できる仕上がりになっているのがなおタチが悪い。 まぁでもその後はいつも通りで逆に安心する。『私は市場競争が社会を不安定化するとわかっていた』『これがアダム・スミスの本当にいいたかったことではなかっただろうか』『現代社会は過度な競争と単純化された能力主義、短期的成果主義のせいで精神を追い詰め、生活を貧弱なものにし、社会を窮屈にしてしまう』『今日の日本人は、経済的には「豊か」であるにもかかわらず、決して「幸福」感を持てないことは間違いないところであろう』などなど。特にデータも示さずに如何にして偉人の威を借りて持論に引きずり込むかに終始する。 僕の知識の少なさゆえ疑わしく見えてしまっているだけの部分もあるだろうに、こんなような本になってしまうのは勿体無くも残念。なるほどと頷いてしまうような解説も随所あるので、しっかりと取捨選択するだけの知識を蓄えてから再読してみたい。
Posted by
現在の「自由主義」経済の限界と、あまりに短絡的な過程、時代錯誤な前提がよく分かります。合理的で納得がいく内容。基本的に現代の経済学を信用していないのですが、その不信感の根っこをきちんと説明してくれた気がします。こういう考えの「経済学者」がいることに安堵しました。 そりゃそう...
現在の「自由主義」経済の限界と、あまりに短絡的な過程、時代錯誤な前提がよく分かります。合理的で納得がいく内容。基本的に現代の経済学を信用していないのですが、その不信感の根っこをきちんと説明してくれた気がします。こういう考えの「経済学者」がいることに安堵しました。 そりゃそうですよね、社会が成熟すると人口が減る、それなのに需要が減らない、そんな前提はおかしいわけで。経済が国家を凌駕するのに国家の統制を必要とする矛盾も面白い。僕は完全自由主義も社会主義・共産主義も上手くいくとは思っていなくて、弾力性のある社会民主主義的体制が最もバランスを取りやすいと考えているので、その矛盾はすんなり受け止められた気がします。まあ、「社会」ってつけると左翼だと思われるんですけどね。その思考停止も何とかしてほしいものですが。 市場主義経済が重商主義的であること、その元になっているアダム・スミスの論に関する曲解、という視点も面白いですね。この解釈が正しいならば、生産要素というものを自由化する現在の市場主義は、アダム・スミスの否定したものになる、ということになる。うーん、時間ないけど国富論読んでみたくなります。
Posted by
『「希少性の原理」による経済学の発想は、基本的に間違っていることになる。「希少性の原理」とは、繰り返すが次のようなものだ。 無限に膨らむ人間の欲望に対して資源は希少である。したがって、市場競争によって資源配分の効率性を高め、また、技術進歩などによって経済成長を生み出すことが必要...
『「希少性の原理」による経済学の発想は、基本的に間違っていることになる。「希少性の原理」とは、繰り返すが次のようなものだ。 無限に膨らむ人間の欲望に対して資源は希少である。したがって、市場競争によって資源配分の効率性を高め、また、技術進歩などによって経済成長を生み出すことが必要となる。 …… だが、もしも私がここで述べてきたような「過剰性の原理」が支配しているとすればどうなるか。「過剰性の原理」は次のようにいう。 成熟社会においては、潜在的な生産能力が生み出すものを吸収するだけの欲望が形成されない。それゆえ、この社会では生産能力の過剰性をいかに処理するかが問題となってくる。』 佐伯先生、前読んだ本と同じこと言ってるなと思ったら、3年前にすでに読んでる作品だった…。 読み返してみても、本作は面白いし、言っていることは感覚的にしっくりくる。
Posted by
「生活の経済」、つまり基礎的な衣食住という必需品への需要が容易に満たされるようになった後には、物の「過剰性」をいかに処理するかが経済の課題となります。 その「過剰性」は、商品に付与された社会的イメージを基礎にして「他人の模倣」という「欲望」を抱いてしまう人間の本性に依ります。...
「生活の経済」、つまり基礎的な衣食住という必需品への需要が容易に満たされるようになった後には、物の「過剰性」をいかに処理するかが経済の課題となります。 その「過剰性」は、商品に付与された社会的イメージを基礎にして「他人の模倣」という「欲望」を抱いてしまう人間の本性に依ります。そのように生み出された「欲望」から資源の「稀少性」が派生するのであって、稀少だから欲するのではないということです。 社会的イメージによる欲望は必需ではないという意味で本質的に過剰なのであるから、過剰から欲望が生まれ、その欲望から稀少性が生まれるということになります。したがって、過剰こそが根本的現象なのであって、故に稀少のための経済学というよりも過剰のための経済学と言ったほうが本質を突いていることになります。 経済学や経済に対する(もちろん1つの側面であり仮説ではありますが)本質的見方を学べました。
Posted by
本書は「経済書」なのだろうか、それとも「経済思想書」なのだろうか。本書を読んで、現在の世界と日本で起きている経済的事象の全体像がより鮮明になったように思えた。 1990年代からの「失われた20年」については、マスコミでよく語られるが「構造改革」は小泉政権のみではなく、歴代の政...
本書は「経済書」なのだろうか、それとも「経済思想書」なのだろうか。本書を読んで、現在の世界と日本で起きている経済的事象の全体像がより鮮明になったように思えた。 1990年代からの「失われた20年」については、マスコミでよく語られるが「構造改革」は小泉政権のみではなく、歴代の政権が常に声高に叫んでいた。そう考えれば、日本経済は相当「構造が改革」されているはずなのに一向にその成果が上がっていないと疑問に思っていたが、本書は「デフレに陥っている経済に対して新自由主義政策は明らかにマイナスに作用する。一層にデフレ圧力をかける」と喝破する。なるほど、説得力がある。 「グローバル資本主義の危機」「変容する資本主義」を読むと、現在の世界の現状がわかったような気もするが、その結論は「先進国においてはもはや無理やり成長を追求できる時代は終わったことを認識すべき」という。 それが苦い現実であるならば、現在の安倍政権は蜃気楼を追いかけようとしていることになるのだろうか。 また「経済学」についても多くの章を割いて論考しているが、その論旨は「合理的な科学としての経済学という虚構」である。実に興味深く読んだ。 その結論の「今日の資本主義のどうにもならないディレンマ・・・今日の先進国の資本主義経済においてはもはや高度な成長は不可能である。にもかかわらず成長を続けなければ経済は破綻しかねない」とは、まさにその通りと頷いた。 本書は、最終章の「脱成長主義へ向けて」で「日本経済はもはや高い成長は望めない」と断定している。 そのための意識のパラダイム転換を訴えているのだが、その内容は「経済思想書」のようでもあるが、本当にそうなのだろうか。日本がもう低成長しかできないのならば、「政治」においても「社会」においても相当な変貌を迫られるように思うが。 本書は、現在と過去の「日本経済」をわかりやすく解き明かした良書であると思うが、それにしても「経済学の犯罪」との「書名」はひどい。この表題からは、本書の内容は全く想像もつかない。もうすこし、内容がよくわかるような「書名」は付けられなかったのだろうかとも思った。
Posted by