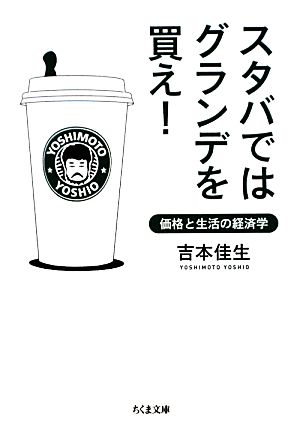スタバではグランデを買え! の商品レビュー
物の価格に関して取引コストから分析されていて大変分かりやすかった。物事のカラクリを考えてみるきっかけになった。
Posted by
色んなものの価格設定の手法について記述があり、参考になった。経済的にはもちろんだが、背景も知ることができ、思考の参考になった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
最近ありがちなキャッチ―なタイトル。経済学の基礎である「裁定」や「取引コスト」で、コンビニ・スーパーの価格、テレビ・デジカメの価格低下、携帯電話、スタバのコーヒーサイズ等々、価格設定について解説。単行本の初版が2007年なので既にやや情報として古くなっている面はあるものの、考え方の基本は同じ。例も多くわかりやすい内容になっています。
Posted by
コストについて分かりやすく理解できる本。普段からコストについては理事長によく言われているから前職のときよりはかなり理解しているつもりだったが、目から鱗のことも多くあった。特に子どもが生まれ医療費が無償というのはありがたいなぁとずっと思っていたが、共働きをしている家庭では無償化にな...
コストについて分かりやすく理解できる本。普段からコストについては理事長によく言われているから前職のときよりはかなり理解しているつもりだったが、目から鱗のことも多くあった。特に子どもが生まれ医療費が無償というのはありがたいなぁとずっと思っていたが、共働きをしている家庭では無償化になったことにより病院で待たされる時間のコストが増大するから、それで仕事を休む時間が増えれば収入も減るし、結局全体のコストが上がるという可能性もある。なんでも無償だからいいというものではないという例は、まさにその通りだと思った。 まぁでも胃がおかしくなるからいくらお得でもグランデは買わんな・・・。
Posted by
経済学なんて言葉を使われると思わず怯える私のような人に、 自販機とスーパーのペットボトル、携帯電話のプラン、 (とりたて専門的でない)事務仕事、そしてスタバのコーヒー、 ごくごく身近な例をあげて優しく根付けの基本を教えてくれる本。 「あぁ、なんとなくわかる、知ってるよ」っという...
経済学なんて言葉を使われると思わず怯える私のような人に、 自販機とスーパーのペットボトル、携帯電話のプラン、 (とりたて専門的でない)事務仕事、そしてスタバのコーヒー、 ごくごく身近な例をあげて優しく根付けの基本を教えてくれる本。 「あぁ、なんとなくわかる、知ってるよ」っという内容を 分かりやすい例と図で説明してくれる。 序盤は「実際はこんなに簡単ではないですが・・・」という枕詞が多用されるので、 本当に本当の基礎なんだろうけどとにかくグラフと図だけで理解できてしまう! あと、啓発っぽい内容?なのかな。 お仕事に関する心構えのところ、すごく救われた気がする。 一人でやるのは効率悪いよ!知ってることだけど、数値で出されると納得。 おぼえたことめも。 ・同じ価値のものを異なる価格で売買されているとき、その差額を利用して設ける裁定取引 ・同じ価値のものでも価格差が生まれるのは取引、物流コストによる差 ・コストの節約は販売側・消費者双方の協力で成り立つ (低価格のサービスなどは手間の半分をお客さんに委ねてコストを節約) ・付加機能に弱い消費者、こだわりをがあれば高くても買う76% 「高く買う人には高く、安く買う人には安く売る」が企業の一番 ・商品にはある程度の固定費(家賃・光熱費・人件費)+材料費(一番安いくらい!)、 だからグランデを買うのはお店にも消費者にもありがたいことなんだよー。 ・比較優位を持つ=機会コスト(その作業をすることで他作業がどれほど犠牲になるか)が安い ・誰にでも相対的にではなく比較優位を高くもてる仕事がある(得意分野がある)から、 うまく仕事を振り分けで全体効率をあげる! ・能力が高いことより自己評価が正しくできることが大切。 自信がなければ確認が厳密になる、奢ると怠慢になる…。 ・仕事は、自分の力を理解し、相手が何を求めるか考え、熱意をもって説明できることが大切。 ・依頼人が見ていないところで手抜きしたり、 利益にならない仕事のしかたをすること、モラルハザード。 ・規模の経済性、「生産規模が拡大されれば1台あたりの生産コストは下がる」という原理。 ・平均的な消費者になる工夫をすれば、お得に生活できる気がする。 何が一般的になれるか見極められるようになりたい。 らくらく収納BOX
Posted by
※書きかけです ◯4章 携帯電話の料金はなぜ、やたらに複雑なのか? 人によって、携帯電話の使用形態が違う(通話やメールをよくする人、しない人など) 携帯電話会社はそれぞれの人の使用形態に合わせて、より多くの利用者に契約してもらうために多くのプランを作成、そのため複雑化してい...
※書きかけです ◯4章 携帯電話の料金はなぜ、やたらに複雑なのか? 人によって、携帯電話の使用形態が違う(通話やメールをよくする人、しない人など) 携帯電話会社はそれぞれの人の使用形態に合わせて、より多くの利用者に契約してもらうために多くのプランを作成、そのため複雑化している 賢い消費者でいる為には、自分の設定している料金プランが自分にあっているのかを日頃チェックすることが大事 ◯5章 スターバックスではどのサイズを買うべきか?
Posted by
コスト構造がわかりやすく説明されている。企業の競争力、ビジネスモデルの違い、マーケティング、基本を学ぶにはいい本。
Posted by
断片的で底の浅い議論。 実例メインで説明したいのは分かるが、構成が甘いので例同士がロジカルに繋がらない。 根っこの原理に触れずに方法論だけですべてを説明しようとする手法は、読者を馬鹿にしていると感じてしまう。 それを、編集の過程で省かれた○×の章があると筆者の考え方がより伝...
断片的で底の浅い議論。 実例メインで説明したいのは分かるが、構成が甘いので例同士がロジカルに繋がらない。 根っこの原理に触れずに方法論だけですべてを説明しようとする手法は、読者を馬鹿にしていると感じてしまう。 それを、編集の過程で省かれた○×の章があると筆者の考え方がより伝わったかと思うと弁明するのは、違うだろうあまりにも。 「一般の人向け」と言って本質を隠すのは、逆効果と言いたい。説明できる筈の筆者なので、余計腹立たしいのである。 規模の経済性のあたりで、生産が増えると一台毎のコストはホラこんなに下がるのです、だからたくさん生産すると経済的にはお得と言うことになります、というのは、何言ってんだ母数増やしてるのに単価だけ見せてホラ利益アップなんて国政みたいな詐欺はヤメロ、という気分でした。 比較優位の話はなるほど、と発見。医療費無償化の話も、なるほどなるほど、と勉強になったが、こんなに伏線なくても理解できるだろう。 あとがきの秀逸さがすさまじく、ほら見ろ伝えたい内容がぶれてるから構成がぶれるんじゃい、と言いたくなったが、評論を読むだにどうもイイ人らしいなこの筆者は、と分かったのでじゃあもう仕方がない。
Posted by
普段から接するモノの値段について、わかりやすく説明することにより、世の中の経済の仕組みがわかるようになっている。 また、それだけでなく、顧客の行動原理というものがよく理解でき、ビジネスのヒントにも活かせるような内容となっている。
Posted by
扇動的な本かと思いきや、結構ガチガチの経済入門書で、なかなか読むのに苦労しました。 しかし、身近な実例を扱って説明が行われているので、分かりやすく、身近な経済に対して興味が湧くような内容です。 内容、ボリューム共に自分にとっては中々読み応えのある本でした。
Posted by