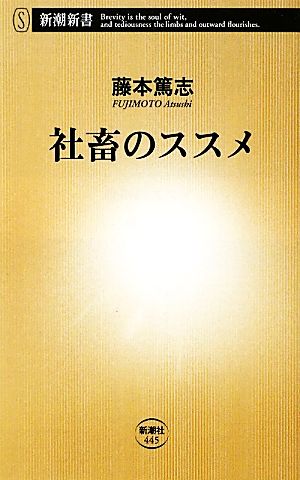社畜のススメ の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
現代社会でよく言われる「個性」や「自分らしさ」に警鐘を鳴らしているのが本書でしょう。 ある人にも「個性」や「自分らしさ」があるのはそうだが、会社にも会社の「個性」や「会社らしさ」があるのであり、会社に所属する以上はそれを順守する必要があると述べている。乱暴な言い方ではあるが、勝手にやりたければ自営業や起業をするべきであり、リスクなどを考えて入社したからには会社の言う事を聞くべきであると主張。 また、自己啓発本やビジネス本などでは「個性」や「自分らしさ」を強調しているが、そういった本を書いている人は所謂「天才型」であり、凡人が真似しても上手くいくはずがないのである。 世阿弥の守破離を会社においても実践するべきだと述べている。守の段階では、会社のやり方や知識を身に付け、会社人としての基礎を高める段階であり、破の段階では、知識を組み合わせたり、応用したりすることが大切であると述べている。近年では守の段階=下積み時代=社畜と捉えるサラリーマンが多く、自分らしさを追求したがる傾向にある。 感想としては納得のいくことが多かった。 会社は組織として動いてあるのであり、組織としての強みは組織力や団結力であり、みんなが一つの目的のために一丸となれる力にある。しかし、近年では個性が強くなってしまい、基礎ができない人が多いと言われている。 これは教育にもいえると考える。子どもの個性の前にみんなで協力したり、人の話を聞く力が大切なのである。天才と言っても一人で実現できる力は限られており、みんなでこなした方が断然早いのである。協調性や組織が上手くいっている段階において個性を発揮することでコミュニティとしても波に乗るのである。
Posted by
自称社畜のわたしからすると当たり前の内容を書かれているので、目新しい発見のあまりない本でした。この本の内容が必要になる 「新入社員」は恐らくこういった啓蒙的な本には興味を持たないので、本の内容が空回りしている印象を受けます。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
仕事に限らず、現状の不満ばかりに嘆いて、本来するべき努力を怠っていたのではないかと考えさせられる内容でした。 新入社員の若者だけでなく、いろんな人が、それぞれの立場で考えさせられると思います。
Posted by
社畜という言葉を使っているが、 もしろ、下積み期間を有効に過ごすための心がけとも言える ベストセラー本の著者の背景を探れば、 より本質に近づけると思います
Posted by
社畜のすすめ / 藤本 篤志 / 2012.7.25(29/108) サラリーマンとして働くための基本的な心構えを就職準備段階で教えていない現在の教育が問題。 サラリーマンの4大タブー:①個性を大切にしろ、②自分らしく生きろ、③自分で考えろ、④会社の歯車にはなるな。 ...
社畜のすすめ / 藤本 篤志 / 2012.7.25(29/108) サラリーマンとして働くための基本的な心構えを就職準備段階で教えていない現在の教育が問題。 サラリーマンの4大タブー:①個性を大切にしろ、②自分らしく生きろ、③自分で考えろ、④会社の歯車にはなるな。 多様性は聞こえはいいが、組織の弱体化を招いている。個々の力ではなく、組織的な全体力でこそ力を発揮するのが日本人の武器だったはず。欧米との競争に勝つために取り入れた舶来の心地よい個人主義が日本人の体質になじんでない。 サラリーマンの不幸なことは、組織の中で孤性化してしまい、居場所がなくなること。 サラリーマンの成長ステップ:①ひたすら知識カードを増やす、②知識カードを組み合わせる練習を繰り返すことで検索エンジンを磨く、③応用を実践することで、さらに知識が増え、検索エンジンの能力も向上する。 守破離のプロセス。守が卒業できてない人が破に行くのは危険。 自分なりに考える、はほとんどどうでもいい。 内部で使用されているロジックや言語をわきまえなければ、まともな議論ができず、力を発揮できない。 ピークエンドの法則(ダニエル・カーネマン):あらゆる経験の快苦の記憶は、ほぼ完全にピーク時と終了時の快苦の度合いで決まる。 成果主義:バブル崩壊の焦りで、左ハンドルの外車に飛びついた。 ダメな社畜にならないために、①すべて一歩早く、②他の世代を見る、③社内人脈はなり行きではなく、意図的に広げる、④社内情報には気を配る、⑤成功者の結果だけみない、⑥継続的な情報収集を心掛ける、⑦自分の見え方を意識する、⑧社畜時代は、管理職になるための通過儀礼。 ワーク・ライフ・バランスではなく、ベターワーク・ベターライフ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
大学生・入社5年目くらいまでの若手”サラリーマン”向けの本。 相当パンチ力あるタイトルから想像できる「社畜になって、大規模農場にしがみつきなさいれ」といった内容というよりは、 将来独立して活躍するビジネスマンになるための基礎固めとしてアウトプットよりもまずはインプットをしてみることの大切さを「社畜時代」としてとらえている。 世阿弥の「守破離」が本文中に出てくるが「自己実現」というなんとも綺麗な言葉に踊らされて、もっとも泥臭い部分を経験することが害のようになっていた自分がいたのでこうした視点で読むとまた社会が新鮮に思える。
Posted by
イタい社員はもういらない! ― http://www.shinchosha.co.jp/book/610445/
Posted by
タイトルからしてなかなか強烈な印象を受けたが、内容は特別厳しいことを言っているわけではなかった。 下積み期間ないしは歯車となる期間が一定以上必要だということは納得できた。組織に所属する以上はその組織の“文法”なるものを理解しなくてはならない。そのためには“歯車”となることは必須だ...
タイトルからしてなかなか強烈な印象を受けたが、内容は特別厳しいことを言っているわけではなかった。 下積み期間ないしは歯車となる期間が一定以上必要だということは納得できた。組織に所属する以上はその組織の“文法”なるものを理解しなくてはならない。そのためには“歯車”となることは必須だ。 そして一定以上歯車としての経験値を積んだ上で、初めて1人前のビジネスマンとして闘うことが出来るのだと納得した。
Posted by
タイトルの付け方で戦略的に勝利。 内容は常識的。 但し、人生はそれぞれなので「かくあるべし」は、ひとつたりともない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
チェック項目12箇所。部下の指導がどうもうまくいかない、甘やかすのも良くないが厳しくすると嫌われるのではと恐れているーーそんな上司、先輩サラリーマンたち、会社のどこが間違っているのかがわからないーー経営者たち、私は、この本をそういう人たちに向けて書きました。サラリーマン生活の快適度が高まることを保証いたします、さらに、サラリーマンの本質がわかるようになることも保証いたします。「自分らしさ」を常に追求することは、人間として健全な行為であるのは間違いないことなのです、しかし誤解を恐れずに言えば、サラリーマンとは、葛藤しながらも「自分らしさ」を捨ててしまう存在なのです。サラリーマンの正しい姿とは、個性を捨て、自分らしさにこだわらず、自分の脳を過信せず、歯車になることを厭わない存在となることである。結局のところ、誰かに雇用されるという人生を選択した時点で、自分の石が通る部分は少ないと自覚すべきです、それが嫌ならば芸能人やプロスポーツ選手や芸術家のようなフリーランスの仕事を選び、なおかつ頂点を目指すしかありません、なぜなら、そういう仕事においてもトップクラスにならなければ、クライアントの意向を気にしなければならないからです。サラリーマンにとって親に相当するのが会社、もしくは上司です、栄養とは、経験を含めた知識です、上司に身を委ねるということは、知識の取捨選択をすることなく、会社側が教えようとしていることを実践を通して、すべて受け入れるということなのです、すべて受け入れることにより、栄養の偏りの結果生じる虚弱体質になる確率は相当軽減され、成熟した大人、つまり歯車を動かす側の立場を十分に担える偏りのない知識が身に付いた、成熟サラリーマンになる土台を築くことができるのです。上場企業や長く続いている企業の多くは、労働基準法に則って業務を行っています、コンプライアンスがうるさい昨今では当然のことです、おそらく、新入社員が「ブラック会社」と感じたことのほとんどは、その会社の伝統的な通過儀礼に過ぎないと思われます。一点ただし書きがあります、栄養を与える側は、腐った食べ物や、心身に害を与える栄養を与えてはいけません、受ける側も吸収してはいけません、 言い換えれば、法に触れる指示命令、人に危害を与える指示命令に対してまで社畜になる必要はないということは付け加えておきます。人は必ず群れを成します、人が複数集まれば、いくつかの集団ができます、その集団が意思を持つようになれば、それは派閥となります、会社で働けば、必ずといっていいほど派閥と接点を持つようになる。上司も部下も酒が好きならば、どんどん呑みに行けばいいだけのことです、早朝のコミュニケーションのほうが、居酒屋でのそれに勝るという保証はどこにもありません。学歴主義に強い抵抗感を示しているのは日本だけのような気がします、お隣の韓国をはじめ、エリートは国家の財産であるという姿勢を打ち出している国のほうが多いのです。安易な世代論は無意味です、それぞれの世代に、良さと悪さがあるのです、安易なレッテル貼りをおして「わかったつもり」になっては、学ぶ姿勢が失われてしまいます。上司を親と考え、会社を自分の家として心に迎え入れてください、まず、上司と会社を信じることから始めるべきです。
Posted by