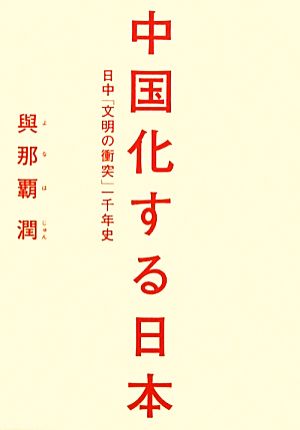中国化する日本 の商品レビュー
久しぶりにへーへーへーっと面白く読むことができた。 「中国化」と「江戸時代化」の揺らぎの中で、近代から現在までの再解釈と未来をちょいちょい。高校時代に日本史とっていなかったことが幸いするのか、作中の大きな文脈が、とっても面白く腑に落ちた。 この解釈が研究者で合意されているなら...
久しぶりにへーへーへーっと面白く読むことができた。 「中国化」と「江戸時代化」の揺らぎの中で、近代から現在までの再解釈と未来をちょいちょい。高校時代に日本史とっていなかったことが幸いするのか、作中の大きな文脈が、とっても面白く腑に落ちた。 この解釈が研究者で合意されているなら、教科書に反映されると良いねぇ。日本の教科書ってどの領域でも、細切れかつ表面的で、幹がしっかりしていないから、つまんないのよね。ちょっと違うけど、教科書も「江戸時代化」の結果だと言えちゃうかな?
Posted by
宋代の中国は世界史上もっとも早く中世(「封建制」)から抜け出し、中央集権的な社会(「郡県制」)を創り出し、かつ自由で競争的市場が成立した社会であった。日本は、源平の争いの中で、そのような近世社会になるチャンスがあったが、平氏滅亡とともにその道は閉ざされ、以後、「建武新政」や「織豊...
宋代の中国は世界史上もっとも早く中世(「封建制」)から抜け出し、中央集権的な社会(「郡県制」)を創り出し、かつ自由で競争的市場が成立した社会であった。日本は、源平の争いの中で、そのような近世社会になるチャンスがあったが、平氏滅亡とともにその道は閉ざされ、以後、「建武新政」や「織豊政権期」を除くと、中国とは異なる日本型近世(江戸時代)を完成させる方向で進化していった。 明治維新政府は、日本型近世の矛盾が噴出し、「中国化」を目指す勢力が覇権を握る政権として誕生するが、その後、すぐに「再江戸時代化」の反動に見舞われる(自由民権運動などもそうした視点から位置づけられる)。やがて昭和に入ると「軍国主義」というブロン(中国化と江戸時代化の混合物)が成立。戦後ももっとも完成した「社会主義国家(=再江戸時代化)」として、高度成長を達成していった。しかし、1970年代の石油ショックとチリのクーデターは、再度世界を「中国化」していく契機となった……。 著者の斬新な切り口によって語られるストーリーを非常におおまかにまとめると以上のようなものかと理解できる。近年の歴史学の研究成果が明らかにしてきた史実をもとに「大きな歴史物語」を構築してみせる著者が、まだ32歳というのには驚きだが、西欧中心史観の限界が明らかになって久しい今、このような視角で歴史を見ることは非常に重要だと思う。 ただし、適宜オリジナルの参考文献にあたって議論をフォローすることも大事。また映画への言及も多く、こちらも見ていない人はきちんと見ておくべきであろう。
Posted by
完読。自社さ政権が小沢一郎の「中国化」政策へのアンチとして成立した江戸時代延長連合だったとの解釈は納得。安倍政権の謳った「美しき国」と「構造改革」のチャンポンが座りが悪いと感じていた理由も分かった。もう一度再江戸時代化をしている時間的な余裕は無い。より良い「中国化」を図っているべ...
完読。自社さ政権が小沢一郎の「中国化」政策へのアンチとして成立した江戸時代延長連合だったとの解釈は納得。安倍政権の謳った「美しき国」と「構造改革」のチャンポンが座りが悪いと感じていた理由も分かった。もう一度再江戸時代化をしている時間的な余裕は無い。より良い「中国化」を図っているべきとの思いを強くした。 5章まで読了。子供の頃、ある一定年齢の老人の名に「義」のつくことが多いに気づき、尋ねた所、田中義一(山東出兵、東方会議、張作霖爆殺と「対外硬」な宰相)にあやかっているのだと聞かされたのを思い出した。 4章まで読了。そういえば江戸が舞台の落語というと、独身男と大家しか出てこないのが多いのを思い出した。著者の、出典をドンドン挙げながら腑分けしていく様が誰かに似てるなあと思ったら、初期の浅羽通明のスタイル近いな。しかし、本読むの遅くなったな私は・・・(´・ω・`) 2章まで読了。「何故日本の貨幣普及は何度も頓挫したのか」という貨幣博物館見学時の謎が解けた。続き読むのが楽しみ(´∀`*)ウフフ
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
最近読んだ日本の近代史に関する本の中で、一番インパクトがあった。近代化は西欧発の近代化という見方が主流であるが、身分制の廃止、自由な市場という意味における近代化は宋代の中国で起こった。この流れが中東を経由して辺境の地ヨーロッパにも広がったという史観のもとに日本近代史を再構成している。この観点で見ると平家とは宋の近代化を日本に輸入しようとした勢力であり、源氏は守旧派である。日本は不幸なことにこの近代化を拒否続け、江戸時代のような反近代的な封建社会を守り通した。しかし、江戸時代の後期に発生した社会の不満が、ヨーロッパ経由の近代化とうまく干渉して、いち早く西欧近代の技術導入、産業化に成功した。しかし、政治的には徐々に反近代化(江戸化)し、封建制的な国家社会主義体制になって、中国との戦争に敗れた。しかし戦後の経済成長は国家の目的が戦争から経済成長に変わっただけで基本的な仕組みは温存され、田中角栄時代に最盛期を迎える。しかし、1970年代後半から米英中は中国化を推進する中で、日本は大きく中国化から取り残される。
Posted by
これは面白かった! 歴史の知識も時々はアップデートしてやらないと、いつまでも中学校で習ったことだけで世の中見ていたら確実に明日を見失う、と強く思った。 論文調で書かれたらとっつきにくい事柄を、くだけた感じで書いてくれてるので、頭に入ってきやすい。 詳しく知りたければ原典に当たれる...
これは面白かった! 歴史の知識も時々はアップデートしてやらないと、いつまでも中学校で習ったことだけで世の中見ていたら確実に明日を見失う、と強く思った。 論文調で書かれたらとっつきにくい事柄を、くだけた感じで書いてくれてるので、頭に入ってきやすい。 詳しく知りたければ原典に当たれるよう、引用文献が載ってるのがフェアでいい。 「ブロン」は流行語に推したいくらいです。
Posted by
本のタイトル、とくにサブタイトルはなんだかなぁ?という感じですが、まあ、刺激的なタイトルで本を売ろうとする手口なのは仕方ないか。 文体も学術書のような文語体ではなく、口語体で読みやすい本です。著者の「中国化」vs「再江戸時代化」という、切り口で歴史を俯瞰してみるという試みは面白か...
本のタイトル、とくにサブタイトルはなんだかなぁ?という感じですが、まあ、刺激的なタイトルで本を売ろうとする手口なのは仕方ないか。 文体も学術書のような文語体ではなく、口語体で読みやすい本です。著者の「中国化」vs「再江戸時代化」という、切り口で歴史を俯瞰してみるという試みは面白かった。 128ページの”「悔しかったらおまえも勉強して勝ち組になれ。話はそれからだ」とお説教してベストセラーになったのが、かの福沢諭吉先生の「学問のすすめ」でした。”というのは、ほんとかなぁともおもうのだが・・・。
Posted by
教科書的な日本史理解はもう古い、「中国化」と「江戸時代化(反中国化)」という二つの対立軸の往還を基調にしたら、まるで違う歴史像が見えてくる!...という趣旨の本。話題になっている新刊だが、筆者の広範な勉強量に支えられており、非常に面白い。 この本では「源平合戦での平氏の立場」か...
教科書的な日本史理解はもう古い、「中国化」と「江戸時代化(反中国化)」という二つの対立軸の往還を基調にしたら、まるで違う歴史像が見えてくる!...という趣旨の本。話題になっている新刊だが、筆者の広範な勉強量に支えられており、非常に面白い。 この本では「源平合戦での平氏の立場」から始まり「戦国時代の意味付け」「近代化=西洋化?」など、様々なトピックを上述の観点から一つのストーリーにまとめていく。ただ総じて、筆者は「日本が中国化してきた」とは語ってなくて、むしろその力点は「なぜ日本は中国化に失敗し続けたか」という「江戸時代」的構造を語る点にある。ただ、いよいよその構造が維持できなくなっていそうな現在、このまま中国化するの?どうするの?という所でこのストーリーは終わる。中世から現在までを一つの観点でまとめていくその手際は見事。歴史学の新しい成果だけでなく、それ以外のジャンルの本や映画なども駆使する博捜ぶりにも、誰しも感心する所だろう。 あと、この本は歴史の本でもあると同時に政治論でもある。権威(道徳)と権力が一致した儒教的体制っていうのは、エリートが人民の幸福を考えて統治するという功利主義的な統治モデルとも親和性が高いはず。この本の「中国化」をめぐる議論は、いわゆる西洋近代の議会制民主主義や、それとはやや異なる「江戸時代的」な小単位を基礎にした日本型民主主義も含めた統治モデルの中から、どういう統治モデルを僕たちが選択するのかという問題でもあるなあと考えさせられた。 ただ一方で、「誤解」をわざと招こうとするタイトルや、「これが真説!」的断言調をはじめ、「その筋の人々」を茶化しながら書き進める筆致は、好みが分かれると思う。正直言って、僕自身はあまり好みではない。これがこの本に限って意識的にとっている文体だということはわかるんだけど、マーケティング意識がちょっとあからさまかなあ。あとどうせ茶化すんなら、「その筋の人々」や「高校の歴史の先生」じゃなくて、同業者を茶化しながら進んだらどう?みたいなことも、ちょっと気になったかも。 でも全体としては色々と刺激を受ける面白い一冊。もちろんこれだけ大風呂敷を広げたらそりゃ細かい所を専門家がつついたら色々と穴が出てくるだろうと思う。まあ、それは「そういうもの」で、そのチェックのためにこその厖大な参考文献一覧。その意味でこれは「この本をサカナにあれこれ言ったり考えたりするための本」という位置づけだし、そういう使い方をされることにこそ意味があるんじゃないかな。ぜひどうぞ。
Posted by