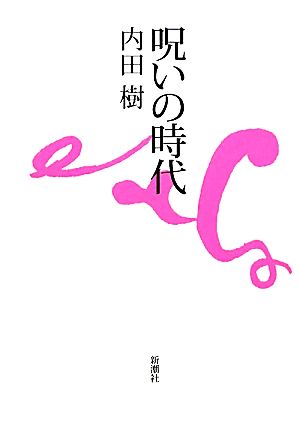呪いの時代 の商品レビュー
やはり本書は、内田樹さんの本でいちばん好き。 テーマも比較的バランスよく、読みやすくまとまっているように思います。 呪い、婚活、贈与、知性の使い方など、共感できる話が多い。 内田さんの本がなんでおもしろいかって、ほかの方たちが突き詰めないようなところまで「自分の頭で」考えているか...
やはり本書は、内田樹さんの本でいちばん好き。 テーマも比較的バランスよく、読みやすくまとまっているように思います。 呪い、婚活、贈与、知性の使い方など、共感できる話が多い。 内田さんの本がなんでおもしろいかって、ほかの方たちが突き詰めないようなところまで「自分の頭で」考えているからなのでは、と思いました。 本書は、何度も何度も読み返して、内田さんの感覚をつかんでいきたいところです。
Posted by
なんかすごい怒ってんなーってぼんやりしつつ読んだけど、結婚ってシステムとか大人になるって感覚とかの一考察は現実的で冷静な面白さがあった。
Posted by
一番印象に残ったのは、9章の『神の言葉に聴き従うもの』です。ユダヤ教に関して、私がずっと疑問だったことの回答がありました。 厳しい戒律を2千年以上守って暮らしてきたのに、神の助けなく600万もの人が虐殺される。民族存亡の危機に、いま救世主が現れずにいつ現れるの?大戦後にイスラ...
一番印象に残ったのは、9章の『神の言葉に聴き従うもの』です。ユダヤ教に関して、私がずっと疑問だったことの回答がありました。 厳しい戒律を2千年以上守って暮らしてきたのに、神の助けなく600万もの人が虐殺される。民族存亡の危機に、いま救世主が現れずにいつ現れるの?大戦後にイスラエルが建国されたことをプラス加点したとしても、周辺国からは攻められっぱなしで、落ち着く暇もありません。そんな神さん、私だったら、とっくに見限ってるわ、とずっと思っていました。 それをレヴィナスという哲学者は、「ホロコーストは人間が人間に対して犯した罪である。人間が人間に対sて犯した罪は人間によってしか購うことはできない。それは神の仕事ではなく、人間の果たすべき仕事である。」と言って説得したそうです。さすがフランス人、大学のセンター試験に哲学の科目があるだけのことはある、と頭の良さに感心しました。
Posted by
呪いっていうとなんだかオカルトな話のようだけど、呪う心が自分の肉体を離れて葵の上を殺す生霊となった源氏物語の六条の御息所。それと同じことがデジタル・情報化時代の今も、呪詛は記号化されて「ある」。という比喩がわかり易かったです。
Posted by
いま、ここ、の自分をカッコにくくること。等身大の、たいしたことのない自分を愛すること。生きる上で学ぶことが多い本。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
1.内田樹『呪いの時代』新潮社、読了。相互の違いを踏まえた上で合意形成を目指す気などさらさらない…これが現在の言語空間の支配的体質ではないだろうか。相手を屈服させる為だけに捻出される無数の言葉はまるで「呪詛」。本書は雑誌エッセイを纏めた一冊だが、呪いを切り口に現在を浮彫りにする。 2.内田樹『呪いの時代』新潮社。勿論、呪詛の背景には、現状を変えたいという苛立ちがあることは否めない。しかし、「『現実を変えよう』と叫んでいるときに、自分がものを壊しているのか、作り出しているのかを吟味する習慣を持たない人はほとんどの場合『壊す』ことしかしない」。破壊は創造より楽だから。 3.内田樹『呪いの時代』新潮社。呪詛する者は、破壊するだけでなく、そのことで自身の承認欲求を満たそうとしている。嫉妬や羨望、そして憎悪が一人歩きする現代。著者は生活とぱっとしない「正味の自分」に注目するよう示唆。等身大の人間とその生活から言語が切り離された瞬間、呪詛は立ち上がる。 4.内田樹『呪いの時代』新潮社。呪詛合戦は疲弊を相互に招き、やすっぽい「征服感」しかもたらさない。そして「苛立ち」をぬぐうことは不可能であろう。だとすれば「呪い」ではなく「贈与」へエネルギーを注ぐほかあるまい。本書は、自身の言説を振り返る契機になる一冊ではないだろうか。 5.内田樹『呪いの時代』新潮社。出版社による内容紹介→ http://www.shinchosha.co.jp/book/330011/ 内田樹「呪いの時代に」:現代ビジネス→ http://gendai.ismedia.jp/articles/-/28694 了。
Posted by
数ある(著者の)著作の中でも、わりに好きな主題(「呪詛」と「贈与」)であったため、面白く読めた。ものすごく大雑把になるが、他者や外部に対する敬意がそこに底流しているからこそ、なかなか気持ちよく読めるのだと思う。最近普通に生活をしていて、どのように他者に対して敬意を払えるかというこ...
数ある(著者の)著作の中でも、わりに好きな主題(「呪詛」と「贈与」)であったため、面白く読めた。ものすごく大雑把になるが、他者や外部に対する敬意がそこに底流しているからこそ、なかなか気持ちよく読めるのだと思う。最近普通に生活をしていて、どのように他者に対して敬意を払えるかということが、自分の中で自覚的になっている。敬意を払うというのは、何も相手の言うことを何でも尊重するとか、争いごとを避けるためのマナーとして(だけ)の行為の話ではない。お互いの”知的パフォーマンスを活性化"させたいがために、敬意を払いたいのだと思う。それは最終的に「正解」を求めたいからとか言うよりも、単純にお互いのパフォーマンスを上げることが気持ち良いから。但し(ビジネスにおける)「正解」を求める姿勢も決して過小評価してはならないため、そこの折り合いをどう付けるかがサラリーマンとして、あるいは集団生活を営む上で大事なことなのだと思う。これからも悩んでいきたい。
Posted by
いやぁ、面白かった。内田樹の面目躍如の文章だった。贈与論に対してまとまった考えが述べられていて、今までの知識が整理されてよかった。知的のんびり状態を満喫できた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「呪詛」と「贈与」を主題にした『新潮45』での不定期連載の内容と、 東日本大震災で露呈したグローバル資本主義と日本的システムの問題点に対する考察をまとめた一冊。 以下、印象に残ったところ。 ◇子供たちに「身の程を知らせる」という学校教育の重要機能 一方で本の後半では、有事に対応出来る"フツーじゃない"人材を育てる重要性を 説いている。 あれ?矛盾してね?と思った瞬間、ハッとした。「身の程を知る」事と、「フツーの人間になる」事を混同していた・・ 。 「身の程を知る」とは「出来る事と出来ない事を認識する事」であって、別に 「出来る事を抑制してフツーになる事」ではない。 だから「無限の可能性を説く事」と「身の程を知らせる事」は矛盾しない。 教育は子供たちに、 「君たちは何でも(any)出来る。けど何でも(every)出来る訳ではない」 と説く必要があるんだな。 ◇「国誉め」 詳細に書けば書くほど実物の美しさを描ききれず、記述すればするほど固定化や定義化は遠のき、"リアル"の無限性と、自分の記号化能力の限界を感じる、と言う話。 ◇大人になるとは、「人間が複雑になる」こと 真の共生とは「感情移入」ではなく、自分の構成ユニットを増やすことで「この他者は部分的に私と同じだ=私自身だ」と認める事、と言う話。 ◇「街づくり」に霊性を取り入れる 勿論、神威によって街が蘇生するのではなく、「神の威徳というのは、そのようなものが存在し、活発に機能していると信じる人間が作り出す」んだけれども、と言う話。 他。 ・「過記号化」が持つ危険性 ・レヴィナスが守った神への信仰 ・原子力は「荒ぶる神」 ・存在しないものを存在するかのように擬制することの効力 様々なトピックについて書かれているのですが、通底しているのは、下記2点かと。 -「ほんとうの私」を受け容れ、自責を引き受けなければ、物事はうまく行かない -存在しないものを存在するかのように信じる事に効力がある いやー、面白かったです。
Posted by
いつもの語り口いつも言っていることでそういえば以前に読んだ内容と思いつつも結局通読してしまうのは結局著書の考え方に同意していてかつ誰かにその内容を伝えようとしてもまだ消化しきれてないことが原因なんだろうと思う。この人の周辺についても埋めていかないとと思う。
Posted by