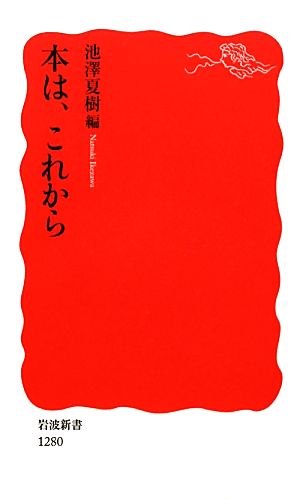本は、これから の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この書籍は、本(書籍)と読者との」関わり合いを電子書籍や書店、古書店、出版社関係の職業や図書館などを書き手など37人の著名人が書かれています。
Posted by
今から9年前、2010年の新書です。ちょうどiPadが発売されたり、kindleの新モデルが出たりして、どうも「電子書籍元年」と言われた年のようです。で、いよいよ今年に入って「紙の本、ピークの半分に」というニュースが報道されています。まさに、この本で予想されていることは予想されて...
今から9年前、2010年の新書です。ちょうどiPadが発売されたり、kindleの新モデルが出たりして、どうも「電子書籍元年」と言われた年のようです。で、いよいよ今年に入って「紙の本、ピークの半分に」というニュースが報道されています。まさに、この本で予想されていることは予想されているように起こっているんですね。ただ、電子出版物の市場全体に占める割合は20%ぐらいなので、次にニュースになるのは、きっと電子の売り上げが紙の売り上げを超えた時なのでしょう。本書にも登場する代々木上原の幸福書房もちょうど一年前閉店したりして、本を取り巻く環境は加速度的に厳しくなっているようです。だからこそ?なのか、本についての本、本屋についての本、読書についての本は、めちゃくちゃ目につくようになっている気がします。そう本の世界の中での絆はどんどん太くなってきているように思え、「本を愛する人」と「本は関係ない人」の二極化を感じさせます。今までは読書中間層的な人々が話題の書籍や雑誌を書くことで成立していたシステムがこわれちゃったのではないでしょうか?この二極化は本に限らず、ファッションや車など生活全般で起こっていることと同じで、だとすると「本を愛する人」が払うコストはもっともっと上がっていきそうな気がします。9年前に、そんな「本を愛する人」たちの多様な、でも似たような短文をまとめた本です。なにしろ「本の、これから」ではなく「本は、これから」というテーマからして、「まだまだ頑張るぞ!」的なエールになっちゃっているのは、岩波書店だから?
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本書タイトル通りのお題に沿って、有識者37名が思い思いの見解を述べる。 「本」としているが、それが意味するところは書き手によって異なるところは面白い。ある者は、”紙”、物質としての本の存在を希求し、ある者は出版に関わる”業界”のこれからを憂う。末端の書店の在り方を語る者もいれば、そもそも、読書という”体験”の未来に思いを馳せる者もいる。それらをひっくるめて「本は、これから」どうなるのか、という構成になっている。 面白いものもあるが、上記のようにとっちらかっているので、概して平均的な指摘や発想が多い印象。短いページ数ながら、過去、現状を俯瞰して真っ向「これから」を述べているものは多くない。個人的な読書体験を開陳してた上で、ちょっとだけ、先のことを言ってる程度のものが大半だ(ほとんどが本人の希望、願望に過ぎない)。 要は、電子書籍に代表されるデジタルなガジェットの登場で、本がどう変わっていくのか、変っていってほしくないのかを語っているわけだが、本、書物より先に、音楽がその洗礼を既に受けている。かつてのレコード、カセットテープの時代からCDの登場を経て、もはや音楽は形を伴った存在ではなくなってきている。そうなった今、音楽の”本質”は変わったか?というと、そんなことはないわけで、むしろライブで愉しむとか、自ら演奏することを楽しむとか、原初的な音楽との関わりが復活しつつあるのかもしれない。 なので、書物が紙を離れてデータ化することに、自分などはなんの心配もしていないのだが、冒頭、編者の池澤でさえ、 「我々の肉体は重力に抗することでこの形を保っている。周辺に置いた道具や素材がみなデジタル化によって重さを失ってゆく時に、どうして肉体が保てるだろう。 本の重さは最後の砦かもしれない。」 などと大仰に論を構える。デジタル化はなにも”本”だけではないし、本が最後の砦とも到底思えない。 思想家内田樹でさえも、 「電子書籍の第一の難点は「どこを読んでいるかわからない」ことである。」 って、そこかっ!? この文章の後、どの位置にあるか分からないと、推理小説の場合、登場人物が犯人なのか、ひっかけなのか予想する楽しみがなくなるのだそうな。阿呆か、と思わず思った。そんなのKindleに言って、画面の片隅に全体の何%の位置なのかを示すインジケータでも付けてもらえばいいだけの話(むしろ、既に付いてたりすんじゃなかろうか?)。 こんな論拠で、紙の本は残っていく、残すべきだとの話が多くて、なんだかなあなのだった。 そんな中、キラリと光るのは松岡正剛。 「本を読むということは本ごと何かを読むということであって、この何かと付き合うのでなければ、書物であろうと電子書籍であろうと、雑誌であろうとケータイであろうと、ぼくにとっては読んだという実感はない。」 言い換えれば、実感が伴えば、つまりその書物で記されている”何かとつき合う”ことさえ出来れば、媒体は問わないと言うことだろう。彼に言わせれば、本のこれからではなく、コンテンツのこれから、あるいはそれとの向き合い方のこれからが肝心ということだろう。彼はハッキリと言い切る。 「ぼくの結論はいたってはっきりしている。読書の本質は変わらない。」 本書は、序を書いた編者池澤夏樹以下、論者はどうやら五十音順に並んでいるようだ。松岡正剛はたまたま後ろから二人目であるけど、この結論が最後にほうにあることで、本書がピリリと締まる。というか、これを冒頭に持ってきたら本書が成り立たなくなるので、五十音順にしたのは偶然か意図的か分からないが、編者の功績かもしれない。
Posted by
「本は、これから」というお題で書かれたエッセーを 集めた一冊。 書き手は、内田樹、上野千鶴子、池上彰、紀田順一郎、 松岡正剛、成毛眞といったビッグネームから、書店主、 古書店主、図書館員、装丁者、編集者など、本や出版 に関わる人々。 バラエティに富んだ人選だけあっ...
「本は、これから」というお題で書かれたエッセーを 集めた一冊。 書き手は、内田樹、上野千鶴子、池上彰、紀田順一郎、 松岡正剛、成毛眞といったビッグネームから、書店主、 古書店主、図書館員、装丁者、編集者など、本や出版 に関わる人々。 バラエティに富んだ人選だけあって、なかなか読み 応えがあった。(50代以上の世代に大きく偏っていた のはちょっと残念。) やはり電子書籍について触れているエッセーが多い中、 いちばん面白かったのは、電子書籍に対する考えと その文章の性質に相関関係が感じられたこと。 電子書籍を正面から受け止め、長所短所を判断している、 あるいは判断しようという人の書く文章は、読者に向かって きちんと投げられている。自分の伝えたいことはきちんと 伝えたいという意思が感じられる。 一方、電子書籍に否定的な人の文章は、読者のために ではなく、どちらかというと自分のために書いていて、 中には、分かる人さえ分かってくれればいいという姿勢 すら感じるものもあった。 この相関関係は興味深い。 それでも、こうして自分の意見を述べているものは読んで いて面白い。 この類のエッセーでいちばんつまらないものは、「~に ついては議論すべきだろう」というトーンのもの。 ワタシが聞きたいのはアナタの考えなんですけど、と つい突っ込みたくなる。
Posted by
錚々たる面々が語る、「本」という文化のいま。 一面的に「紙の本」を賛美するつくりではなく、ある人は紙の本を賛美し、ある人は「電子の本」に期待し、ある人は出版業界の今後を憂い、ある人は本という文化を思う。 さまざまな意見を並列に並べて見せる事で、「いま」がどういう時代なのを冷静な視...
錚々たる面々が語る、「本」という文化のいま。 一面的に「紙の本」を賛美するつくりではなく、ある人は紙の本を賛美し、ある人は「電子の本」に期待し、ある人は出版業界の今後を憂い、ある人は本という文化を思う。 さまざまな意見を並列に並べて見せる事で、「いま」がどういう時代なのを冷静な視点から描き出す事に成功した本だと思う。 個人的には、電子書籍は雑誌や新聞の代わりになっていくメディアなのだろうなと思っている。 移り変わりの激しい教科書や参考書、あるいは、購読者の数が限られている専門書などにも適しているだろう。 しかし一方で、じっくりと読むタイプの作品を発表するためのメディアとなるには、まだまだ多くの課題が山積しているのも事実。 重さや場所を気にしなくていいと言う点は魅力であるし、流通などに関わるコストを省ける事で、値段が下がるという点も嬉しい事ではある。 けれど、紙に書かれた「本」という形態であるからこその魅力がある事も、またれっきとした事実だと思う。 中身さえ充実していれば、容れものは何でもいい、という考え方もあるけれど、容れものによって中身が規定される(制限される)ということもある。 どれか一つが無条件に正しい、ということではなく、中身に相応しい器を選ぶ、というのが本当に大切な事。 一面的なメリットだけに左右されず、冷静に、多面的な価値観で判断して、よりよい方向性に進んでくれるといいな、と思う。
Posted by
本お題に関して、単著ではさすがにキツそうだから、多方面からの論文を纏めることになったのは賢明。ただ、玉石混交ってか、読んでてしんどかったり、完全に読み飛ばしたりしたものもちらほら。結局、その著作を多少なり見聞きしたことのある著者を中心に、って感じになってしまったけど、本当は、新し...
本お題に関して、単著ではさすがにキツそうだから、多方面からの論文を纏めることになったのは賢明。ただ、玉石混交ってか、読んでてしんどかったり、完全に読み飛ばしたりしたものもちらほら。結局、その著作を多少なり見聞きしたことのある著者を中心に、って感じになってしまったけど、本当は、新しい知見ってことで、全く知らんかった著者をこそ、読んでみるべきだったのかも。個人的には、紙媒体としての本にまだまだずっと頑張っていって欲しいけど。
Posted by
電子書籍が話題になり、将来の紙の本の存在を考えざるを得なくなってきた。本に関連する人たち(著述家、編集者、本屋、出版社、etc.,)のエッセーである。
Posted by
皆さんiPad=電子書籍という観念をお持ちだったのは意外でした。それだけインパクトがある商品だったということですね。
Posted by
今後の本のあり方や行く末を作家・書店員・装丁家・図書館・読者と、あらゆるジャンルの人間がそれぞれの立場で書いているのが面白い。個人的には幸福書房の岩楯社長の章が好きだな。今でも神田村へお客の顔を思い出しながら仕入に行く町の本屋さんが、電子書籍とも上手に共存出来る世の中。そんな未来...
今後の本のあり方や行く末を作家・書店員・装丁家・図書館・読者と、あらゆるジャンルの人間がそれぞれの立場で書いているのが面白い。個人的には幸福書房の岩楯社長の章が好きだな。今でも神田村へお客の顔を思い出しながら仕入に行く町の本屋さんが、電子書籍とも上手に共存出来る世の中。そんな未来を期待したい。紙だろうが電子だろうが、みんな本が好きなのだから。
Posted by
玉石混交、硬軟取り混ざった論考集。 形は変わっていくだろうけど、「本」というもの自体はけっこう有用なもので、なくなることはまずないだろうなあと個人的には思う。
Posted by