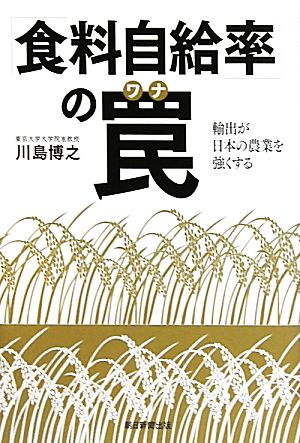「食料自給率」の罠 の商品レビュー
何をしなければならないか、何を目指すべきかではなく、何が問題なのか、どうなっているのかを知りたいのならお勧めできると思う。 誤植の多さはもう少しなんとかならなかったのかと思うが。
Posted by
自給率の低下に対して、多くの国民は不安を抱いている。それは、農林水産省や農業関係者が行う「なにかの際に食料が輸入できなくなると、日本はパニックに陥る」との喧伝に踊らされている面はあるにしても、自給率の著しい低下が不安の背景にあることは確かであろう。 農地を規模拡大して農業の効率...
自給率の低下に対して、多くの国民は不安を抱いている。それは、農林水産省や農業関係者が行う「なにかの際に食料が輸入できなくなると、日本はパニックに陥る」との喧伝に踊らされている面はあるにしても、自給率の著しい低下が不安の背景にあることは確かであろう。 農地を規模拡大して農業の効率を高めても、国民経済全体を考えると、それほど大きなメリットがない。 人口が減少局面に入った日本はこれから、農業に限らずあらゆる分野で「選択と集中」をしていく必要がある。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2010年刊。東京大学大学院農業生命科学研究科准教授。「「作りすぎ」が日本の農業をダメにする」の著者で、同書の内容と被る。基本的には著者は、日本の地形、狭隘な地形での産物(畜産業を含め)が重要と説く。なお、著者は、米は現状維持と言うが、後継者不足なら田畑の集約化も可能ではないか、という気もする。また、基幹的食料品の輸入高が全輸入高の50分の1程度、ソ連への食料封じ込めが失敗した等食料による封じ込めは奏効しないことを安心材料とするようだ。後者はもう少し分析が要る気もするが、一つの見方として知っておくべきか。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
いちいちさ、罠を仕掛けないでほしいよね、いろんなところにさ。政府とかメディアとかその他もろもろ。引っかかっちゃうじゃんね。知らんし。事情とか。 端的に言うと、食料自給率あげなくていいよーってはなし。あげることは現実的じゃないんだよーってはなし。あげなくても問題ないんだよ。 戸別所得補償制度は自給率あげるのに役には立たないけれども、別のいいところあるよ、って話もある。 面白いよ!! すごくわかりやすく、納得しやすい論調。だけど、だからって思考を停止させるのは良くないので、いろんな意見をきいてかないとね。難しいね。
Posted by
食料自給率のことがよくわかる良本。まず自給率が日本より低いオランダが、農業で儲けている(輸出額>輸入額)ことにびっくりした。特に知見のない自分からしたら、「自給率?あげた方がいいんじゃん?」くらいにしか感じてなかったが、世界と日本の自給率の比較、自給率を上げられるのか?自給率が低...
食料自給率のことがよくわかる良本。まず自給率が日本より低いオランダが、農業で儲けている(輸出額>輸入額)ことにびっくりした。特に知見のない自分からしたら、「自給率?あげた方がいいんじゃん?」くらいにしか感じてなかったが、世界と日本の自給率の比較、自給率を上げられるのか?自給率が低くて問題があるのか?農業を強くするには何をすべきなのか?なぜそれが出来ないのか?自分の中の疑問が一気に解消され、とてもためになった。
Posted by
そもそも食料自給率はどこまであげることができるのか。それは国際的な水準などと比較してどうなのか。っていうか他の国ってどうなの?なんで日本の農業ってこんな感じなの?と、一つずつ紐解いていく。 結局、著者の試算によれば、日本でカロリーベースの食料自給率は上がっても50%ぐらい。そこに...
そもそも食料自給率はどこまであげることができるのか。それは国際的な水準などと比較してどうなのか。っていうか他の国ってどうなの?なんで日本の農業ってこんな感じなの?と、一つずつ紐解いていく。 結局、著者の試算によれば、日本でカロリーベースの食料自給率は上がっても50%ぐらい。そこに色んな補助金を投入したり、土地の集約を進めることの不可能性を考えると、たとえばオランダでやってるように、少ない土地で高く売れる農業にシフトしていくべきでは、という主張。 日本の農業は畜産と野菜がメインですってだけでも、発見。いかにイメージしか持ってなかったか、ということについてだけでも、読んだ甲斐がありました。
Posted by
日本は主要な農産物をアメリカから輸入している。特に日本が最も大量に輸入しているトウモロコシ、大豆、小麦。 他には、カナダ、ブラジル、オーストラリア。 日本は石油などの燃料を輸入するために、農産物を輸入するために必要な金額の数倍を使っている。 日本はコメの24倍もの量の石油を消費し...
日本は主要な農産物をアメリカから輸入している。特に日本が最も大量に輸入しているトウモロコシ、大豆、小麦。 他には、カナダ、ブラジル、オーストラリア。 日本は石油などの燃料を輸入するために、農産物を輸入するために必要な金額の数倍を使っている。 日本はコメの24倍もの量の石油を消費している。 戦後の政治の中で、農民の立場が極めて強かったことは、米や小麦の生産者価格が国際価格に比べて、極めて高いことが示している。戦後の農民はその政治力によって経済的な苦境をしのいで成功した。
Posted by
タイトルは声高に叫ばれる食料自給率へのアンチという感じだが、それ以上に日本の農業が抱える問題点がよく整理されており、またそれだけでなく日本の農業の課題に関して解決の方向性を提示しているという点で良書だと思う。全体的にグラフ等のデータも多く、文章も平易で分かりやすくなっている。なお...
タイトルは声高に叫ばれる食料自給率へのアンチという感じだが、それ以上に日本の農業が抱える問題点がよく整理されており、またそれだけでなく日本の農業の課題に関して解決の方向性を提示しているという点で良書だと思う。全体的にグラフ等のデータも多く、文章も平易で分かりやすくなっている。なお、食料自給率については日本独自のカロリーベースの試算である点と海外飼料を使った畜産を自給率に含まない点など恣意的な統計をナンセンスとしている。なお、著者の農業問題に関する主張としてはチーズを多く輸出するオランダのように日本も高付加価値の農産物を輸出することで競争力を持つことができる(逆に土地面積に問題がある日本では穀物の栽培は絶望的に価格で劣勢になる)というもの。実際、畜産、野菜、花木など生産効率性も高く有望である。しかし、原発事故後では輸出とか難しいんだろうな・・・。技術の輸出というのはあるのかも。あるいは海外への農業移転?
Posted by
地に足のついた好著。国土が狭く、人口密度の高い日本では穀物の生産量向上には限界があり、自給率向上は厳しい。それよりも、同じように狭い国土ながら農業輸出で279億円ももうけているオランダのように、野菜や畜産や花きなどの広い面積を必要としない品目で勝負すべきと熱弁。一方で「小家族制や...
地に足のついた好著。国土が狭く、人口密度の高い日本では穀物の生産量向上には限界があり、自給率向上は厳しい。それよりも、同じように狭い国土ながら農業輸出で279億円ももうけているオランダのように、野菜や畜産や花きなどの広い面積を必要としない品目で勝負すべきと熱弁。一方で「小家族制や日本文化に根付いたコメは保護すべき」とも語る。農業政策はこのぐらいの認識を土台にしないと話が進まない。
Posted by
「選択と集中」が大事。 本書ではコメは現状を維持し、広い土地を使わない畜産を競争産業にすべきだという。 確かに、コメは個別所得補償制度などによって手厚く保護されている。 しかし、コメもいまでは中国の富裕層が大量に買っているという現状があれば競争産業になるのではないだろうか。
Posted by
- 1
- 2