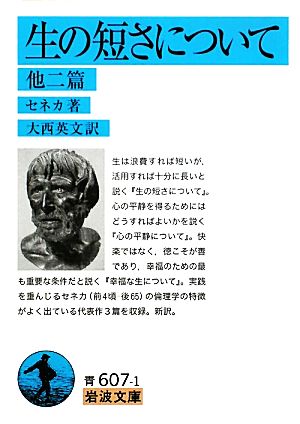生の短さについて 他二篇 の商品レビュー
セネカ「生の短さについて(他二篇」読了。後期ストア派。およそ二千年前の文章と思えない現在でも十分通じる処世訓であった。一例として、「生きることにとって最大の障害は、明日という時に依存し、今日という時を無にする期待である」繰り返し読み続けていこうと思う。
Posted by
ローマ時代の哲学者セネカ。皇帝ネロの先生だったが、晩年ネロから自死を言い渡される。 モンテヴェルディのオペラ「ポッペアの戴冠」の中では立派なようでちょっと煙たがられる微妙な役どころ。実際はどんな考えの持ち主だったのだろうと思い読んでみた。 彼の考える幸福とは、やはり、智を愛し、真...
ローマ時代の哲学者セネカ。皇帝ネロの先生だったが、晩年ネロから自死を言い渡される。 モンテヴェルディのオペラ「ポッペアの戴冠」の中では立派なようでちょっと煙たがられる微妙な役どころ。実際はどんな考えの持ち主だったのだろうと思い読んでみた。 彼の考える幸福とは、やはり、智を愛し、真理を追究することだったようである。 世事にあくせくして時間を浪費しないように説いている。 まあ、ローマ時代の賢者のボヤきとも言えるが。 共感することもあるけれど、時代の大きな違いを感じることも時々出てくる。 50,60歳まで幸運に生き延びたとして・・みたいな言葉もあって、80歳が常識だと思ってる我々からすれば、ちょっとびっくり。 だからこその表題で、セネカにしたら長生きしたかったことだろうと思う。学問は長し。 この間から「奴隷制度」っていったい何だったのだろうと考えていたのだけれど、丁度答えになるような引用があった。 ある賢者の奴隷が逃げた。しかし賢者は奴隷を連れ戻しに行かなかった。なぜかというと、「奴隷は私を必要としていないのに私が奴隷を必要としているのは恥ずべきことだ」だからだそうだ。 奴隷制度が当たり前の時代にこの発想はなかなか出来ないと思う。さすが!
Posted by
人生は短い。ただ、本来は十分な時間があるはずなのに、実際に短くしてしまっているのは我々自身である。財産、上司、見栄、異性、怠惰、名誉などに関わりすぎているのだ、という主張。これが2000年前の文筆家による著書だと知ると、人間って変わらないんだと苦笑。別の短編では心の安定について、...
人生は短い。ただ、本来は十分な時間があるはずなのに、実際に短くしてしまっているのは我々自身である。財産、上司、見栄、異性、怠惰、名誉などに関わりすぎているのだ、という主張。これが2000年前の文筆家による著書だと知ると、人間って変わらないんだと苦笑。別の短編では心の安定について、特に仕事において吟味しておくべき三つのことが語られてる。自分をよく知ること、仕事の内容をよく知ること、誰にために誰と一緒に仕事するかをよく知ること。これジョブスも言っていた気がする。
Posted by
古代ローマ帝国のストア派哲学者セネカによる古典。「生の短さについて」は、「芸術は長く、人生は短い」という諺がありますが、本書を読めば、(そうかもしれないけど)時間の活用次第でいろいろなことにチャレンジができるのだと思わせてくれる書です。
Posted by
結局最後になって否応なしに気づかされる事は、今まで消え去っているとは思わなかった人生がもはやすでに過ぎ去っていることである。…われわれは短い人生を受けているのではなく、我々がそれを短くしているのである。われわれは人生に不足しているのではなく濫費しているのである。10ページ
Posted by
箴言集。全体として言いたい事はよくわからなかったが、ところどころ「なるほど」と思わせる文があった。 「仕事はさらなる仕事をよぶ」「未来のことを考えるあいだに、現在がすりぬけている」「人は死に際で評価が決まる」 セネカは哲学者だと思っていたが、解説によれば政治家でもあったらしい。実...
箴言集。全体として言いたい事はよくわからなかったが、ところどころ「なるほど」と思わせる文があった。 「仕事はさらなる仕事をよぶ」「未来のことを考えるあいだに、現在がすりぬけている」「人は死に際で評価が決まる」 セネカは哲学者だと思っていたが、解説によれば政治家でもあったらしい。実世界と切り離された「哲学」ではなく、処世訓のような側面が強くておもしろかった。
Posted by
ルキウス・アンナエウス・セネカは、古代ローマ帝国のユリウス・クラウディウス朝時代(B.C.27年~A.D.68年)の政治家・哲学者。第5代皇帝ネロの幼少期の家庭教師を務め、ストア派を代表する哲学者としても有名で、多くの悲劇や著作を残した。 本書には、表題作『人生の短さについて』の...
ルキウス・アンナエウス・セネカは、古代ローマ帝国のユリウス・クラウディウス朝時代(B.C.27年~A.D.68年)の政治家・哲学者。第5代皇帝ネロの幼少期の家庭教師を務め、ストア派を代表する哲学者としても有名で、多くの悲劇や著作を残した。 本書には、表題作『人生の短さについて』のほか、『心の平静について』、『幸福な人生について』の2篇が収められているが、いずれも親類、友人、同僚政治家らにあてて書かれたものである。 その中には、例えば以下のような印象的なセンテンスがいくつも含まれている。 ◆『人生の短さについて』~「生きることの最大の障害は期待をもつということであるが、それは明日に依存して今日を失うことである。運命の手中に置かれているものを並べ立て、現に手元にあるものは放棄する。君はどこを見ているのか。どこに向かって進もうとするのか。将来のことはすべて不確定のうちに存する。今直ちに生きなければならぬ」、「生きることを止める土壇場になって、生きることを始めるのでは、時すでに遅し、ではないか」 ◆『心の平静について』~「要するにわれわれの求めているのは、いかにすれば心は常に平坦で順調な道を進み、おのれ自身に親しみ、おのれの状態を喜んで眺め、しかもこの喜悦を中断することなく、常に静かな状況に留まり、決しておのれを高めも低めもしない、ということである。これが心の平静ということであろう」 ◆『幸福な人生について』~「人生に関する事柄は、多数の者に人気があるほうが善いというふうにはならない。最悪のものだという証拠は群衆なのである。それゆえ、われわれが知ろうとするのは、一体何を行うのが最善であるか、ということであって、何が最も多く世の中に行われているか、ということではない」 現代においても何ら古びることのない、五賢帝のひとりマルクス・アウレーリウスによる『自省録』と並ぶ、古代ローマの叡智を示す作品のひとつである。 (2006年6月了)
Posted by
■人生の短さについて 現代、特に日本では、誰も自分の人生が短いとは感じてないと思いますが、「自由な時間がない(少ない)」とか、「もっと時間があれば良いのに」とは、多くの人が思っていると思います。 ただ、それに対して「怠惰な多忙」とはよく言ったものだと思いますが...
■人生の短さについて 現代、特に日本では、誰も自分の人生が短いとは感じてないと思いますが、「自由な時間がない(少ない)」とか、「もっと時間があれば良いのに」とは、多くの人が思っていると思います。 ただ、それに対して「怠惰な多忙」とはよく言ったものだと思いますが、自分の時間を浪費している人は(書いてる自分も含めて)多いんだろうなぁと思います。人が考えること、苦労していることは、2000年以上前とそんなに変わらないんだな、と感じました。 ■心の平静について セレヌスがセネカに、贅沢な暮らしがいいのでは?国政の中枢に携わることはいいことなのか?と疑問に思うことをぶつけて、それに対してセネカが答える内容。 貧困はダメだが華美もダメ、適度に豊かであれば良い。貧しくなるより、贅沢になるのを我慢する方がよっぽど我慢しやすい。仕事については、自分をよく知り、やろうとしている仕事をよく知り、仕事仲間をよく知ること。心を平静に保つには、適度な休憩、お酒を飲むことも良い。自然に任せることも肝要。 ■幸福な人生について ここは理解が今一つ足りないが、繰り返されている言葉は「徳」という言葉で。心が平穏で動揺しない、これが、幸福な人生の要諦というような趣旨のことが書かれている。
Posted by
生の短さについて、幸福な生について、心の平静について、の三篇である。マルクス・アウレリウスの自省録と同様セネカも、快楽や欲望に溺れたり、こだわり過ぎないように説いている。人間は無から生まれて無に還っていく。従って、その間に得られたものや失ったものは全て重要なものではないとする。共...
生の短さについて、幸福な生について、心の平静について、の三篇である。マルクス・アウレリウスの自省録と同様セネカも、快楽や欲望に溺れたり、こだわり過ぎないように説いている。人間は無から生まれて無に還っていく。従って、その間に得られたものや失ったものは全て重要なものではないとする。共感する。 また、他人の行状を非難したり気に病むような時間の余裕はないとも言っている。セネカの時代から、人は時間の大切さを知らず、あたかも永遠に人生が続くかのように日々を無為に過ごしていたようだ。多忙の中に身を置く中で、本当に大切なものを見失い、老いてからそれを嘆いていたようだ。まさしく現代人と同じである。アウグストゥスのような人物でさえ、日々の仕事に忙殺され、余暇を求めていたようだ。 私達は普段「自分の人生」「自分の時間」を生きているのだろうか?それとも、誰かの人生、誰かの時間を生きているのだろうか?もし自分の人生を生きていないなら、それは不幸なことだとセネカは説く。仕事に縛られ、忙殺された人生ではなく、自分の精神を、心から為したいことに向けよと言う。自分という船の舵取りをせよということだろう。こちらも、大いに共感できる。 人生は短い。にもかかわらず、現代人は様々なものに縛られてばかりである。過度に情報化された社会の中で「かくあらねばならない」という妄想にとりつかれている。私はその縛りから解放されて、自分の心を知り、それに従った人生を送りたい。そう思った。
Posted by
どれだけ人間の歴史が続いたとしても、文明が発達しても衰退しても、人間って成長しないし、だからこそ人間として続くのかも。 短い人生だったなぁ、と過去を振り返った。 長く濃密な1日を過ごしていかねば。。。
Posted by