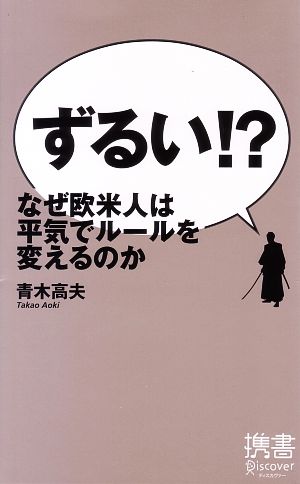ずるい!? の商品レビュー
日本選手が大活躍した長野五輪の翌年、ジャンプ のルールが改定。 ホンダがターボ・エンジンでF1連勝を果たした 翌シーズン、同エンジンが禁止。 こんな実例を挙げながら、ルール変更について 分析を試みた一冊。 少し論理付けが足りないと感じる部分もあるが、 主旨は明快...
日本選手が大活躍した長野五輪の翌年、ジャンプ のルールが改定。 ホンダがターボ・エンジンでF1連勝を果たした 翌シーズン、同エンジンが禁止。 こんな実例を挙げながら、ルール変更について 分析を試みた一冊。 少し論理付けが足りないと感じる部分もあるが、 主旨は明快で、展開も分かりやすい。 しかも、いたずらにルール変更に関して憤ったり 批判したりするだけでなく、それに対する日本の 対応や、結局長い目で見たときの勝者は誰だった のか、というところまで掘り下げてあって納得感 も十分。 ところで、この本、内田樹の『日本辺境論』と 合わせて読むのが俄然面白い。 欧米がルールを変更し、それに対応してゆく日本 という構図には、内田さんご指摘の日本人の辺境性 が明確に表れている。 「辺境人たる日本人の面目躍如」というサブタイトル をこの本に冠したい。
Posted by
よく日本人は「ルールを守る」と言われるが、逆になぜ欧米人は「ルールを変える」ことがうまいのかについて分析し、その上で日本人がどう対処すればよいかを描いた一冊。 日本人はグローバルスタンダードという感覚にまだ慣れていないので、なかなか難しいと感じた。
Posted by
なぜ欧米人は平気でルールを変えるのか~ルールとプリンシプル,日本人のプリンシプルは外国人には理解されにくい~ あまり好きじゃない奴・ホンダ小僧
Posted by
ウインタースポーツなどで日本が勝ちすぎるとルールが変わる。 そんなのを目にすることがあるが、他の分野でもルール変更を当然と考えるのが欧米の文化。 しかしルール変更したからと言って変更して側が必ず勝つ訳ではない。 ルール変更を新たなチャンスと捉えて、大きく成長しよう。 でもルールを...
ウインタースポーツなどで日本が勝ちすぎるとルールが変わる。 そんなのを目にすることがあるが、他の分野でもルール変更を当然と考えるのが欧米の文化。 しかしルール変更したからと言って変更して側が必ず勝つ訳ではない。 ルール変更を新たなチャンスと捉えて、大きく成長しよう。 でもルールを黙って受け入れるのではなく、変更には参画しよう。 参画しても公益を大事にしよう。 そんな本。
Posted by
ルールについて取るべき3つの行動 1:ルールの意味と目的を理解しておく 2:ルールが実状に合わなくなったら変更を提案する 3:ルールが必要なら、ルール作りを率先して行う ルールとプリンシプルは違う ルール:行動が準拠すべき、または準拠することを要求されるプリンシプル プリンシプ...
ルールについて取るべき3つの行動 1:ルールの意味と目的を理解しておく 2:ルールが実状に合わなくなったら変更を提案する 3:ルールが必要なら、ルール作りを率先して行う ルールとプリンシプルは違う ルール:行動が準拠すべき、または準拠することを要求されるプリンシプル プリンシプル:理性や行動の基礎となる、基本的な真理・法律 ルール変更が必ず勝ちに結びつくとは限らない 勝ちすぎは社会を豊かにしない 欧州は、喧嘩をしても全体のバランスを大切と考える ルールは成長の糧になる ルール作成はまずは、社益、最後に公益を考えること つまり、製品を作るようにルールを作る
Posted by
ルールを変えるには? →ルールについて認識すべき点として 1.ルールの意味と目的を理解しておく 2.ルールが実状にあわなくなったら変更を提案 3.ルールが必要なら、ルール作りを率先して行う
Posted by
事例、その後、考察と段階を踏んで説明されているので、納得性が高い。「ずるい」と思考停止にならずに、そこに切り込んでいくことの重要性を教えられた。 また、ルール(規制・制限)があるから成長できるは、本当にその通りだと思う。
Posted by
スポーツ競技やビジネスシーンで、ルールや法律が変わってしまい、日本人選手や日本企業が不利になってしまうことがある。変える側は欧米で、変えられる側は日本という構図がすっかり出来上がっている。 そんな状況に対してずるいと思う日本人は多いが、ただの感情論では済まない。ルールや法律...
スポーツ競技やビジネスシーンで、ルールや法律が変わってしまい、日本人選手や日本企業が不利になってしまうことがある。変える側は欧米で、変えられる側は日本という構図がすっかり出来上がっている。 そんな状況に対してずるいと思う日本人は多いが、ただの感情論では済まない。ルールや法律は生き物と同じで時代や状況が変化すれば変わるもので、一度出来上がったら永久に不滅ですとはいかない。新たなルール作りに積極的に加わり、キツネやタヌキを見習って老獪な外交を駆使して少しでも日本にとって有利になるようにしないとお話にならないと言うのが今回の本だ。 とは言っても、どこかの国の告げ口オバ様のようにネガティブキャンペーンを展開しても良いことはない。まだ政権末期でもないのに「反日キャンペーン実施」か。せっせと反日活動したらポイントがたまって素敵なお皿が当たるのかしら。もし実施していてもやる気が起きない。 東京オリンピック招致のように、ロビー活動を日ごろからするのは重要だ。孫子の兵法を読んで「敵」の動きを読んで必要とあらば、主張する。テレパシー・コミュニケーションは通用しないのだから。
Posted by
最近、増補版として事例などをもっと新しくしたものも出ているようだが、基本は変わらないようなので2009年版を読んでみた。著者はホンダの会社員として、F1などのレースにも立ち会っている人。 内容としては、日本と欧米のルールについての文化的な違い、日本がルール変更でずるいと思った事...
最近、増補版として事例などをもっと新しくしたものも出ているようだが、基本は変わらないようなので2009年版を読んでみた。著者はホンダの会社員として、F1などのレースにも立ち会っている人。 内容としては、日本と欧米のルールについての文化的な違い、日本がルール変更でずるいと思った事例を挙げて、ルール変更で勝者が変わったかを検証している。そのうえで、ルールがあってこそ成長すること、ルールの形になっているが、その前のプリンシパルが大切であり、勝者が一方的に勝つことが、結果的に業界全体ではよくなくなることが多いことが欧州の知恵であるように紹介している。 被害者意識が強くなり、ルール変更が日本叩きに思考停止してしまうが、そのあたりを丹念に検証することが大切だと感じた。また、日本のプリンシパルがわかりにくいことは、法学における、道徳と法の関係に近いと感じた。
Posted by
日本人と欧米人の、ルールに対する考え方の違いをまず取り上げてます。それによると、日本人はあくまでルールには準拠するのが当たり前と考えており、それが美徳にも繋がっている。一方で欧米人は、ルールは自分たちにとって都合のよいように解釈し、必要があれば変更・修正して、より好いものにしてい...
日本人と欧米人の、ルールに対する考え方の違いをまず取り上げてます。それによると、日本人はあくまでルールには準拠するのが当たり前と考えており、それが美徳にも繋がっている。一方で欧米人は、ルールは自分たちにとって都合のよいように解釈し、必要があれば変更・修正して、より好いものにしていくものと考えている、らしい。 これだけ聞くと欧米人は酷いな、という風にも思えますが、そこはきちんとフォローされてます。著者いわく、「欧米人は相手とケンカをしてでも、その世界全体のバランスを取り、全体としての魅力を保つことを考える視点がある」とされています。この論に対しても是非はあるだろうけど、首肯できる部分もあります。 そんな背景を踏まえ、ルール作りに積極的に参加し、「自分の利益だけを追求せずに、その世界全体にとってプラスとなるようなルールを自分たちで作り、守っていく」ことが大事だというのが著者の結論。ただただ利己的にルールを作ればいい、と言っている訳ではないところは共感できました。 誰かが一人勝ちするようなルール(もしくは偏った戦力、独占的な市場など)では、スポーツでも経済でも政治でも他のアクターが不満を持ち、その世界の魅力が落ちていくという指摘は納得でした。だから、最近の野球は面白くないんですね。
Posted by