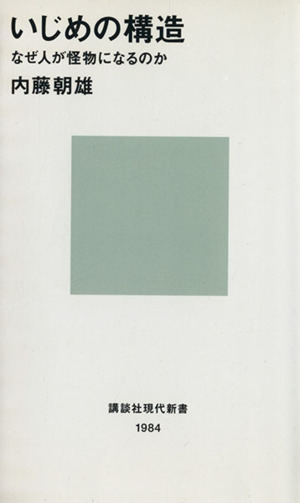いじめの構造 の商品レビュー
いじめの問題を、ただ単に、加害者、被害者の問題としてではなく、社会制度のあり方、組織の中の人間行動の本質まで踏み込んでいる点に、目から鱗が落ちた。
Posted by
全体的になぜ人はいじめるのかを書いていた。私には「全能筋書」や「全能感」などのワードの意味があまりしっくり掴めなかった。いじめの起きる原理、その連鎖がなぜなのか、新たな視点で見ることができるかと思う。
Posted by
一見すると「幼稚」にしか見えないいじめ。それをやっている人がどういう仕組みで、そういう行動に至るのか、という「(社会)構造」に注目した一冊。 寄生虫に乗っ取られた虫がわざわざ次の宿主に食われるような行動をとるように、場の空気に飲まれた人は”いじめが止まらないモード”に移行してし...
一見すると「幼稚」にしか見えないいじめ。それをやっている人がどういう仕組みで、そういう行動に至るのか、という「(社会)構造」に注目した一冊。 寄生虫に乗っ取られた虫がわざわざ次の宿主に食われるような行動をとるように、場の空気に飲まれた人は”いじめが止まらないモード”に移行してしまう。 そして、いじめる行動によって「全能感」を得た人は、その全能感を外されて不全感を感じずに済むよう「全能を具体的なかたちにして表すこと(全能筋書)=いじめ行動」に執着する。 いじめを世渡り上手になって切り抜けた「タフな人」は、今度はかつて自分がいじめられたような方法で他人をいじめることで、「かつての自分よりも強い自分(=いじめる側)になれた」と確認することで、自分を癒している。 本ではこういう構図をもっと詳しく説明しているのですが、「確かにそうだな~」と納得する部分は多い(それは”思い出しむかつき”を誘発するくらいにw)。 ただ、それだけにその解決法として、そういう「閉鎖的な空間=学級」をなくしてしまえばいい、あるいは学校を義務教育校以外からも自由に選べるようにすればいい、という提案がされているのは、「理屈はわかるんだけど…そうもいかないよな~」というのが個人的な本音だった。 学校のような「閉鎖的な空間」だからこそいじめが起こる、というデメリットを理解しつつ、一方でそういう「安定感のある親密な空間」であればこそ学べるし生きていける人も結構いる、というメリットも生かせる学級・学校づくりはないのか、という「素直な感情なんだけど…そうもいかないよな~」という読了感を抱いた一冊でした。 いじめられる側にとってはあまり役立ちませんが、「なんであいつはいじめるんだろう?」という理解が必要な立場の人におすすめしたい一冊。
Posted by
大変な名著。学校のいじめを通じて普遍的ないじめ、つまり「人間が人間にとっての怪物になる心理ー社会的メカニズムである、普遍的な現象としてのいじめ」の構造を分析し、そのようないじめが生まれないための構造の作り方(制度設計論)を提案している。短期的な教育制度改革論から、中長期的な社会構...
大変な名著。学校のいじめを通じて普遍的ないじめ、つまり「人間が人間にとっての怪物になる心理ー社会的メカニズムである、普遍的な現象としてのいじめ」の構造を分析し、そのようないじめが生まれないための構造の作り方(制度設計論)を提案している。短期的な教育制度改革論から、中長期的な社会構想まで論じられている。その構想はリチャード・ローティの「リベラル・ユートピア」に通じる。
Posted by
いじめという局所的な事象の構造を明らかにするだけでなく、私達が暮らす社会に内蔵する中間組織的全体主義について言及した非常に感銘を受ける良書であった。教育関係者には一読することを勧める。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「閉鎖空間でベタベタすることを強制する学校制度」(第5章1節タイトル) これを読んで、大学進学以降、中高時代の友人が「あの頃に戻りたい」というたびに「絶対にいやだ」と言い続けてきた理由がわかりました。 「みんな」で「仲良く」が求められること、同一同進度を求められることが苦痛でたまらなかったんだろうなぁ…。 もちろん、そういう環境が好き・いいと思う人はいるだろう。しかし全員がそうであるとは限らないのである。 「学級制度をやめる」ほか、様々な提案(実現は難しそう)があった。 「治外法権」をやめ、何かあれば「警察」を呼ぶというのは徹底されてほしいなぁ…。いじめることが損である、というメッセージは大半のいじめを落ち着かせることができるような気もする。 また学級制度やそうでない形を学ぶ側が選べる形になってほしいとも思う。
Posted by
戦争中の大人、水槽に閉じこめられたメジナは市民性を失い、いじめを行う。 いじめは中学生を中心に起こっているものと捉えるのではなく全ての人間が「豊さ」を獲得するために考えるべきことではないだろうか。 具体的な教育制度改革には一部賛成、一部反対という感じだ。
Posted by
学校のいじめを社会モデルの形態そのものが引き起こす「メカニズム」としてとらえた社会学的考察本。著者の提唱する、国家より下位にある「中間集団全体主義」における「群生秩序(その群の論理)」がいじめの発生源であるから、その秩序を一般社会の「市民秩序」などの導入で、脱構築してしまえばいじ...
学校のいじめを社会モデルの形態そのものが引き起こす「メカニズム」としてとらえた社会学的考察本。著者の提唱する、国家より下位にある「中間集団全体主義」における「群生秩序(その群の論理)」がいじめの発生源であるから、その秩序を一般社会の「市民秩序」などの導入で、脱構築してしまえばいじめはなくなる、という論理は、報道や身近な見聞で耳にする「いじめ」の話題に触れるたびに思うことだが、一般感覚からいって、不思議な思考がまかりとおり、容赦ない人間関係が強要され、法律の手が届きにくいという学校という構造の特殊さを思えば、おそらく大半の人は納得がいくのではないかと思う。問題は、著者がいうように、その「共同体主義的な理念」は、学校だけにあるものではなく、市民の社会にもあり、(これは自分の個人的な意見だが)おそらく日本人にとって少なからず「好感のもてる理念」であるということだ。まずはそういった社会の仕組みや、そういった仕組みを取り入れたいと思う心性についてよく知ることが大切だと思う。
Posted by
学校のいじめに限れば、学校に行かないという選択肢を親が子供に与えない限り、学校という閉鎖社会から子供は逃げられないし、逃げ場がないから自死に逃げるという事が多々起こっているのではないか。 この本からは、生きる為に選択肢を出来るだけ多く持つ重要性を教えてくれるし、選択肢が多い社会...
学校のいじめに限れば、学校に行かないという選択肢を親が子供に与えない限り、学校という閉鎖社会から子供は逃げられないし、逃げ場がないから自死に逃げるという事が多々起こっているのではないか。 この本からは、生きる為に選択肢を出来るだけ多く持つ重要性を教えてくれるし、選択肢が多い社会こそが、最大のセーフティネットだとも感じさせてくれた。 この本の内容は、学校だけではなく、閉鎖的閉塞的でローカルルールが蔓延する集団に大抵適用できる有用なものだろう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「私たちは人間が人間にとって怪物になるメカニズムを発見し、それを抑止する方法を作り出すこともできるはずだ。」いじめと言う問題を社会の構造上の問題ととらえなおし、制度設計を見直すことを提唱している。難解な言い回しが残念。もう少し分かりやすい文章にしてくれたら助かる。
Posted by