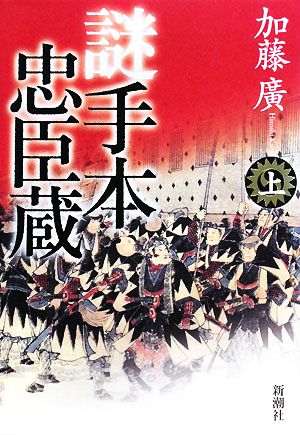謎手本忠臣蔵(上) の商品レビュー
最新作の「空白の桶狭間」を読んだのですが、その時に、この本がすでに書かれていたことに気づきました。今回は、本能寺の変に引き続いて、「忠臣蔵」にまつわる事件をベースにした小説です。このレビューは小説の中で触れられている、当時の経済・歴史の秘話等を垣間見ることができる内容を中心に、気...
最新作の「空白の桶狭間」を読んだのですが、その時に、この本がすでに書かれていたことに気づきました。今回は、本能寺の変に引き続いて、「忠臣蔵」にまつわる事件をベースにした小説です。このレビューは小説の中で触れられている、当時の経済・歴史の秘話等を垣間見ることができる内容を中心に、気になったことを抽出しておこうと思います。 以下は気になったポイントです。 ・家康が関が原の戦い時に、家康が福島正則に与えた保障として、「秀頼を地方大名として残さなかった場合には、その誓書の持参者に江戸城を明け渡す」という内容を記述したものがあった(p36) ・当時の官僚である目付は、徒頭・小十人頭・御小姓からの、先輩目付の投票により選ばれ、若年寄の認可を経て就任する、年功序列とは全く異なる実力主義のシステムであった(p62) ・綱吉時代の銀換算700貫は、金換算すると、9300両となる(p127) ・当時の大名が直接抱える藩士は、平均して禄高の3厘(0.3%)以下であり、赤穂浅野家(公称:5.3万石、塩収入入れて6.5万石程度)の場合は150人程度、それに対して実際は200数十人であったので多い(p129) ・内蔵助が会得した剣法(東軍流)は、最初から相手の絶命を狙うことを意図せず、もっぱら耳・指・腕・脚を切って相手の戦闘意欲を失わせることにある、剣が刃こぼれすることもなく、何人相手にしても戦闘能力が落ちない、やられた敵が生きているため、僚友は放置するわけにもいかず、さらに戦闘能力は下がる(p270) ・女一宮(将軍家光の姪)を次期天皇(明正天皇)にすることで、女帝は夫を持つことがないため、徳川の血統を一代で終わらすことに成功した(p312) ・旧来の「宣明暦」は862年に唐からもたらされていたが、800年間において誤差を生じていた、それを日本向けに工夫したのが「大和暦」で、織田信長が変更しようとしてから102年後の1684年に採用された(p321) ・秀吉は、金(慶長大判、小判)を褒美にあたえる「見せ金」として、流通には、銀と銅を使う、二重貨幣政策を採っていたが、家康はこれを理解できず、生活貨幣に金を混ぜるという愚を犯してしまった(p335) ・元禄小判発行による慶長小判との出目(金の差額利益)は、5000万両(3兆~5兆円)に及んだので、綱吉も四代の家綱同様に浪費を続けることができた(p336)
Posted by
著者が挑む忠臣蔵の謎解き。側用人・柳沢吉保へスポットを当てて、対朝廷政策、浪士びいきの世論の醸成など、事件の背後で操っていたという説をとる。 どこまで史実か不明な点と人物描写であまり感情移入できなかったが、忠臣蔵の背景を推理した点は興味深かった。
Posted by
柳沢吉保の視点からスタート 内容忘れた 一年半ぶりに読み返す 忠臣蔵はやはり大好物 神君の秘められた約定が全ての原因だったのか 痞(つかえ)の発端は9歳で、幕府の秘密に触れたが 原因だとすれば・・・そして、発動した原因は朝廷を ないがしろにした高家吉良上野介の態度であるが ...
柳沢吉保の視点からスタート 内容忘れた 一年半ぶりに読み返す 忠臣蔵はやはり大好物 神君の秘められた約定が全ての原因だったのか 痞(つかえ)の発端は9歳で、幕府の秘密に触れたが 原因だとすれば・・・そして、発動した原因は朝廷を ないがしろにした高家吉良上野介の態度であるが 表ざたにするのも天皇をないがしろにすることになる ジレンマに病気の中であるにも関わらず従容と死に 向かった主君の気持ちに気がついた大石
Posted by
加藤廣さんの作品ということもあり、どんな忠臣蔵を描いてくれるのかと期待して読み始めました。やはり今までの忠臣蔵とは違う!下巻が楽しみです。
Posted by
柳沢吉保の視点で忠臣蔵の展開をみるという点では面白い趣向で読み進めました。上巻の段階での大石内蔵助の描き方は、まぁ無難な感じですかね。下巻が楽しみな終わり方になってて良かったです。
Posted by
江戸時代、忠臣蔵ってあまり興味がなくて手がでなかったが、作者につられて読んでみると・・・案外読む手が止まらなかった。忠臣蔵そのものを詳しく知らないが、印象と違って複雑に入り組んだ事情のあるミステリーな事件なのだなと感じた。
Posted by
「信長の棺」「秀吉の枷」「明智左馬助の恋」と続く、加藤廣の新作 毎回なかなか良く出来ており、感心する。 「温故知新、すべての問題も解答も、我々の歴史の中に隠れておりまする」 忠臣蔵の謎はいかに?
Posted by
将軍綱吉の母・桂昌院に従一位を取らせる「桂一計画」の使者として朝廷との往復を重ねるも遅々として進まぬ吉良上野介。 綱吉たってのこの望みを叶えるべく頭を悩ます側用人・柳沢保明(吉保)は、同時にその存在すらあやふやながらも、真実であれば徳川幕府の消滅にもつながる《神君密書》探しにも躍...
将軍綱吉の母・桂昌院に従一位を取らせる「桂一計画」の使者として朝廷との往復を重ねるも遅々として進まぬ吉良上野介。 綱吉たってのこの望みを叶えるべく頭を悩ます側用人・柳沢保明(吉保)は、同時にその存在すらあやふやながらも、真実であれば徳川幕府の消滅にもつながる《神君密書》探しにも躍起になっていた。 密書が真に存在するとすれば、大いにその鍵を握るであろう浅野内匠頭は、年中行事の勅旨を迎える接待役を持病を理由に断ろうとする。持病は神君密書が原因で起こり始めたのではないか――。 保明が穿った見方をしつつ様々に思いを寄せている中、勅旨を迎える当日、当の内匠頭が殿中にて吉良に斬りつける事件が起こる。その原因の不透明さはもちろん、本来刺す用途の小さ刀で斬りかかるという内匠頭の異常さ、背後から襲ったという武士にあるまじき行為などが浮き彫りになる中、何よりも衝撃的な報が保明を揺るがす。 ――朝廷勅旨登城時間繰上げ。 内匠頭の刃傷事件が公家たちに丸見えだったということではないか!! そして、時間繰上げは吉良の独断によるものとの情報が入り、吉良への怒りがこみ上がる保明。同時に、公家たちは内匠頭による刃傷事件を予見して傍観のために時間を繰り上げたのではないかという疑念も浮かぶ。 一方、殿中での刃傷事件の責任をとって内匠頭が即日切腹させられた報に、蜂の巣をつついたが如くの赤穂藩。 激昂する藩士を尻目に主君の本意を探ろうとする大石内蔵助。内匠頭が吉良に抱いた「遺恨」とは一体何なのか――。 (2009/3/9 読了)
Posted by
浅野の殿は、幕府に殉じて果てたのだ―。 浅野内匠頭が最期まで秘匿した事実は、幕閣・柳沢吉保を震撼させた―。 朝幕の紛争・喪われた密書の行方…日本人は三百年間騙されていた! 『信長の棺』を凌駕する、壮大な歴史ミステリー。
Posted by
歌舞伎やドラマだと討ち入りに向かう浪士たちの心の動きがメインになりますが、『謎手本・・』ではあくまでその謎に焦点をあてている・・感情に押し流されるのではなく冷静に現状を見つめる2つの目から(大石 柳沢)話しが進められていきます。そのせいでしょうか小説・・と言うよりは「その時歴史が...
歌舞伎やドラマだと討ち入りに向かう浪士たちの心の動きがメインになりますが、『謎手本・・』ではあくまでその謎に焦点をあてている・・感情に押し流されるのではなく冷静に現状を見つめる2つの目から(大石 柳沢)話しが進められていきます。そのせいでしょうか小説・・と言うよりは「その時歴史が動いた」っていうテレビ番組を活字で読んでいる感覚でした。(笑)小説の中にいきなり作家目線の文章が出てきたりするので小説読みはちょっと戸惑うかもしれませんが慣れればOKです。(再現ドラマの後の松平さんの解説みたいな・・感じ?)私はちょっと読むのに手こずりましたが 忠臣蔵をよく知らない人でも楽しめる本だと思います。
Posted by
- 1
- 2