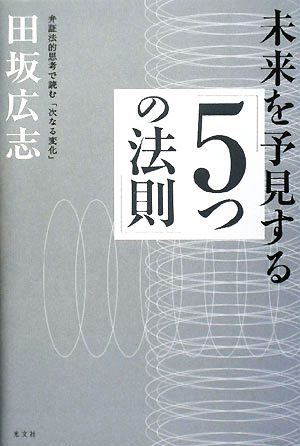未来を予見する「5つの法則」 の商品レビュー
ヘーゲル 存在するものは合理的である 知識社会においては、言葉で表せる知識が価値を失い、言葉で表せない智恵が価値を持つようになる
Posted by
以前の著作の「これから何が起こるのか」と「使える弁証法」で述べられていたことが、ミックスされて、さらに要点をまとめて整理された感じの本。 前作では、「螺旋的発展」という内容に一番重点がおかれていて、それに大きなインパクトを受けたのだけれど、この本の中では「矛盾による発展」というこ...
以前の著作の「これから何が起こるのか」と「使える弁証法」で述べられていたことが、ミックスされて、さらに要点をまとめて整理された感じの本。 前作では、「螺旋的発展」という内容に一番重点がおかれていて、それに大きなインパクトを受けたのだけれど、この本の中では「矛盾による発展」ということについての説明が、かなり衝撃的だった。 例えば、企業における「利益追求」と「社会貢献」、「短気収益」と「長期戦略」、政策における「市場原理」と「政府規制」、というような対立するニ項がある時、どちらかに決めてスパッと割り切るのではなく、その中庸を選択するのが、今後重要になるのだという。 「バランスを取る」というのはソフトな言葉だけれども、それではまだ中途半端で、本来であれば相容れないはずのものを自分の心の中に同居させて、一つ高い次元へと止揚させる器の大きさが、ここで言われている「矛盾のマネジメント」だ。 これは、「キリスト教」対「イスラム教」、「先進国」対「新興国」というような、さらに大きな枠組みに対しても、同じように適用出来る。この、多くの価値観を認めるという考え方は、まさに、21世紀の理想形を言い表したものだろうと思う。 田坂氏の本がいいのは、ビジョンの方向性の表現の仕方がとても前向きなことだ。 個人が、仕事とプライベートで異なったペルソナを持って、別々の表現するというのは、とらえ方次第では、現代の病理の一つとして片付けられてしまうこともある。 しかし、この本の中では、その多様性はそれぞれの個人にとって大切な「癒し」と解釈されて、しかも「矛盾による発展」のために必要な要素であると言っている。 著者の目からは、本当にシンプルな形で、世の中の進み方の原理が見えているんだろうということが、よく伝わってくる。西洋の知識と、東洋の心とが融合されたような奥行きがある。その思考のエッセンスが、とても読みやすく、わかりやすい形で表現された、素晴らしい本だと思う。 「存在するものは、合理的である」 このヘーゲルの言葉は、何を語っているのか。 現実に世の中に存在したものには、必ず「意味」がある。 そのことを語っているのです。 すなわち、この世の中に存在したもので、 全く「意味」が無いにもかかわらず、存在しているものはない。 ただ、時代が変わり、社会が変わったことによって、 その「意味」の大きさが変わり、相対的な「重要度」が低くなったため、 社会の表面から姿を消したにすぎないのです。(p.61) ネットワーク社会における技術や商品やサービスは、 それが多くの人々が使うものになればなるほど、 誰にとっても役に立つ技術や商品やサービスになり、 ますます多くの人々が使うようになるのです。 「ユーザー数」が増え、ある一定の水準を超えると、 そこから「自己加速」が始まり、社会や市場の性質が、 急速に、そして大きく、変わっていく。(p.128) 世の中の物事が、変化し、発展し、進化していくのは、 その物事の中に「矛盾」があるからである。 そして、その「矛盾」こそが、物事の発展の「原動力」であり、 物事を変化させ、発展させ、進化させていく 「生命力」に他ならない。(p.147) 昼は、企業のマネージャーとしてのパーソナリティを生き、 週末は、社会企業家のパーソナリティを生きる。 ウェブの世界では、商品開発に参加するデザイナーの人生を生き、 自身のブログでは、小説家やエッセイストとしての人生を生きる。 そして、ときに、ウェブサイトでの写真展を開く写真家の人生や 自作の曲を自演するミュージシャンとしての人生を生きる。 そうした形で、我々は、これまで「ペルソナ」の陰に抑圧してきた 様々な「パーソナリティ」を表現し、生きることがでいるのです。 そうした「脱ペルソナ社会」とでも呼ぶべきものが、到来するのです。 では、それが、なぜ、重要な意味を持つのか。 「癒し」だからです。 「抑圧された自己」や「隠れた自己」を発見し、受容し、表現すること。 それは、人間にとって、深い「癒し」だからです。(p.201) かつて、文化人類学者、レヴィ・ストロースが、 「文明」と「未開」という言葉の持つ落とし穴を鋭く洞察し、 我々が「未開」と呼ぶ人々の中に、 実は、優れた智恵が数多く宿っていることを述べましたが、 まさに、その言葉通り、かつての「古い文明」の中に、 優れた「生命論的な智恵」が、数多く眠っているのです。(p.223)
Posted by
《要旨》 未来を知りたい。その思いは誰にでもある。「具体的な変化」を予測することはできないが、「大局的な方向」を予見することはできる。この大局観を身につけるのに必要なのが「弁証法」である。弁証法の哲学は世界の発展の「5つの法則」を教えている。 まずは、「螺旋的プロセス」に...
《要旨》 未来を知りたい。その思いは誰にでもある。「具体的な変化」を予測することはできないが、「大局的な方向」を予見することはできる。この大局観を身につけるのに必要なのが「弁証法」である。弁証法の哲学は世界の発展の「5つの法則」を教えている。 まずは、「螺旋的プロセス」による発展(1)。上から見ると、昔の場所に「復活・復古」していくように見えるが、必ず一段高い場所へ登っている。古いものが新たな価値を伴って復活してくるプロセス。だから、消えていった機能の「復活」を読む。2つ目は「否定の否定」による発展(2)。現在の「動き」は必ず将来反転する。だから、現在の動きの反転を読む。この2点で次の主戦場がどこに移行するか予見する。その移行する可能性を見るのが3つ目の「量から質への転化」による発展(3)である。この量が一定の水準を超える目安の一つが「キーワード」が忘れられたか(社会全体に広がり浸透した)というもの。これらに加え重要なのが、「対立物の相互浸透」による発展(4)である。対立する両者は「融合」し、「統合」されていく。 この4つの根底にある基本法則が「矛盾の止揚」による発展(5)である。矛盾を機械的に解消するのではなく、弁証法的に止揚したときに物事は発展する。これにより、どのようなパラダイム転換が起こるか予見できる。 《印象に残ったコトバ》 未来に起こる「細かな動き」は分からない。しかし、未来に向かっての「大きな流れ」は分かる。(略)それが、本来、「大局観」と呼ばれるものです。そして、その「大局観」を働かせることによって、未来は「予見」できるのです。 《感想》 この本を読んだ時に、「虫の目、鳥の目、魚の目」というコトバを思い出した。虫の目で細かいところを見て、鳥の目で俯瞰する。それだけでなく、魚の目で潮流を捉える。初めて、魚の目でモノを見る方法を与えられたと思った。 《目次》 序話 未来を予見する鍵は弁証法にある。 第一話 世界は、あたかも、螺旋階段を登るように発展する。 第二話 現在の「動き」は必ず、将来、「反転」する 第三話 「量」が一定の水準を超えると、「質」が、劇的に変化する。 第四話 対立し、競っているもの同士は、互いに、似てくる。 第五話 「矛盾」とは、世界の発展の原動力である。 第六話 弁証法的思考で予見する未来
Posted by
本書は、結論から言うと良い。そして、買うべきだと思う。 ビジネス書としているが、ビジネスに関係なく、物事の本質を 見抜くための、一つの有益な視点を提供してくれる内容である。 未来を予見する。細かい動きは分からない、誰だって予測不可能だ。 しかし大局的な流れは予想できる。そのため...
本書は、結論から言うと良い。そして、買うべきだと思う。 ビジネス書としているが、ビジネスに関係なく、物事の本質を 見抜くための、一つの有益な視点を提供してくれる内容である。 未来を予見する。細かい動きは分からない、誰だって予測不可能だ。 しかし大局的な流れは予想できる。そのための思考法として弁証法的思考が有効だ。 螺旋階段を上るように世界は発展し、ある時点で今は反転する。水準を超えれば、 質が劇的に変化する。という内容である。 そして、本書の醍醐味は、 1.螺旋階段的現象の理解 2.弁証法的思考 3.歴史知識の重要性の認識 の3つだと個人的には思う。 1は、3と似た部分がつまり「歴史は繰り返す」という事。しかし、単に繰り返す だけではない。一周して戻ってきた時には、より高みにいる。これが螺旋階段的現象 である。私達が新しいと思っている事は、実は古い前のシステムをより良い物にして 再実現しているのに過ぎないかもしれない。 2は、多少哲学をやっている人なら分かるだろうが、相反する物事を昇華させて 新しい物事を作り出す事である。物事には、必ず負と正の両方の面を持ち合わせている。 それに目隠しするのではなく、ぶつかり合わせ、さらに発展できないかを考える。 これが、神髄である。 3は、歴史が繰り返すのであれば、歴史を俯瞰して置くことは、当たり前の話だろう。 最後に、もう一点重要な点を、 4.存在したものには、必ず良い部分がある。逆を言えば、消えてしまったシステムでも 必ず参考になるものはある。 早速、本書の要点を参考にさせてもらおう。
Posted by
2008.11.23 はまちゃんから。 敬愛する田坂氏の新刊。 私が好きだと知ってて貸してくれる。 「使える弁証法」にあらたにプラスされ 日本発の知の技法として活用されたい。 ☆未来予測はできないけど、大局的な方向は予見できる。 ☆弁証法5つの法則 ?螺旋的プロセスによる発展...
2008.11.23 はまちゃんから。 敬愛する田坂氏の新刊。 私が好きだと知ってて貸してくれる。 「使える弁証法」にあらたにプラスされ 日本発の知の技法として活用されたい。 ☆未来予測はできないけど、大局的な方向は予見できる。 ☆弁証法5つの法則 ?螺旋的プロセスによる発展の法則 世界はあたかも、螺旋階段をのぼるように発展する ?「否定の否定」 現在の「動き」は将来、必ず「反転」する。 ?「量」から「質」への転化 一定水準を超えると劇的に変化 ?「対立物の相互浸透」 対立し、競っているもの同士は、互いに似てくる ?「矛盾の止揚による」 矛盾とは、世界の発展の原動力。
Posted by
■能力UP ?未来を予測するには大局観を見つける事が最も大切であり、それは世界発展の法則を学ぶことです。 ?ただ懐かしいものが復活するのではない。便利になった、懐かしいものが復活する。 ?世の中をみつめる4つのステップ:1、何が復活してくるかを読む2、何が消えていったのかを見る3...
■能力UP ?未来を予測するには大局観を見つける事が最も大切であり、それは世界発展の法則を学ぶことです。 ?ただ懐かしいものが復活するのではない。便利になった、懐かしいものが復活する。 ?世の中をみつめる4つのステップ:1、何が復活してくるかを読む2、何が消えていったのかを見る3、なぜ消えて言ったのかを考える。4、どうすれば復活できるかを考える。 ?互いに矛盾し、対立するかに見える二つのものに対して、いずれか一方を否定するのではなく、両者を肯定し、包含し、統合し、超越することによって、より高次元のものへと昇華していく。
Posted by
◆目次 第一の法則 世界は、あたかも、螺旋階段を登るように、発展する 第二の法則 現在の「動き」は、必ず、将来、「反転」する。 第三の法則 「量」が、一定の水準を超えると、「質」が、劇的に変化する。 第四の法則 対立し、競っているもの同士は、互いに、似てくる。 第五の法則 「矛盾...
◆目次 第一の法則 世界は、あたかも、螺旋階段を登るように、発展する 第二の法則 現在の「動き」は、必ず、将来、「反転」する。 第三の法則 「量」が、一定の水準を超えると、「質」が、劇的に変化する。 第四の法則 対立し、競っているもの同士は、互いに、似てくる。 第五の法則 「矛盾」とは、世界の発展の原動力である。
Posted by
さすが田坂さん、というべき本。 本自体の構成の仕方が非常に読みやすくなっている。 圧巻は最後の章。 とにかく読んでいてワクワクする。 こんなにもおもしろい時代に生きていることを 改めて実感させられた。 友人にもすぐに読ませました!w 大切にしたい本の一つです。
Posted by
これから何が起こるのか? 未来を知りたい。 そう思う方は多いと思います。 知る為にはどうすればよいのか? そのヒントが溢れている本です。 著者は、 《未来は、「予測」できない。 しかし、「予見」はできる。》 と書いています。 未来を「予測」できな...
これから何が起こるのか? 未来を知りたい。 そう思う方は多いと思います。 知る為にはどうすればよいのか? そのヒントが溢れている本です。 著者は、 《未来は、「予測」できない。 しかし、「予見」はできる。》 と書いています。 未来を「予測」できなくても、「予見」ができれば、充分でしょう。 台本どおりにすすむ人生ではおもしろくないでしょう。 ですか、「予見」するのは難しいです。 「予見」する為に、本書を読んでみてみないですか? 新しい未来が見えてくるのでは。
Posted by