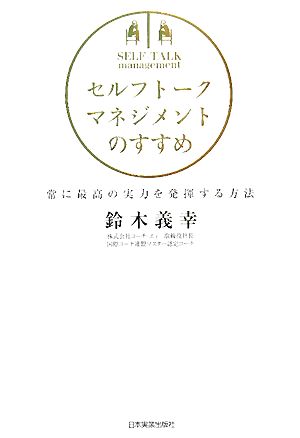セルフトーク・マネジメントのすすめ の商品レビュー
この本の核になるのがビクトール・フランクルの言葉。 「刺激と反応の間には、いくばくかの「間」が存在します。 私達はこの「間」の中で、自分の反応を選択します。 私達の成長と自由は、私達が選ぶ反応にかかっているのです。」 刺激→ビリーフ(アイデンティティ、価値観、世界観)→セルフト...
この本の核になるのがビクトール・フランクルの言葉。 「刺激と反応の間には、いくばくかの「間」が存在します。 私達はこの「間」の中で、自分の反応を選択します。 私達の成長と自由は、私達が選ぶ反応にかかっているのです。」 刺激→ビリーフ(アイデンティティ、価値観、世界観)→セルフトーク→感情→行動 ティモシー・ガルウェイ 「インナーゲーム」 →「セルフ1」と「セルフ2」 セルフトークAとセルフトークBの考え方 Aを減らし、Bに変換 P55 指揮者ベンジャミン・ザンダーの話 コンサートに来なかった学生に叱るのではなく、自分が悪いと謝った。 ・デール・カーネギー「話し方入門」 ・ミハイ・チクセントミハイ 「フロー体験:喜びの現象学」 ・フロー、ゾーン、何も考えない状態、瞑想 ・イチローのバッターボックスでのしぐさは集中のためのスイッチ 再読必要。
Posted by
セルフトークという考え方はわかりやすい。実践は難しそうだが、刺激と反応に対しての悩みに整理して考えるきっかけができた。
Posted by
セルフトークとは、「感情や欲求、思考、行動の引き金として、自分の中に生まれる『言葉』」(p.19)であり、これを自らがコントロールしていくことで日常のあらゆる場面において良い結果をもたらすことを説明している。「感情」に結びつく言葉である「反応」としてのセルフトークAが生まれるのは...
セルフトークとは、「感情や欲求、思考、行動の引き金として、自分の中に生まれる『言葉』」(p.19)であり、これを自らがコントロールしていくことで日常のあらゆる場面において良い結果をもたらすことを説明している。「感情」に結びつく言葉である「反応」としてのセルフトークAが生まれるのは、実際の今の自分と理想像ともいえるアインデンティティやビリーフとの間にギャップが生じたためという。感情的な行動をコントロールするには、セルフトークBと区分した、理性的な「対応」としての行動に移す言葉が必要とされる。また、セルフトークは、過去―未来のX軸と、自責(肯定)―他責(否定)のY軸の4象限でその質を評価できる。 これらのセルフトークを自らの境遇や状況により、使う、減らす、なくすことがセルフトークマネジメントである。この枠組みを知っているかどうかで、人生が変わってくるといっても過言ではないと思った。 http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20090831/203802/?rt=nocnt
Posted by
【2015/3/26】 紹介者:米山 レビュー:米山 大切なテニスの試合であがっちゃってネットばっかり、 就活の面接であがっちゃって何言ってるかわかんない、 上司に怒られながらの指示が頭に入ってこない、、、 それって、頭の中の会話が原因だった!? 自己と自己の会話から、自己を...
【2015/3/26】 紹介者:米山 レビュー:米山 大切なテニスの試合であがっちゃってネットばっかり、 就活の面接であがっちゃって何言ってるかわかんない、 上司に怒られながらの指示が頭に入ってこない、、、 それって、頭の中の会話が原因だった!? 自己と自己の会話から、自己をコントロールするための書。 理屈から、解決方法まで!
Posted by
自分の深層心理に問いかける。 ネガティブなワードをポジティブにする。 マイナスになるセルフトークへの気気付きがまず第一歩ですね。 感情的な部分を治せそうです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
自己暗示、心の声、セルフトークについての本。なかなかためになる部分も多くおもしろかった。オーディオブックにて。 <メモ> ・セルフトークはアイデンティティを守るために生まれる ・思春期はセルフトークが生まれやすい。アイデンティティを固めていくために。 ・ダウトはダブルハートが語源 ・ネガティブなセルフトークをポジティブなセルフトークへ ・感情に呼び起こされる反応と理性によって呼び起こされる対応がある。 ・反応ではなく、対応する。 ・反応と対応を意識する。 ・問いが変わるとはじめて脳の中で新しい検索が行われる。 ・悩むは頭の中がぐるぐる、考えるは答えに向かう問いを立てること。 ・逃げないためのセルフトークBを準備しておく。 ・恐怖に打ち勝つためにはどのようにすべきか。事前にセルフトークを決めておく。たとえば緊張しそうな時、緊張するな!ではなく、汗かけ!もっと緊張しろ!と考えると自分を冷静にみることができ緊張がとける。 ・くせになっていることを意識化することにより、コントロールできるようになる。 ・ストレスを自分でコントロールできる、終わりがくると思えばいい。 ・話したくて仕方がないというレベルまでスピーク原稿をレベルアップさせることで緊張しなくなる。 ・ゾーンとフロー。セルフトークがなくなる状田。セルフトークBで満たされた状態。 ・達人はその時を生きている。セルフトークがない状態。 ・自分の中の未完了をへらすこと。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
自分自身を上手くコントロールすることでコンスタントに実力を発揮することができる、という考え方がこのセフルトーク・マネジメント。 通常、人間の感情や行動を引き起こすプロセスは、 1.アイデンティティや価値観を刺激 2.セルフトーク 3.感情 4.反応 というステップに分解されるそうです。このうち2番めの「セルフトーク」を意識することで、「感情」ではなく「理性」をもって「反応」ではなく「対応」としての行動を導くというのがセフルトーク・マネジメントの目指すところです。 よく「気の持ちよう」なんてことが言われますが、これを意図的に良い方向に持っていくテクニック、とでも言えば分かりやすいでしょうか。
Posted by
久しぶりにコーチング系の本を読んだ。科学的な論拠が多いわけではないのに、その内容に相変わらず納得してしまうのは、著者の論理的な話の展開と豊富な事例やアナロジーから来るものだと思う。そしてそれらが自分の体験と大いに重なるからだ。 “セルフトーク”の概念は著者・鈴木氏のオリジナルのも...
久しぶりにコーチング系の本を読んだ。科学的な論拠が多いわけではないのに、その内容に相変わらず納得してしまうのは、著者の論理的な話の展開と豊富な事例やアナロジーから来るものだと思う。そしてそれらが自分の体験と大いに重なるからだ。 “セルフトーク”の概念は著者・鈴木氏のオリジナルのものであると思うが、同じようなフレームワークは実際に存在する。しかし、鈴木氏独自の視点が興味深く納得する。 セルフトークが「感情」を生み「行動」になる。ネガティブなセルフトークはネガティブな行動と結果につながる。ネガティブなセルフトークは“アイデンティティ”を守ろうとすることから無意識的に発生する。アイデンティティを変えることは難しいから、ネガティブのセルフトークを変えたり、なくしたりすることに注力する。究極の状態は“FLOW”。 コーチング系のスキルは頭で分かっていてもなかなか実践できないからいつまでもたってもモノにならない。habitとして身につけるためにその理屈を知ることは大切。
Posted by
●私たちの成長と自由は、 私たちが選ぶ反応にかかっているのです。 ★★★☆☆ 「セルフトーク」とは、「自分の中での会話」のこと。 この本の中では、 人の感情や行動と密接に関係しているセルフトークを通じて 自分自身をコントロールする方法を示しています。 自分自身をコントロール...
●私たちの成長と自由は、 私たちが選ぶ反応にかかっているのです。 ★★★☆☆ 「セルフトーク」とは、「自分の中での会話」のこと。 この本の中では、 人の感情や行動と密接に関係しているセルフトークを通じて 自分自身をコントロールする方法を示しています。 自分自身をコントロールすると思うと 難しそうですが 変えるべきネガティブなセルフトークは2つだけ 「もし~しなかったら(if not?)」 「どうしてこんなことに?(why not?)」 たった2つだけでいいのかと思えば 私は少し気が楽になりました。 どんな状況でも実力を出せるように 取り組みたい1冊です。
Posted by
コーチングの専門家による本。 刺激により感情や行動の引き金として自分の中に生じるのがセルフトーク。 これには感情を呼び起こして反応としての行動にいくものと、理性を呼び起こして対応としての行動につながるものがある。本書では前者を減らして自身をコントロールする方法について書かれている...
コーチングの専門家による本。 刺激により感情や行動の引き金として自分の中に生じるのがセルフトーク。 これには感情を呼び起こして反応としての行動にいくものと、理性を呼び起こして対応としての行動につながるものがある。本書では前者を減らして自身をコントロールする方法について書かれている。 自分の思考の癖を直したり、ストレスを貯めないように自己管理したりと、習得できたら便利そう。
Posted by