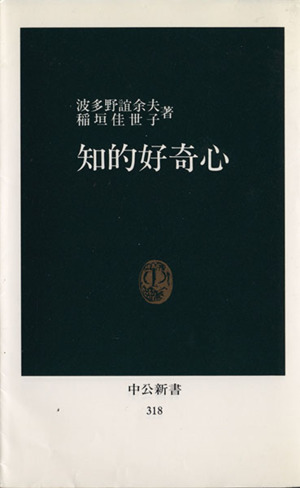知的好奇心 の商品レビュー
Na図書館本 動機づけの講座で紹介されて。 1973年に書かれた本ですが、今読んでも何の違和感もない。 知的好奇心には二つ。 1情報への飢えから生ずるもの 2知識の不十分がわかった時に生ずるもの 人は内在的に向上心あるのでは? 好奇心や向上心のようなプラスの動機づけ。 自発性...
Na図書館本 動機づけの講座で紹介されて。 1973年に書かれた本ですが、今読んでも何の違和感もない。 知的好奇心には二つ。 1情報への飢えから生ずるもの 2知識の不十分がわかった時に生ずるもの 人は内在的に向上心あるのでは? 好奇心や向上心のようなプラスの動機づけ。 自発性は遊びや好きなことの一種。遊びは新しい技能獲得や習熟と結びついている。 その能力の発達が止まってしまえば新たな経験を求め探索したり、知識を高めることがなくなる。面倒になり、従来はものぐさだという伝統的理論モデルに近づくことになる。 人は本来学習する動物。 子どもの教育や労働、ムチとニンジンによる管理を繰り返すより人間らしく働ける喜びを。 信頼することで向上心アップすることも。 人はもともとイヤイヤ働くに過ぎない存在との考えを否定。条件さえ整えば、働くことこそ最高の自己表現の機会であり、楽しい経験をもたらすものという前提に立たねばならない。労働意欲をどうやって高めるか。労働者の自発性や参加を引き出す。内的動機づけについてを述べている。
Posted by
外発的動機づけに基づく心理学を怠け者の心理学という。 人の内発的動機に目を向けて歴史的な一冊。 この一冊のお陰で、動機づけ理論にパラダイムシフトが起きたのではないだろう。
Posted by
知的好奇心の観点から教育を捉えた本。旧来の教育の根本には「人間は怠け者である」という人間観があり、それは心理学の見地から否定されているという論から始まり、人間に内在する知的好奇心を大いに活用する教育にはどんなものがあるのかを具体例とともに紹介している。 1973年に発行された本に...
知的好奇心の観点から教育を捉えた本。旧来の教育の根本には「人間は怠け者である」という人間観があり、それは心理学の見地から否定されているという論から始まり、人間に内在する知的好奇心を大いに活用する教育にはどんなものがあるのかを具体例とともに紹介している。 1973年に発行された本にも関わらず今読んでもかなりの示唆に富んだ本であり、教育に少しでも携わる人なら読んで損はないかと思う。 コロナのご時世で「子どもが怠けてしまって、いかに勉強をさせるか」という論点で議論されていること自体まだまだ時代は変わっていないのだなあと思う。むしろ枠組みが緩んだ今だからこそ「もっと子ども本位の学習をするにはどうしたらいいか」を試行錯誤するいい機会であり、この本はかなりの程度参考になるのではないだろうか。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
様々な実験を通して、人間の知的好奇心について探っていく。前提は「人間は怠け者だ」ということ。さて本当に怠け者なのか、知的好奇心旺盛の動物なのか。 印象的なのは「感覚遮断」の実験。ここで私の中にあった「怠け者説明」は大いに変わった。
Posted by
"知的好奇心というタイトルに惹かれて購入した。知的好奇心とは何かを前段に語り、後半はその知的好奇心を刺激する教育の方法について触れている。後半は興味なく、前半はそれなりに面白かった。 人間は、そもそも怠ける者なのか、あるいは勤勉な者なのか?という疑問についていろんな視点...
"知的好奇心というタイトルに惹かれて購入した。知的好奇心とは何かを前段に語り、後半はその知的好奇心を刺激する教育の方法について触れている。後半は興味なく、前半はそれなりに面白かった。 人間は、そもそも怠ける者なのか、あるいは勤勉な者なのか?という疑問についていろんな視点から探っていく。 知的好奇心を持った、勤勉な生物だということを前提に前半は話が進すむ。怠けることを前提とした教育や仕事のやり方を批判している。 そんな本。"
Posted by
Posted by
人は本来怠け者で、労働や勉強をさせるにはアメとムチが必要だとする「伝統的心理学」に真っ向から対抗する。人は本来的に知的好奇心があるから、それをうまく育ててあげることが大事だということらしい。 たしかに、人に知的好奇心があることは理解できるし、勉強も仕事も、やらされるのではなく、...
人は本来怠け者で、労働や勉強をさせるにはアメとムチが必要だとする「伝統的心理学」に真っ向から対抗する。人は本来的に知的好奇心があるから、それをうまく育ててあげることが大事だということらしい。 たしかに、人に知的好奇心があることは理解できるし、勉強も仕事も、やらされるのではなく、自発的に取り組めるようになれば、もっと楽しくなるんだろうと思う。 でも、、、現実を見ると、勉強や仕事を「やらされてる」人の多いこと。これはいったいどうしたことか。人に本来的に知的好奇心があるのなら、もっとそうした人が少なくなっても良いはずなのに。そこで、私は次のように考えました。 人には知的好奇心が本来的に備わっている反面、怠け者である面も否定できず、意志の強さ、環境等に左右されるものではないか。したがって、意志の強さや環境を変えるためにはアメとムチも一定程度必要なのではあるまいか。 そういった意味で、伝統的な心理学にも理解を示したいところ。もちろん、自分自身がそうだと信じているように、人にはやっぱり知的好奇心ってあるよな~とも。
Posted by
人間は怠惰である、だからアメとムチで使うべし。という古典的な考え方を否定する。 好きなだけゴロゴロしてていいよ、ただし五感は遮断するからね、という実験では2日ほどしかもたなかったという。本来、人間は内から湧き出る好奇心を持っているものだということらしい。 それをどう活かすかという...
人間は怠惰である、だからアメとムチで使うべし。という古典的な考え方を否定する。 好きなだけゴロゴロしてていいよ、ただし五感は遮断するからね、という実験では2日ほどしかもたなかったという。本来、人間は内から湧き出る好奇心を持っているものだということらしい。 それをどう活かすかという点では、学生向けの話が主に出てくるので、社会人向けに応用するには、読み替えが必要。という点が残念だった。
Posted by
http://www.chuko.co.jp/shinsho/1973/03/100318.html
Posted by
(1987.05.23読了)(拝借) *解説目録より* 伝統的な心理学の理論は、人間を「ムチとニンジン」がなければ学びも働きもしない怠け者、と見なしてきた。だが、この理論は人間の特色を正しく把えているだろうか。著者たちは、興味深い実験の数々を紹介しつつ、人間は生まれつき積極的に情...
(1987.05.23読了)(拝借) *解説目録より* 伝統的な心理学の理論は、人間を「ムチとニンジン」がなければ学びも働きもしない怠け者、と見なしてきた。だが、この理論は人間の特色を正しく把えているだろうか。著者たちは、興味深い実験の数々を紹介しつつ、人間は生まれつき積極的に情報的交渉を求める旺盛な知的好奇心を持っていること、そしてそうした知識や情報への欲求こそが人間らしく生きる原動力であることを実証し、「人間怠けもの説」に支配されている現在の学習や労働のあり方を鋭く批判する。また、楽しい学習の設計や幼児の知的教育の可能性が具体的に追求される。毎日出版文化賞受賞。
Posted by
- 1
- 2