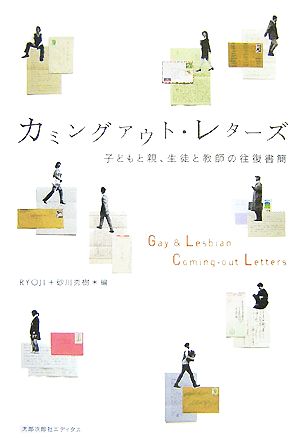カミングアウト・レターズ の商品レビュー
p183「ゲイが人口の数パーセントいるとすると、親はその二倍やん。人口の一割以上がゲイの家族やねんな(後略)」 -------------------------------------------------------------------------------- 同性愛...
p183「ゲイが人口の数パーセントいるとすると、親はその二倍やん。人口の一割以上がゲイの家族やねんな(後略)」 -------------------------------------------------------------------------------- 同性愛者とその周囲の人の手紙のやりとり。 同性愛者であることをカミングアウトする人、された人達の心の葛藤。 手紙だからこその言葉であり、手紙だからそば見えるものもある。 文体も文章も書き方もみんな違うし内容だって違う。けど、みんな普通に読めるのだから、違いなんてないのです。 この本の内容はそういうことと似ていると思いました。 p61「約四十年前に買った『家庭の医学』には、同性愛は頭・脳の病に分類されている(中略)四十年もの歳月が経過したいま、一般の先入観も、知識も理解も、さほど進歩したとは私には思えないのだ。」(letter3) このletter3のお母さんの文章が好きでした。次第に文体がお母さんになっていく感じがなんとも。 p139『そしてぼくはそんなクローゼットのなかで、表通りを、五月のような陽光に祝福を受けて外を歩く人びとを、ひっそりと見つめ、ため息をつき、あるいは妬んで、憎みさえして、そこで生きていたいわけじゃないんだ、ということです』(letter7) 葛藤しなからも彼らが受け入れていった現実。強い文章ばかりでした。 読んだ私は、同性愛者でもなければカミングアウトされた人間でもない、全くの第三者です。 でもそういった第三者・もしくは、自分とは全くの無関係だと思っている方にも、読みやすい本ではないかと思います。
Posted by
特別な人たちではない「生活者」の人々の手紙。 たくさんの葛藤、困惑、痛み…の先にあるのは、誠実で真摯な思いだった。 セクシャルマイノリティが「特別」と括られている訳じゃなく、当たり前にそこに存在している人であった。同じ目線の高さで当事者と家族や先生が話していて、これこそ「社会の...
特別な人たちではない「生活者」の人々の手紙。 たくさんの葛藤、困惑、痛み…の先にあるのは、誠実で真摯な思いだった。 セクシャルマイノリティが「特別」と括られている訳じゃなく、当たり前にそこに存在している人であった。同じ目線の高さで当事者と家族や先生が話していて、これこそ「社会の多様性」だ、と感動した。 一方、最後の対談で、どこか理解したくない部分を持つ一人のお母さんがでてきたが、全てを理解をすることは単純じゃないな、と感じた。でもそれを否定することは違う。 理解しようとしてくれる、そうまでいかなくても否定しない。それだけでも多分良いんだと思う。 現代は「多様性」がキーワードとなっている。 この問題に興味がある人以外の人にもぜひ読んでもらいたい。「多様性」とそれへの向き合い方がわかるはず。 若いうちに読めてよかった一冊だ。
Posted by
うーん、難しい。 カミングアウトして何が悪い。差別する方が悪いんだ。 それはたぶん正論だ。でも、実際にはそう簡単にはいかない。親だって友人だって、偏見の中にどっぷり浸かって生きてきたんだから。 この本に収められた書簡では、大体においてカミングアウトされた側(親や先生など)が最...
うーん、難しい。 カミングアウトして何が悪い。差別する方が悪いんだ。 それはたぶん正論だ。でも、実際にはそう簡単にはいかない。親だって友人だって、偏見の中にどっぷり浸かって生きてきたんだから。 この本に収められた書簡では、大体においてカミングアウトされた側(親や先生など)が最終的には理解を示してくれてる。その裏で何人のレズビアンやゲイがカムアウトを通じて人間関係に亀裂を生じたり、勘当されたり、そして自殺したりしているんだろうか。 あ、ちょっと引っかかったのが、「たとえゲイでも、あなたは私の息子だから。」っていう言い方。それって、「たとえ殺人者でも、あなたは私の息子だから。」と同じように聞こえる。結局、差別から抜け出せてはいないんじゃないかな。もっとも、理解を示してくれるだけですばらしいことなんだけれど。 うーん、難しい。
Posted by
ゲイ、レズビアンであることをカミングアウトした人と、彼らの告白をうけとめた親や教師との間の往復書簡をおさめたもの。特に親や教師たちの側が、きれいごとじゃなく自分自身の動揺や悩みについて率直に語った文章のいくつかが心に残る。これからカミングアウトを考えている人や、告白をどう受け止め...
ゲイ、レズビアンであることをカミングアウトした人と、彼らの告白をうけとめた親や教師との間の往復書簡をおさめたもの。特に親や教師たちの側が、きれいごとじゃなく自分自身の動揺や悩みについて率直に語った文章のいくつかが心に残る。これからカミングアウトを考えている人や、告白をどう受け止めていいか迷っている人には、大きな勇気をあたえてくれる本だと思う。しかしなぜ男親は女親にくらべて受けとめるのが難しいんだろうか、とも思った。
Posted by
どういう経緯でこの本と出会ったか忘れちゃったけど、感想をブログに載せたら、それを見た友人が自分の親にカミングアウトしたという出来事がありました。 「面と向かって言うのはウマく話せないから手紙を書いて伝えよう」 この本には前向きな気持ちが詰まっています。読めば背中をグッと押された気...
どういう経緯でこの本と出会ったか忘れちゃったけど、感想をブログに載せたら、それを見た友人が自分の親にカミングアウトしたという出来事がありました。 「面と向かって言うのはウマく話せないから手紙を書いて伝えよう」 この本には前向きな気持ちが詰まっています。読めば背中をグッと押された気になると思います。 それにしても、この本に出てくる親はみんな理解があって、完成された人たちだなぁと思います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2008.01.09 ひょんなことから読み始めた「カミングアウト・レターズ 子供と親、生徒と教師の往復書簡」に号泣しました。 タイトルの通り、これはゲイ/レズビアンの人たちがカミングアウトを振り返る手紙、あるいはカミングアウトをする手紙、それに対する返事が収められています。 特にねえ、1通目はやばいっす。ああ、子供に対する親の愛というのはこういうものなのかと……「寒いから」という理由でさっさと帰省を切り上げて帰ってきたばかりの私としましては、故郷に住む父母に、なんかちょっと申し訳なく思いましたよ。 周りの友人たちがどんどん「親」になっていく中、子供を持つということがどうにもこうにもぴんと来てない私ではありますが、親になるというのはすごいことなんだなあとそれだけはなんとなくわかった。 それから、セクシャルマイノリティとして生きることはまだまだ大変なんだなあ、とも。 1通目で、母親は息子にこう語りかけています。 「たくさんのものを見なさい。そのなかで覚えておきたいものだけ、胸に残しなさい。(中略)悲しみの前で足を止めるのでなく、どんな世の中でも生き抜く強さをもちなさい。優しくしたたかでありなさい。涙を涸らさず、笑顔でいなさい。そして長生きして、世の中が変わるところを見届けなさい」 その通りだ、その通りだとすごく思った!! 「常識」も世の中もどんどん変わっていく。それを変えていくのは、今の時代を生きる私たち。 同性愛者も異性愛者も、ぜひ一読をおすすめします。
Posted by
親との関わりあいで悩んだときに読んだ。 私もいずれ父にはカミングアウトをしたい。 でも怖い。母にしていたって受け入れられてるとは違う。 手紙、か。 つらいなあ。 いたかったです。
Posted by
つらかったし、苦しかったろうと思う。自分は言う気はないけど同じ立場だったらどうかなーって考えちゃう。いろいろな団体の知識も手に入って交流してみようかなって気になった。
Posted by
一般人の手紙の寄せ集めなので上手な文章、というわけではないですが真摯な気持ちが伝わってくる文面でした。ゲイの方々の父母世代の方々の手紙を読んで、やっぱりこのくらいの世代の同性愛についての一般認識はこういう感じなのか…と思って悲しい気持ちになりました。でも兄弟世代だとだいぶ偏見も薄...
一般人の手紙の寄せ集めなので上手な文章、というわけではないですが真摯な気持ちが伝わってくる文面でした。ゲイの方々の父母世代の方々の手紙を読んで、やっぱりこのくらいの世代の同性愛についての一般認識はこういう感じなのか…と思って悲しい気持ちになりました。でも兄弟世代だとだいぶ偏見も薄れているなあ…この本に出てくるカミングアウトはみんな、一筋縄ではいかなかったけれども受け入れてもらえて良かったと思います。こういう気持ちの繋がりがほしいなあと思った次第です。
Posted by
ゲイとレズビアンの(元)こどもたちと、親や教師との往復書簡。 痛い、とか イラつく、とか、 うわあ、いいなあとか。 いろいろどーんときた。 カミングアウトを薦める本じゃなくて、しても大丈夫だって思える本。 世の中には素敵な人もいるんだよって。 しかしみんな謙虚だな…年齢が上...
ゲイとレズビアンの(元)こどもたちと、親や教師との往復書簡。 痛い、とか イラつく、とか、 うわあ、いいなあとか。 いろいろどーんときた。 カミングアウトを薦める本じゃなくて、しても大丈夫だって思える本。 世の中には素敵な人もいるんだよって。 しかしみんな謙虚だな…年齢が上の人たちは、「受け入れられないのが当たり前」って思っているように見える。 だから完璧な理解を求めずにいられるんだろうか。 私はもっとちゃんと解れよと思ってしまう。 非当事者が理解できるまで待ってあげる姿勢っていうのも大事だ。 でも結局、カムアウトしようとか、してよかったとか、されてよかったって思える人たちは、別の困難にも耐えられるような関係性を最初から作っていたわけで、それは「親子」だからどうのって話じゃないよな。 ターリさんのお母さんが素敵だ。 詳しい感想⇒http://melancholidea.seesaa.net/article/149245016.html
Posted by