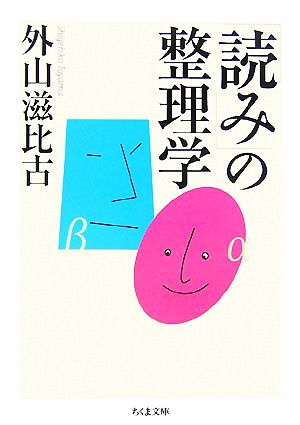「読み」の整理学 の商品レビュー
この本は、お茶の水女子大学名誉教授である外山滋比古さんの著書です。全4章で構成されています。 本の序章では、「わかることは読めるが、わからない事は読めない」というものがある事を書かれています。例として、ワープロのマニュアルが挙げられています。ワープロのマニュアルは一般に初心者には...
この本は、お茶の水女子大学名誉教授である外山滋比古さんの著書です。全4章で構成されています。 本の序章では、「わかることは読めるが、わからない事は読めない」というものがある事を書かれています。例として、ワープロのマニュアルが挙げられています。ワープロのマニュアルは一般に初心者には解りづらいもので、マニュアルの文章のせいにしてしまいます。しかし、ワープロに明るい人がそのマニュアルを読むと、初心者とは違いある程度解りやすいものになります。このように、ある程度知識があれば理解できる事や、あるいはきちんと読み進めれば理解できる事が有ります。それなのに自分が理解できないから、「このマニュアルが悪い」と決め付けてしまう事に落とし穴が潜んでいるとしています。 この本では、読み手が理解できるような「既知」のものを読むことをアルファ読みと称して、逆に読み手が理解不能な「未知」なものを読むことをベータ読みと定義して話を進めています。戦前の日本では、難解のものを読むことが良とされており、ベータ読みが多く行われていました。しかし、戦後アメリカの文化が日本に入ってくるにつれて、平明至上主義の考え方ができ、解りやすい文章が好まれるようになりました。 この本では、人はベータ読みをして、みずからの力によって悟らなくてはならないとし、現代人がアルファ読みからベータ読みに移行するにはどのような事が必要かを書かれています。
Posted by
本を読む場合,既知を読む場合(アルファー読み)と未知を読む場合(ベーター読み)とがある。未知を読むには「読書百遍意おのずから通ず」である。 確かに難解な文章を読むのは辛い。大変なんですが,本当の読書とはと考えさせられる著書です。
Posted by
昨年、東大・京大で一番読まれた本 『思考の整理学』 の著者が、難解な文章の読み方等を教えてくれる作品。 私も「言葉」を使う職業なので… 読み始めました。
Posted by
読書、あるいは文章を読むということはどういうことか。プルーストとイカ(メアリアン・ウルフ)では読書が脳にどういう影響を与えるのか?について解説があったが、この本は読むことについて注目した本。素読、既知と未知、そして未知を読む方法については、たえず新しいものに挑戦するエンジニアにと...
読書、あるいは文章を読むということはどういうことか。プルーストとイカ(メアリアン・ウルフ)では読書が脳にどういう影響を与えるのか?について解説があったが、この本は読むことについて注目した本。素読、既知と未知、そして未知を読む方法については、たえず新しいものに挑戦するエンジニアにとっては必見のノウハウだ。
Posted by
もう一度、読書の方法を検討する必要がある。ベータ読みは新しい知的世界の発見につながる可能性を秘めている。聖書は究極の古典かもしれない。
Posted by
大雑把に言えば、既知を読むアルファー読みに終始せず、未知を読むベーター読みへ移行すべき、という内容。 私は比較的『難しい本』(自分にとって)を読むほうがすきで、でもその難しさに心折れて途中でやめることが多かった。 その一方で、読者に『分かりやすい本』は読みきることができるものの、...
大雑把に言えば、既知を読むアルファー読みに終始せず、未知を読むベーター読みへ移行すべき、という内容。 私は比較的『難しい本』(自分にとって)を読むほうがすきで、でもその難しさに心折れて途中でやめることが多かった。 その一方で、読者に『分かりやすい本』は読みきることができるものの、何か物足りなさを感じていた。 この本を読んで、この感覚は結構大切にすべきものなんじゃないかな、と勇気付けられた。 一度挫折したとしても、多少の時間をかけてでも、何度でも未知と向き合い、ベーター読みをしていきたい。 ちなみにこの本のレベルは私にとって『普通』くらい。
Posted by
本書では、「読み」という作業を2種類に分け、既知の事柄に関して読むことを「アルファ読み」、未知の事柄に関して読むことを「ベータ読み」と呼ぶ。最近の人間は、この「未知を読む」力が弱まってきている、と著者は指摘する。文字そのものをなぞるだけで「この文章はわかりやすい」「この文は読みに...
本書では、「読み」という作業を2種類に分け、既知の事柄に関して読むことを「アルファ読み」、未知の事柄に関して読むことを「ベータ読み」と呼ぶ。最近の人間は、この「未知を読む」力が弱まってきている、と著者は指摘する。文字そのものをなぞるだけで「この文章はわかりやすい」「この文は読みにくい」と判断するのは、本当に「読んでいる」とは言えない。そして、文を書く側の人間も最近の若者たちに「読みやすい」と思われる文章を書こうと「本の商業化」に走る傾向にあることに警鐘を鳴らしている著者の鋭い視点に、大きく肯ける。印象に残ったのは、「幸福な人はなかなか読書の奥義に参入することが難しい」という言葉。これこそ、「読み」の極みだと思う。「葦編三絶」という素敵な言葉にも出逢えたので、得るものが多い1冊だった。ただ、「読書についての書物」というのは、読んで欲しい肝心な人々に読まれないと思っているので、ましてや、本書のような難しい塩梅での主張は受け容れられにくいのではないかと危惧する。
Posted by
「わかることだけ読み取る読書じゃダメ」。書いてある内容には納得できるのですが。 …一方で、やっぱり「人に何かを伝えたいのだったら、もう少し言葉を咀嚼できるギリギリなところまで咀嚼してみてはいかがか」と思いたくなる文章ってありますよね…。これを読む人にそんな勘違いはないとは思うけど...
「わかることだけ読み取る読書じゃダメ」。書いてある内容には納得できるのですが。 …一方で、やっぱり「人に何かを伝えたいのだったら、もう少し言葉を咀嚼できるギリギリなところまで咀嚼してみてはいかがか」と思いたくなる文章ってありますよね…。これを読む人にそんな勘違いはないとは思うけど、この本を「難しくても読みづらくても、読者は努力して読め」と単純に取られちゃったらイヤだなとは思いました。 あと、ベータ読み推奨は納得なのですが、戦前みたいな音読推奨になっちゃうところには論理の飛躍を感じました。懐古主義的においを嗅ぎ取ってしまい、ちょっと引いたかな。
Posted by
既知を読むアルファ読みと未知を読むベータ読み, 二つの読みの違いとベータ読みをしなくなった現代人への 注意を様々な具体例を用いて述べていた. 内容はぼちぼちだったけれども, 最初の中学生からの手紙についての 扱いが気になった. いちいち,中学生からの手紙が悪者にされているもの...
既知を読むアルファ読みと未知を読むベータ読み, 二つの読みの違いとベータ読みをしなくなった現代人への 注意を様々な具体例を用いて述べていた. 内容はぼちぼちだったけれども, 最初の中学生からの手紙についての 扱いが気になった. いちいち,中学生からの手紙が悪者にされているものの, 著者が正しいのか中学生が正しいのかが はっきりしないので,著者に同調できなかった. それが最後まで尾を引いて,あまり良い本とは思えなかった.
Posted by
ほんと、「わかってることを読む」読書と「わからないことを読む」読書は、まったく違うものだよなぁ。 まったく意味のわからないものを読むのを勧めてみたりとか、ちょっと不思議に思う点もあったけれども、 基本的に納得できる点ばかりだったので、★5つ。 本は複雑にかかれてればいいってもん...
ほんと、「わかってることを読む」読書と「わからないことを読む」読書は、まったく違うものだよなぁ。 まったく意味のわからないものを読むのを勧めてみたりとか、ちょっと不思議に思う点もあったけれども、 基本的に納得できる点ばかりだったので、★5つ。 本は複雑にかかれてればいいってもんでもないけど、 易しければいいってもんでもない。 なんにも考えないで読めるような本しか読めないでは読書とは言えない。
Posted by