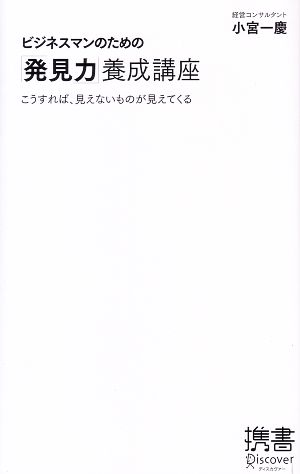ビジネスマンのための「発見力」養成講座 の商品レビュー
書籍整理中に発見したので再読。セブン-イレブンのロゴや時計描写テストを初めて読んだとき自分の「発見力」不足が炙り出されたようで強烈な印象が残っている。ただ本書を読み通すと、この話、著者のセミナーネタの掴みであることが良く分かる。筆者の「掴み」という関心がこのエピソードを手繰りよせ...
書籍整理中に発見したので再読。セブン-イレブンのロゴや時計描写テストを初めて読んだとき自分の「発見力」不足が炙り出されたようで強烈な印象が残っている。ただ本書を読み通すと、この話、著者のセミナーネタの掴みであることが良く分かる。筆者の「掴み」という関心がこのエピソードを手繰りよせたのだろう。 「発見力」を養うために仮説を持て、というのはまさにその通りなのだが、よくも悪くもセミナー形式のやや散漫な浅い内容となってる感は否めない。10年前読んだときは目から鱗のエピソード満載に感じたが、冷静に分析できるようになったのは本書の効果と時の経過からであろうか。
Posted by
よくアンテナを張れ!と言ったり、言われたりするけど、その張り方がよくわからない。 だから、それこそ、いわゆる”アンテナ”に何も引っ掛からない。 そのアンテナの張り方、発見力をを高めてくれるヒントをくれるのがこの本書。 関心を広げるところから始めてみる。
Posted by
小宮氏の養成講座シリーズ。 毎度、似たり寄ったりな内容ではあるが、基本の確認って大事ね。 あらゆる物事に興味を持つ、疑問に思う、そして検証すること。そして、継続。 広がる視野。 字面にすると簡単だが、中々、習慣化させるってのが、凡人には難しい。 初心にかえり、素直にまいり...
小宮氏の養成講座シリーズ。 毎度、似たり寄ったりな内容ではあるが、基本の確認って大事ね。 あらゆる物事に興味を持つ、疑問に思う、そして検証すること。そして、継続。 広がる視野。 字面にすると簡単だが、中々、習慣化させるってのが、凡人には難しい。 初心にかえり、素直にまいりましょう。
Posted by
2017年最初の一冊。 要は何事も関心をもって接していないと気付かないよ。と言うこと。字が大きく、読みやすいが情報量は少なめ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
何万回見ても見えないものは見えない (セブンイレブンの最後が小文字とかね) 関心を持てばものは見える。仮説を立てると完全に見える。 1秒だけ財務諸表をみるなら、「流動負債が流動資産より多いか少ないか」 (流動資産とは1年以内に使うか現金化できるもの) ものが見えるようになる10のヒント 1.先に要点を知る。 2.ヒントを先に得る。 3.分解する 4.情報を減らす 5.気づいたことをすぐにメモ 6.比較する 7.一部を取り替える 8.視点を変える 9.複数で話す 10.素直になる
Posted by
セブンイレブンやローソンのロゴ、毎日見ているのに正確に思い出せないことか、普段見えていないことを実感した。発見力を付けて自分自身のプラスにしたいと思う。
Posted by
良書、ビジネスにおける課題発見力を養うための本。観察することの重要性とそのやり方を例示してくれる。当然そこからどのように解決するかは自分しだいですが、答えのない仕事をやってる人にはうってつけの本ではないでしょうか
Posted by
普通だなー。著者が気が付いた「発見力」を書いているのだが、まとまりがない。 もうすこし「これと、これと、この発見力はまとめるとつまりこうゆうことである」といったまとめが欲しいところ。 以上
Posted by
本書の内容はコンパクトにまとめられるとはいえ、内容に目新しさはなく、一般的に言われる知的創造ステップに通ずる。 本書の中で説明されている何かしらの"発見"にいたるメカニズムをシンプルにすると ①物事に関心を持つ ②過去に頭にストックしておいた情報と関連付...
本書の内容はコンパクトにまとめられるとはいえ、内容に目新しさはなく、一般的に言われる知的創造ステップに通ずる。 本書の中で説明されている何かしらの"発見"にいたるメカニズムをシンプルにすると ①物事に関心を持つ ②過去に頭にストックしておいた情報と関連付ける ③仮説を立てる ④検証する というステップであり、要は、新しく仕入れた情報と過去にストックしておいた情報を材料に頭の中でピラミッドストラクチャーを作る作業だと理解した。 新しい情報に過去に触れて頭にストックしておいた情報と紐付けるという流れはよく言われているひらめきを生むためのプロセスと同じで、本質的な部分は変わらない。 発見力(発想力)を鍛える上で特に重要なのは以下の2点だと考える。 1点目は関心の幅を広げることでキャッチした情報とリンクできる情報を増やすこと。 そのためには、ある程度受動的に情報をキャッチする必要があると感じた。能動的な情報取得ではテーマの幅がすでに関心のある分野に偏ってしまいがちであるため、何らかの形で自分以外の誰かが選んだ異分野の情報に定期的に触れる機会を増やす必要がある。 著者は新聞を網羅的に読むことを薦めているが、他にも例えば雑誌の定期購読など、特定の情報ソースを自分なりに選定してそのソースで取り上げられた情報は関心の有り無しに関わらず、情報化する習慣をつけておくことなどが有効だと思う。 2点目は頭の中にストックしてある情報の整理しておくこと。 本書内では特にその部分について触れられていないが、例えば、内田和成氏著『スパークする思考』で推奨されているように、頭の中の情報に"タグ"づけをしておく。そのように整理しておかないと新しい情報とストックされてある情報との関連付けがスムーズに行えない。 「多様な情報に触れること」「情報を整理して頭にストックしておくこと」この2点がすなわち"発見力"の素養になると考える。
Posted by
小宮さんシリーズ2つ目 ・発見には関心が必要➡仮説➡検証 仮説を立てる時は「分解(減らす)」「全体(拡大する)」要素から洗う
Posted by