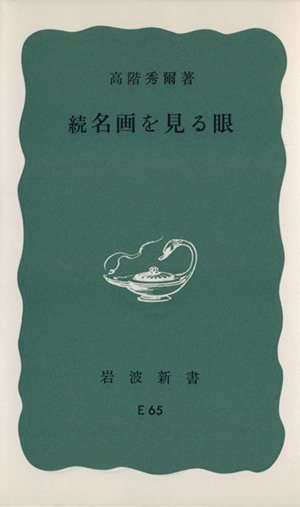続・名画を見る眼 の商品レビュー
モネ「パラソルをさす女」、ムンク「叫び」、モンドリアン「ブロードウェイ・ブギウギ」などの名画14枚を解説した本。印象派からキュビズム、抽象画にいたるまでの作品が取り上げられている。 一見してわかりにくい作品が多いけれど、だからこそ知識を持って見ると、見方が変わって面白いと思った。
Posted by
続編。モネ からモンドリアンまでの14作品。前編同様に非常に読み易い文章。後半はキュビスム(立体派)から抽象主義の画家が中心になる。現代絵画において抽象画は一つの主流であるがどうも理解し難い部分がある、ピカソは好きだが。本書を読んで少し抽象主義への流れが理解できた気がする。少し絵...
続編。モネ からモンドリアンまでの14作品。前編同様に非常に読み易い文章。後半はキュビスム(立体派)から抽象主義の画家が中心になる。現代絵画において抽象画は一つの主流であるがどうも理解し難い部分がある、ピカソは好きだが。本書を読んで少し抽象主義への流れが理解できた気がする。少し絵画を見る目が変わればいいなと思った。
Posted by
私は絵を観るのが好きでよく美術館に出かけるのですが、正直言えば、絵の良さが本当にわかっているわけではありません。単に自分が好きな、あるいは自分好みの絵を見つけて、何となく満足した気分になって美術館をあとにする、という程度です。だから、美術館に滞在している時間も、かなり短い方だと...
私は絵を観るのが好きでよく美術館に出かけるのですが、正直言えば、絵の良さが本当にわかっているわけではありません。単に自分が好きな、あるいは自分好みの絵を見つけて、何となく満足した気分になって美術館をあとにする、という程度です。だから、美術館に滞在している時間も、かなり短い方だと思います。極端なことを言えば、好みの絵が見つからなければ、あっという間に通り過ぎて終わり、ということもあるくらいですから。 そんな私でもこの本はとても読みやすくて、名画の世界にすんなり入っていくことができました。内容ももちろん素晴らしいのですが、何より筆者の語り口がとても自然で、1971年といささか古い本ですが、全く古くささを感じさせません。「本当に頭がいい人とは、難しいことを易しく説明できる人だ」とよく言いますが、本当に名画のことがわかっている人だからこそ、その絵の良さをやさしく説明することができるのだと思いました。 名画はもちろん、例えば印象派とか、キュービズムとか、そうした当時の人たちの絵に対する考え方も、実にわかりやすく説明されています。素人の私には、写実的な絵の素晴らしさはわかっても、抽象的なものはどうしてもピンとこないものが多いのですが、この本を読むことで視点ができ、ずいぶんと解決するように思います。 p.130に、ムンクの言葉が紹介されています。「芸術は自然の対立物である。芸術作品は、人間の内部からのみ生まれるものであって、それはとりもなおさず、人間の神経、心臓、頭脳、眼を通して現われて来た形象にほかならない。芸術とは、結晶への人間の衝動なのである。」とても重い言葉ですが、これぐらいの心持ちで、これからは絵画に接したいと思います。 なお、続編から読んでしまったので、2年前に出ている『名画を見る眼』も読んでみようと思います。
Posted by
テンポ良く画家一人一人を解説しながら大局的に絵画の歴史を辿る。作品だけでなく、各章の末尾に画家のバックグラウンドも解説され、人間味も同時に感じさせてくれる構成は嬉しい。 いやぁ、うっとりするまでに著者の言葉遣いが繊細。 141pは鳥肌。
Posted by
前編よりも個人的には親しみがある印象派から抽象画がテーマになっていておもしろい。 しかし古い本なので仕方ないとは言え、挿し絵の不明瞭さや白黒がどうしても気になってしまった。
Posted by
美術はそれ自体で心惹かれるものであるが、そこにはやはり、ひとの精神が息づいてゐる。 長い時間の中で、ひとは見えたもの感じたものをどのやうにつくり上げていくか、挑み続けた。写真の代わりとしての意味合いがあつた時代もあれば、力の象徴としてブランド品として愛でられたこともあつた。それで...
美術はそれ自体で心惹かれるものであるが、そこにはやはり、ひとの精神が息づいてゐる。 長い時間の中で、ひとは見えたもの感じたものをどのやうにつくり上げていくか、挑み続けた。写真の代わりとしての意味合いがあつた時代もあれば、力の象徴としてブランド品として愛でられたこともあつた。それでも、ここに取り上げられた画家たちはただ自らの内で叫び続ける何かを描く、それを成し遂げた。それが彼らの人生であつた。取り上げられた作品は、さうした闘ひの中でのひとつの道しるべだ。 絵を眺める。すると、ああきれいだなとか、これはなんだらうだつたり、かう見えたのだろうかだつたり、どうしてわざわざかう描かないとだつたのだらうかなど様々な印象が過ぎていく。さうした印象が絵のどういつたところから生じるのか、見つめなおす。 それはたとえば幾何学的な構図や錯視の利用、どのやうな色調かといつた描き方の観点や、そこに何が描かれてゐるのかといつた図像学的な観点、どのような社会状況や人生であつたのかといふ歴史的な観点を重ね合わせる。 絵をみてきた彼にとつては、絵を分析すること以上に、そこに描いたひとをみてゐるのだと感じられる。さうした表現に行き着き、現せるといふことが、絵画の天才が天才である所以ではないか。ピカソの絵に対して、こんなの小学生でも描けるといふが、それを他でもない描き、意図的にやつてのけるからこそ、ピカソがピカソたるものなのだ。 名画を見る眼とは、解釈の仕方ではなく、名画に出会ひ、その奥で描いたひとと出会ふことだ。確かに抽象絵画など絵の前に立つて眺めた時、これは一体なんだ、と強烈な不可解さに落とされる。しかし、そのやうに感じられる心は時代を超えていつも連続してゐる。それなら、それからわからないと目を背け、拒絶をする前に、わかるだけの努力をしなければならない。絵の社会的な意味合いが過去のものとは変はつてきてゐる以上、絵画に対する人間的な理解とその努力が絵画を目の前にした自分自身に求められてゐる。
Posted by
やはり前作より落ちるかな、続編の定めか。 指摘のとおり印象派から100年程度の間の変化はそれまでの比ではない、その理由は画家が頭で考えに考えたゆえということが暗に仄めかされている。 でもやはり考え過ぎの嫌いがあるように思うのだが、近代の画は。頭でっかちと申しましょうかね。
Posted by
前作同様こちらも読みやすくて面白かった。ピカソのアヴィニョンの娘たち、モンドリアンのブロードウェイブギウギなど、全然分からないと思っていた作品も分かったような気がした。もっと続きが読みたい。シリーズで10巻ぐらい出てたら良いのに。
Posted by
学生の時の授業で使用した本。 再読。 永久不滅の名盤です。 ますますニューヨークMoMAへ行きたくなった!
Posted by
続編ですが、この前のものは読んでいません。 印象派以降の名画14点をピックアップし、それぞれを解説。 表現・技法・画家の一生など。 作品がどれも白黒画像なのが残念。 やや古い本ですが解説は解りやすかったです。
Posted by
- 1
- 2