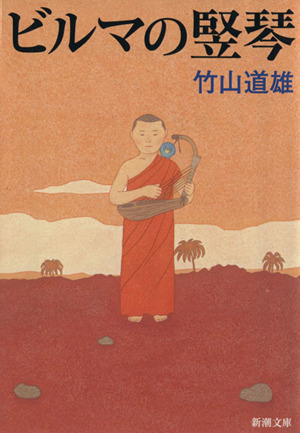ビルマの竪琴 の商品レビュー
戦争に命を奪われ、生きた証を残すことの叶わなかった人たちがいる。 骨となり異国に戻ることのできない人たちがいる。 レクイエムは、生きていくものたちのための救いでもある。 発表当時は「児童向け」として書かれた作品ですが、小学校高学年でもこのままは読みづらいかもしれません。中学...
戦争に命を奪われ、生きた証を残すことの叶わなかった人たちがいる。 骨となり異国に戻ることのできない人たちがいる。 レクイエムは、生きていくものたちのための救いでもある。 発表当時は「児童向け」として書かれた作品ですが、小学校高学年でもこのままは読みづらいかもしれません。中学生におすすめ。
Posted by
南方から帰ってきた傷痍軍人で溢れ、焼け野原が残るーそんな時代にこの本は書かれた。 当時の日本は、復興という明るい使命感に燃えるものの、戦中から一転、戦争を絶対悪と見なし、戦争に対して、また戦争に関わったものたちに対して、冷静な分析をするものがいなかった。亡き者たちを英霊などと言っ...
南方から帰ってきた傷痍軍人で溢れ、焼け野原が残るーそんな時代にこの本は書かれた。 当時の日本は、復興という明るい使命感に燃えるものの、戦中から一転、戦争を絶対悪と見なし、戦争に対して、また戦争に関わったものたちに対して、冷静な分析をするものがいなかった。亡き者たちを英霊などと言って語っては、戦争賛美になってしまう。多くの人が死にすぎたからこそ、戦争の惨状を過去の遺物として、なきものとして、葬ることを選んだーーー しかしそんな中、竹山氏は「鎮魂」というテーマで、あえて児童書という形を取って書き上げた。おそらく、この本に救われた元軍人や残された家族は多かったのではないだろうか。遺骨も見ることなく、遠い異国で家族や友人は死んだと言われた人々の悲痛な叫びは、水島一等兵が語ってくれている。 この本の舞台、ビルマ(現ミャンマー)側からの戦争の追憶も読まねばならないとも思う。戦争に巻き込まれ、多くの犠牲を出した国は日本だけではない。インパール作戦で巻き込まれた人々の数は知れない... 戦争の追憶を忘れずに、霊に敬意を払う。それは新たな戦争のためではなく、今後こんな悲惨なことがないように祈るため。文学人であり、批評家でもあり、また戦後各方面の人間(東京裁判のレーリング判事なども!)との交流のあった竹山氏の書を読んで、改めてそう思わされた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
アジア・太平洋戦争中、日本はビルマ(今のミャンマー)にも軍隊を送り込んでいました。この小説に出てくる部隊は、戦争が終わってイギリス軍の捕虜になってしまいます。しかし、まだイギリス軍に降伏せず、死ぬまで闘うと言って抵抗している部隊があると聞き、隊長は竪琴の上手な水島という兵士を説得に向かわせます。しかし、部隊は全滅。水島も帰って来ません。しばらく後で彼らはその水島にそっくりな顔をしたビルマ人のお坊さんとすれ違います。はたして彼は水島なのかどうか。彼だったら一緒に日本に帰ろうと願うのですが・・・。戦争で死んだ人をどのように弔うのかという、現代のものでもある大きな問題について問いかけてくる作品です。
Posted by
児童文学ということもあって、文章は平易で、難しい語彙にはルビがあったり説明があったりするので読みやすい。 戦争とはどういうものなのか、戦で死んでいくというのはどういうことなのかを垣間見ることができ、襟を正したくなる。 ミャンマーも行ってみたい
Posted by
『ビルマの竪琴』は「1946年(※昭和21年)の夏から書き始め童話雑誌『赤とんぼ』に1947年3月から1948年2月まで掲載された」(Wikipedia)。一高(東大の前身)の教師だった竹山は従軍していない。そのため現地などの情報に多くの誤りがあることを詫(わ)びている。 htt...
『ビルマの竪琴』は「1946年(※昭和21年)の夏から書き始め童話雑誌『赤とんぼ』に1947年3月から1948年2月まで掲載された」(Wikipedia)。一高(東大の前身)の教師だった竹山は従軍していない。そのため現地などの情報に多くの誤りがあることを詫(わ)びている。 https://sessendo.blogspot.com/2018/06/blog-post_2.html
Posted by
子ども向けに書かれた小説、とのことで、やさしい言葉で書かれているが内容はとても深く難しい。若いときに一度は軍に入隊しなくてはならない当時の日本と、僧として修行しなくてはならないビルマ(ミャンマー)。どちらがすぐれているか。どちらが良いのか。どちらが豊かか。幸せとは、豊かさとは何か...
子ども向けに書かれた小説、とのことで、やさしい言葉で書かれているが内容はとても深く難しい。若いときに一度は軍に入隊しなくてはならない当時の日本と、僧として修行しなくてはならないビルマ(ミャンマー)。どちらがすぐれているか。どちらが良いのか。どちらが豊かか。幸せとは、豊かさとは何か、深く深く 考えさせられる。
Posted by
軍人と僧侶、文明国日本と未開のビルマ。この対比により、人間としてどうなることが幸せなのか、何が世の中を幸せに導くのかを、ビルマで終戦を迎えた日本兵が考える。 ビルマが未開か、(戦争をしている)日本が野蛮か。 文明の利器を持っていても、肝心のそれを使う人間の心が野蛮ではないのか。 ...
軍人と僧侶、文明国日本と未開のビルマ。この対比により、人間としてどうなることが幸せなのか、何が世の中を幸せに導くのかを、ビルマで終戦を迎えた日本兵が考える。 ビルマが未開か、(戦争をしている)日本が野蛮か。 文明の利器を持っていても、肝心のそれを使う人間の心が野蛮ではないのか。 あとがきに、戦中の葬儀の話が書かれているが、この頃、南方で亡くなった隊員の葬儀には遺骨も遺髪も何もないこともあったようだ。こういった事実を読むと、水島が僧となり、日本にも帰れず、供養もされず異国の地に埋まっている日本兵を供養してまわらなければと決心したこともうなづける気がする。
Posted by
「おーい、水島。一しょにかえろう!」 終戦後のビルマを舞台にした児童文学。戦闘態勢だった英国人と、歌を通して和解し、ともに合唱する場面がとても感慨深かった。ビルマの山奥で、極限状態のなか、敵陣地から耳慣れた曲が聞こえてきたときの心情とはどうゆうものなのだろう。読み終わってすぐ「...
「おーい、水島。一しょにかえろう!」 終戦後のビルマを舞台にした児童文学。戦闘態勢だった英国人と、歌を通して和解し、ともに合唱する場面がとても感慨深かった。ビルマの山奥で、極限状態のなか、敵陣地から耳慣れた曲が聞こえてきたときの心情とはどうゆうものなのだろう。読み終わってすぐ「はにゅうの宿(Home sweet home)」「庭の千草(The last rose of summer)」を聞いたが、素敵な曲だった。また本作は作者の想像で書かれたものだというのも驚きだった。作者いわく、戦争食後は戦時中の情報を得ることは厳しく、内情を知る手掛かりは人づてに聞くしかなかったそうだ。史実と異なる場所もあるかもしれないが、かつて映画化もされた作品で、心温まる作品であると思う。
Posted by
え、これ児童文学なのか。渋いな。昔の児童。戦争だろうと、敗戦だろうと、歌を歌えばなんとかなる。そう、ディズニーならね。
Posted by
初めて読んだのは、中学の頃。以来、何度か読み返して、手元にあるのは2冊目。 何度読んでも、涙が出そうになる。水島は、どうして日本へ帰らなかったのか。
Posted by