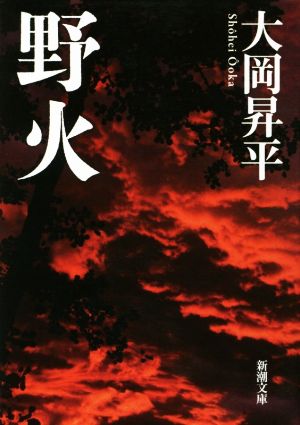野火 の商品レビュー
戦記文学として、きちんと読んだの初めてか。戦艦大和の最期とはまた違った壮絶な戦いが見えた。 今の時代も形を変えてあるのかもしれない
Posted by
たまに無性に文学が読みたくなる。現代の受賞作を漁るのも良いけどやっぱり名作を読みたいなと思う。そこでNHKの「100分de名著」のアーカイブから見つけ出したのが、大岡昇平の「野火」。 1944年、既に戦争の主導権を失ってしまっていた日本。「決戦」などと謳いながら無謀な抵抗を続け...
たまに無性に文学が読みたくなる。現代の受賞作を漁るのも良いけどやっぱり名作を読みたいなと思う。そこでNHKの「100分de名著」のアーカイブから見つけ出したのが、大岡昇平の「野火」。 1944年、既に戦争の主導権を失ってしまっていた日本。「決戦」などと謳いながら無謀な抵抗を続け、最後の1年間だけでおそらく200万人以上が死んでいる。その中でも数万数十万人の死者を生み出した、フィリピン、ビルマ、長崎広島、大都市空襲といった現場を舞台に数々の戦争文学が紡がれてきた。そして、フィリピンやニューギニアを採り上げるとカニバリズムが絡んでくる。これまでの自分は無意識にそのテーマを避けてきたのかもしれない。しかし、NHKの番組で紹介された冒頭部分の描写の美しさに惹かれて読むことにした。 物語は肺を病んだ田村一等兵が所属する中隊を追われるところから始まる。上官は偉そうな訓戒を垂れるが、既に米軍はレイテ島上陸に成功し、大勢は決している。彼らの中隊も現地農民から徴発した芋を大事に抱えて敗走の途上にある。 中隊からも野戦病院からも追われた田村が得たのは、自由。30過ぎの補充兵としてこの地に送られた田村は、軍隊慣れした兵士達とは異なり、フィリピンの美しい景色を眺めながら思索を巡らせることができる。そんな自由で孤独なはずの彼に付きまとうのが、野火。 農民の野焼きか、それともゲリラの合図か。米軍が迫撃砲や戦闘機の機銃による攻撃しかしてこない段階だから彼には逃げる自由が与えられているのだけど、野火は大事な場面で彼の心象に現れる。おそらく、彼は「見られている」のである。 彼は罪を犯しながらも、その許しの象徴なのか芋と塩を得る。しかしそれらも尽きると、彼に本当の試練が訪れる。瀕死の将校は彼に、俺が死んだら食べてもよいという。しかしその死後、剣を握った彼の右手を左手が掴んで止める。「汝右手のなすことを左手をして知らしめよ」、つまり内なる他人から見て恥ずかしくない行為をせよという聖書の一節から得られたこのシーン、やはり彼は「見られて」いて、ここではギリギリ踏み止まるのだが、やがて「サルを狩る」という同僚と再会し、そこから、彼の精神つまり彼の中に響く神の怒りは、限界を超えていく。 文庫本で200ページ程度の中編小説だが、その文学的価値は高い。21世紀になっても映画化(2回目)されたということは、この本を読んで心に何かを刻んだ人が多いということだ。字句の一つ一つを丹念に読ませるような、私小説を超えた「文学」はなかなか日本には少ないけれども、この歳になって文学に出会えたことに感謝し、時が来たらまた読み返してみたい。
Posted by
戦争は絶対に行ってはいけないと改めて実感する。敗勢が決定的になったフィリピンレイテ島でのあてのない彷徨、孤独、殺人、人肉食・・。平和な時代に生きていることに感謝しつつ、これを未来につなげなくてはいけないと切に思う。
Posted by
戦記ものには共通して言えることだが、心が奮い立つような展開などない。 ただ極限状態の本能が剥き出しにさらけ出されるのみである。
Posted by
■極限下の敗残兵の行為に、すべてをそぎ落とした人間の真の姿を見る■ 著者は自身、終戦前のフィリピンを体験している。著者の体験記、ノンフィクションかと思わせるほど真に迫る生々しい描写。感情を抑え、醒めた視点で淡々と描写されるグロテスクな映像からは臭気すら漂ってきて僕の食欲を奪う。...
■極限下の敗残兵の行為に、すべてをそぎ落とした人間の真の姿を見る■ 著者は自身、終戦前のフィリピンを体験している。著者の体験記、ノンフィクションかと思わせるほど真に迫る生々しい描写。感情を抑え、醒めた視点で淡々と描写されるグロテスクな映像からは臭気すら漂ってきて僕の食欲を奪う。 小説自体は短いが、文体や用語が固く決して読みやすくはない。それでも僕はいつしか弾薬も食料も希望もなく、見捨てられた敗残兵としてレイテ島の野山をさまよっており、後半は一気に読み進めてしまった。 ある者は最前線での行軍や惨めな敗走を強いられ霧散し、ある者は師団や隊からお荷物として捨てられ、病院でも受け入れてもらえず。生きる希望も死にたいという欲望もなく、ただ死が迎えに来るまで惰性で、あるいは本能で生を続ける。そのために人間はどこまで人間らしさから遠のくことができるのだろう。 現代日本で衣食住に何不自由なく暮らす僕には、この地獄を生き抜いた人間の心情を真に理解することはもちろん、行為の善悪を説く資格などあろうはずがない。 裸の人間の生命力、崇高さ、残忍さがごちゃ混ぜになって、ただただ強く印象に残る。
Posted by
屍体や情景の独特な書き方。ページ数は少ないが読了するのに時間がかかった。時代背景から見た主人公が抱える生命への葛藤を感じた。
Posted by
大岡昇平 著「野火」、1954.4発行。著者はよく知ってる名前、薄い文庫本なのですぐ読めると思いましたが・・・。209頁の本、54頁位でなかなか先に進めず。普段は先に見ない解説(吉田健一氏の解説)を読んだら、なおさらこの本がわけがわからなくなり、無理をしてまで読むことを止めまし...
大岡昇平 著「野火」、1954.4発行。著者はよく知ってる名前、薄い文庫本なのですぐ読めると思いましたが・・・。209頁の本、54頁位でなかなか先に進めず。普段は先に見ない解説(吉田健一氏の解説)を読んだら、なおさらこの本がわけがわからなくなり、無理をしてまで読むことを止めました。フィリピン戦線での飢えのなかで、人肉を食べるかどうかなどがテーマのような気もしますが・・・。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
太平洋戦争の末期、比国レイテ島に召集された田村一等兵。主要基地を奪取された日本軍の歩兵団は死を覚悟していた。田村は結核を発症し、病院に行くが治療が終了したとのことで隊に戻される。隊長より、「使えない者は死ね」との命令、隊を離れ空腹とともに彷徨う。転がる死体、自分の血を吸うヒルを食し、同僚との諍いにより射殺するなど、レイテ島での狂気を記した。死臭、泥、蠅、死体の体液、屍を常に目にし、いつこの状況が終わるのか分からない。過去読んだ戦争小説は、一瞬でも戦争を美化していなかったか?戦地で亡くなった方々へ、合掌。
Posted by
夏に映画を再見したことがきっかけで手に取った。戦時下の過酷な経験を回想する中で綴られるフィリピンの自然の雄大さと、そこで右往左往して殺し殺される兵士たちの行為の愚かさの対比、飢えと銃撃が激しくなるにつれて失われていく人間性、その他挙げるときりがないが、やはり戦争など起こしてはいけ...
夏に映画を再見したことがきっかけで手に取った。戦時下の過酷な経験を回想する中で綴られるフィリピンの自然の雄大さと、そこで右往左往して殺し殺される兵士たちの行為の愚かさの対比、飢えと銃撃が激しくなるにつれて失われていく人間性、その他挙げるときりがないが、やはり戦争など起こしてはいけないし、そういう状況に現在向かってきているのを感じるからこそ、ちゃんと読んでおいてよかった。
Posted by
著者自身の戦争体験を綴った一冊。壮絶な戦争の一面を現代に残す貴重な記録だと思う。己の命を繋ぐために自身の血を吸ったヒルの血を吸い、乾いた人肉を食べざるを得なかった極限とは。戦争の悲劇のある一面の記録である。
Posted by