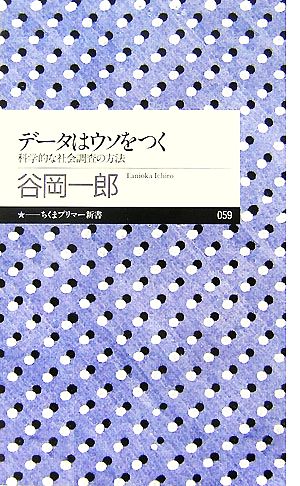データはウソをつく の商品レビュー
調査結果を視覚化する際に、調査者の求める結果ありきで行われる事がある。注意深く検証しないと、簡単に騙される事となる。
Posted by
社会科学の分野は蓋然性の世界であり、自然科学のように白か黒かははっきりせず、すべてが灰色の世界だという。 著者が「図やグラフを見たらアラ探しをしなさい」と言うように懐疑主義的な見方を常に意識しておく必要がある。例によって文章は読みやすく、ところどころに挿入されている四コマ漫画も著...
社会科学の分野は蓋然性の世界であり、自然科学のように白か黒かははっきりせず、すべてが灰色の世界だという。 著者が「図やグラフを見たらアラ探しをしなさい」と言うように懐疑主義的な見方を常に意識しておく必要がある。例によって文章は読みやすく、ところどころに挿入されている四コマ漫画も著者の主張を補強するようで、効果的
Posted by
社会学の専門でない人にも、分かりやすくデータの落とし穴を解説しています。新聞などのデータに紛らわされないためにも、ぜひ読んで下さい。
Posted by
いしいひさいちさんの漫画がいいアクセントとして効いてます。 この本の趣旨としては、自分の頭で考えないと人に動かされる立場になるよということです。
Posted by
いい本がよく売れるとは限らない、その典型。 第一章 社会科学における「事実」認定プロセス 第二章 マスコミはいかに事実をねじ曲げるのか 第三章 実際にデータを分析してみよう 第四章 質問票作りのむつかしさ 第五章 リサーチ・リテラシーとセレンディピティ メディアがいかに世論...
いい本がよく売れるとは限らない、その典型。 第一章 社会科学における「事実」認定プロセス 第二章 マスコミはいかに事実をねじ曲げるのか 第三章 実際にデータを分析してみよう 第四章 質問票作りのむつかしさ 第五章 リサーチ・リテラシーとセレンディピティ メディアがいかに世論をもっともらしいデータで誘導しているのか、またそんなデータに騙されないためにはどうすればよいのか、の二点がこの本を大枠。ただ、筆者自身も主観性が入りすぎている感が否めない。「嫌い」と「悪い」は分けて考えるべきかと。 P.21 宝くじ売り場でよく見かける(中略)という類の看板… このフレーズはいかに日本人がオカルトじみた国民性か、ということを述べている章に出てくる。宝くじ売り場の看板は誰もが一度は目にするし、「ここで○等○円が出ました」というのを売りにしている。個人的にはこういう看板にはいわゆる「景表法」のような法的な規制が働かないのか、と疑問に思った。もうひとつ。よく当たるという文句のもとで購入して外れても、ほとんど問題になってないのが宝くじのいやらしいところ−所詮宝くじですからという逃げ口−だな、と思った。 第二章では、マスコミの世論誘導に終始しているが、その軸となるが「主観性」である。筆者は、この章でマスコミによる情報を「マスコミがタレ流すゴミ」と表現している。いちいち共感させられる部分が多かった。 第三章、第四章は、特に統計とかグラクを用いて論文を書く大学生とか読むべきところ。証明ではなく、ただのこじつけになりがちなデータの使い方がよくわかる。 第五章こそ、この本の要所。ここだけでも読むべき。「教養」「リサーチ・リテラシー」「セレンディピティ」の3つをゴミと情報を見分ける前提としている。どれも思考に絡むもので身に着け方が難しいが、筆者はその根本には「学ぶ楽しさ」があると説いている。 最後に学問に向いていない人として、「非科学的な大前提を持つ人」「スポンサーの顔色を見る人々」「人間関係に埋もれる人」を挙げており、筆者も書いているが日本人に学問に向いていない人が多い。ここで「最近の学力低下や経済成長の低迷はそのせいだ」と書いたらマスコミと一緒なので、そういうことは書かないが、未だに日本人は集団志向が多いのかと思わされる。 これだけマスコミ批判してたら、口コミからしか売れない本だと思った。
Posted by
メディアリテラシーの入門書としては最適なのです。いしいひさいちの4コマ漫画も良いアクセントになっています。
Posted by
2007/07 図書館から借りて読んだ。人をばかにした本になっている。まえがきで編集が言う「『社会調査』のウソ」ではウソデータの見抜き方をやったのはわかった、では今度はまっとうな「つくりかた」を、というコンセプトがちっとも貫かれておらず、ぐだぐだ。何が言いたいのかわからない。文章...
2007/07 図書館から借りて読んだ。人をばかにした本になっている。まえがきで編集が言う「『社会調査』のウソ」ではウソデータの見抜き方をやったのはわかった、では今度はまっとうな「つくりかた」を、というコンセプトがちっとも貫かれておらず、ぐだぐだ。何が言いたいのかわからない。文章の構成としてだめだ。最後まで読んで、図書館で「児童」のコーナーに刺さっていたわけがわかったのだけれど、奥付に「ちくまプリマー新書刊行にあたって」みたいな文もないし、唐突でなにごとかと思った。筑摩、しっかりして。PR誌「ちくま」6月号でパオロ・マッツァリーノが、本書の発売後に「ネットや雑誌・新聞に『データを疑う眼が大切だと、本書は教えてくれる』みたいな書評がたくさん載るはずです」と書き、その態度すら鵜呑みであると疑義を申し立てる。 もしや谷岡一郎も、他人の分析をただすのは得意でも、自分でつくるのは苦手なのでは?と思うと、上記書評は先輩に対する皮肉でもあり、苦労をねぎらう言葉でもあり、単なるヨイショではないだろうなとみている。 いしいひさいちのマンガを引用して、寸評を加えているところだけ立ち読みしたらいいと思う。
Posted by
前著を受けて、今度は具体的に方法を、ということで本書が位置づけられているそうです。とは言え、前半部分では、こんなデータ操作で困ったことになる、という実例を豊富に紹介していて、分かりやすく方法論に入っていける。
Posted by
かのダレル・ハフの名作「統計でウソをつく法」を彷彿とさせる(実際、本文中で引用されていましたが)、データから恣意的な結論を引き出すトリックの基本が学べます。後半は実践的な内容なので、どちらかと言えば学生さん向きですが、前半だけでも価値はありますよ!
Posted by
重要な情報を多数扱い、真実もしくは偽証を見つけていく仕事柄、常に目の前のデータと睨めっこ。本当なのか、嘘なのか。もし本当なら、それを裏付ける証拠はどこにあるか。もし嘘なら、嘘と証明できる情報はどこに隠されているか。 しかも、推理小説のように好きな時に好きなところで謎を解き明かすの...
重要な情報を多数扱い、真実もしくは偽証を見つけていく仕事柄、常に目の前のデータと睨めっこ。本当なのか、嘘なのか。もし本当なら、それを裏付ける証拠はどこにあるか。もし嘘なら、嘘と証明できる情報はどこに隠されているか。 しかも、推理小説のように好きな時に好きなところで謎を解き明かすのではなく、あくまで仕事ですから、限られた時間内に、少なくとも顧客の望む情報を見出さなくてはならない。そんな日々が続く中で、今最も欲しているスキルが、瞬時に且つ的確な判断を下せる能力と、あらゆる視点で可能性を見出しながらも、必要な情報を絞り込む能力です。 社会人になって早数年。それなりの能力は身についているとは思いますが、まだまだ未熟なところが多々あります。 『ウソをつく』という突拍子な表題に惹かれたこともさることながら、自分の欲する能力を、もっと大きく、もっと磨きをかけるために読んだ本です。要約すれば、「提示された情報を鵜呑みにするな。あらゆる可能性を考え、あらゆる視点から見据え、真実を探り出せ」ですが、具体的な事例を提示しつつ、分かりやすく面白おかしく述べられています。 ここでいう『ウソ』とは、あくまで「データがついている」のではなく、「人間がデータにつかせている」というのが正しいでしょう。特に社会というのは人間によて作り出しているため、そこで形成される情報もまた、人間によって操作されている。得てして人間は自己顕示欲が強い動物ですし、都合の悪い部分は目を合わせない性質があります。そこに一石を投じ、「では〜〜とは考えられないか」「〜〜という可能性はないのか」というのが、今後あらゆる事象の真実を見抜く上で必要になっていくのでしょう。 それにしても。 最近は、テレビといいニュースといい、「このデータは真実に則っている」と思わせることが巧みですね。独創的なものだと比較材料は乏しいし、これだけ情報が溢れている現在だから、メジャーなデータであれば無数の比較材料が存在する。 それでも、その中から重要なものを、正確なものを見つけ出すにはどうすればいいか。そえは、常日頃からの『思考力』の鍛錬。やはり何事も、基礎の積み重ねが一番なんですね。
Posted by