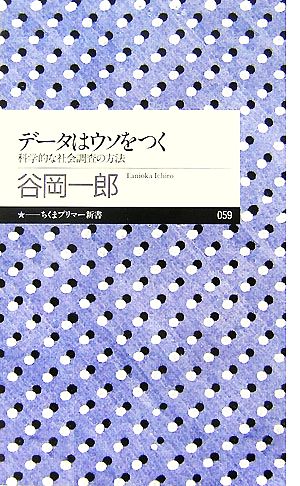データはウソをつく の商品レビュー
同じ著者の別の図書と関連のある内容だったそうなのだけれども、そちらは恐らく未読。マスコミなどの調査結果の報道のウソを見抜く方法から、社会調査のデータ分析の方法(ざっくり)まで。 クリティカルシンキングという考え方(でいいのか?)があるけれども、世論調査などの量的調査に対しても、基...
同じ著者の別の図書と関連のある内容だったそうなのだけれども、そちらは恐らく未読。マスコミなどの調査結果の報道のウソを見抜く方法から、社会調査のデータ分析の方法(ざっくり)まで。 クリティカルシンキングという考え方(でいいのか?)があるけれども、世論調査などの量的調査に対しても、基本的にはその姿勢で対した方がいいよ、という話。量的調査の結果は、自分の見たい/見せたい結果を出すために加工できてしまうものなので、提示された結果を鵜呑みにせず、疑いの眼差しで受け止めよう、と。鵜呑みにしないと言えば、たしか昨年末頃の週刊誌の新聞広告で「納豆を食べると死ぬ」という見出しがあり、かれこれ半年、うちの実家では延々とそれを弄ったネタが流行っている。 「こんな人にはこの本は向いていない」「こんな人は研究者には向いてない」で挙げられていた例に、クスリと笑ってしまった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
【概要】 第一章では社会科学においてどのように理論が構成され説明されるか、どのように事実として認定されるかを説明している。第二章ではマスコミが社会科学の「事実」を発表する際に如何に恣意的に結果を曲解するために表現を工夫しているかを説明している。第三章ではそのような社会科学アンケートの分析が恣意的に曲解できるか、また真面目に作成したとしても陥りやすいわなをせつめいしている。 【感想】 一回書いて消えてしまったので省略 【キーワード】 理論仮説検証のためのアプローチ方法 ○帰納法…現実で集められたデータを説明するために理論を構築する手法(データ→理論) ○演繹法…先に理論を構築し、それと現実に集められるデータを使用して証明する方法(理論→データ)
Posted by
「社会調査のウソ」ほどのインパクトはなかったな。 でも、マスコミを疑い自分で考えることは重要である。 考えることをめんどくさがらない。これがビジネス上必要不可欠である。
Posted by
カテゴリ:図書館企画展示 2015年度第1回図書館企画展示 「大学生に読んでほしい本」 第1弾! 本学教員から本学学生の皆さんに「ぜひ学生時代に読んでほしい!」という図書の推薦に係る展示です。 木下ひさし教授(教育学科)からのおすすめ図書を展示しました。 開催期間:...
カテゴリ:図書館企画展示 2015年度第1回図書館企画展示 「大学生に読んでほしい本」 第1弾! 本学教員から本学学生の皆さんに「ぜひ学生時代に読んでほしい!」という図書の推薦に係る展示です。 木下ひさし教授(教育学科)からのおすすめ図書を展示しました。 開催期間:2015年4月8日(水) ~ 2015年6月13日(土) 開催場所:図書館第1ゲート入口すぐ、雑誌閲覧室前の展示スペース ◎手軽に新書を読んでみよう 1938年に岩波新書が創刊されたのが新書の始まりです。 値段も分量も手ごろな新書は「軽く」見られがちなところもありますが、内容的に読み応えのあるものも多くあります。気に入った著者やテーマで探してみるとけっこう面白い本が見つかるものです。広い視野を持つために、興味や関心を広げるために新書の棚を眺めてみましょう。刊行中の新書を多様な角度から検索できるサイトもあります。(「新書マップ」) ◇新書で社会を読んでみる 本に書かれていること(情報)すべてを鵜呑みにすることはできません。しかし、情報を判断するための情報もまた必要です。多様なニュースソースから情報を得て、物の見方や考え方を養いマスコミに騙されないような自分をつくりたいものです。
Posted by
おすすめ資料 第98回 数字に潜むウソを見抜く(2009.10.9) 本書は、2000年に出版された『「社会調査」のウソ : リサーチ・リテラシーのすすめ』の続編です。 前作では、導き出したい結果が得られるように細工された調査の手法や、データを読み解く能力の不足、または予断を...
おすすめ資料 第98回 数字に潜むウソを見抜く(2009.10.9) 本書は、2000年に出版された『「社会調査」のウソ : リサーチ・リテラシーのすすめ』の続編です。 前作では、導き出したい結果が得られるように細工された調査の手法や、データを読み解く能力の不足、または予断を持ったために起こった分析ミスの実例など、調査に潜む様々なウソが暴かれました。 皆さんも既に、メディアなどで紹介されていることの全てが正しいとは限らないことをご存知だと思いますが、では、正しいプロセスで調査をするにはどうすればよいのでしょうか。 リサーチのプロセスの中でどのようにして誤りが生じているのかという実例紹介に力が注がれていた前作に比べ、本書では、実際の分析の手順と、各段階で気をつけるポイントの解説に頁が割かれています。 また、著者は大学で教鞭を執っていることもあり、内容は大学生を対象としたものが多くなっています。 研究に必要な能力として、社会調査のウソを見分ける能力である「リサーチ・リテラシー」が提唱されているのですが、本書を読めばその基礎的な力が身につくはずです。 さて、レポートで参照した調査結果、その数字は信頼に足るものでしたか?
Posted by
恐るべきフォースドチョイスの世界を説き、 それがいかに行われるか、正しいリサーチとは何かを説く。 著者にかかればいかなる統計も可能だそうである。
Posted by
良著。昔知人に頂いた積ん読本。新聞雑誌などの統計データの批判的読み方を、実例を交えて解説。全体的には社会調査技法の教科書になってる。挿絵の四コマ漫画やコラムも軽妙で面白い。
Posted by
2014/7/12 そりゃそうだと思うことばかり。それを知った上でってことがもう少しあるかなと期待してたけど...
Posted by
「事実」(ニュースや統計・アンケート等データで示されるもの)がどのように生まれるか、認定されるかについて書かれている。また、示されたニュースやデータに対して抱く印象・そこから生じる考えがいかに操作されているか(誤解しやすいか)についても述べられている。 本書の趣旨はもちろん、こ...
「事実」(ニュースや統計・アンケート等データで示されるもの)がどのように生まれるか、認定されるかについて書かれている。また、示されたニュースやデータに対して抱く印象・そこから生じる考えがいかに操作されているか(誤解しやすいか)についても述べられている。 本書の趣旨はもちろん、これらの情報操作に惑わされないように、という注意喚起にある。 マスコミの情報操作についての第二章とコラムが面白く読めた。参照されたし。 以下は特に興味深かった頁のメモ *** 私は夢を見ているのでしょうか 16頁 セレンディピティを磨くための考えるくせ 148頁 マニュアルを作る人、マニュアルに従う人 153頁
Posted by
統計資料、データ、数字、と言えば一見「科学的」、あるいは「実証的」と言えそうだが、データは採り方、見せ方で如何様にも変わるという危険性、そのデータの本質を見抜くことの重要さを説いた本。著者の主張が「いしいひさいち」という人の「ののちゃん」という四コマ漫画で端的に表されているとい...
統計資料、データ、数字、と言えば一見「科学的」、あるいは「実証的」と言えそうだが、データは採り方、見せ方で如何様にも変わるという危険性、そのデータの本質を見抜くことの重要さを説いた本。著者の主張が「いしいひさいち」という人の「ののちゃん」という四コマ漫画で端的に表されているというのが特徴的。 情報を使いこなす能力として、「教養」、事実や数字を正しく読むための「リサーチ・リテラシー」、ゴミの中から本物を嗅ぎわける「セレンディピティ」の3つ(p.143)が挙げられていたが、とても共感できる。サブタイトルは「社会調査の方法」となっており、データの採り方、解釈の仕方なども説明されているが、その根本として、学問をするということがどういうことなのかが書かれており、良い本だと思う。(2013/06/--)
Posted by