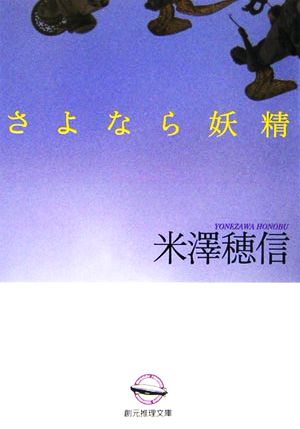さよなら妖精 の商品レビュー
遠い異国の地から日本にやってきた少女との偶然の出会い、共に過ごす二カ月間の思い出、帰国後にはじまる謎解き。 今の情勢にタイムリーな作品。いつ読むのかと問われたら、今読むべき作品だろう。 読んでるうちに結末が読めてしまった。ページが半分過ぎても物語の変調は見られず、日常描写がダ...
遠い異国の地から日本にやってきた少女との偶然の出会い、共に過ごす二カ月間の思い出、帰国後にはじまる謎解き。 今の情勢にタイムリーな作品。いつ読むのかと問われたら、今読むべき作品だろう。 読んでるうちに結末が読めてしまった。ページが半分過ぎても物語の変調は見られず、日常描写がダラダラ続く。大して盛り上がることはなく終わったなぁという印象。ミステリー要素はほぼないかと。 登場人物全員に全く魅力を感じられない。 登場人物は本当にみんな高校生?と思うくらい変に大人びてるわりに、ユーゴに行きたいという守屋には、(観光目的ではなく色々な思いがあることも理解しているけど)浅はかだし短絡的だと感じてしまった。 太刀洗万智の周りくどい感じも本当に苦手。 登場人物誰一人にも感情移入できず。 初米澤穂信作品だったが、この作品は私には合わなかった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
今の情勢と似ているところがあった。 「人間というものは、殺された父親のことは忘れても、奪われた財産のほうはいつまでも忘れない」 最後のオチに向けての物語だと感じた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
端々は好みで、楽しく読んだが、とりわけミステリとして若干の物足りなさを感じる作品だった。そして、仮にも西洋史を専攻しておきながら、現代東欧史への自分の理解の浅さを恥じながら読んだ。 それでも、はっとするモチーフは随所にある。マーヤがネーションを形成しようとしているのだ、という辺りが中心なんだけど、「伝統の創造」に言及があったりなど。「国家」という入れ物を満たす「国民」を創造することは難しい。共通項でくくろうとしてみても、特にその共通項が新しく「見出された」ものであるほど、互いの差異は際立ち、まとまらない。 知識があれば、最も深くまで食い込んで、洞察や批判を行えたかも知れないが、どうにもずっと輪郭ばかりをなぞっていたように思う。コソヴォを筆頭に、ユーゴの内戦は知っていたから、ゴールはなんとなく予測はできたけれど。 雨が降り続いていたのが印象的で、陰鬱な雰囲気をより際立たせている。 とはいうものの、 マーヤにまつわる思い出それ自体は明るいものが多く、青春小説っぽさを感じたり、コメディタッチに描かれるシーンは少なくない。それだけに、最後の展開の落差が辛く感じる、というのはあると思うけれど。 挫折と悔恨を描かせたら右に出るものはいない米澤先生。今回は、自分自身も読んでいて「ん?」と思った、主人公がユーゴへの渡航を決意するシーンをあとで振り返って、「あれは結局エゴで、なんも見えてなかった」と悔やむところが好き。今回は違う、と無茶な計画を構想するエネルギーも、振り上げた拳をあてどなくおろさざるをえなくなるもの。 書きながら思いついたけれど、「なににも本気になれない」と評された主人公が、ようやく本気で目指したいことを見つけた話だと取ることもできるのか。そしてそれをなし得ないことにしてしまう話。残酷な作家だなあ(そんなところが好き)。 ミステリとして読むとどうか、というと、最後の謎解きはマーヤの出身地を絞り込んでいくのがメインになっていて、「こういうのもあるんだな」と感心した。答えを知っているホームズがいて、ワトソンがなぞときを行うのも、ちょっと捻りが聞いている。その一方で、冒頭で提示された一番大きな謎については、ずっと表面でうろちょろして、最後一気に本論に入ったことによる間延び感がある。回想で語られる「日常の謎」が、大きな謎とそこまで密接に関係する訳でもなく、その謎自体もトリックも大したことがないというのが大きいように思う。 良いでも悪いでもないけれど、〈古典部〉シリーズのように、ヒロインに引っ張られてやむなく謎解きをする、という手法を取っていながら、こちらは異文化の眼差しを持つゆえに、日常の中の非日常に気づく、という体裁をとっていたように感じた。 同シリーズとは、主人公のキャラクター造形という点でも若干似ているような気もする。軽妙かつ豊富な語彙で語るのは、当初提示された「何にも本気になれない」というキャラクターからすると意外な感じがするけど、奉太郎同様、それなりに読書家であることが明かされるし、この時代に出版業界が最盛期を迎えていたことを考えれば、まあそこまで意外でもないのかも。 日記という形で過去のエピソードを提示する語り口、最後には現代においついて、その先を語る、というやり方は好み。ただ、日記の体裁を取るには本編の文体が普通の小説なので、単に日記を起点に記憶を呼び起こしている、つまりこのテクストは日記そのものではなく、その時点の描写ないし回想を文字起こししたものと捉えるのが妥当だろう。 日常と暴力(死)を架橋した作品としては、〈小市民〉も挙げられるだろうけれど、本作はバックボーンを書き込むことで、よりリアルに接続されていると思う。外部からやってきたマーヤという存在が、人間関係に痛烈な一打を加えて去っていくのも良い。
Posted by
再読。守屋と同い年のときに読んでとても重い衝撃を受けた記憶が生々しいけど、その頃に比すると十分に歳を取った今読んでも、ショックが大きい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
90年代のユーゴスラヴィアを話に絡めてきた以上こうなるのは分かっていたけど、何なもっと明るい話にして欲しかったな。 ウクライナで同じことがまた繰り返されているの哀しいね。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
訳あって再読。 古典部3冊目として描かれていたものを改稿し別版元から出版。 ユーゴスラビアからやってきた少女マーヤと、高校生3人との二か月間の物語。 異邦人であるマーヤを通して解かれる日常の謎。 日本の文化の哲学的意味。高校生たちの心の変化。 ユーゴスラビアの歴史的背景、現状、マーヤの使命。 単純な青春もので終わらせない米澤節。 守屋路行と太刀洗万智の存在感。
Posted by
太刀洗万智とは『真実の10メートル手前』という本で初めて出会った。とてもよかったので彼女が出てくる他の本も読みたくなり、『王とサーカス』を選んだ。でも、それはこの『さよなら妖精』の続編だと何かに書かれていたので、こっちを先に読むことにした。 まだ太刀洗がライターになる前の学生時代...
太刀洗万智とは『真実の10メートル手前』という本で初めて出会った。とてもよかったので彼女が出てくる他の本も読みたくなり、『王とサーカス』を選んだ。でも、それはこの『さよなら妖精』の続編だと何かに書かれていたので、こっちを先に読むことにした。 まだ太刀洗がライターになる前の学生時代の頃の話だ。 守屋路行と白河いずるは、以前ユーゴスラビヤから日本にきたマーヤという女の子について喫茶店で話している。二人はマーヤにまつわる何かの謎を解明しようとしているらしいが、解こうとしている謎が何なのかは分からない。 彼らは当時の記憶をなぞりながら、当時守屋の書いた日記を読み返すことにする。 これからこの本を読む人もいるだろうから、守屋と白河が解き明かそうとしていた謎には触れない。 遠くで起きたことを、自分に関係ないことだと流してしまうことは多々ある。それをひとつひとつ手に取って考えていたら、日常がままならないからだ。地球上にはたくさんの人間がいて、それ以外の多くの動物がいて、数えきれないほどの重要な問題を抱えている。それは大小様々なのだけれど、自分と距離の近い問題は大きく見えて、遠くで起こっている問題は大抵小さく感じる。ものの感じ方にも遠近法はあるのかもしれないと思ってしまう。 正直言って、最後のほうまであまり面白いと思って読めなかった。だけど、太刀洗が感情を露わにして、守屋君に心の内を吐露するラストシーンがとても胸に響いた。 無表情で冷たい顔立ちが故に、誤解されやすい太刀洗万智。 「でも、守屋君、あなたちょっと、わたしを冷たく見積りすぎじゃないの!」という彼女の言葉がなぜかやたらと心に残っている。見積もり。 しかし。 彼女は守屋君のことが好きだったのかな。それがこの本における、わたしにとっての最大のミステリーだ。
Posted by
ユーゴスラビアのこと全く知らなかった。 紛争の起きる地域がまだあるのに やはり平和ボケしてるのだなと反省した。 民族が1つになることを目指すことは儚い夢だったのだろうか。 ミステリーと絡めるのは少し無理があった気がする。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
読み終わってしばらく経つけど、何を書いていいかわからない。 前半が古典部シリーズのように、日常の謎を、ある意味微笑ましく解く内容だっただけに、後半の展開がとても辛い。 何かをしなければ、と思う主人公の気持ちが痛いほどわかる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
重厚で読んでいることに誇りさえ感じる。 ユーゴスラビアに興味を持たざるを得ない。 マーヤの故郷を当てる?ことへの伏線回収はまさにミステリーだが、この小説の真骨頂はやはり太刀洗万智の存在だと思う。 太刀洗万智のことをもっと知りたい。
Posted by