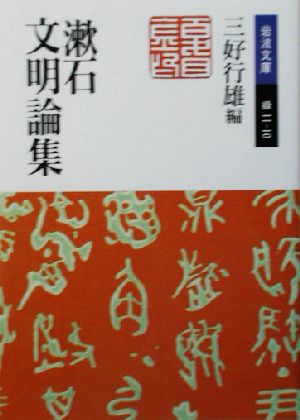漱石文明論集 の商品レビュー
漱石が近代人として評価されていることの真の意味を知った。学習院での講演「私の個人主義」では、小説だけでは見えにくい漱石の思想の遍歴が披露される。 明治期、様々な外来思想が輸入され社会が大きく変わる時代のなかで、戸惑いのなかに生きる漱石が啓示のように感じたであろう自己本位の思想。先...
漱石が近代人として評価されていることの真の意味を知った。学習院での講演「私の個人主義」では、小説だけでは見えにくい漱石の思想の遍歴が披露される。 明治期、様々な外来思想が輸入され社会が大きく変わる時代のなかで、戸惑いのなかに生きる漱石が啓示のように感じたであろう自己本位の思想。先進的な社会であろうとも後進的な社会であろうとも、外部の環境に影響されない自己本位の思想。自己が価値判断の基準となること、そのためには自分勝手という意味ではない真性の個人主義が必要となること。そんな漱石にとっての切実な悩みと回答が学生の前で力説されている。 絶対的な身分社会の江戸期には生じない思想であろうし、輸入品としての西洋思想こそ正しいとされた文明開化期の思想でもない。社会漱石の語る近代性は、きっと大正デモクラシーの下地になっている。
Posted by
タダでも読めるんだけど、編集の付加価値を頼りに購入。100年以上も前にこんなこと書いた人がいるんだなあ。「西洋」を体感し、苦悩した経験があるが故の説得力。幕末以前が舞台の青年立志小説にはないリアリティが満載。各自、頑張りましょう。 ・理想は見識より出づ、見識は学問より生ず。学...
タダでも読めるんだけど、編集の付加価値を頼りに購入。100年以上も前にこんなこと書いた人がいるんだなあ。「西洋」を体感し、苦悩した経験があるが故の説得力。幕末以前が舞台の青年立志小説にはないリアリティが満載。各自、頑張りましょう。 ・理想は見識より出づ、見識は学問より生ず。学問をして人間が上等にならぬ位なら、初めから無学でゐる方がよし ・真面目に考へよ。誠実に語れ。摯実に行へ。汝の現今に播く種はやがて汝の収むべき未来となつて現はるべし ・二と二が四となるとは今世論理の法則である。昔はそうも相場がきまっておらなかった。きまらぬ所に面白味があった。物は何でも先の見えぬ所が御慰みだ ・昔は上の方には束縛が無くて、上の下に対する束縛がある。これは能くない、親が子に対する理想はあるが子が親に対する理想はなかった。妻が夫に臣が君に対する理想はなかったのです ・私のような詰まらないものでも、自分で自分が道をつけつつ進み得たという自覚があれば、あなた方から見てその道が如何に下らないにせよ、それは貴方がたの批評と観察で、私には寸毫の損害がないのです。私自身はそれで満足するつもりであります
Posted by
明治文学上もっとも西洋化、近代化された作家の一人である夏目漱石。 本社に収録されている中では著名な「私の個人主義」のほか、「断片」も非常に印象に残った。 人間「夏目漱石」とは、どのような人柄であったのだろう。 科学的かつ思想的そして明晰であることが本書を読むとよくわかる。 漱石の...
明治文学上もっとも西洋化、近代化された作家の一人である夏目漱石。 本社に収録されている中では著名な「私の個人主義」のほか、「断片」も非常に印象に残った。 人間「夏目漱石」とは、どのような人柄であったのだろう。 科学的かつ思想的そして明晰であることが本書を読むとよくわかる。 漱石の場合、小説だけでなく随筆や本書のような講演を読んでみるのも大変参考になる。
Posted by
今春高校生になる娘への課題で出たので読んでみた。 「私の個人主義」は、これから様々なことを学び リーダーシップをとっていく人たちにとって 大切なことが解りやすく書かれているので 高校生にぜひ読んでもらいたい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
夏目漱石の講演や評論文をまとめた本。 『私の個人主義』は非常に論理的で明快。論理的思考の訓練にもなります。100年近く前の文章であるということを差し引いても読みやすく、頭に残りやすい論旨である。他人の個性を尊重しなければ本当の個人主義にはならないというのは今も続く命題である。国家が安定しているときは国家主義よりも個人主義に重きが置かれるという主張にも納得。 他の文も読みたい。
Posted by
烏兎の庭 第一部 書評 5.27.04 http://www5e.biglobe.ne.jp/~utouto/uto01/yoko/kisoy.html
Posted by
小説家として好きな漱石が西洋文明について述べた一冊。高校生のときに読んで感銘を受けてしまった。「個人主義」とな何なのか。小説にはユーモアがありながら、進んだ思想の持ち主でもあったことがうかがえる一冊。
Posted by
夏目漱石は森鴎外と同様に、西洋文明を丸々コピーすることには反対していた知識人であった。今や、西洋的考えを否定することはできなくなってしまった。それほど、日本の中に多くの西洋物が存在する。厳密に言えば、日本は、純日本的なものと中国・朝鮮などの東洋諸国の文化が日本式になったいわばハ...
夏目漱石は森鴎外と同様に、西洋文明を丸々コピーすることには反対していた知識人であった。今や、西洋的考えを否定することはできなくなってしまった。それほど、日本の中に多くの西洋物が存在する。厳密に言えば、日本は、純日本的なものと中国・朝鮮などの東洋諸国の文化が日本式になったいわばハーフの文化が存在していた中に、明治になって外科手術的に西洋文明を上書きしてしまったと言える。 今まではそうやって外のものを自分たちの良いように上手く吸収して日本になじませる(言わば、守・破・離のような)形式で、中国や朝鮮などの文化を自分たちのものとしてきた。しかし、西洋文明は今、十分に消化されているのか?そもそも、西洋的な考えは東洋とは相容れない部分が多い。例えば、排中律や二項対立。これらは仏教的な考えには存在することが難しい概念である。排中律でどうやって生=死を証明しろ、というのか。 西洋がダメで、東洋が素晴らしい、という議論をしたいのではない。それでは、Binarismにおける第1項と第2項との立場が入れ替わっただけでしかない(「美が望まれるべきで、醜は避けられるべき」が、「醜が望まれるべきで、美は避けられるべき」に変わったところで、根本的なBinarismの構造は変わらない。Parallaxでしかない)。 今は、そこの所を再考するべきなのかもしれない。西洋がどうだ、とか東洋がどうではなく、日本にとって、どう西洋・東洋を吸収すればいいのか?を考えるべきなのではないか。 だから巷に出ている、勝間和代のような西洋に傾きすぎた人間は、ちょっと危険だと思う。そして、自分の親が子どもだった頃やもっと前の頃(「古き良き日本」とでも呼べばいいのか?)の考え(伝統?)を日常的に触れるのが難しいのはさらに怖い、ように思う。 抽象的であまり現実味がないが、こんなことを考えさせるような本だった。
Posted by
母校での講義を文字に直したもののようです。 以下は、中の「模倣と独立」のかんそうです。 そのひとは、人間全体を代表しているのと同時に、そのひと一人を代表している。 そこから発展して、 人には、人の真似をしたいという本能(「流行に赴く」と表現されてます。単に圧迫されて嫌々従うの...
母校での講義を文字に直したもののようです。 以下は、中の「模倣と独立」のかんそうです。 そのひとは、人間全体を代表しているのと同時に、そのひと一人を代表している。 そこから発展して、 人には、人の真似をしたいという本能(「流行に赴く」と表現されてます。単に圧迫されて嫌々従うのではないということ)と、独立自尊の傾向を併せ持つ。 そういうひとがいる、という意味じゃなくて、一人の人間の中にその両者が存在している。 ということが面白おかしく漱石節で書かれてます。 この人、話し言葉になると余計にリズム感の良さが際立つ気がする。 下駄禁止の話、真宗の親鸞、文展、イブセンの「人形の家」のノラ、のっぺりした紳士、学生のいたずら、例をいっぱい挙げて、「模倣と独立」がどっちも大事だと主張しています。 この話を読んで、カントが似たようなことを言ってたはずと思って本棚をあさり、 「世界市民という視点からみた普遍史の理念」という論文の中にみつけました。 カントが書いてたのは、 人間には、集まって社会を形成しようとする欲求と、 孤立して全てを意のままに処分したいという反社交的な欲求が同時に存在している。 その対立関係が、最終的に秩序を生み出していく。人類を発展させていく。 ということでした。
Posted by
マードック先生の『日本史』: ”マードック先生のわれら日本人に対する態度はあたかも動物学者が突然青く変化した虫に対すると同様の驚嘆(きょうたん)である。維新前は殆んど欧洲の十四世紀頃のカルチュアーにしか達しなかった国民が、急に過去五十年間において、二十世紀の西洋と比較すべき程度に...
マードック先生の『日本史』: ”マードック先生のわれら日本人に対する態度はあたかも動物学者が突然青く変化した虫に対すると同様の驚嘆(きょうたん)である。維新前は殆んど欧洲の十四世紀頃のカルチュアーにしか達しなかった国民が、急に過去五十年間において、二十世紀の西洋と比較すべき程度に発展したのを不思議がるのである。” 日本の進歩の成果を西洋諸国に評価してもらえるかどうかを問う夏目漱石、勝手に日本の未来を悲観するマードック先生、二人とも大まかなところの予想はあたってるきがする。これは私が勝手に日本を憂いてるから。
Posted by