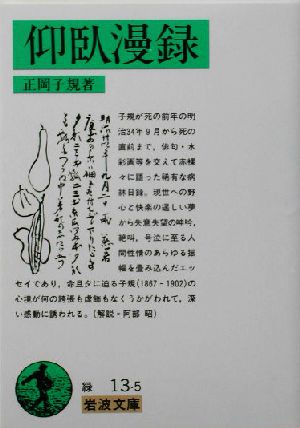仰臥漫録 の商品レビュー
壮絶。 でも食欲旺盛でびっくりする。 ノボさんとかミチクサ先生読んだ時も思ったけど、お母さんと律さんは大変だったろうなぁ
Posted by
このような本があるなんて。 この本は正岡子規の晩年、既に外へ出歩くこと叶わず。 日々を毎日記録したものなのです。 本は、来訪客、三度の食事内容、お金のこと、家族のこと、そして俳句のこと。 始まりは子規が死するちょうど1年前から始まります。 妹の律と母が彼を自宅で介護し、看取るの...
このような本があるなんて。 この本は正岡子規の晩年、既に外へ出歩くこと叶わず。 日々を毎日記録したものなのです。 本は、来訪客、三度の食事内容、お金のこと、家族のこと、そして俳句のこと。 始まりは子規が死するちょうど1年前から始まります。 妹の律と母が彼を自宅で介護し、看取るのです。 最初は色々事情がよくわからないまま読んでいたので子規のその食欲に驚愕です。 とにかく凄い、とても病気とは思えず。 食事以外でも飄々とした感じでついつい頁をめくってしまいます。 ただやはり病魔は確実に子規を捉えており、途中からは狂気が密やかに忍び寄ってくるのです。 ご存知でしょうが、子規は大学生の頃に結核にかかります。そして脊椎カリエスになるのです。脊椎カリエスとは結核菌が脊椎へ感染したもの。こうなると脊椎の中で化膿が起こり、それが皮膚を突き破って穴を開けるようです。本の中で律が綿を買いに行ったり包帯の交換をしているのはそれです。歯肉の膿を出すとかいう描写もそれです。非常に残酷な病気だと思います、抗菌剤の登場まではこの日記の40年後まで待たなければいけない。子規の生きた明治では抗菌剤は登場していないから。 読んでいる私は子規が亡くなった日を知っています。それを知っていてこの日記を読むと胸の奥がキューっと締め付けられます。最初の章は呑気な感じですすむのにその後半、そして二章へ。後半はちっとも楽しくなくて、読むのが辛い辛い。 こんな本があるなんて知らなかったよ。
Posted by
私は、いま「俳句」を生み出したいと思っている。短い言葉で、宇宙を表したいという欲望が強い。とにかく、文字を書き連ねている。それを凝縮したい。画像を見て、俳句をひねり出す。 なんか、その行為がスリリングだ。 寺田寅彦は、夏目漱石に俳句とは何かを質問する。 夏目漱石は「俳句はレトリッ...
私は、いま「俳句」を生み出したいと思っている。短い言葉で、宇宙を表したいという欲望が強い。とにかく、文字を書き連ねている。それを凝縮したい。画像を見て、俳句をひねり出す。 なんか、その行為がスリリングだ。 寺田寅彦は、夏目漱石に俳句とは何かを質問する。 夏目漱石は「俳句はレトリックの煎じ詰めたものである」「扇のかなめのような集注点を指摘し描写して、それから放散する連想の世界を暗示するものである」 夏目漱石は、やはり面白い見方をしている。扇のかなめに集中して、放散させるという視点は大切だ。1867(慶応3)年に、正岡子規と夏目漱石は生まれた。正岡子規は、松山藩士正岡常尚と八重の間に長男として生まれた。翌年に明治維新となる。1889(明治22)年に第一高等中学校で、2人は出会う。2人は、影響を与えあった。 本書は、正岡子規の死去する前年の1901(明治34)年9月、10月の日記が書かれている。子規は結核菌が脊椎を冒し脊椎カリエスと診断される。数度の手術も受けたが病状は好転せず、やがて臀部や背中に穴があき膿が流れ出るようになった。3年ほど寝込んでいた。まさに晩年である。 寝たきりで、前に庭が見える。それが世界だった。 最初に始まるのが、明治34年9月2日雨 蒸暑し。 「朝 粥四椀、はぜの佃煮、梅干砂糖つけ 昼 粥四椀、鰹のサシミ一人前、南瓜一皿、佃煮 夕 奈良茶飯四椀、なまり節、茄子一皿 此頃食ひ過ぎて食後いつも吐きかえす。二時過牛乳一合ココア交て、煎餅菓子パンなど十個ばかり」 この子規の食欲に驚かせる。これが連日続くのだ。お腹が痛くなるくらい食べ、吐いてしまう。それでも、食べる大食漢。お椀の大きさはどれくらいだったろう。調べてもわからなかったが、四椀なのだ。ここに、子規のもつ生きようとする苦しいほどの熱意。食べることは生きることだ。ずーっと調べたが、葉物野菜を食べていない。炭水化物主体の食事である。昔は、ご飯いっぱい食べれれば満足という時代だったんですね。 あとは、痛みを耐えることと、そして庭を見るのだ。そして、句を読む。死を直前にして、癇癪を起こす。結核なので、人はあまり見舞いには来れないはずだが、よく友人たちは来る。 『彼は癇癪持ちなり、強情なり、気がきかぬなり、人に物問うことが嫌いなり、彼の欠点は枚挙にいとまあらず、家人恐れて近づかず』と描写する。死の間際にあっても、自分を外から見る。 気に入った俳句。 棚の糸瓜思ふところにぶら下がる 糸瓜ぶらり夕顔だらり秋の風 物思ふ窓にぶらりと糸瓜哉 雨の日や皆倒れたる女郎花 蝉なくや五尺に足らぬ庭の松 秋もはや塩煎餅に茶渋哉 餓鬼も食へ闇の夜中の鱒汁 町川にボラ釣る人や秋の風 美女立てり秋海棠のごときかな 芙蓉よりも朝顔よりも美しく 馬の尾に仏性ありや秋の風 秋の蝿殺せども猶尽きぬかな 秋の蝿追へばまた来る叩けば死ぬ 鶏頭や今年の秋もたのもしき 干瓢の肌うつくし朝寒み 糸瓜には可も不可もなき残暑かな 栗飯や病人ながら大食ひ かぶりつく塾柿や髯を汚しけり 黒きまで紫深く葡萄かな よべここに花火あげたる芒かな 人問はばまだ生きている秋の風 成仏や夕顔の顔へちまの屁。 ふーむ。きりがない。句が実にシャープだ。 大飯を食らい、ただひたすらに読み続ける子規。 生きるって、そういうことだ。どんな状況にあろうとも。どんなに身体が痛く、壊れていようが、意志で生き抜く。天晴れ、正岡子規!
Posted by
病床にある正岡子規が、日々衰弱していくなかで見せる異様な食への執着の記録。 壮絶な病状の記述も霞んでしまうほどの飽食ぶり。死ぬ前にいろんな物を満足いくまで食べたい…そういう心境は理解できるのだが、その量たるや半端ではない。健康な人間より遥かに多い。「生きた証し」を残そうとする人は...
病床にある正岡子規が、日々衰弱していくなかで見せる異様な食への執着の記録。 壮絶な病状の記述も霞んでしまうほどの飽食ぶり。死ぬ前にいろんな物を満足いくまで食べたい…そういう心境は理解できるのだが、その量たるや半端ではない。健康な人間より遥かに多い。「生きた証し」を残そうとする人は多いと思うが「食った証し」をここまで執着して残そうとする人は珍しい。 来訪する人々はのちに著名な俳人や文士になった人も多く興味深いのだが、何せ膨大な食の記述に圧倒される。
Posted by
仰臥漫録 (和書)2009年08月13日 22:53 1989 岩波書店 正岡 子規 「病床六尺」を以前に読んでいます。今回「仰臥慢録」を読んで病を患い死が刻々と迫って来る中の、その生活の日記を読みそこに凝縮されたものを感じた。子規が特別だと言うのではなくそこに書かれた作品が...
仰臥漫録 (和書)2009年08月13日 22:53 1989 岩波書店 正岡 子規 「病床六尺」を以前に読んでいます。今回「仰臥慢録」を読んで病を患い死が刻々と迫って来る中の、その生活の日記を読みそこに凝縮されたものを感じた。子規が特別だと言うのではなくそこに書かれた作品が人間と言う存在を際だたせているのだと思います。そこが特に興味深かった。
Posted by
見舞い客の中に後世 名を成す著名人が多い。「紅緑来る」とあるのは、佐藤紅緑だろう。その愛娘が佐藤愛子なのだから、子規の生きた明治がそれほど大昔ではないと思えてくる。 巻末40ページに及ぶ俳句集に難儀した。ハイキングしていたら、目の前に垂直の絶壁!という印象だ。
Posted by
最晩年の正岡子規の日記、というか日々の記録に近い。 「一」は、食事の報告が大半を占めていて、欲求を食で補う無茶食いの典型的な状態。もう長くないから食いたいものを食おうという意思も有ったかもしれない。 逆に「一」の最後から「二」については、かなりの病状の進行により、苦しむ姿が...
最晩年の正岡子規の日記、というか日々の記録に近い。 「一」は、食事の報告が大半を占めていて、欲求を食で補う無茶食いの典型的な状態。もう長くないから食いたいものを食おうという意思も有ったかもしれない。 逆に「一」の最後から「二」については、かなりの病状の進行により、苦しむ姿が多く見られる。「癇癪を起こす」なんてさらって書いてあるけど、その行間には病に苦しむ、「どうにも出来ない」「どうにもならない」ことへの怒りがあるんだろうなと。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
言ってしまえば他人の日記をのぞき見をしているのだか、絶句としか表現できない。読み進めるほどに、他人の日記をのぞき見しているだけの行為を読者はしている状況ではなくなる。10月12日の日記にはギラギラとした目つきの筆者が思い浮かぶ。彼は生きたいのだ。
Posted by
「文人御馳走帖」での正岡子規の食べ物に対する描写やそのコダワリが楽しかったので、これもついでに読もうかなと気軽に手に取ってみたんだけど、とんでもない。最初の1日目の日記だけですっかり心を鷲掴みされてしまった。 紡ぐ言葉の美しさ、秘めた心の壮大さ、目線の素朴さ、生活の瑞瑞しさ、生へ...
「文人御馳走帖」での正岡子規の食べ物に対する描写やそのコダワリが楽しかったので、これもついでに読もうかなと気軽に手に取ってみたんだけど、とんでもない。最初の1日目の日記だけですっかり心を鷲掴みされてしまった。 紡ぐ言葉の美しさ、秘めた心の壮大さ、目線の素朴さ、生活の瑞瑞しさ、生への執着と諦念、そして食への拘泥。 1日目の記録でまず、お粥と白米を合わせて12杯も食べてその後菓子パンを10個も食べながら「最近食べ過ぎてよく吐きかへす」なんて書いてるかと思ったら、急に人様の家の家賃比べしたり、夕食に食べたものの俳句を2ページ分つくったり、絵を描いたり詩を書いたり、とにかく毎日いろんな突拍子もない事をするもんだから読んでてクスクス笑ってしまう。もう!すき!なんて人なの! しかしその分、段々病魔に冒され衰弱していよいよページも飛び飛びになってしまうとその空白や言葉の少なさが辛くて、ページが進むにつれて文字数は少なくっていくのに反比例して読み進める速度はどんどん遅くなった。 頑固な人柄と柔軟な思考が、品のよい巧みな文章にのせられてするすると流れてくるもんだから、本を開いてただぼうっとしているだけでいつの間にか骨抜きにされてしまう。
Posted by
どんだけ喰うのだこの病人。カルマを感じる。もう餓鬼!喰いに喰って今度は腹が膨れて苦しくて、こっちが涙出てくるよ。便通だの精神錯乱だの、子規がこんなにあらぶっていたとは知らず。これっぽっちと言えど読んでるこっちが苦しくて読むのに2ヶ月。
Posted by