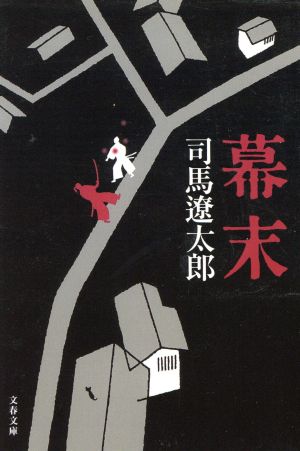幕末 新装版 の商品レビュー
幕末時に起こった暗殺集。 逃げの小五郎は司馬の創作の言葉だったとしたら、感服。 暗殺にくらさはつきものである。
Posted by
山中に隠遁でもしていなければ何とも物騒騒然とした世相で、想像するほどに空恐ろしい。攘夷提唱なぞ到幕派の因縁かと思いきや、佐幕派も唱えていたり、とにかく狂乱、剣呑であること極まりない。いずれの側にせよ明日の命は知れず、斬るか斬られるか。暗殺事件、というより暗殺者を描いた12話。
Posted by
幕末の暗殺に関する短編。書の中で一番印象だった言葉は(一流の人間は死んで残ったのは三流の人間だった。)くだり。多くの歴史小説を読んだか本当にそうだとうなづけた。司馬遼太郎はきちんと取材してあるので話に重みがある。
Posted by
新選組のマイブーム経由で読んでみた。 自分はまだ幕末の知識が浅いので、背景はうっすらしか分からず本作を十分に楽しめなかった。 また歴史の知識を身につけた後、再読してみようと思ふ。
Posted by
春の雪を血で染めた大老井伊直弼襲撃から始まる幕末狂瀾の時代を、十二の暗殺事件で描く連作小説。 歴史はときに血を欲す。 暗殺者も凶刃に倒れた死骸も、共に我々の歴史的遺産である。 これも何度も読んでます。ww
Posted by
やはり司馬遼はストーリーの上手い作家ではない。 こういった短編になるとそれが如実に表れる、ただ話が羅列されている感じ。ご本人もそれを自覚しているのか、あとがきで少々の言訳がなされている。 それにしても皆血に染まってますな、それが革命というものだろうが、今に至るまでの日本を見るに考...
やはり司馬遼はストーリーの上手い作家ではない。 こういった短編になるとそれが如実に表れる、ただ話が羅列されている感じ。ご本人もそれを自覚しているのか、あとがきで少々の言訳がなされている。 それにしても皆血に染まってますな、それが革命というものだろうが、今に至るまでの日本を見るに考えさせられるものがあります。
Posted by
ときどき、無性に歴史小説が読みたくなる。今回は大好きな司馬遼太郎作品のなかから、たまには短篇をと思い本作をチョイス。表題どおり幕末を舞台にしたこの短篇集は、暗殺にスポットライトを当てた作品ばかり12篇を収録している。内容は、桜田門外の変のような有名な事件や、桂小五郎(木戸孝允)や...
ときどき、無性に歴史小説が読みたくなる。今回は大好きな司馬遼太郎作品のなかから、たまには短篇をと思い本作をチョイス。表題どおり幕末を舞台にしたこの短篇集は、暗殺にスポットライトを当てた作品ばかり12篇を収録している。内容は、桜田門外の変のような有名な事件や、桂小五郎(木戸孝允)や井上聞多(馨)のような有名な人物を主題にしたものもあるが、いっぽうではじめて耳にする事件や人物も描かれており、それ自体が歴史好きとしてはまず面白かった。また、井上や桂などのエピソードも、知っているものもあったがやはり筆力が一流なので、面白く感じずにはいられない。暗殺が主題ということだが、そこには血なまぐささよりはむしろそれぞれの熱い想いがこめられており、たんなるエンターテインメントを超えた面白さがあった。それと同時に、深く考えさせられる部分もある。歴史の教科書では、桜田門外の変すらほんの数行の記述に終わり、取り扱われてさえいない幕末の志士たちも多いけれど、暗殺ひとつとってみても、そこには多くの人物のさまざまな想いが詰まっていて、複雑な権謀術数を踏まえた結果として暗殺があるのであり、そういう背景は、教科書ではけっして知ることができないので、そこまで知ったうえで「幕末」というものをあらためて考えてみると、簡単には言い表せない複雑な気持にもなる。やっぱり人間ドラマの部分が、歴史小説の最大の魅力だと思う。本作もその要素がたっぷりと含まれているという点で、文句なしの傑作である。
Posted by
【なんでも芋】 司馬遼太郎氏の幕末を舞台とした短編集。 幕末から明治を駆けた偉人達の意外と知らないエピソードが満載です! 福岡国際大学:もんた
Posted by
時間に限りがあり、最後まで読めなかった...。 司馬遼太郎の本ということで、とにかく辞書を引きまくりながら読みました(笑) 様々な人の生き様を魅せてもらいました。 やっぱり複雑な心境です、今の平和な世を生きるわたしにとっては。 歴史からもっと私たちは学び、そして未来を今よりもよい...
時間に限りがあり、最後まで読めなかった...。 司馬遼太郎の本ということで、とにかく辞書を引きまくりながら読みました(笑) 様々な人の生き様を魅せてもらいました。 やっぱり複雑な心境です、今の平和な世を生きるわたしにとっては。 歴史からもっと私たちは学び、そして未来を今よりもよいものにできるよう努力せねばならないと思った。
Posted by
幕末の時代にピュアに筋を通す生き方をしたか、したたかに時代の潮流にのり、カメレオン化したか、後者の方が明治まで存命し位までついているように思う。 蛤御門ノ変の後、逃げ隠れする桂小五郎(のちの木戸孝允)を描いた「逃げの子五郎」。明治元年に英国公使の列に切りつけた朱雀操と三枝シゲル...
幕末の時代にピュアに筋を通す生き方をしたか、したたかに時代の潮流にのり、カメレオン化したか、後者の方が明治まで存命し位までついているように思う。 蛤御門ノ変の後、逃げ隠れする桂小五郎(のちの木戸孝允)を描いた「逃げの子五郎」。明治元年に英国公使の列に切りつけた朱雀操と三枝シゲル(草冠に翁)は、その罪として平民に落ちさらし首となった「最後の攘夷志士」、三ヶ月前では烈士と称えるられたはずで、司馬さんも「節を守り、節に殉ずる」生き方として心よせている。 婚礼資金の借りと「刀どおしが兄弟」と言われ坂本竜馬の仇討に加担するお桂と後家鞘(後の土居道夫大阪府県知事)。その個人的な気持ちの繋がりが暗殺する理由なのがさらに竜馬の魅了を増しているようで、好きな作品「花屋町の襲撃」
Posted by