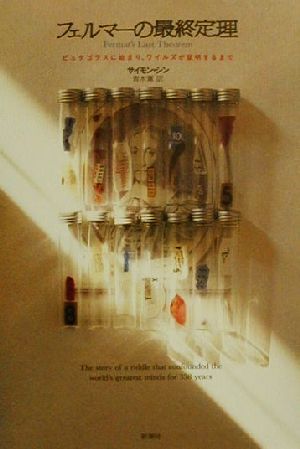フェルマーの最終定理 の商品レビュー
ピュタゴラス、オイラー、ガウス、パスカル、コーシー、フーリエ、 ガロア、ダランベール、ラグランジュ、ヒルベルト、ディリクレ、 ルジャンドル、リュービル、ポアンカレ、ゲーデル、チューリング。 フェルマー。ワイルズ。 全てこの物語の登場人物である。数多くの偉大な学者たちが ほんの...
ピュタゴラス、オイラー、ガウス、パスカル、コーシー、フーリエ、 ガロア、ダランベール、ラグランジュ、ヒルベルト、ディリクレ、 ルジャンドル、リュービル、ポアンカレ、ゲーデル、チューリング。 フェルマー。ワイルズ。 全てこの物語の登場人物である。数多くの偉大な学者たちが ほんのひとときこの本に登場し、自分の役割を演じる。 それぞれにドラマがあり、苦悩がある。一種のオムニバスであろうか。 彼らを繋いでいるのはフェルマーの最終定理である。 もちろんこの物語は作り話ではない。実話である。しかし とても実話とは思えない楽しさ、面白さ、壮大さ、そして悲しさ。 フェルマーの最終定理を軸に、これほどの物語を作りあげた 著者にはまさに脱帽である。 物語の前半は数学の成り立ちからフェルマーの最終定理が 作られたいきさつ、それに対する様々の数学者の 必死の挑戦、苦悩が書き綴られている。 さらにゲーデルによる物語を根本から覆すような 示唆。 そして二人の日本人が登場する。彼らがフェルマーの最終定理に、 そして数学界に与えた影響は計り知れない。 彼らの登場により物語は一気にクライマックスへと進み出す。 ワイルズそして彼を取り巻く人間たちのドラマは この物語の一番の見せ場だと個人的には思う。 ワイルズの努力と挫折、あきらめ、そして・・・ ワイルズが得たもの、失ったもの。ワイルズの「大切なもの」。 ワイルズの心情については共感できると感じる方は少なくないだろう。 是非この実に起伏に富んだ物語を体験してみてほしい。 あくまで主役はフェルマーの最終定理ではなく それを取り巻く人間達である。 個人的には、訳者あとがきにもあるが、日本人を非常に良く (というか公平に)書かれていると感じた。一瞬「著者は日本人か?」 と思ったほどである。 記述も実に読みやすく、判りやすい。 数学の専門家でも、全く知識がない人でも読めると思う。 掛け値無しにお薦めの一冊である。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
数学の起源や、難問を残したフェルマーについて、様々な数式を生み出した数学者たちについて、そしてワイルズの証明について、どれも興味深いことばかりでした。その中でも印象に残っているのは、わずか数行しか書かれていなかったエウクレイデスの話でした。エウクレイデスは数学的真理の追求そのものに価値を認め、自分の仕事を応用することなど考えていない人でした。そんな彼に一人の生徒が「教えていただいた数学はどんなことに使えるのですか?」と質問をした。たぶん誰もが学生の時一度は思う疑問なのではないかと思います。しかしエウクレイデスにその質問をした学生は放校処分を受けてしまいました。厳しい話だとは思いますが、それだけ数学というのが利益を求めない、真理の追究だけを目的とした純粋な学問だということなんだと思います。この本に出てきた数学者たちの中にも利益を本位に求めた人はいなかったと思います。真理は「それが何の役に立つのか」と尋ねる人には役に立たないものなのでしょう。だからエウクレイデスはその生徒を放校処分にしたのかもしれません。生徒の質問に対する答えは「役に立たない」だったのではないか、と思います。 或る小説に以下のような会話が書かれていました。 「先生ならどう答えられますか?学生が数学は 何の役に立つのか、て聞いたら」 「何故、役に立たなくちゃいけないのかって聞 き返す」 (中略) 「だいたい、役に立たないもののほうが楽しい じゃないか。音楽だって芸術だってなんの役 に立たない。最も役に立たないということ が、数学が一番人間的で純粋な学問である証 拠です。人間だけが役に立たないことを考え ているんですからね?」 高校生の頃にこの文を読んで、本当にそうなんだろうか?と、疑問を抱いていましたが、「フェルマーの最終定理」読んで納得しました。
Posted by
x^n+y^n=z^n n>2の時、整数解はない。 小生でも問題の意味は理解できるのに、何百年も証明されなかったフェルマーの最終定理が証明されるまでの物語。翻訳物は苦手なのだけれど、青木さんの訳も読みやすくてよい。 同じコンビの「暗号解読」もおすすめ。
Posted by
世紀をまたにかける超難問を巡る数学者たちのドラマチックな物語はまるで映画のようで、数学に苦手意識のある私でさえも途中で本を投げ出すことはなかった。純粋な数学者たちのパーソナリティーが垣間見れる。
Posted by
16世紀、数学者フェルマーが残した一枚のメモ「私はこの命題について真に驚くべき証明をもっているが余白が狭すぎるので此処に記す事はできない」というフェルマーの最終定理をめぐる400年間の軌跡がつづられた本。 長い!とりあえず長い!! 飽きっぽい自分は読むのにすごく苦労した。 所々...
16世紀、数学者フェルマーが残した一枚のメモ「私はこの命題について真に驚くべき証明をもっているが余白が狭すぎるので此処に記す事はできない」というフェルマーの最終定理をめぐる400年間の軌跡がつづられた本。 長い!とりあえず長い!! 飽きっぽい自分は読むのにすごく苦労した。 所々面白い記述もあるが、全編が基本的に単調。 フェルマーの最終定理とかコリヴァギン・フラッハ法とかケプラーの法則とか、とりあえず数式の名称は名前がカッコいい。
Posted by
3 以上の自然数 n について、x^n + y^n = z^n となる 0 でない自然数 (x, y, z) の組み合わせがない。このフェールマーの最終定理が証明されるまでの歴史が書かれている。 300年以上前にフェルマーが残したこのシンプルな定理の証明に対して、20世紀の終わり...
3 以上の自然数 n について、x^n + y^n = z^n となる 0 でない自然数 (x, y, z) の組み合わせがない。このフェールマーの最終定理が証明されるまでの歴史が書かれている。 300年以上前にフェルマーが残したこのシンプルな定理の証明に対して、20世紀の終わりまで、数多くの数学者が挑戦し、その中で数学が大きく発展していった経緯が詳しく書かれている。その経過での人間ドラマや数学の面白さが伝わる本でもある。 とてもおもしろかったし、自分の中で数学に対する興味が大きく増した。谷山志村予想に関する話もたくさん書かれていてよかった。 ただ、自分はワイルズの秘密主義的な姿勢はあまり好きではない。確かに、ワイルズの我慢強さは素晴らしいと思うが、数学者達は皆、お茶を飲みながら自分の考えを共有するというオープンな慣習が自分は好きであり、さらに数学史上に残るフェルマーの定理の証明も、ワイルズだけの力では無く、今までの数学者達の力の結集によるものであるからだ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
フェルマーの最終定理とは、 3 以上の自然数 n について、x^n + y^n = z^n となる 0 でない自然数 (x, y, z) の組み合わせがない。 という定理である。17世紀の法律家、ピエール・ド・フェルマーが残した数学会最大の謎だった数論の問題を、1993年にプリンストン大学のアンドリュー・ワイルズが解くまでのドキュメンタリー小説。イギリスBBCのサイモン・シンが制作した「フェルマーの最終定理」という番組が元になった本である。 一見すると、中学生にも理解できるような簡単な式である。よく見かけるものとして「ピタゴラスの定理」と非常ににている形だが、指数のnを3以上にしてしまうと、解が存在していないことがわかるのだ。試していないが、全くないらしい。 初めてこの定理を私が知ったのは、覚えていないが、現役の大学受験の時、予備校の担任が、教材としてこれを英語版を読ましてくれた。先生が「高校英語くらい知っていれば、英語がよめるんだよ」と話てくれて、英語と数学の面白さを知ったのを覚えている。確かその時は、「川の全長の長さ」を「川の源流点と河口点までの直線距離」で割ると、だいたい3.14円周率に近づくといったものだった その時から読もう読もうと思っていたけど、それから随分経ってしまったと思う。 内容自体は、ピタゴラスから始まり、ディオファントス、オイラー、ジェルマン、ラメ。近代に至っては、日本人の谷山豊、志村五郎、そしてワイルズまでの360年余りの壮絶な数学史が延々とつづられている内容だ。途中途中で、数学の定理、問題なんかも出てきて、素人でも1つのドラマとして読める作品だ。 数学史関係の本をこれ以外でも読んだことがあるので、その時感じた感覚と似ている部分として、数学者たちが費やした時間は、文章の中には書き込めないとうことである。そして、本を読む私たちは、「解けた」という文字が出てきた瞬間には、その行間から数学者たちの血ににじむような、数字と自分との格闘を読み取らなければいけないことである。 ほとんどの数学者たちは鉛筆と紙のみで、事例を沢山作ることではではなく、1つの証明のみで全てを証明しなければいけない使命を持っている。東野圭吾の「容疑者Xの献身」は物理学者と、数学者の戦いだったが、あの中でも物理学者は「仮定→実験→真理」といったプロセスが大事とあり、数学者は「真理→証明」という、真理に至る過程が全く逆だと語っていた。(容疑者X~の中でこのような発言や、四色問題、コンピューターによる解法に疑問があると石神が語っていた点からして、この本から十分といえる影響があったかもしれない。) たいてい、数学者たちの格闘は数行でしか語られない、語ることができないが、その数行から真理にいった苦労を読めなければいけないと思う。ワイルズも大学の教授の仕事の傍ら、誰にも知られずに少年の時からの夢の実現のために自宅に引きこもり、証明をずっと続けていた。「数論の父」と言われたフェルマーとの戦いを1人で(過去の先人たちの武器を使いながら)していたのだ。 もう1点、和訳をした青木薫さんもあとがきで書いていたが、フェルマーの最終定理を近代的なアプローチで証明するためには、「谷山・志村予想」の証明が必須となる。どちらかを証明すると、どちらかも証明されるという性質を持っていたため、フェルマー~の証明には2人の日本人が大きく関わっているのである。360年に及ぶ戦いの中で、日本人が関わっていたということは、日本人にとって何か誇りに感じる、親近感が感じる話でもあった。 本の存在を知ってから数年がたってやっと読めた本は、数学という世界は取っ掛かりにくい物ではなく、長いドラマとして捉えれば、エンターテイメントといて十分楽しめるものである。しかし、そのエンターテイメントの終わりは誰もわからない。そして、エンターテイメントとかんじるのは、それを後から外から知る大多数の人間なのだ。当事者として数学と向き合ってきた人たちにとっては、対した苦労の連続であり、楽しみというのはほとんどなかったと思う。その苦労を知る側も享受、知ろうとしながらでなければ読んではいけないと思う。 長くなりました。「ここで終わりにしたいと思います」。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
フェルマーの最終定理なんかはじめて聞くという人でも読める。数学という学問の美しさが全体から溢るロマンティックな本でもある。サイモンシン氏の説明展開のほどよいスピード感と、原著を読んだ訳ではありませんが、翻訳も良いのでしょう。
Posted by
数学のキライな人にこそ読んで欲しい1冊かも。300年以上に渡り数学者達を悩ませつづけてきた「フェルマーの最終定理」が10年ほど前にワイルズによって証明されるまでを、紀元前の数学の黎明からひも解きつつ紹介しています。 これは、著者と訳者の努力の賜物だと思うのですが、この本では、数...
数学のキライな人にこそ読んで欲しい1冊かも。300年以上に渡り数学者達を悩ませつづけてきた「フェルマーの最終定理」が10年ほど前にワイルズによって証明されるまでを、紀元前の数学の黎明からひも解きつつ紹介しています。 これは、著者と訳者の努力の賜物だと思うのですが、この本では、数学特有の「小難しさ」が最小限に抑えられています。ワシは高校で数学をドロップアウトしましたが、読むのにはほとんど不自由しませんでした。 所々に挿入される「証明」の鮮やかさ、ワシらが何気なく学んでいた「定理」ってのが、どのようなプロセスで発見されたか、それを読むだけで感動で一瞬頭が真っ白になってしまうくらいです。 (2004年読了)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
フェルマーの最終定理がどのように証明されるかを書いているというよりは、 フェルマーの最終定理を理解するための背景知識というか、背景となる情景を映し出している。 数学の本は、単調で、理解できないと、挫折してしまう。 この本を片手に、原理の理解を進めようとすると、 挫折しても、また、もう一度やり直そうという気力がわいてくる。 数学は、無味乾燥な学問ではなく、理論の背景があって成り立つ学問であることを再確認できる。 知的好奇心だけでは読み続けることができないかもしれない。 美的センスと信念について、ある種の啓示をしているかもしれない。
Posted by