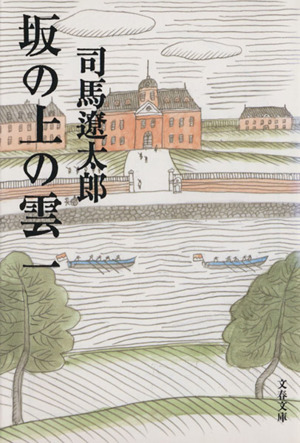坂の上の雲 新装版(一) の商品レビュー
【言い訳メモ】 一度図書館等で借りて読んで 手元に置きたくなったら購入派なのでコロナによる図書館離れが辛い。。 会社もなるべく在宅、変則的就業となり 時間はあるはずなのに マイペースに登山できず、休憩なしで歩き続けたり 無駄にダッシュしてるような感覚で気疲ればかりして妙に体力も削...
【言い訳メモ】 一度図書館等で借りて読んで 手元に置きたくなったら購入派なのでコロナによる図書館離れが辛い。。 会社もなるべく在宅、変則的就業となり 時間はあるはずなのに マイペースに登山できず、休憩なしで歩き続けたり 無駄にダッシュしてるような感覚で気疲ればかりして妙に体力も削られている日々 ようやく読書できるまで気力回復。 でもまだ電車内で読める気分では無い。。我ながら変な状況である。。。 家にある漫画一気読みも楽しかったけれど。 SNS巡りもしたけれど、自分やはり紙媒体読書が好きなのだなぁ、と実感。 あと、情報が逆に溢れている現在、逆に気合入れてアンテナたてないと読みたい本に出合わないという矛盾。。 実写ドラマ化のポスターを見た記憶しかなく なんとなく戦争もの、という前知識のみ。 司馬遼太郎氏も食わず嫌いならぬ読み嫌いだったがもったいないことをしていたと後悔。 とても読みやすい。 1996年ご逝去されているのに戦後あたりに没とか何故かもっと昔の人だと思っていた。 日露戦争の秋山好古氏についての物語。 彼については知らなかったが 周囲の人間関係と、歴史について 司馬氏がちょいちょい後世ネタを挟んでくれるので点と点が線でつながっていく感じで 一巻は読みやすい歴史書のよう。 騾馬が牝馬と牡驢馬の掛け合わせだとは知らなかった。。というへぇ~が満載。 もっと文学者や 軍や戦争について知っていればもっと楽しめるのだろうなぁ。。 まだ戦争の気配はないけれど 始まると銀河英雄伝説みたいになるのだろうか。。。不安でもある。。。 ・秋山氏の弟は正岡子規の友人で 松山出身であるから、正岡子規の友人である夏目漱石氏はその松山の学校で教鞭をとる。 ・正岡子規は野球を広めたとうあの横顔のイメージだったが御年34歳という若さで亡くなっている。 もっと壮年位だと写真では感じていた。。 ・秋山兄弟共に大層彫が濃い。写真残っていたが、知らなければ欧米人かと。。。 ・正岡子規氏東京受験の際、明治の文豪らと会っていた。出身が東京というのが今でいう私立卒エリートの恵まれた条件を彷彿とさせる。。。 ・が、一方で廃藩置県の際、思い切った改革をした旧藩士らが意外に多かった。 戦国時代や幕末が人気だけれど、この時代の人たちについてもっと知りたい。。。 ・トルコ親日のきっかけになった遭難船の事件はこの時代だったのか。。。
Posted by
ドラマ版が大好きで何度もみました。 小説だと当然ですが、より細かく出来事、描写がありひきこまれます。
Posted by
<開明期を迎えた小国“日本”とそこに生きた人々の、“独り立ち”の物語> 上記のように評しても間違いはないはず。 司馬遼太郎は昔よく読んでいましたが、この本は全八巻ということでなかなか手がでませんでした。 んで昨今のNHKのプッシュに触発され(TVなくてドラマは見れないし)、読...
<開明期を迎えた小国“日本”とそこに生きた人々の、“独り立ち”の物語> 上記のように評しても間違いはないはず。 司馬遼太郎は昔よく読んでいましたが、この本は全八巻ということでなかなか手がでませんでした。 んで昨今のNHKのプッシュに触発され(TVなくてドラマは見れないし)、読みだしました。 思えば、外圧に押され、その外圧に負けないために明治維新がおこり、 初めて国民国家というものを経験し、富国強兵に励み、 欧米列強の一角であるロシアと戦いそれに勝つ・・・ わずか30年程度の期間でやりとげたことは奇跡といってもよいものです。 しかし司馬遼太郎はそれを奇跡と認めながらも、人々の、弱者の、日本人の力と描いています。 最初の青年期では、能力さえあれば何者にもなれる明治という時代にあって、 秋山兄弟と正岡子規の青春に胸を熱くさせられ、 日露戦争では、山本権兵衛や大山巌に指導者・経営者の偉大さを、 評価が分かれる乃木や、児玉とともに戦った旅順・奉天等の会戦では 締め付けられるような痛みと悲しみを、 そして東郷をして歴史に名を残さしめた日本海海戦では、緊張と高揚と喪失感を・・・ これだけでは言い表せないほど、たくさんのものをこの本からいただきました。 歴史は断片断片で見るのではなく、一つの文脈としてみるべきなのでしょう。 だからこそ、先にあげた人だけでなく、その他たくさんの人々が、 “日本”を創ってきた・・・このことを感じずにはいられません。 全8巻という大長編に没頭できたこの時間を本当に幸せに思います。
Posted by
司馬さんの代表作。 実は学生の頃、2度全巻読破を試みているものの、半分あたりで躓いてしまい、今回3度目の挑戦。笑 特に進行を妨げる要因が、その膨大な研究から生まれる「余談ながら」という件である。例えば。 秋山好古が、日本の騎兵が従来のフランス式からドイツ式に切り替えられようとし...
司馬さんの代表作。 実は学生の頃、2度全巻読破を試みているものの、半分あたりで躓いてしまい、今回3度目の挑戦。笑 特に進行を妨げる要因が、その膨大な研究から生まれる「余談ながら」という件である。例えば。 秋山好古が、日本の騎兵が従来のフランス式からドイツ式に切り替えられようとしている時、その危険性について、時の陸軍総帥、山県有朋に進言する場面が出てくるが、「余談ながら」、山県というのは実に運の良い人で、軍人としての才能がそれほどでもないにも関わらず、同郷の大村益二郎という秀才が維新で死んだことにより脚光を浴び、その山県がドイツに行った明治22年、「余談ながら」、その頃ドイツ語の通訳は日本に何人もおらず、その一人が司馬凌海といい、そもそもこの人は、長崎で初めての官立の洋医学塾のただ一人の門人であった松本良順が彼の才能を知っていて佐渡から呼び寄せた人物であり、「余談ながら」、この人はめっちゃ語学ができてドイツ人からも「あなたは何年ドイツに居たんデスカー?」と聞かれたという逸話が残る。 長い!!!とにかく長い。 もう誰が誰だか分からない。 しかしそれほどの大研究の末にどこを切り取るかを考えて文章にまとめあげているのだから天晴れ。 今後もその特徴はより濃厚になっていくが、根負けせず読んでいきたい。特に司馬さんの本の中でも膨大な巻数を誇る本作は、「小説としてどのような話か」ではなく「司馬さんは自分の研究をどのように編集したか」という目線で見た方がわかる気がする。 あくまで歴史小説なので、研究に下支えされつつ司馬さんの主観も入っていることは忘れないようにしつつ、ドラマチックな司馬さんワールドを堪能しようと思う。
Posted by
昔から歴史苦手で、幕末も明治維新も戦争の順番もぐちゃぐちゃで知識ゼロだけど、小説なら楽しく読めるかなと、最近司馬遼太郎に挑戦中。これまで、燃えよ剣と関ヶ原を読了。龍馬がゆくは何度か挑戦するも5巻くらいで挫折中。全8巻の坂の上の雲は最後まで読み通せるといいな。1巻はひとまず3人の登...
昔から歴史苦手で、幕末も明治維新も戦争の順番もぐちゃぐちゃで知識ゼロだけど、小説なら楽しく読めるかなと、最近司馬遼太郎に挑戦中。これまで、燃えよ剣と関ヶ原を読了。龍馬がゆくは何度か挑戦するも5巻くらいで挫折中。全8巻の坂の上の雲は最後まで読み通せるといいな。1巻はひとまず3人の登場人物の青春時代。外国の話が出てくるとちょっとややこしくなるけど、今のところおもしろく読めそう。
Posted by
司馬作品でも維新期は全く読んでなかった。息子の松山赴任を期に手に取った。 秋山兄弟と子規の青春記は楽しく読んだが、3人から離れ明治期の軍人が多数出てくるとトーンダウン。子規の死をきっかけに脱落。
Posted by
この辺りの歴史に詳しくないので、理解度には自信がないですが、三人の主人公の歩みが描かれているのがおもしろく、三者三様の個性がいいです。続きが気になります。
Posted by
人生3度めの「坂の上の雲」。「まことに小さの国が、開化期をむかえようとしている。」で始まる、司馬遼太郎氏の代表作の一つ。明治維新をとげ、近代国家の仲間入りをした日本は、息せき切って先進国に追いつこうとしていた。四国松山出身の3人の男達の物語。
Posted by
190523 正岡子規、秋山好古、秋山真之 エネルギーに満ちている 死ぬことに覚悟を決めている人たち。 覚悟を決められる、そんな人になりたい。 親と離れているが、家族との暮らせてることが幸せだと思う。
Posted by
ノブレスオブリージュという言葉を思い出します。高貴な地位には社会的な責任が伴う、という言葉。私は無理難題ばかりを押し付けられて腐っている後輩に、この言葉と本書を薦めるようにしています。 このとき私が伝えたいノブレスオブリージュとは「出来る子は頑張らなあかん」ということです。君...
ノブレスオブリージュという言葉を思い出します。高貴な地位には社会的な責任が伴う、という言葉。私は無理難題ばかりを押し付けられて腐っている後輩に、この言葉と本書を薦めるようにしています。 このとき私が伝えたいノブレスオブリージュとは「出来る子は頑張らなあかん」ということです。君は仕事が下手な人たちと違って努力は成果として認められるし、周囲の信頼を得るし、尊敬すらされる人になれる。眼先の苦労や不公平感だけにとらわれてはダメよ、頑張って褒められる恵まれた人が世にどれだけいるのか、と。そして君ならできると信じて託されたその責任を全力で果たそうと努めるんだぞと。 真之は人から褒められるからなんてことは微塵も考えていなかったかもしれません。身命を賭して、学び、考え、周囲を動かし、備え、遂には日露戦争日本海海戦に参謀として臨んだ秋山真之。そして数々の困難と逆風を乗り越え見事に日本の未来がかかったその重責を果たした彼は、ただただ自分がやらねば誰ができるのかという思いだったのかもしれません。でも褒められ、認められることの喜びも込みでもいいから、真之のように社会や組織に献身することの尊さや偉大さを知ってもらいたい。 時代のうねりや時代の空気感まで伝わってくるような緻密な描写、イキイキと浮かび上がる熱い登場人物たち。後半になるにつれどんどん引き込まれていく展開の妙。何度でも読みたくなる名作です。 根底に流れる戦争の愚かさや失敗の本質をえぐろうとする作者の意図が込められているそうです。史実を元にしたフィクションであることを忘れてはいけません。 何度でも読みたくなる名作です。是非。 この本で熱くなった方には司馬先生の「峠」もお薦めです。
Posted by