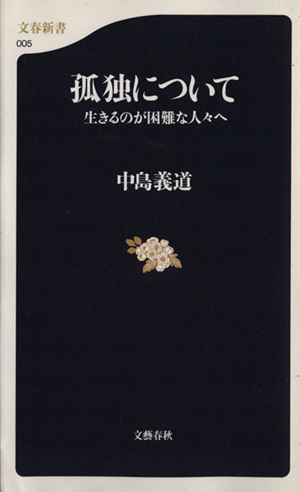孤独について の商品レビュー
父母の家柄についてや…
父母の家柄についてや、少しも馴染めなかった小学生時代から、とても長い大学生活、ウィーン時代、五十歳になるまでの著者自身の人生の葛藤・苦悩を見つめなおし、孤独の美学を追求してます。著者のファンなので、とても興味深かった。でも、どうしてそんなに死が怖いのかは、やっぱりさっぱりわかりま...
父母の家柄についてや、少しも馴染めなかった小学生時代から、とても長い大学生活、ウィーン時代、五十歳になるまでの著者自身の人生の葛藤・苦悩を見つめなおし、孤独の美学を追求してます。著者のファンなので、とても興味深かった。でも、どうしてそんなに死が怖いのかは、やっぱりさっぱりわかりません。
文庫OFF
孤独について時々考…
孤独について時々考える。一人でいることが孤独なのではない 周りに人がいる状態でだれとも心が触れ合えない状態が孤独なのだ。いわゆる指南書とは一味違って読みやすいし興味深い
文庫OFF
誰にも看取られず、後悔しながら絶望しながら死んでゆきたい。著者の考えはマジョリティではないのかもしれない。しかし、この本を読んで必ず共鳴する人もいるはずだ。偽りがなく泥臭いこの本は、少しヒントになったかもしれない。
Posted by
まさしく、わかる!この感覚! わかりながらも、また、受け取り方や、生き方が異なるのは、すべての脳がオリジナルだから。 悩み苦しんでいた学生時代の私にプレゼントしてあげたい。ま、でも、助けにはならなかっただろうけど。(笑)
Posted by
哲学者の著者が、これまでの人生における人びととのかかわりを振り返りながら、「孤独」を求めるようになった経緯を語った本です。 権威主義的な両親や、「子どもらしく」振る舞うことができず疎外感を味わった少年時代、迷走をくり返した大学時代、そして教授のイジメに耐えた助手時代のエピソード...
哲学者の著者が、これまでの人生における人びととのかかわりを振り返りながら、「孤独」を求めるようになった経緯を語った本です。 権威主義的な両親や、「子どもらしく」振る舞うことができず疎外感を味わった少年時代、迷走をくり返した大学時代、そして教授のイジメに耐えた助手時代のエピソードなど、著者の自伝的な記述に多くのページが割かれており、「孤独」そのものについての考察は多くありません。しかしながら、他人に興味を抱かず、徹底的に自分自身にのみ関心を向け続けることが「孤独」であるとするならば、こうした記述になるのはなかば必然的なのかもしれない、という気もします。
Posted by
初めはこれが新書なのか疑ってしまった。文学かなんかじゃないのか。 ただ読み物として大変面白いことは確か。 最後は見事な帰結を見せた。 哲学者の著者は、読者に救いを与える代わりに、自分の頭でよく考えなさい、悩みなさい、観察しなさい、と至極真っ当な言葉を突きつける。
Posted by
もうすぐ死んでしまうあなたが、必死に日常的な問題にかかずらっていること、それはたぶん最もむなしい生き方である。「死」を目前に控えて震えている死刑囚よりも虚しい生き方である。キルケg-ルとともに言えば、日常に絶望していないことこそ絶望的なのだ。 あなたの孤独は、あなた自身が選び取...
もうすぐ死んでしまうあなたが、必死に日常的な問題にかかずらっていること、それはたぶん最もむなしい生き方である。「死」を目前に控えて震えている死刑囚よりも虚しい生き方である。キルケg-ルとともに言えば、日常に絶望していないことこそ絶望的なのだ。 あなたの孤独は、あなた自身が選び取ったものだということを認めなさい。そして、その(表面的な)不幸を利用し尽くしなさい。それは、とても「よい」状況になり得ることを信じなさい。 自分が選び取ったものがたとえ自分に苦痛を与えるとしても、耐えられるのである。自分が選び取った大学、自分が選び取った結婚、自分が選び取った職業は「肯定する」ほかないではないか。 孤独になり不幸になることは、たいそう辛いからこそ貴重だといいたいのだ。その辛さがあなたの目を鍛えてくれる。日ごろ、つい見過ごしてしまう「人生の黒々とした根っこ」がはっきり見えてくる。 私は、あらゆる人にとって孤独が一番だといいたいわけではない。そうではなく、独りでいることが好きな人も決して人間的欠陥ではなく、それもまたいいのではないかと言いたいだけである。そうした人もまた豊かな人生を送れる。それにはー変な言い方だがー孤独を固有の「かたちあるもの」にしていく、それ相応の努力が必要であるといいたいのだ。 読者諸君は、自分の幼年時代・少年時代をとくと反省してみる必要がある。そして、そこに真性の不幸を見出したら、その不幸をどこまでもどこまでも思い出すこと。気分の悪くなるまで追求すること。そうすると、そこに自分の生きる方向が見えてくるはずだ。 哲学研究者になれないとしたら、いったい自分は何になったらいいのだろう?とにかく生きなければならない。そのためには職業を選ばねばならない。 「なぜ哲学をやめて法学部に入るのですか?」「因果関係の理論や責任論など、哲学の抽象的な理論ではなくもっと具体的に実際の社会に即して学びたいからです。」私は嘘を言った。そして合格した。 孤独を楽しみそれを活用するための絶対必要条件は次の二つだけである。第一の条件は、あなたが他人とうまくやっていけないこと。他人の一人ひとりが嫌いなのではないが、他人と一緒にいても自由に心を開くことができず、楽しくない。そして、とにかくくたびれる。すぐに独りになりたいと思ってしまう。そして第二の条件はあなたが真に不幸であること(であったこと)。しかも、その不幸は社会を改良すればあるいは環境を変えれば解消してしまうような類の不幸ではなく、あなたのうちに深く巣くっているいるような不幸であること。あえて言い切ってしまえば、「自分が嫌い」であるという不幸であること。 あなたが、思い出すのも鳥肌が立つほどのつらい体験があるとしたら、自分の最大の欠点を自覚しているとしたら、目をそむけたくなるほど厭な自分の一面を知っているとしたら、それから目をそらさず、それらをとことん観察しなさい。そして、それらを大切に「育てなさい」。そこに必ず、「固有の自分のもの」へのヒントが見えてくるはずである。あるいは、どんなに努力しても効果のない時にこそ、私はそこにヒントを読み取る。他人から軽蔑され嘲笑された時にこそ、私はそこにヒントを読み取る。 もしあなたが孤独に死ぬことは恐ろしいと躊躇するなら、あなたはカインではない。あなたには人々に囲まれてにぎやかに生き、人々に囲まれて「安心して」死ぬほうがふさわしい。実は、あなたには孤独は似合わないかもしれないのだ。 ウィーンのスィーベリング。 曾野綾子「仮の宿」 大人たちはなぜ、青年たちに、この世は信じがたいほど思いのままにはならないところなのだということを、きっちりと教え込まないのでしょうか。そして人間は、誰も、そのような不合理な生涯にじっと耐えてーつまりいい加減にー生きているものだということを。なぜ、それほど絶望的な現世に、私が自殺もせずに生きているかというと、第一は(省略)、第二に、(省略)第三に、ろくでもない、絶望的な所だということが確定してしまうと、私のようなヘソマガリはそこでやっと安心して、あたりを見廻すのです。そして、なんだかよくはわからないのですが、「ウン、それにしては面白いこともある」と呟いてみてもいい心境になります。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
冒頭でびっくり! ファンに会いたいと言われても「僕は会いたくないです」と言い放つ。なるべく関わりを持ちたくないのだと言う。 変わった方だなぁと思いました。著者の言いたいこともよく分かりました。自分が置かれている状況を受け入れる、諦めるのではなくそのまま認め、そこからどうするかは自分次第ということなのかなぁと思いました。著者の生い立ちも、恵まれているようでそうでもないのだなぁと、むしろ期待に応えないといけないというのはキツいことかもしれません。どんな人でもそれぞれ違った背景をもって生きていると実感した一冊。
Posted by
著者は自ら認めている通り、一般社会からみれば病的なほどの自己中心主義者で人間嫌いだ。 そしてこの本は、同じく不器用で生きる事が苦手な人々に対する著者からの「血のメッセージ」である。 著者は社会不適合者である自分が歩んできた苦闘の歴史を、まさに「血の言葉」によって自らの手で暴き出...
著者は自ら認めている通り、一般社会からみれば病的なほどの自己中心主義者で人間嫌いだ。 そしてこの本は、同じく不器用で生きる事が苦手な人々に対する著者からの「血のメッセージ」である。 著者は社会不適合者である自分が歩んできた苦闘の歴史を、まさに「血の言葉」によって自らの手で暴き出している。その内容は苛烈を極め、これまで出会ってきた知人や仕事関係者のみならず、親類縁者でさえ批判と糾弾の対象とし、傷付ける事も辞さない。 そして「明るく希望を持って生きよう」とする人達を「鈍感で欺瞞的な社会の多数派」と断じ、この多数派が支配する社会からの決別を自ら選択する道を示している。 著者の虚飾や欺瞞を排した剥き出しの言葉に身がすくむ思いがした。この本はきっと僕みたいな世俗や因習にまみれた人間が読むべきものではないのかもしれない。 しかしその一方で、自分は死という逃れられない人生の命題に真正面から向き合っているのか?もっと言えば真の意味で生きていると胸を張って言えるのか?と問い詰められた気がする。
Posted by
孤独でも良いのだという一押しをしてもらえた。 孤独はとても辛く、苦しい。 でも孤独は間違いではない。 それを知ってホッとした。 著者自身の人生譚と、そこから導き出される孤独について。
Posted by