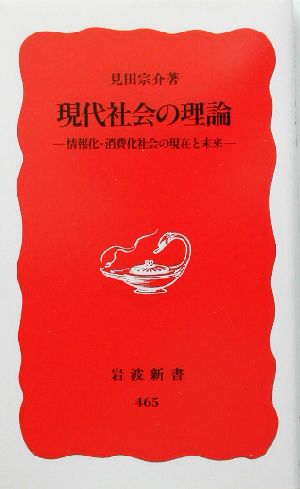現代社会の理論 の商品レビュー
メディアの真の意義と…
メディアの真の意義とは!! 現代なので資料も豊富です!!!
文庫OFF
私たちが抱えている社…
私たちが抱えている社会的不安を和らげるものにしたいですね。
文庫OFF
文章が難解で読みにくかった…。現代文の入試問題に使われていそう。。 同じ筆者のまなざしの地獄という本を読んだので、面白そうだと思ったが、この本はとにかく読みにくかった。 内容としては、冷戦終結後、この「情報化・消費化社会」がどうなるか、どうあるべきかを論評した本と解釈した。...
文章が難解で読みにくかった…。現代文の入試問題に使われていそう。。 同じ筆者のまなざしの地獄という本を読んだので、面白そうだと思ったが、この本はとにかく読みにくかった。 内容としては、冷戦終結後、この「情報化・消費化社会」がどうなるか、どうあるべきかを論評した本と解釈した。 筆者は、あくまでこの情報化・消費化社会の原理的な部分を肯定しつつ、環境問題や南北問題に代表されるような他者収奪的な問題をどう解決するかを論評している。 重要な観点が、原義としての消費=生の充溢と歓喜に直接的な享受にに立ち返ることと、「情報化」のメリット(データによるモニタリングと社会的費用を製品の中に組み込むこと、そして製品情報を組み込むことで資源を凝縮して使用すること)を最大限活かして、資源消費を抑えること。 書かれた時代が1996年と、ずいぶん違うから、なんとも言えないが、 ・このことを言うのに、いくらなんでも難解すぎやしないか?(もちろんこの筆者が偉大な社会学者ということは知っているので、おそらくこの本の書き方が私には合わなかっただけだと思う) ・果たしてこの抽象的な理論でこの社会は本当に持続可能になるのか?理想的やすぎないか?(個人的には、情報化とか、いわゆるITが社会を変えるという理論には果てしなく懐疑的。あくまで目の前から見えなくなっているだけで、裏ではデータセンターやらで果てしなく資源を消費しているのだから。) という観点で、なんとなく同意しかねる。 山崎正和の「柔らかい個人主義の誕生」でも、同じように消費社会への対峙の仕方が書かれていた。そこでは、自我の確立のために、モノを消費するだけの消費から、消費の過程を楽しむ消費が提起されていた。要するに同じようなことを言っているのだろうなと思ったが、なんとなくこっちの方が自分ごととして考えられるし、わかりやすかった。あと同時代に書かれた本だが、やはり「消費」をテーマにしていることから、当時のモノの消費はとんでもなかったんだろうな、という感覚をいだいた。
Posted by
情報化/消費化社会の限界(資源の有限性、廃棄の有限性)の克服について。計画経済への転向では無く、自由主義を維持しつつ、限界を可視化(=情報化の上手い運用)により、マインドを変える。
Posted by
冷戦終結後に書かれた「情報/消費社会」についての本。 「情報/消費社会」を肯定的に捉えつつ、そのままでは資源、環境、貧困などの「限界問題」が解決されないことから、その「転回」を主張している。 その主張は現代のSDGsに極めて近いことは、以下の引用から分かる。 "転...
冷戦終結後に書かれた「情報/消費社会」についての本。 「情報/消費社会」を肯定的に捉えつつ、そのままでは資源、環境、貧困などの「限界問題」が解決されないことから、その「転回」を主張している。 その主張は現代のSDGsに極めて近いことは、以下の引用から分かる。 "転義としての「消費社会」についてはどうか? 転義としての消費社会(商品の大衆的な消費の社会)もまた、それが現在あるような形ではなく、その可能性について考えられるなら、「限界問題」をのりこえることがあるだろうという見とおしを、私はもっている。けれども、このためには「消費社会」が、原義としての<消費>というコンセプトを軸足として、転回されることが必要だろう。<消費>をその原義において豊かなものとしてゆくための、方法としての市場システムを、破綻なく活性化しつづけるための形式として、「方法としての消費社会」というべきものを、構想しなければならないだろう。このことは「消費社会」が、資源/環境の臨界問題、域外/域内の貧困問題を不可避の影として帰結する現在地の構造からの、解き放たれた展開を獲得するために、基底的に必要な条件であるように思われる。"
Posted by
前半は現在の情報化・消費化社会の諸問題を挙げており、後半は前半で挙げた問題の解決の糸口を提示している。 内容もさることながら、文章も難解で一度では理解しきれない部分が多かった。 現代社会(の情報化・消費化)という面について、過去と現在、表と裏、内部と外部など比較や対立を持ちいた表...
前半は現在の情報化・消費化社会の諸問題を挙げており、後半は前半で挙げた問題の解決の糸口を提示している。 内容もさることながら、文章も難解で一度では理解しきれない部分が多かった。 現代社会(の情報化・消費化)という面について、過去と現在、表と裏、内部と外部など比較や対立を持ちいた表現が多いことが特徴で、読み間違えれば混乱してしまうが、正しく読めれば著者の意図を十分に理解するに足る文章になっていると感じた。
Posted by
予言の書みたいだ。20年以上前にこの本が書かれていることに驚愕する。 資本主義がこれまでぶつかってきた限界と課題 ① 需要の限界 → 不況と戦争 ・モノが人々の手に行き渡り、「必要」を根底とする需要が無くなる。市場が飽和するという限界。 ・モノが売れなくなることで不況が発生し、...
予言の書みたいだ。20年以上前にこの本が書かれていることに驚愕する。 資本主義がこれまでぶつかってきた限界と課題 ① 需要の限界 → 不況と戦争 ・モノが人々の手に行き渡り、「必要」を根底とする需要が無くなる。市場が飽和するという限界。 ・モノが売れなくなることで不況が発生し、不況を乗り越える(需要を創出する)ために、戦争が発生するという課題 ★ 需要の限界は、需要創出を「戦争」以外の方法で乗り越えること、で克服された。 ・ケインズ:政府によって、有効需要を作り出す(公共事業とか) ・情報(デザイン・広告・モード): フォードとGMの例で説明する。 - フォートは、「便利な」車を、単一モデルで、生産ラインを徹底的に合理化・効率化することで、低価格で販売し、市場を席巻した(=市場を飽和させる) - 一方GMは、車を「デザイン」で売った。「魅力的」なデザインの車を売り、そして定期的な「モデルチェンジ」を行い「新しい」車を売っていった。デザインには、「正解」がないため、需要には、理論上限界がない(ブランド車を複数所有する金持ちとかをイメージするとわかりやすいかと。便利さだけなら一台で良い。「魅力性」を王ならば、理論上需要/欲望は底なしとなる)。そして定期的な「モデルチェンジ」を行うことで、既存の車はどんどん古いものとなり、新たな「新しい」車への需要を創出する。デザインとモデルチェンジを人々に広めるために、需要を喚起するために、広告が活用される。 モードに関してはMEMO モードのリズムは以下の二つによって構成される ・消耗のリズム(u) ・購買のリズム(a) モードは、a/u。購買が消耗を上回っている時、モードが存在する。 購買のリズムが消耗のリズムを超えていればいるほど、モードの力が強い。 モデルチェンジと<モードの理論>が消費社会を駆動するメカニズム。 モードは、広告を通じて、自己否定することで、回転を早くしていく。 ② 資源と環境の限界 → 資源の枯渇と環境の破壊と格差 ・「情報」によって、需要が無限になったことで、大量生産→大量消費のサイクルが回る。 ・「大量採取→(大量生産→大量消費)→大量廃棄」という限界づけられたシステムであり、地球の「資源」と「環境」という外部的な制約にぶつかる。 「資源」:エネルギー、鉱物、一次産品、労働力など 「環境」:地球環境 ★ 資源の枯渇と環境の破壊と格差は、大量採取・大量廃棄しない、システムを構築することで、克服される。 ・本書では、<消費>すなわち「存在それ自体の幸福」的な話になっている。 ▶︎ 個人的には、情報(エンタメ)を消費する社会になると考えている。今後は、基本的に「必要」がテクノロジーによって満たされ始めるので、本書に即していうならば、情報(エンタメ)商品としての「消費」する社会になるかと。 <消費>とエンタメ「消費」がメインとなる社会になると思う。 Youtuber、「好きなことして生きる」、生き様コンテンツ、信用経済、諸々これに関連している。見田さん的に言えば、これらは「ソフト」な側面に属するのかと。 最高に面白い本。
Posted by
「貧困」の定義について考えさせられた。貧困とは文字通り貧乏ということではあるが、けれどもそれは、GNPが低いイコール貧困という単純な図式ではないということだ。 GNPを必要とするシステムの内に投げ込まれてしまった上で、GNPが低いから貧困になってしまうのである。実際、お金を必要...
「貧困」の定義について考えさせられた。貧困とは文字通り貧乏ということではあるが、けれどもそれは、GNPが低いイコール貧困という単純な図式ではないということだ。 GNPを必要とするシステムの内に投げ込まれてしまった上で、GNPが低いから貧困になってしまうのである。実際、お金を必要としない村で幸せに暮らしている人々はたくさんいる。人の幸不幸がGNPでは決められないこと、その人が生活している社会のありかたと、各々の社会に敬意を払うべきなのではないだろうか。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
再読。現代が消費化/情報化社会であるとして、その欠陥点が〈消費〉の概念を社会全体が正しく捉えられていないこととして指摘、その解決を情報化と〈生の直接的な充溢と歓喜〉へと消費の概念を見詰め直すことに見出している。 以下、昔書いたまとめを。 ------ <一章要点> ・資本主義という一つのシステムが、必ずしも軍事需要に依存するという事なしに、決定的な恐慌を回避し反映を持続する形式を見出したという事、この新しい形式として、「消費社会化」という現象をまず把握しておく事が出来るという事。 ・自己否定、自己転回 ・デザインと広告とクレジットを柱とする、ソフトなより包括的な戦略、「消費者の感情と動機と欲望に敏感な」システム ・消費社会としての資本制システムが存立する事の前提は、(この労働の自由な形式に加えて、)<欲望の自由な形式>である。 ・<欲望の抽象化された形式>、<労働の抽象化された形式> ・古典的な資本制システムの矛盾——需要の有限性と供給能力の無限拡大する運動との間の矛盾、これが「恐慌」という形で顕在化する。 ・上記の矛盾を、資本の基本システム自体による需要の無限の自己創出という仕方で解決し、乗り越えてしまう形式が<情報化/消費化社会>。 ・自己の運動の自由を保証する空間としての市場自体を、自ら創出する資本主義。 ・<情報化/消費社会化>こそ、初めての純粋な資本主義である。 ・誘われたままでいる事を享受し、あるいは寧ろ、よく誘惑するものであるか否を、鋭敏な批判の基準として選択する対処の仕方は、1970年代以降の世代達にとっては、平常の基礎的な情報消費社会の内部を生きる事の技法となっている。 ・<大衆が消費する事は、それが資本の増殖過程の一環をなすからといって、それが大衆自身の喜びである事に変わりない> ・この社会の固有の「楽しさ」と「魅力性」という経験の現象、それがこのシステムの存立の機制自体の不可欠の契機である <二章要点> ・「自動的な廃滅化という現代の傾向」 ・上記の様に呼ばれているのは、「モードの理論」と同じ戦略によるものである。つまり、<消費の為の消費>を通しての繁栄というシステムの基本の論理そのもの。 ・根源的独占は、商品システムというものが、必要を充足する為の他の方法を排除してしまう事を通して、生活の仕方を選択する自由を否定する。それは、自然的な他の共同体的な選択肢を解体してしまう事を通して、商品システムへの依存を強制する。 ・農村と都市の構造から家族の形態に至る、日本社会の基本的な構造が変容したのは、1960年代を中心とする、「高度経済成長期」である。日本に於ける「現代社会」の創成期である。 ・現在の<情報化/消費化社会>が、自分で自分の無限定の成長と繁栄の為に設定する無限空間——人間達の現実的な必要を離陸する<欲望の抽象化された形式>、あるいは<欲望のデカルト空間>とは、このような<消費の為の消費>、<構造のテレオノミー的な転倒>の、純化され、洗練され、完成された形式である。 ・ 生産の最初の始点と、消費の最後の末端で、この惑星とその気圏との、「自然」の資源と環境の与件に依存し、その許容する範囲に限定されてしか存立しえない。 ・ 現代の情報化/消費化社会は、資本制システムの「自己準拠化」の形式として成立した。 ・ 人間達の「必要」に制約されない無限定の消費に向かう欲望を、情報を通して自ら再生産する。 -------- <一章> 現代社会は資本主義社会である。世界恐慌等を経験し、決定的な恐慌を回避し持続的な繁栄を実現する為に<情報化/消費化>した。というのも、<情報化/消費化>は「消費者の感情と動機と欲望に敏感」になる事で、需要の無限の自己創出を可能にしたからである。そして、このシステムが成立するのは、<大衆が消費する事は、それが資本の増殖過程の一環をなすからといって、それが大衆自身の喜びである事に変わりない>事とこの社会の固有の「楽しさ」と「魅力性」という経験の現象によって裏付けられている。 <二章> 一章で先述されている、『需要の無限の自己創出』とは、必要を充足する為の他の方法を排除してしまう事を通して、生活の仕方を選択する自由を否定する根源的独占と、人間達の「必要」に制約されない無限定の消費に向かう欲望を、情報を通して自ら再生産する事で可能となった。また、先述の日本に於ける『現代社会化』は農村と都市の構造から家族の形態に至る、日本社会の基本的な構造が変容したのは、1960年代を中心とする、「高度経済成長期」に起こった。
Posted by
三章 南の貧困/北の貧困 すばらし。この人の講義を受けた人は幸せだな。 一つ残念なのは文章が難解で万人受けではないこと。全集、まだ読めていません。
Posted by