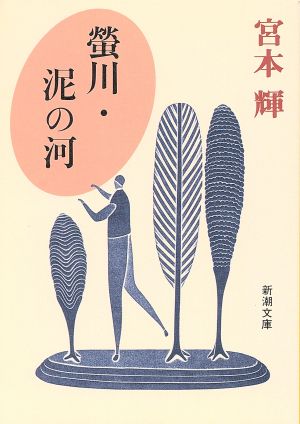蛍川・泥の河 の商品レビュー
情報科教員MTのBlog (『螢川・泥の河』を読了!!) https://willpwr.blog.jp/archives/51316955.html
Posted by
ひととの関係とか、その美しさとか汚さとかを含めて、とても上質なやわらかい文章。 泥の川のおじいさんはどこにいってしまったのだろうか。
Posted by
「信雄が火を消そうとして畳に四つん這いになったとき、眠っていたはずの銀子がゆっくり起きあがった。そして燃えている蟹の足をそう慌てるでもなくつまみあげると、ひとつひとつ川に投げ捨てていった。」 正統派。イマドキの小説とは違う。 読み始めたらすぐに世界に引き込まれて、 気が付いたら...
「信雄が火を消そうとして畳に四つん這いになったとき、眠っていたはずの銀子がゆっくり起きあがった。そして燃えている蟹の足をそう慌てるでもなくつまみあげると、ひとつひとつ川に投げ捨てていった。」 正統派。イマドキの小説とは違う。 読み始めたらすぐに世界に引き込まれて、 気が付いたら半分読み終わっていた。 読みながら、 小説の中のねっとりした空気が絡み付いてくる気がした。 不思議とすんなり小説の世界が目に浮かんでくる。 船の家といい、銀子の母親といい、なぜだかリアル。 見てきたように情景が思い浮かぶ。 「物凄くオススメ!」と人に熱く奨めるというよりは、 「興味があれば読んでみて、損はしないから」という感じ。 大絶賛はしないけど、長く心に残る作品だろうなぁと思った。 冒頭の一文に何故だかゾクッとした。
Posted by
何度読んでもジーンと胸に響きます☆ と同時に頭をガツンとやられた感じは否めません★ 作家ってモノスゴイ職業ですね。
Posted by
「泥の河」 太宰治賞受賞作品 P.83 大きな茶碗にランプ用の油を注ぐと、喜一はその中に蟹を浸した。 「こいつら、腹いっぱい油を飲みよるで。」 「どないするのん?」 「苦しがって、油の泡を吹きよるんや。」 喜一は声を忍ばせてそう言うと、船べりに蟹を並べ、火をつけた。幾つかの青い...
「泥の河」 太宰治賞受賞作品 P.83 大きな茶碗にランプ用の油を注ぐと、喜一はその中に蟹を浸した。 「こいつら、腹いっぱい油を飲みよるで。」 「どないするのん?」 「苦しがって、油の泡を吹きよるんや。」 喜一は声を忍ばせてそう言うと、船べりに蟹を並べ、火をつけた。幾つかの青い火の塊が船べりに散った。 動かずに燃え尽きて行く蟹もあれば、火柱をあげて這いまわる蟹もいた。悪臭を孕んだ青い小さな焔が、何やら奇怪な音をたてて蟹の体から放たれていた。燃え尽きるとき、細かい火花が蟹の中から弾け飛んだ。それは地面に落ちた線香花火の雫に似ていた。 この小説の舞台は、昭和三十年の大阪。まあ馬車引きが残っており、水上生活者もいた。高度経済成長が始まる直前の時代、昭和十年代の生活風俗が残っていた最後の時期である。 お化け鯉が何を暗示しているのかとか、深いことは僕には難しくてわからなかった。だけど、わからないからこそ、この人がどうしてこの話を書いたのかを思いきって考えてみることにした。この話にはやっぱり廓舟が欠かせないのだろう。揺れ動く家庭環境や住環境、環境によって変わる人間には違いが生まれてくる。それを、その気持をうまく言葉で表せない子供を通して(言葉で表さない分、そこにお化け鯉に意味があるのかも)、表現したかったのかな。 この話には、どこか鳥肌が立つような怖さがあった。 「蛍川」 芥川賞受賞作品 P.179 せせらぎの響きが左側からだんだん近づいてきて、それに沿って道も左手に曲がっていた。その道を曲がりきり、月光がはじけ散る川面を眼下に見た瞬間、四人は声も立てずその場に金縛りになった。何万何十万もの螢火が、川のふちで静かにうねっていた。そしてそれは、四人がそれぞれの心に描いていた華麗なおとぎ絵ではなかったのである。 螢の大群は、滝壺の底に寂寞と舞う微生物の屍のように、はかりしれない沈黙と死臭を孕んで光の澱と化し、天空へ天空へと光彩をぼかしながら冷たい火の粉状になって舞い上がっていた。 こちらの話はお酒を飲みながら、少しふわふわしながら読んでたから、内容を深くは覚えていない。だけど、何万何十万もの螢火が現われたときの情景の美しさったら筆舌しがたいものがある。美しい文章というのはこういうものなのかと、今、引用のために文章を写していて気付いた。 こんな名作を二つも読めるなんて、得した気分です。
Posted by
・泥の河 「……おもしろいことて、なに?」 この最後の喜一の蟹遊びの場面のインパクトったら。 子どもの純粋・無垢ゆえの残酷さ・大胆さがそれぞれの場面を生かすように描かれているけれども、ラストは特に顕著。燃え上がる蟹、育ちの違いから喜一の感性に違和感を感じ、助けを求めるように見遣っ...
・泥の河 「……おもしろいことて、なに?」 この最後の喜一の蟹遊びの場面のインパクトったら。 子どもの純粋・無垢ゆえの残酷さ・大胆さがそれぞれの場面を生かすように描かれているけれども、ラストは特に顕著。燃え上がる蟹、育ちの違いから喜一の感性に違和感を感じ、助けを求めるように見遣った先では知らない男とまぐわう喜一の母親。格差ってこういうことか。子どもだから超えられるその境、見てしまった。 ・螢川 竜夫が主人公なのに、母親・千代がとても印象的でした。それまでのすべてを失ってでも家を出たかったという過去。蛍の大群に逢えるか逢えないか、それに未来を託そうという小さな決意。 竜夫に関しては、関根くんの死、英子への恋。なんといってもやはり、ラストが印象的。英子の体から蛍が生まれているような…夜の深い闇に浮かび上がる、少女にまとう無数の蛍。なんて素敵な光景。
Posted by
北陸富山を舞台に父の死、友の事故、淡い初恋を描いている。ラストシーンで「いたち川」のはるか上流での蛍の大群は美しくも、哀切で深い情感を描き出している。
Posted by
季節感溢れる情景描写が綺麗。 昭和中期の貧困層の生活力みたいなものが克明に写しだされていて、方言がそれに一役買っている感じ。レポートはこれで書けばよかったな。 星空の下で入る露天風呂でふと出る「良い湯だなぁ。」という一声とこれを読み終わったあとに出る「良い本だなぁ。」はな...
季節感溢れる情景描写が綺麗。 昭和中期の貧困層の生活力みたいなものが克明に写しだされていて、方言がそれに一役買っている感じ。レポートはこれで書けばよかったな。 星空の下で入る露天風呂でふと出る「良い湯だなぁ。」という一声とこれを読み終わったあとに出る「良い本だなぁ。」はなんか似てる。 今、一番薦めたい作家。
Posted by
主人公が見て、触れて、聞いているものが肌に直接伝わってくるような語られ方だと思う。 淡々と描写されているようなところが、かえって想像力を掻き立てて何か空恐ろしいことのように感じさせる。 ざわざわと胸に何かが芽吹き、読まなければならないと迫られるように最後まで読みきった。 哀しくて...
主人公が見て、触れて、聞いているものが肌に直接伝わってくるような語られ方だと思う。 淡々と描写されているようなところが、かえって想像力を掻き立てて何か空恐ろしいことのように感じさせる。 ざわざわと胸に何かが芽吹き、読まなければならないと迫られるように最後まで読みきった。 哀しくて美しい。
Posted by
どちらの話もすき。 『蛍川』の蛍をやっと見つけたときの文章は、思わず写してしまったほど、感動した。 美文ってこういうのをいうんだなあと、大学1年の頃に読んで思った。
Posted by