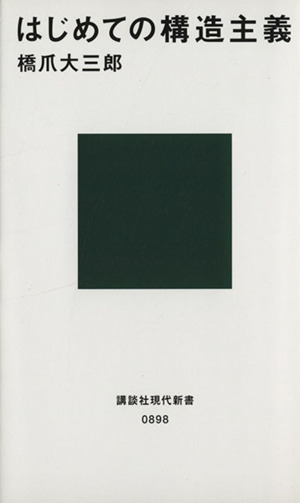はじめての構造主義 の商品レビュー
構造主義がどれくらい近代思想にとって破壊的だったかよく分かる本。 哲学書の類いはほぼ読んだことが無かったが、詰まることなく読み進められた。分かりやすい。
Posted by
レヴィ・ストロースの人類学を見ていけば、最近読んだ本たちによくでてきた、黒人奴隷の問題の出口がわかってくるのかもしれないという予感の元、読み進めていきました。まあ、構造主義自体もう何十年も前にできたものなので、そのころからすでに開かれた出口ではありますが、今でも解決されていない問...
レヴィ・ストロースの人類学を見ていけば、最近読んだ本たちによくでてきた、黒人奴隷の問題の出口がわかってくるのかもしれないという予感の元、読み進めていきました。まあ、構造主義自体もう何十年も前にできたものなので、そのころからすでに開かれた出口ではありますが、今でも解決されていない問題ですし、かといってそれ以降よい方向へ向かわせてもきただろうから興味がありました。構造主義の「構造」とはなんぞや、といえば、人間でも物事でも社会でも、その根っこの部分の仕組み、みたいなもの、と言えるでしょう。因数分解していって残ったところで眼前にあらわれる法則、と言い換えてもいいです。そして、付け加えるならば、それははっきりと言葉にできないし、はっきり見えません。それが「構造」なんだと理解しています。たとえば、言葉にするとき、文章にするときに、その元となる動機があると思うんです。それは言葉になる前なので、ふわふわどろどろ形もなくてまだ名付けられてもいない。そういうところを動機とし、スタートとして、言葉が生まれる。もうちょっと厳しく言うと、言葉に当てはめる。要は言葉という枠にはめることなので、言葉になる前のふわふわどろどろしたものと、言語化したものは等価ではないです。まあ今回はそこのところはいいとして、そのふわふわどろどろしたものを見つめてみる行為と、「構造」を見つめてみる行為はちょっと似ているんじゃないでしょうか。そんな見方をして知覚するのが「構造」なんじゃないでしょうか。「構造」というものについては、まあ、そのくらいにしておきます。レヴィ=ストロースの人類学で見えてきたのは、欧州中心主義の否定です。それは、奴隷にされたアフリカの黒人や、アメリカ先住民、オーストラリア先住民など、いわゆる未開の民族への差別を許さないものでした。欧州人が優れている前提で彼らを頂点とするヒエラルキーを作り、下位に位置する民族からはいくらでも搾取をしていい、という植民地主義の間違いを指摘するものだった。著者は、「西欧近代の腹のなかから生まれながら、西欧近代を食い破る、相対化の思想である」と本書のはじめのほうで構造主義を表現していました。そのくらい、衝撃的な思想なんですね。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
twitterのTLにフェミのひとが、「女性が男にできるだけ平等に行き渡る世界」を男の勝手な妄想、と批判する投稿をよく見かけるようになった。確か、構造主義はそういうことを扱っていたはず、と読んでみた。 インセスト・タブーは女性の実用価値を廃して交換価値にするためで、「価値」がうまくまわらないと社会がなりたたない。フェミのひとが激怒しそうな内容で、本書でもカッコでフェミのひとに配慮した断り書きが挿入されている。
Posted by
構造主義の生みの親レヴィ・ストロースがどのような経緯を経てこのような考え方を主張するに至ったかを易しく解説した本。ソシュールの言語学の方法論を応用。
Posted by
#はじめての構造主義 #橋爪大三郎 著 #講談社現代新書 西洋文明を否定した構造主義。当時、どれだけ多大な影響を与えたか、その破壊力がよくわかる1冊。構造主義は人類学、言語学との関わりが深く、これらの話がメインになっていて、初学者にはちと厳しいかもしれません。タイトル通り、...
#はじめての構造主義 #橋爪大三郎 著 #講談社現代新書 西洋文明を否定した構造主義。当時、どれだけ多大な影響を与えたか、その破壊力がよくわかる1冊。構造主義は人類学、言語学との関わりが深く、これらの話がメインになっていて、初学者にはちと厳しいかもしれません。タイトル通り、平易には書かれていますが厳しそうなら #寝ながら学べる構造主義 のあとに読むと抵抗なく読めると思います。 “構造主義は、人間のあり方を、歴史(といって悪ければ、西欧思想の色めがね)抜きに直視する方法を発見した。” “構造主義くらい人間に理解を示した思想は、これまでにないんじゃないか。これぞ人間主義の究極のかたち、と言わなければ嘘だ。” “名前にごまかされてはいけない。「構造」といっても、骨組みやなんかではなく、もっと抽象的なもののことである。そして、たぶん、現在数学にいう<構造>の概念と、いちばん似ているようだ。” “「未開人だ野蛮人、文明にとり残されて気の毒だと、偏見でものを見るのはよそうではないか。彼らは、繊細で知的な文化を呼吸する、誇り高い人びとだ。われわれのやり方とちょっと違うかもしれないが、そして、物質生活の麺では簡素かもしれないが、なかなか”理性”的な思考をする人びとなのだよ。」” “世界のあり方は、言語と無関係ではなく、どうしても言語に依存してしまうのである。...言語が異なれば、世界の区切り方も当然異なるのだ。” ““価値あるものだから交換される”のはない。その反対に、“交換されるから価値がある”のである!” “社会がまずあって、そのなかにコミュニケーションの仕組みができる、というのじゃない。そうではなくて、そもそも社会とは、コミュニケーションの仕組みそのものだ” “構造主義は、心理を“制度”だと考える。精度は、人間が勝手にこしらえたものだから、時代や文化によって別のものになるはずだ。つまり、唯一の心理、なんてどこにもない。” #本 #読書 #読書倶楽部 #読書記録 #本屋 #本棚 #本が好き #本の虫 #読書タイム #古本 #古本屋 #文庫 #文庫本 #活字中毒 #哲学 #構造主義 #ポスト構造主義 #人類学 #言語学 #レヴィストロース #アルチュセール #ラカン #フーコー #バルト #デリダ #ソシュール
Posted by
構造主義とは本質的にはどんな思想なのか、「構造」とは一体何なのかという点には他の入門書と謳う本を読んでもずっと引っかかってたけど、この本でその部分が少しは掴めたような気がする。構造主義が数学に源泉を持つという話は所々で目にするけど、その関連性をここまでしっかり解説してる本に出会っ...
構造主義とは本質的にはどんな思想なのか、「構造」とは一体何なのかという点には他の入門書と謳う本を読んでもずっと引っかかってたけど、この本でその部分が少しは掴めたような気がする。構造主義が数学に源泉を持つという話は所々で目にするけど、その関連性をここまでしっかり解説してる本に出会ったのは初めてだった。結びに書かれている日本思想のあるべき姿なんかも含めて凄く得るものが多かった。これを起点に色々と広げて行きないなと思わせてくれた。
Posted by
”「ブリコラージュ」が載っていない。なぜだろ!? <抄録(抜き書き)> ・私の思うに、「構造」をどこかにある実体みたいに考えてしまうから、わかるものもわからなくなってしまうんじゃないか。名前にごまかされてはいけない。「構造」といっても、骨組みやなんかでなく、もっと抽象的なものの...
”「ブリコラージュ」が載っていない。なぜだろ!? <抄録(抜き書き)> ・私の思うに、「構造」をどこかにある実体みたいに考えてしまうから、わかるものもわからなくなってしまうんじゃないか。名前にごまかされてはいけない。「構造」といっても、骨組みやなんかでなく、もっと抽象的なもののことである。そして、たぶん、現代数学にいう〈構造〉の概念と、いちばん似てるようだ。(P.28) <きっかけ> 人間塾 第74回読書会の『レヴィ=ストロース入門』を理解するための副読本として…”
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
正直言ってしまえば難易度は高いものです。 はじめての~ととは付いていますが 優しい代物ではないぜこりゃ。 だけれども、こんな考え方が世の中には 存在し、それを席巻する一方で どんな欠点があったのか、というのを 知る意味では興味深いものがありました。 最後の人物紹介は… おいおいちょっと待ちなさい、 夭折している人多いじゃないか!! 分からなくても、文章が良いので 面白くは読めるはず。
Posted by
「構造主義」という、言葉は聞いたことあるものの、具体的な定義や意味についてよく理解できていなかった代物について、初学者の私でも「少しは理解できたかな」という気持ちにさせてくれる本。 構造主義の始祖であるレヴィストロースの半生の解説から始まり、レヴィストロースがどのような人々と出...
「構造主義」という、言葉は聞いたことあるものの、具体的な定義や意味についてよく理解できていなかった代物について、初学者の私でも「少しは理解できたかな」という気持ちにさせてくれる本。 構造主義の始祖であるレヴィストロースの半生の解説から始まり、レヴィストロースがどのような人々と出会い、影響を受けたか、またその結果、なぜ当時の人類学とは違う論理体系(=構造主義)を構築することができたのかについて、分かりやすく、飽きさせない洒脱な文章で解説してくれます。 私のつたない理解で構造主義を一言で要約してしまうと、「抽象化」であると捉えられました。従来型の人類学では、事実を機能により意味づけすることで理解しようとしていたけれども、その分析には限界があった(具体例は後述)。そのような状況の中、言語学や数学の世界で発展していた「構造化」(=事実を抽象化し、その重要な要素をとらえる手法)を人類学に適用することで、単純な機能の説明ではなく、その事実がなぜ・どのように構成されているかを理解できるようにしたのだと感じました。 本書では、構造の具体的な例として、人類学における婚姻可能な範囲の問題と、神話学の体系化の大きく2つ挙げています。ここでは、特に面白かった婚姻可能な範囲の問題について触れます。 世界中の様々な文化・部族において、近親相姦はタブーとされていますが、その範囲についてはまちまちです。例えば、日本ではいとこの結婚はOKですが、ある部族では、いとこの結婚は認められず、またある部族では、いとこでも母方の交叉いとこの娘(=母の男兄弟の娘)はOKだが、父方の交叉いとこの娘(=父の女姉妹の娘)はNGなど。従来型の機能に着目した意味づけでは、父方と母方のいとこに違いは認められず、これは意味不明で説明がつかないことでした。 レビィストロースは、この事実を解釈するにあたり、「そもそも婚姻は親族や部族間での女性の交換である」という仮説を立てます。この仮説に従うと、母方の交叉いとこの娘は自分の所属する部族とは別の部族の出身となり、結婚相手の候補となりえますが、一方で父方の交叉いとこの娘は、他部族に嫁いだ母親の、その娘ということになり、女性が嫁ぎ先から送り返されているということになり、婚姻を女性の交換ととらえた際には認められないことになります。このようにぱっと見の事実を分析者の主観に基づき分析するのではなく、主観を排除しその裏にある構造に基づき事実を分析することで、より高度な理解が得られるというのです。 構造主義について勉強してみたい人の最初の本には最適だと思いました。
Posted by
第1章 「構造主義」とはなにか 第2章 レヴィ=ストロース―構造主義の旗揚げ 第3章 構造主義のルーツ 第4章 構造主義に関わる人びと―ブックガイド風に 著者:橋爪大三郎(1948-、神奈川県、社会学)
Posted by