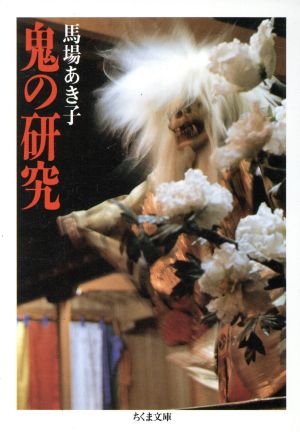鬼の研究 の商品レビュー
社会不安の幻影、反体制としての存在、衰退した土地神など、古代〜中世の鬼を様々な文献から分類、体系化して論じられている。 鬼という存在を「鬼にならざるをえず」「凄惨な結果が、きわめて人間的なものの回復をねがうところに生まれた欲求」として、加害者であると同時に被害者であると、そのあは...
社会不安の幻影、反体制としての存在、衰退した土地神など、古代〜中世の鬼を様々な文献から分類、体系化して論じられている。 鬼という存在を「鬼にならざるをえず」「凄惨な結果が、きわめて人間的なものの回復をねがうところに生まれた欲求」として、加害者であると同時に被害者であると、そのあはれを代弁するように引き寄せて語られている所が胸に響いた。 後半の能や面についての中で「小面のひとつひとつが般若に変貌する刹那を保留している」という一文があり、誰もが例外でなく人間の普遍的、本質的な部分だなぁと考えさせられた。 「うらみ」「羞恥」については読んでいて、河合隼雄の「昔話と日本人の心」も思い出した。 すばらしかった。歌集も読んでみたい。
Posted by
鬼と山人の関係を豊富な文学作品や歴史記録から考察している労作。鬼は悪と切り捨てないで、鬼の目線から民衆史を構成する。
Posted by
「すべての小面のかげにはひとつずつ般若が眠っているのだ」。 能『求塚』のある場面ある表現を見て、筆者はこう思うに至る。 これは1人の少女の内面だけでなく、女性に限らず、すべての人に起こる、生まれるものに違いない。 そう思わせてくれる、『鬼』について主に人間という立場でその正体を...
「すべての小面のかげにはひとつずつ般若が眠っているのだ」。 能『求塚』のある場面ある表現を見て、筆者はこう思うに至る。 これは1人の少女の内面だけでなく、女性に限らず、すべての人に起こる、生まれるものに違いない。 そう思わせてくれる、『鬼』について主に人間という立場でその正体を描いた一冊。 鬼については、解説をかかれた谷川健一氏などが解いた製鉄民との関わりや、武士団盗賊といった現実的勢力、疫神や水神、境界や異界への信仰といったさまざまな視点の本が出されているが、これはどこまでも「人」に寄り添った内容。 物語のほか、能や歌といった人の内面に根付く素材から鬼を見ているのも特徴。 製鉄民や異界といったものからの探求が知的好奇心をともなうなら、これは時に自分自身の苦しみや辛さ、経験にも通じる哲学的というか内省的な視点になる。 「自分のなかに鬼なんかいない」と言い切れる人が果たしてどれだけいるのだろうか? 昨今「コンプライアンス」の名のもとに節分の豆まきや昔話の中の鬼にも配慮をせよ、という話が出てきている。 それはそれでひとつの時代なのだろうけれど、 本書で描かれるような「鬼」たちは 「仲良くしましょう、配慮しましょう、大切にしましょう」 と優しく声をかけるだけでは決して解消されることも、解脱することも、救われることもない。 そういう居場所で人間社会に回帰した鬼の事例も挙げられているが、 身を焼くほど相手を憎みながらも愛しくて愛しくてならないという情念や、権力闘争から弾き出されそれへの思いを絶てない執着や、放逐した相手がそれを恨みに思っているだろうという恐怖、忘れ去られていく昔から涌き出てきた幽鬼、どうしようもない境遇に日を暮らす人の哀切から産み出された暴力、中央への服従を余儀なくされた土着の人々。 これらは生半可な「コンプライアンス」では解決しない。 解決しないどころか、ただ単に綺麗事で臭いものに蓋をしただけにもなりかねない。 「鬼」はなぜ鬼として描かれているのか、を改めて見直す必要があるのではないか。 「衆生本来仏なり」という和讃があるが、それを借りれば「衆生本来鬼なり」。 御息所のように鬼にならねば仏になれなかった存在もまたいる。 それがいいか悪いかはともかく、自分もまた鬼であると思って、この人生を生きていかねばならない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
これまで読んできたちくま文庫の中では、かなり読みにくい部類の本だった。版が古くて文字が小さく、ページあたりの文字数が多いというのもあるが、シンプルに「テーマが難しく、文章の語調がとっつきにくい」というのもある。さらに、古典の中に出てくる「鬼」を紹介するにあたり、古典をそのまま文章内に引いていて、いわゆる「現代語訳」を充てていないので、古文を読みながら話を追っていく必要があり、そこもページを繰る手がなかなか進まない理由の一つ。いわゆる、研究者が論文として書いたものを、そのまま文庫にしたような感じ。 ただ、内容自体は面白い。鬼の起源とは何かについて、様々な古典や民間伝承などをもとに、丁寧に追いかけている。戦や普段の生活で四肢や目、耳などを欠いてしまった「異形の人」が、忌み嫌われ、人々の輪からはじき出された結果として「鬼」として扱われていたことなどは、こういう本をしっかり読まないと分からない。 しっかりとした分かりやすい「結論やまとめ」を用意してくれているわけでは無いので、本筋を捉えるにはきちんと読み進める必要があり、一度、通読したぐらいでは内容は把握しきれないのだが、本棚に置いておいて数年後、また手に取ってみるのも面白いのではないか、という読後感だった。
Posted by
日本の古典文学に登場する「鬼」のモティーフについて、文学的および民俗学的な観点から考察をおこなっている本です。 大学受験現代文の問題集で本書の一節を読んだことがあり、そのときに強い印象を受けたことをおぼえています。問題にとりあげられていたのは、情愛から生じた心の闇によって鬼女と...
日本の古典文学に登場する「鬼」のモティーフについて、文学的および民俗学的な観点から考察をおこなっている本です。 大学受験現代文の問題集で本書の一節を読んだことがあり、そのときに強い印象を受けたことをおぼえています。問題にとりあげられていたのは、情愛から生じた心の闇によって鬼女となった女性についての考察がおこなわれている箇所でしたが、本書の議論は王朝文化における恋のありかたの一面についての考察のみならず、柳田國男の山人論などについても議論がおよんでいます。とはいっても、著者は単純に反体制的な立場に立つことになった人びとが「鬼」というイメージへと形象化されたと論じているのではなく、彼らの複雑な内面のうちに「鬼」への変貌の契機を読み取ろうとしており、その点に王朝文化のなかで孤独な「鬼」となった女性たちにもつながるような深層的な意識のありかたに分析のメスを入れています。 日本の精神史のなかで「鬼」のモティーフがどのような意味をもっていたのかという問題を、広い観点から明らかにしている本だと思います。
Posted by
鬼とは何か◆鬼の誕生◆鬼を見た人びとの証言◆王朝の暗黒部に生きた鬼◆天狗への憧れと期待◆極限を生きた中世の鬼◆鬼は滅びたか 解説:谷川健一 写真:吉越立雄
Posted by
仏教説話の鬼、「ぬし」としての鬼、反体制側の「鬼」… 「鬼」を色々な角度から解説している。 この世で虐げられながらも、この世にとどまろうとする鬼、一方天狗は神仙思想と結びつき、どこかユーモラスな浮世離れした存在。
Posted by
以前より読みたいと思いながら、冒頭部分が韜晦であるため、なかなか読み進めなかったのですが、読み通しました。鬼とは何かを問い、鬼の誕生、上古期、王朝期、そして中世における鬼のありようを豊かな感性で多くの文献、能などの芸術の中に追いかける興味深い書です。
Posted by
大学の卒論のテーマが「鬼」だったので、締め切りに追われながら読んだ思い出。 古代からの鬼についての考察。 異民族や順はぬものとしての鬼や、疫病等の目に見えない脅威としての鬼など、様々な形の鬼についての研究で、学生当時はかなり参考になった。
Posted by
なじ■ 歴史・伝説・能などの世界の「鬼」について。 歌人の馬場あき子さんの著だけあって、 文章や情景描写などが凄く美しくて流れるように読めました。 他の鬼研究の本とは違って、 鬼の心情について深く考察されているのも興味深かったです。
Posted by
- 1
- 2